
インタビューその10:森の奥深くに個性豊かな「帽子の花」を咲かせる人
イラストレーター&文筆家・陽菜ひよ子です。
今回の記事はインタビュー企画です。わたしのまわりにいる「クリエイティブな活動をしている人」に「仕事や創作」について赤裸々にきき、その人の「クリエイティブのタネ」を見つけよう!という企画の第10回。
今までのインタビューは↓コチラでごらんになれます。
今回お話を伺ったのは、帽子の学校 スダシャポー学院・学院長で帽子作家の須田京子さん。
須田さんの略歴など。
須田京子
帽子作家。東京都生まれ
「帽子の学校スダシャポー学院」設立者である父・須田京之助より直伝で帽子づくりを学ぶ
1988年 「帽子の学校スダシャポー学院」アシスタントを経て講師へ
1996年 江東アカデミースクールにて、手縫い帽子講座をスタート
2010年 『帽子DESIGN FILE 世界と日本の帽子作家60名による作品』(アートボックスインターナショナル)に招待作家として掲載
2013年 「帽子の学校スダシャポー学院」2代目学院長に就任
2018年 NHK朝ドラ「半分、青い。」のために帽子制作
◎活動について
大塚本校制作指導
個人・企業用オーダーのデザイン制作
各種イベントの企画運営
ヴォーグ学園東京校の手縫い帽子講座
目白ファッション&アート学園の帽子講座など多数
◎メディア出演・掲載
NHKラジオ 帽子の質問対談出演(1時間)
NHKテレビ ニュース番組
日本テレビ「TVぶらり途中下車の旅」
テレビ東京「モヤモヤさまぁ~ず」
BS-TBS「吉田類の酒場放浪記」
東京ケーブルネットワーク「あらぶんちょ!」
TOKYOMXテレビ「5時に夢中!」
新聞、雑誌など多数
とっても尊敬する帽子の先生
須田京子先生は、わたしが東京時代に通っていた帽子の学校の先生です。
帽子の学校・スダシャポーは、京子先生のお父さまである須田京之助先生が設立した学校。京之助先生が研究の末生み出された「立体裁断の型紙」による布帽子を中心に、さまざまな帽子づくりを学ぶことができます。
東池袋でひとり暮らしをしていた頃には、新大塚にある帽子の学校は自宅から歩いてすぐでした。通い始めた当時はのめり込んで、昼の部も夜の部も通うほど。
当時のわたしはイラストの仕事を始めたばかりで、絵本作家をめざしていました。しかし、もともと帽子好きだったこともあり、いつしか帽子作家を夢見るように。
決して手先は器用ではないのですが、帽子愛と熱意だけはあったのを買われたのか、帽子の体験講座のアシスタントなども経験。
2011年夏に、諸事情で実家のある名古屋へUターンすることに。帽子作家の夢は消えてしまいましたが、今も京子先生との交流は続いています。

小町テレビ(CSチャンネル日テレG+)の取材時に撮影。
下写真中央:帽子の製作体験をされた三遊亭楽生さん
右隣が須田京子先生、その右隣ピンクのエプロンがわたし。
帽子作りとは無縁な子ども時代
「不思議な我が家」
須田:私自身のことをお話しする前に、先に私の家や家族のことをお話しした方がいいかもしれません。
大塚にある教室は、今は建て替えた建物ですが、私が生まれた頃の自宅はちょっと変わった家だったんです。

――――変わった家?
須田:1軒屋の木造階建てでしたが、地下室や中二階があったんです。それでなぜか地下室には鉄棒があって。その周りは、何に使うのか分からない工具や骨董、帽子材料などが所狭しと置かれていて。
友達からは珍しがられて、あまり親しくない同級生が見に来たこともありました。
――――地下室!そしてなぜ鉄棒が?
須田:なぜ鉄棒があったのか、未だにわからないんです。最近、母とも話していたのですが、母もわからないと。
祖父が建てた家なんですが、この祖父が変わった人で。自由業で、骨董品の修理などを行っていたのですが、誰かについて習ったわけではなくて、自己流だったんですね。2階建ての木造の家も大工さんと祖父と2人で建てたそうで。
――――おうちまで建てられたとは、手先が器用な方だったんですね。
須田:そうですね。お風呂も設計して、洗い場もセメントを流して手作りで。いろんな色のタイルがはめ込まれていた事を覚えています。
子ども部屋の窓を開けるとすぐに柿の木があったんですが、2階の窓より高く育ってしまって。そうしたら、祖父が私のベットの真上の天井に穴をあけて扉を付けて、柿を収穫できるようにしたんです。
――――天井に穴をあけて??自由ですねーー。
須田:祖父は「自分の判断はすべて正しい」みたいに考える頑固な人だったんです。でも、モノづくりに関しての発想は、とても自由だったんですね。才能もあったと思います。
動かなくなった西洋アンティークの時計などの難しい修理もできたので、家にはなんだか、怪しい雰囲気の骨董屋さんが出入りしていました。
家族や家が個性的すぎて、小学生の頃に「不思議な我が家」という作文を書いたこともあります。
――――わたしは生前の京之助先生(スダシャポーの創設者で京子先生のお父さま)は、ちらっとお見掛けしたことがあるだけですが、古くからいる生徒さんから、とても個性の強いカリスマ的な方だったと伺っています。
おじいさまも個性的な方だったんですね。
須田:そうですね、我が家は祖父も父も個性的ですが、病弱な文学少女のような祖母も別の意味で個性的でした。
そんな個性の強い人がそろう家に嫁いで、父の奇抜とも思えるアイディアやチャレンジも、すべて面白い!と、一度も躊躇することなく応援できた母も、ある意味自由な人だったのだなぁと思います。
でも、そこに生まれた私は、なぜか、生真面目を絵に描いたような性格だったんですよね。
――――確かに京子先生は、キチンとした方、という印象です。京子先生は、ブログによると、とてもおとなしくて人見知りなお子さんだったそうですね。
須田:そうですね、おとなしくて体が弱くて、本ばかり読んでいるような子どもでした。
――――今の京子先生からは想像できるような、そうでもないような。。。
須田:こんな風に人前で話すような自分が、昔は想像できませんでしたね。
そういえば、ブログに書かなかったことで、ひとつ思い出したことがあるのですが、私は子どもの頃、パズルを組むのが得意でした。おもちゃのブロックで建物をつくるのも好きで。
亡き父が行っていたことも、一つの絵を完成させてゆくパズルの面白さに、どこか似ている所があるかも知れません。
父は、さまざまな帽子のイベントを企画しては、実現していました。周りの人はいつのまにか、役割を与えられてイベントに巻き込まれていくのですが、最後は楽しく、イベントの完成を一緒に見るんです。その様子は、まるでパズルの一枚絵を作り上げるようで。
私には父のような巻き込み力は無いのですが、パーツを組み立てたり、ものをあるべきところに収めたりすることは好きです。教室を使いやすく、すっきりと整理整頓することも、割と得意なんだと思います。

おやつにブルーベリー♪
2008年夏ごろ。
エレクトーンとワーキングホリデー
――――京子先生はもともと帽子づくりではなく、エレクトーンをなさっていたそうですが、それはどういったきっかけなんですか?
須田:エレクトーンを習うことになったきっかけにも、父が大きく関わってるんです。父の話をし出すとホント、キリがないくらいいろいろあるんですが(笑)。
――――ぜひ、伺いたいです!
須田:祖父が鍵盤楽器が弾けたせいか、家にアコーディオンとピアノがあって、私は小学3年生くらいの時に、ピアノを習っていました。
ピアノは好きだったんですが、習っていた先生がわりとメンタルのアップダウンがあり、不機嫌な時が怖くて楽しめなくなり、辞めてしまったんです。
またいずれ始めるつもりだったんですが、小学4年のある日、学校から帰ったら、ピアノがなくなっていたんです。
――――ピアノがなくなった?
須田:新しい物好きだった父がエレクトーンをやってみたくなり、急に買い替えてしまったんです。今までピアノがあった場所にはエレクトーンがあって。
帽子の生徒さんの娘さんがエレクトーンの先生をやっていることがわかり、さっそく来てもらって習おうと、購入したんですね。でも父はすぐに、今ひとつ自分に向いてないことがわかって。お断りするのも何なので、私が習うことになったんです。
――――それでも、お仕事にしようと考えるくらいエレクトーンはお好きだったんですね。
須田:そうですね。リズムボックスと、両手と両足の全身を使って演奏するのは好きだした。でもちょうど資格を取ろうとした頃に、エレクトーンの世界がこれまでとは、大きく変わる時期に入ってしまって。
事前にコンピュータの打ち込みをするようなことも増え、評価の対象もガラリと変わったように感じました。
打ち込みができるようなマシンはどんどん進化するので、講師になるのであれは、使いこなすため買い替えなくてはいけないのですが、一台100万円以上するような高価なもので。これはもう大変だな、ちょっと違うかなと思いはじめて。
――――それで、エレクトーンを辞めて、帽子の方に?
須田:当時は会社員をしていたんですが、ちょうどその頃流行っていたワーキングホリデーでオーストラリアに行きたいと思うようになって。
エレクトーンを辞めて、少しゆっくり先のことを考えたいと思って会社も辞めたんです。それで、ワーキングホリデーの費用を貯めるために、家の仕事を手伝うことになりました。
実は、その後すぐに祖父が亡くなってしまって。家族が1人欠けたのに、その上自分まで家を空けるのも・・・と思ううちに、ワーキングホリデーの話は立ち消えになってしまったんです。
父の信念
「普通」禁止令
――――こうして帽子の学校のお手伝いを始められたわけですが、ブログによると、非常に苦労されたそうですね。
須田:今言っても、信じてもらえないんですが、裁縫が苦手で。家庭科の宿題を母にやってもらうような子だったんです。学生時代の友人はそれを知ってるので、みんな驚いてました。
OL時代は、出版関係の電算部だったのですが、エレクトーンでなければ本作りの方に進むことはあっても、帽子はない、とみんな思っていたようです。
――――家業を継ぐ事について、お父さまから何か言われたことはなかったんですか?
須田:それはなかったんですね。「自分の生き方は、自分で決めていい」という方針でした。「帽子は継がなくていいよ」と言われていましたし。
――――素晴らしいですね。
須田:我が家は「普通」という言葉が禁止されていたんです。
「『普通』じゃなくて、全て自分で考えなさい」と言われて育ちました。だから「子どもだから親のあとを継ぐのが普通」ということも、全く言われませんでした。
また父の話になりますが、父は小学校入学してすぐに、小学校に絶望した人なんです。
――――小学校に絶望?
須田:父はほんの小さな子どものころから、自分なりに哲学的なことを考えていて、小学校では、どんなことを教えてもらえるのだろうと楽しみにしていたそうです。
ところが、いざ入学したら、教科書で「みんなが同じ答えになること」しか教えてもらえない、と絶望してしまったと言うんですね。
父が言うには「正解が一つに決まっていることは、わからなければ調べればいい。暗記よりも『自分だけの考え方』が大事なのだ」と。
だから我が家では、誰かが言っていたことをそのまま言うと、ツッコミがすごくて。
――――子どもがよく言う「みんな言ってる」みたいな感じですね。
須田:そうですね。それを言うと「なぜ、そう考えるのか?なぜ、自分がそう思ったか、説明できるか」と突っ込まれます。
学校教育に価値を見出していないので、試験でいい点とったとしても、それで何になるの?本当に自分でやりたいと思っているの?と言われて、試験勉強を止められるんです。でも子供の私は、試験勉強はしなくちゃいけないと思いますよね。
――――それは大変だったでしょうが、真理でもあると思います。
須田:そうですね。父はとことん自分で考えて、自分の人生を生きることに一生懸命な人だったんですよね。
スダシャポーの始まり
――――お父さまのお話、すごく興味深いです。もう少しお伺いしてもよろしいでしょうか?
須田:父の話はホントいくらでも出て来るのでキリがありませんが・・・
父は子供の頃から身体が弱く、人生について深く考える、悩み多き少年といった感じで。美術品やファッションなどの美しいものを雑誌で見ることが楽しみだったようです。
大人になって文具の会社に入社しましたが、サラリーマンとして求められる事務的なことや、書類の管理などが本当に苦手で。やることも遅い落第生で、同僚に助けられてばかりだった言っていました。
当時は物資のない時代で、食べ物やお酒の調達などは得意だったので、喜ばれる一面もあったそうですが。通常の事務仕事のあまりの苦手さに、自分は役に立たない、と屋上でこっそり泣いていたこともあったと聞いています。
――――クリエイターって「ほかの人が普通にできること」が苦手な人、多いんですよね。わたしもお父さまのお気持ち、わかる気がします。
須田:そんな時にいつも眺めていた雑誌で、洋服よりも帽子が気になり始めて、自分でも帽子を作れるのだろうかと調べたら、学校があることがわかって。それで日本で最初の帽子の学校である「サロン・ド・シャポー」に習いに行ったんです。
帽子作りに夢中になった父は、学校で学んだことを熱心に研究し、ぐんぐん腕を上げていったそうです。授業だけで飽き足らなくて、同じクラスの財閥系のお嬢さまたちから帽子が載っている洋書を借りて。
型紙は載ってないので、写真を見て何週間か家で研究して、写真そっくりに仕上げた帽子を見せて、お嬢さまたちを喜ばせていたんですね。そうこうするうちに「教えて欲しい」と言われるようになったと聞いています。
――――それがスダシャポーのはじまりなんですね。
須田:最初は6畳くらいの小さな部屋からスタートしました。父は身体が弱かったんですが、帽子を作ってるときだけはめちゃめちゃ元気だったそうで。
祖母は病弱で20歳まで生きられないとまで言われてた人だったので、父のこともすごく心配していたようです。でも、夜更かししてても帽子を作っていると聞くと、祖母が安心するくらい、父は帽子を作ってるときは生き生きとしてたんですね。
――――本当にお好きだったんですね。天職ですね。
須田:父は「帽子で女性を幸せにしたい」が口癖で。帽子をかぶると女性が華やぎ、幸せになれると信じていました。作った新作を、次々に祖母に被せて、祖母が喜んでくれたのも、うれしかったのかもしれませんね。
――――お母さまは、お父さまの生徒さんだったという事ですが、お母さまは手先は器用な方なんですか?
須田:母は器用ですね。当時講談社でアルバイトをしていて、オシャレ好きで、物のない時代には自分でコートをつくってしまうような人で。
父の教室には「装苑」に載っていたパターンでつくったフェルトのベレーをかぶって見学に行ったそうです。自分で考えて帽子に付けていた葉っぱの飾りを父に褒められて嬉しかった想い出があると言っています。
――――なれそめですね、ステキ。
須田:母は90歳目前で個展をするようなバイタリティがあって。裏方でずっと父の夢実現のサポートに徹していましたが、ふんわりしている中に、個性と芯の強さがある人だと思います。
失敗ではなく発見
――――帽子を制作するうえで大変なことや、難しいと感じて、イヤになったりすることはありませんか。
須田:難しいことは、大変だとは思わないんですね。おもしろいなって思います。こうなるんだーという感じで。
上手くいかなかったやり方も、発見だと思えば一つもムダはないんです。「『この素材で、こうすると、こんな風になって綺麗に仕上がらない』という事がわかった」ということなので。
これで、生徒さんが同じようなことをやろうとした時に「これをやると、こんな風になりますよ」って言ってあげられると考えれば「引き出しが一つ増えた」ってことなんですよね。

――――先生が「これはちょっと難しいかも」と助言してくださったことは、すでにご自分でも失敗されたことだったんですね。
須田:そうですね、フフフ。
それは父も同じで。私が怖いもの知らずで、難しい技術にチャレンジして、もう半泣きで作ってる横で、「それはそうなるんだよ。やってるね~」って言って笑いながら見てました。父もすでに同じことをやって、全部お見通しだったんですね。
――――NHK『ソーイング・ビー』でエズメやパトリックが「この生地は辞めた方がいいと思うけど」って言うのも、彼らも過去に失敗してたから、なんですね。止めても言うこと聞かなくて、大抵後悔してますよね。
須田:そうですよね。あ、そういえば、帽子づくりは曲線を縫うことが多いので、カーテンのように直線をひたすら縫う、というのはあまり好きじゃないかもです。帽子のようにカーブが多くて、気を抜くと上手くいかなくなるような、変化に富むのが好きなんだと思いますね。

帽子を「うまくつくる」より大切なこと
父の啓蒙活動に巻き込まれて行く人々
須田:父の話はホント尽きないのですが、父は「できない」という言葉が辞書にない人で、もう「どうやるか」しか頭にないんです。
「イカ天」が流行っていた頃、帽子の啓蒙活動も兼ねてイベントをしようと、「帽子美人コンテスト」を企画しました。最初は、生徒さんや知人が出場して、父やファッション関係の知人が審査員になる感じで。
場所は当時にぎわっていた原宿のホコ天で、手作りの文化祭のようなものだったんです。
――――「イカ天」が流行っていた頃というと、1990年頃ですね。

TBSで放送された深夜番組『平成名物TV』の1コーナー
1989年2月開始、1990年12月に多くのバンドを輩出して幕を閉じた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/三宅裕司のいかすバンド天国
須田:それがいつのまにか、帽子業界を巻き込んでの大イベントになったんですよ。原宿のイベントを見に来てくれたアルプス・カワムラという大きな会社が出資してくれて。
映画「イースターパレード」を再現したいという父の夢もあり、2回目には開催場所は銀座のホコ天に移り、エントリーした人は帽子をかぶって大通りを練り歩いたり、松屋デパートに審査会場として協力していただくまでになりました。
300名超えの大きなイベントで、マスコミ取材も受けました。
各会場へのスタッフ配置や役割からイベント進行台本まで、ド素人の私が父に任されてやり遂げるという、今考えると恐ろしく無謀なチャレンジでした。もう、無我夢中で深夜まで頭を悩ませ、準備も大変でしたが、無事成功して。今となっては本当に良い想い出になりました。
青山円形劇場で自作自演の帽子ショーもやりました。帽子教室の生徒さんが中心の全くの素人集団でしたが、入場料をいただけるレベルのものを目指したんです。
父の企画構成演出で、一丸となって頑張りましたね。プロを雇う予算はないので、音響ミキサーは私の友人に頼んだり、ナレーションは母だったり、舞台裏のキューを出すのも舞台スタッフ経験ゼロの生徒さんがやったりしました。

日本初の完全円形オープンスペースというユニークな形態の劇場。
2015年3月閉館。
父の想い~ダイアナ妃の3つの帽子
須田:父は、大きなイベントを「業者に任せて、ダダーンとやる」というよりは、自分たちの手で創り上げてゆくことに情熱を注いでいたように思います。何もないところから「想いありき」で作り上げることを大切にしていました。
帽子の素敵さを伝えるために、皆で知恵を絞り力を合わせることでエネルギーが生まれる感じや、皆がイベントを成し遂げた感動を分かち合ってゆくという事が好きだったんですね。
「帽子」という小さなモノづくりの世界ですが、もっと奥深い魅力、大きく言えば、ご自身の生き方の可能性も広がるような力があると。
帽子を通じて、人とのご縁を結びながら、「帽子を作って終わり」ではなく、そこからつながるもの、生み出せるものを大切にしていたんだな、と今は感じています。
――――すごくスケールの大きなお話ですね。
須田:実は、父は「ダイアナ妃のご成婚時に、3つの帽子を贈る」ということにもチャレンジしました。
「帽子が国の架け橋になる」と本気で言うくらいの想いを込めて、「愛」「平和」「情熱」の3つのテーマでデザインしました。
一般人の贈り物が届くことは難しいことはわかっていましたが、いろいろ調べて、母が英文の手紙を書いて奇跡を祈りつつ送りました。
後日、王室ご担当の係の方から丁寧な英文のお便りが届いたんです。セキュリティーの観点もあり公にはお渡しできないことへのお詫びと、感謝の意がつづられていました。
どんな状況でも「自がやりたいと思ったことは、やる前にあきらめるということは無く、最善を探して全力を尽くす」のが、父の生き方だったなぁと思います。
そうそう、お礼のお手紙をくださった係の方が「ハットフルさん」というお名前だったんです。大きな夢はかないませんでしたが、父の帽子への想いは届いたような、嬉しい偶然を感じました。

(2011年・Orange Gallery・池袋)
コミュニケーションツール・帽子を通じての人生
須田:ひよ子さんも教室で学ばれたと思いますが、顔の形によって似合う帽子というのは確かにあるんです。でも、帽子が似合う似合わないって、顔の形だけじゃないんですよね。
単純に形だけで分類したら似合わないものも、似合ってしまうことってあるんです。そういうとき、帽子と人は2人で一つの新しい完成形みたいになってるんですね。
――――それは少し、思い当たるところがあります。
わたしは学校に通う前は、自分に似合わない帽子があると考えたことがなかったんです。どんな帽子でも、角度を変えてみたりして、自分なりにかぶっていたからなのかな、と思います。これって正しい認識ですか?
須田:そうですね、いろいろ試して似合うかぶり方を探すのは、すごく大事ですね。正しいと思います。
帽子には秘められた力があります。デザインの素敵な帽子をかぶることで、自分自身を表現したり、無言で何かを発信することができますよね。かぶり方ひとつでも、さまざまな表現ができます。
――――「帽子で発信」も実感します。
わたしは本来地味な容姿ですが、帽子をかぶっているというだけで覚えてもらえたり、オシャレな人に見られたりといった「効能」に、今の仕事ではすごく助けられています。
個人的には、フリーランスは絶対帽子をかぶった方がいいと思います。

須田:ホントそうですよね。私も印象に残らないタイプだと思いますが、帽子のお陰で覚えてもらえたことはよくありました。
それだけじゃなく、帽子は心と密接しているんですね。帽子のかぶり方ひとつで、人相を変えてしまうくらい、違う印象になります。ブリム(つば)の角度ひとつで、一瞬で変わるんですよ。
例えば酔っ払って陽気になった人の帽子は、だんだん帽子が後ろにずれて、前が上がってくるんです。開放的なのに、きちんと目深にかぶっている酔っ払いっていませんよね。

逆にブリムが深く下を向いてくると、心も平常心を保ち、内向的になります。
帽子のかぶり方は無言の信号なんです。帽子はコミュニケーションツールでもあるんですよね。
もっと素敵に楽しめる 帽子何でもQ&A
須田:この春に、「もっと素敵に楽しめる 帽子何でもQ&A」(自社での簡易製本)を再編・加筆して販売開始する予定です。
帽子の扱い、マナー、似合うデザインだけでなく、被り方を含む「面白帽子心理学的なこと」も少し、みなさんに知っていただけるとよいな、と思っています。

※購入者特典 被り方レッスン動画QRコード付き
帽子の森に迷い込んで
朝ドラ『半分、青い。』“鳥の巣”帽子
――――スダシャポーはさまざまな媒体から取材を受けたり、『ぶらり途中下車の旅』などの、たくさんのまち歩き番組の訪問を受けたりしています。
中でも気になるのは、2018年のNHK朝ドラ『半分、青い』のために京子先生が制作された帽子です。
須田:鳥の巣帽子ですね。

――――あれはどういった経緯で?
須田:主人公が働く100円ショップのオーナーさんのお宅が、かつて栄えた帽子屋さんで、今はアトリエで帽子教室をやっているという設定で、その監修を頼まれたのがきっかけなんです。
帽子のアトリエ・教室内の様子や道具を、ドラマの年代に合わせて再現する際の監修を依頼されました。当時の時代に合わないものがあったり、逆に帽子で使うミシンや道具など、無いとおかしいものが置いていなかったり、ということがないように。
――――そういう視聴者のチェックって厳しそうですね。
須田:そうなんです。NHKさんには、歴史的な背景など「何かおかしい」と視聴者から指摘が来てしまうそうで。リアルな取材が必要なんですね。
そのうちに「収録に帽子が必要」だというお話が来ました。
「野鳥好きの妹のために、帽子デザイナーのお姉さんが誕生日プレゼントに作った鳥の巣のような帽子」を被っている場面があるとのことで。
「その『鳥の巣帽子』を作れないか」という話になって。
――――野鳥好き、まるでわたしのような。。。
須田:引き受けたものの、そこからが大変でした。帽子はたくさん作っていますが、鳥の巣は一度も作ったことがないので(笑)。
美術部のデザイナーさんが描かれたイメージ画に合わせて作るのですが、奇抜なデザインではあるので、それをどう素敵な帽子に仕上げるかを考え、本当に大変でした。
――――先生がそうおっしゃるとは、相当複雑なものだったんですね。
須田:クラウンの部分が鳥の巣そのもののようなイラストだったので、それに寄せて作ることになりました。自然な感じに見せたくても、思うような材料がなくて、染色から取り掛かったんです。チャチなものにはしたくなかったので。

素材も何種類も購入して、しっくり来なくて没にしたものもあります。染色も、最初はナチュラルにコーヒー染をしたのですが、ラフィア素材は油分が多くて色がうまく入らず、最終的には化学染料にしました。
試行錯誤の時間も必要でしたが、撮影のため、納期期限もタイトで。
――――素材の段階から作られたんですね。鳥も先生の手作りなんですか?
須田:鳥は、別途専門家にオーダーされたものが、納期ぎりぎりに完成して届きました。鳥は飾りとしてはそぐいにくいもので。それを美しい角度にキープして止め付けるのも、かなり吟味が必要で苦労しましたね。
完成間際になったとき、なんだかデジャブを感じたんです。今は亡き父と一緒にテレビで見た帽子のことを思い出して。
滅多にほめない父が、ある感動的なドラマのラストシーンで、主人公の女性が被っていた帽子をほめたんです。
「作者の渾身の作品だね。いつか、ああいうのを、京子もつくれるといいね」
テレビ画面を通して見ても、つくり手がどれだけ命を込めて作ってるかがわかるような、そんな帽子。
それも「野鳥の乗った帽子」だったんです。
先生の魔法の手
須田:新しく「素敵をみつけて、楽しむ 帽子の森」というテーマで楽しむ帽子の世界を、ご案内したいと考えています。「帽子の森」としたのは、「心の中で、森で遊ぶように」楽しんで欲しいからです。
帽子を作ることと同時に、かぶることももっと楽しんで欲しい、という想いから始めました。
――――帽子って顔に近い分、すごく印象が変わるんですよね。華やかな帽子をかぶると気分が明るくなって、幸せな気持ちになれるというのは、本当にそうだと思います。
けれど、多くの人は「似合わない」とあきらめてしまいます。それがもったいなくて。
須田:そうなんですよね。今の帽子屋さんは、かぶり方まで教えてくれるお店がなかなかなくて。専門店自体が少なくて、コーナーで販売しているようなお店だと、なかなかコンシェルジュがいるというのは難しいですね。
――――わたしは学校に通う前から帽子がすごく好きで、自分はそれなりにかぶりこなせていると思っていましたが、それでも最初にベレーのかぶり方を、京子先生に教えていただいた時の感動は忘れられません。
わたしが思いつくかぶり方以外にも「こんな風にもかぶれますよ」といくつものかぶり方を教えてくださって。同じ帽子でも、ちょっと角度を変えるだけで、ガラッと印象が変わる。本当に「魔法のよう」でした。
あの感動を、ぜひ多くの人に味わってほしいです。

2009年6月巣鴨にて(撮影:宮田雄平)
個性豊かな「帽子の森」
須田:不思議なんですけど、「森」というキーワードが私にとって、いつの間にか帽子と繋がるテーマのようになっているんですね。NHKドラマで制作したのも野鳥の帽子でしたし、「野鳥といえば森」という感じで。
野鳥の好きなひよ子さんに、こうしてインタビューしていただいたという事も、「帽子の森」のご縁かもしれませんね。
――――帽子の森、奥深くずっと広がっていくというイメージでしょうか。森の中を軽やかに飛ぶ鳥は、みんな好きな帽子をかぶっていて・・・
須田:「さまざまな個性を持った命が共生しながら、未知の可能性に満ちている森」というのが、私の感じる帽子作りの世界と似ている気がするんです。
生徒さんは、本当におひとりおひとりタイプが違って、作る帽子も、本当に、個性豊かでさまざまなので。針を持つのも初めてという方から、すでにプロとして洋裁をされているような方まで、いろんな方が入って来られます。
それぞれのレベルで、ご自身にとっての帽子の世界を、冒険するように楽しんでいただけたら良いなと。
通常は初等科からスタートしますが、物創りでプロの方が入学されることもあります。力量があり、具体的な目的を持って受講される方には、様子を見て、お仕事にすぐに役立つように高等科レベルのことをお教えすることもあるんです。

木型で型を取って制作する帽子のこと。
これはわたしのつくった夏帽体(2008年制作)
――――誰もが初等科から始めるわけではないんですね。
須田:初心者のほとんどの方は、初等科かメンズハット科で基礎から積み上げる形になります。
初等科で学ぶ布帽子は、基礎が詰まっていて帽子のことが分かるようになるので1番おススメです。
帽子の森のその奥に
すべてが整う日なんて来ない
――――最初は帽子が好きで通い始めたスダシャポーでしたが、お教室自体が本当に楽しくて。引越しが決まって辞めるのは本当に辛かったです。
京子先生やスダシャポーが特に素晴らしいと感じるのは、生徒をトコトン応援してくださるところ、だと思うんです。
オリジナル作品ができたら「どんどん販売してみて下さい」って言ってくださいますよね。その言葉に勇気をいただいて、わたしも販売してましたが、今思うと厚かましかったなぁと。

須田:そんなことはないんですよ。長いスパンで、しっかり学び続ける意思があるなら、「今できる範囲での力試し」という感じで、販売し始めてもOKだと考えています。
なぜかといえば、キリがないんです。帽子は奥が深くて、やってもやっても「まだまだ」って思うんですよね。だから、すべての技術を習得するまで待っていたら、いつまで経っても販売できないんです。
――――京子先生でも、今も「まだまだ」と感じることがあるんですか?
須田:もちろん、今もよく思いますよ。学ぶことには終わりがないので。
それと、もうひとつ思うのは、作ってお客様に販売すること自体が学びだということ。自分の作品の良いところも未熟なところもわかって、自分に返ってくるものがたくさんあります。
一人で作っているだけより、仕上がった帽子を通して人とつながることができると、そこに喜びが生まれます。もっと良いものを作りたいという活力にもなりますよね。
――――確かに、学ぶことってキリがないですよね。仕事として描くことが一番の成長の近道だ、と言われるのは、イラストも同じです。
須田:以前通ってらした男性の生徒さんで、中等科まで進んだところで、ご家庭の事情で来られなくなった方がいるんです。
中等科で学ぶオリジナルの型紙完成は、まだ数点のみ(※)、という段階です。それでも、その数点を作っては地元のイベントに出店したり、ご自分でレンタルボックスを借りて販売したり、できることでコツコツ活動を続けられています。
先日お電話で、折を見て復帰して、もっと学びたいとお話を聞き、嬉しかったです。
※スダシャポーのカリキュラムでは、初等科は学校の型紙で制作技術を学ぶ(課題は販売不可)。中等科に進んでからオリジナルの型紙を制作。
ちゃんと技術を身に付けて行くお気持ちがあり、長期スパンの学びを視野に入れての「オリジナル帽子の販売」は、早めにスタートしても良いと考えています。販売活動もしながら、学びも充実させていくというやり方も、応援してゆきたいと思っています。

初日すぐに売れてうれしかった!(2011年4月)
「きらめきのかけら」を見逃さないこと
須田:フェルトやストローハットなどの帽体だけ学びたい方のために、最近では帽体専門コースを設けました。
帽体は課題デザインの指定はなく、必要な技術項目を身に付けていけていくスタイルで進めます。相談しながら、その人に合わせたレベルでできる事をお伝えしています。
――――技術を身につけることは簡単なことではないし、くじけそうになることもありますよね。
須田:課題の合格かどうかというラインも、一律にはしていないんです。完璧を求めすぎて心が折れることのないように、その人その人の成長度合いを見て変えているので。
でも、ある課題では「やり直しぎりぎりのライン」でOKにした人も、その後も地道に学び続けて行くと、必ずどこかで、一気にものすごく成長するタイミングが訪れるんです。その人にしかない「きらめき」を見せてくださるんですよね。
そんな「きらめきのかけら」を見逃さないよう、見守りながら、その部分が伸びるようにお声掛けしていくように心がけています。
そこから、その人独自の世界観のようなモノが、作品にちゃんと現れてくるように感じています。そうなるとそこから先、その人の作品にどんなものが出てくるのか、私もすごく楽しみになるんです。

――――きらめきのかけら。。。そのタイミングも人それぞれなんですよね。早い人もいれば遅い人もいて。
須田:遅いことは全然大丈夫なんですよ。むしろ途中でいろんなことに気づきながら、じっくり積み上げていく方がいいというくらいに考えています。
器用な人は、なんとなくササッと仕上がってしまいます。そのせいで、途中で感じる、ささやかだけれど大事なことに気づかずに、飛ばして行ってしまうこともあるので。
――――なんだかホッとします。わたしもホント、できのいい生徒ではなかったので。
須田:長い目で見ると、本当にどうなるかってわからないんですよ。初等科ではとても上手とは言えなかった人が、ほんとにコツコツ継続して、のちに大きな賞を取ったりすることもあるので。
むしろ大切なことは、帽子への想いの強さと粘り強さですね。あきらめないで、好きで研究して作り続けていれば、必ず素敵な花が咲きます。
「人が好き」なことが最大の武器
――――ブログを拝見して心に残ったのは、お父様は手先が器用で、カリスマ的な指導者だったのに対して、京子先生は「人が好きだった」ことで講師を続けて来られたということでした。
須田:そうですね、高校時代、文化祭出し物で、本気で「ほめ屋さん」をやようってクラスに提案したことがあるんです。それくらい、「人の良いところを見つけたり、それを伝える」のが好きですね。文化祭では却下されちゃいましたけど。
人見知りで、親しい人以外あまりしゃべらないけれど、「あの人は、こんなところを持っているなぁ、素敵だなぁ」って感じながら、いろんな人を見てる、そんな子でした。
――――京子先生の人柄のせいか、スダシャポーは個性的で温かい生徒さんばかりで、本当に大好きでした。
うんと年上の生徒さんに混じって、かわいがっていただいて。当時わたしは新婚だったので、40代なのに「新妻」って呼ばれてたんですよね。
須田:そうでしたね。ひよ子さんは、結婚式の帽子も作られてましたね。
――――それもみなさんに手伝っていただいて。そういえば、鳥の刺繍の帽子でした。

コレをどうしてもウェディングでかぶりたくて、無理言って
前倒しで教えていただき、周りを巻き込んで何とか完成。(2008年10月)
実際に初等科を卒業できたのは2009年2月でした。
須田:もうひとつ、スダシャポーの特徴は、生徒さんの作風が、まったくバラバラだという事なんです。
学校によっては、雰囲気やシルエットで、なんとなく、どこの生徒さんかわかるようなところもあるんですよ。でもうちの学校には、そういった意味では、統一感のある「スダシャポーらしさ」はありません。
生徒さんの、「唯一無二の『個性』が花開いて行くことこそが素晴らしい」というのが、父の、そしてわたしの考えなので。
思えば、生徒さんたちの帽子の夢を叶える「良き伴走者」でいたいという気持ちは、不器用で何もできなかった私が、帽子を研究し続けた強い原動力でした。
長年の経験で、たくさんの引き出しを持っている今でも、変わらず持ち続けている、根っこの想いなんですよね。
帽子の森の先へと続く道
先生へのインタビューはここまで。
京子先生、素晴らしいお話を聞かせていただき、ほんとうにありがとうございました。
信じられないのは、わたしがスダシャポーに通っていたのはたったの3年間で、それからすでに10年以上の月日が流れてしまったということ。
短い期間でも、スダシャポーで過ごした日々は、わたしの人生の中に確かにしっかりと「きらめきのタネ」を残してくれているように思います。
帽子が好きだったことで、素晴らしい出会いもたくさんありました。それについては長くなるので、また別の機会に書くことにします。
京子先生のすごい!エピソードをもうひとつだけ。
我が家にはわたしに負けないくらい帽子好きの夫がいるのですが、彼の夏帽体を制作中、かなり派手なリボンをつけようとしていたときのこと。
「ご主人のお顔立ちでしたら、もっとシンプルなリボンがいいと思いますよ」と京子先生が助言してくださり、細いリボンに変更したら、まさにその通りで。濃い顔の彼には、あっさりしすぎてるくらいでちょうどよく。

太いリボンだったらきっとイマイチでしたよね。
先生は夫とは数回しか会ったことがない上、助言いただいた時、夫はその場にいたわけではありません。それなのに、夫のことを思い浮かべながら適切な助言ができるって、ホント神業だわ!と思いました。
京子先生の鳥の巣帽子にはもちろん到底及びませんが、わたしも「鳥」と「森」を表現した帽子をつくったことがあります。それが2009年『帽子まつり』のアート作品として出品した帽子。
新婚旅行で行ったコスタリカの森の奥深くで見た、世界で一番美しい鳥・ケツァール。

ケツァールの住む「雲霧林」の深い緑の葉ときらめく光に、ケツァールの食べるリトルアボカドの実を散らしてみました。
こうして振り返ると、帽子の勉強を続けることができなかったことのさびしさがこみ上げてきます。

コスタリカに行くときに、ハチドリなど野鳥柄の帽子も作りました。
国内でかぶる勇気はなかなか持てませんが(笑)
中等科の途中で引っ越してしまったので、わたしは初等科しか修了していません。でもいつかまた帽子づくりを学びたい、という想いは心の奥に持ち続けています。
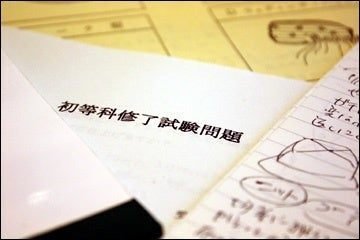
もし、この記事を読んで「面白い」「役に立った」と感じたら、ぜひサポートをお願い致します。頂いたご支援は、今後もこのような記事を書くために、大切に使わせていただきます。
