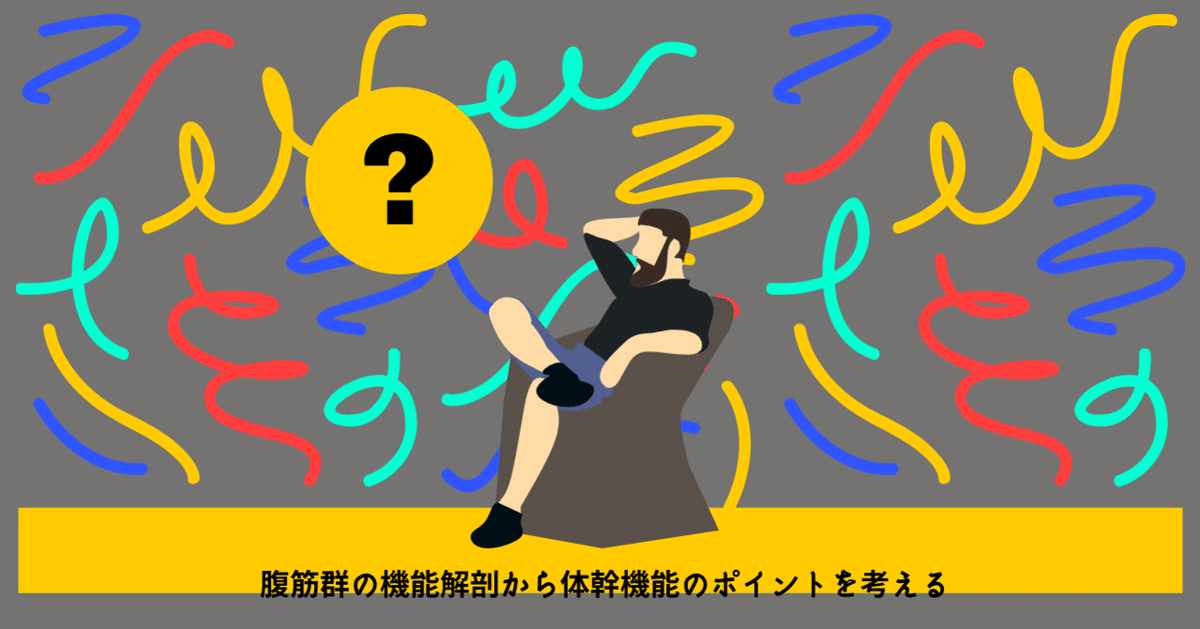
腹斜筋群の機能解剖から体幹機能のポイントを考える
火曜日ライターの松井です!
圧迫骨折や腰椎椎間板ヘルニアなどの体幹機能障害を伴う疾患、それ以外の上下肢の疾患においても体幹の機能障害を伴うことは多いですよね。
そんな症例に対して、体幹の運動療法を取り入れることがあるはずですが、思考停止で臥位で上体起こしやドローインをしていませんか?
明確な理由があってそれを実施するのであれば問題ありませんが、何となく実施して効果があまり出ていないにもかかわらず継続するのは考え直さないといけません。
では、体幹機能障害を改善するにはどんな運動が適しているのか?臨床ではどんなことを考えるべきなのか。
今日はこの疑問について解説していきます!
体幹を構成する筋群を知ろう
いわゆる上体起こしで働くのは腹直筋です。
ですが、日常生活で上体起こしのような運動形態で腹直筋を働かせることってそんなに多くはないですよね。
唯一、起き上がりがそれに近いかなという感じです。
個人的に重要なのは腹斜筋群の機能。
腹直筋を働かせるにしても腹斜筋群の機能は重要なので、まずは腹斜筋群の機能解剖を復習しましょう。
<内腹斜筋>
横行上部繊維→起始:胸腰筋膜 停止:第10~12肋骨の下縁
横行下部繊維→起始:鼠径靭帯、腸骨稜 停止:腹直筋鞘
斜行繊維→上前腸骨棘、腸骨稜 停止:腹直筋鞘
<外腹斜筋>
斜行繊維→起始:第5~7肋骨の外側 停止:白線、恥骨結合前面、鼠径靭帯
縦行繊維→起始:下位肋骨 停止:腸骨稜
腹斜筋群と言っても細かく見ると、繊維が分かれており、それぞれ機能も異なるため、分けて考えることがポイントです。
内腹斜筋と外腹斜筋の違いは、外腹斜筋が第5肋骨まで付着するのに対し、内腹斜筋は第10肋骨までしか付着しないこと。
それも踏まえて、それぞれの機能を見ていきましょう。
ここから先は

リハ塾マガジン
臨床で感じるなぜ?を解決し結果を出したい人のためのWebマガジン。 機能解剖、生理学、病態やメカニズムの理解、そこから考えられるアプローチ…

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜
365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
