
教員が「暮らすように働く」としたらー心が軽くなる12例
私は50歳で25年間の教員生活を終え、新たな人生をスタートした、只今54歳主婦です。退職後の試行錯誤でやっと、Webライターとして報酬を得られるようになりました。
教員時の収入とはずいぶん差がありますが、それでも自分でゼロから稼ぐということを実現した今、自分を褒めてあげたいなあ、と素直に感じています!
さて、noteの投稿をスタートして2週目に入ったところで、私のプロフィール&ヘッダーにある言葉「暮らすように働く」のお話に入ります。ちなみにサムネイルの色はピンクからグリーンに変わりました。
タイトルにあるように教員が「暮らすように働く」のは可能です。いわば、自分のための働き方改革です。その理由も含めて今回は、「暮らすように働く」の意味、教員の働き方を変えるヒントを紹介します。これらすべてではなく、ご自身がやりやすいものをぜひ取り入れてみてください。
※ちなみに5000字を超えていますので、見出しの気になるところだけでもOKですよ。
まず、「暮らすように働く」の意味について一緒に考えていきましょう。
「暮らすように働く」とは?

「暮らすように働く」は、簡単にいえば「仕事と生活を分けない」ことです。そんなの無理でしょう?といわれそうですが…。ネットで調べると、意外に暮らすように働く人たちが存在していることがわかります。
その方々の言葉から推測すると、単に仕事と生活を分けない、という意味だけではなさそうです。生活の中に仕事を入れる、でもないし、仕事の中に生活を入れる、というのでもない…。私見ですが、生活と仕事と分ける意識すらなく、今を楽しんでいる、といった感じでしょうか。
「仕事」という言葉が示すように、事に仕える、というのは、もっと多様な見方や考え方があっていいのだと再認識できます。
在宅ワークや地域に根差した活動もまた、「暮らすように働く」の一種でしょう。コトやヒト、モノに仕えることを通じて日々の暮らしが豊かになっていくと感じる姿勢です。
そう、「姿勢」なんですね。「暮らすように働く」は、何か特別な場所に行ったり環境を変えたりして実現できるもの、といった狭い見方ではありません。
環境から影響を受ける自分ではなく、自分が自分を気持ちよくしていく姿勢とでもいいましょうか。ちょっと屁理屈かもしれませんが、私はそう解釈しています。
そう考えると、「暮らすように働く」といった姿勢は教員にも可能ですよね。私の教員時代、それが可能だと思う経験と「いい働き方をしてるなあ」と思う先生を拝見しましたので、今回はそのことをお伝えしようと思います。6つの視点(計12個)の方法や先生方の姿勢を紹介しますので、ご自身が取り組みやすいものをピックアップしてみましょう。
職場でも「家族」がそばにいるような感覚を持つ
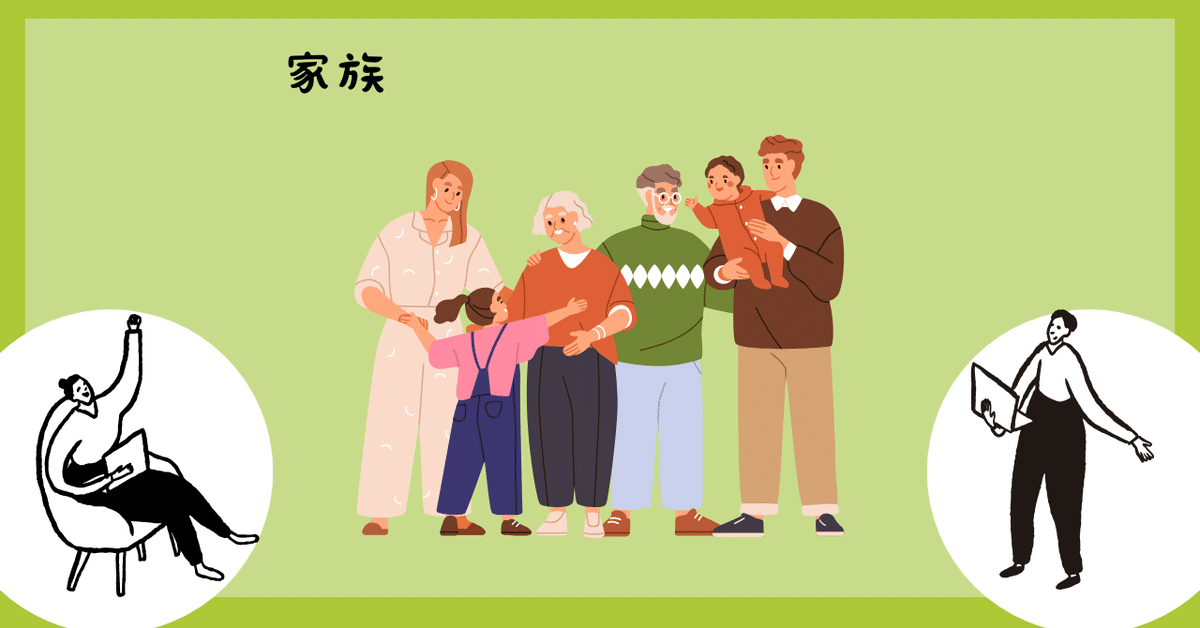
学校という職場ークラスの子どもたちや同僚、保護者と関わる場で、家族のような温かさや親密さを意識することで、「暮らすように働く」に近づけるかもしれません。
①子どもたちを「我が子」や「孫」のように考える
子どもたち一人ひとりの成長や悩みに寄り添い、彼らが家庭でも安心して過ごせるような環境づくりを目指します。まるで家族を育てるように、愛情を持って接する姿勢です。
こうした姿勢の先生は、結構多くいらっしゃいます。本当に子どもが好きなんだなあ、と羨ましく感じることもあり、決して職員室で子どもの悪口をいいませんでした。もちろん、同僚に対しても温かい接し方が印象的でした。
②同僚と「家族のようなチーム」を築く
同僚との日常的な雑談や、悩みを共有し助け合う関係性を育む先生も多く出会いました。私は、25年間を通じて比較的学年に恵まれていたほうだと思います。
そのなかでも、私を娘のように大切に、そして厳しくも温かく指導してくれた先生との出会い、互いの視点を共有しつつ兄妹姉妹のように学年の子どもたちを引っ張った思い出は今でも私の心にほっこりと存在しています。
職場が「もう一つの家」のような心地よさを持てると、仕事の時間が自然と暮らしに溶け込む感覚が生まれますよね。しかも、そうした学年経営で育つ子どもたちは安定します。
教室の雰囲気を居心地よくする

次に、教室をただの勉強の場にとどめず、居心地の良い「暮らしの空間」に変える工夫です。
③植物を育てる
植物が好きな先生は、子どもたちと一緒に観葉植物や花、野菜などを育て、教室に自然の息吹を取り入れます。植物があることでリラックスした空気が生まれ、生徒も先生も「暮らしている」ような感覚を持ちやすくなります。ただし、「子どもたちと一緒にやるのがストレスになりそう」と思う先生は無理しないでください。その場合は、一人で植物を育てていきましょう。
実際に、観葉植物やカラーが大好きなS先生は、教室の窓側に鉢をたくさん並べて大切にお世話をしていました。子どもに対してはどちらかといえば厳しい先生でしたが、愛情深く、問題児といわれる子も先生を頼りにしていました。
④季節感を大切にした装飾
季節ごとの飾りつけや、子どもたちが作った作品を定期的に入れ替えることで、教室が単なる学びの場を超えた「暮らしの空間」としての温かみを持ちます。これは子どもたちのためでもあるし、先生自身の楽しみでもあります。
私は、掲示物の作成や貼り替えが下手で、よその学級を見ては「○○先生は、本当に素敵に掲示しているなあ」と何度も思っていました。真似しようにも、なかなか難しいものです。
ただ、季節ごとの掲示、という点では自分でも少し取り入れるだけで、心が明るくなるのを知りました。子どもたちと同様に、大人もこうした楽しみ、エキスを教室に入れるのは「暮らすように働く」の一つの方法だと思います。
おしゃれを楽しむ

日常的な仕事の場でも、自分らしさや楽しさを取り入れることが、「暮らすように働く」姿勢につながります。なぜなら、いい暮らしは、自分の好きなものと関係しているためです。ここでは「おしゃれ」について取り上げます。
⑤服装や小物で自分らしさを表現する
教員という職業柄、ある程度の服装規定があるかもしれませんが、その中でスカーフやシューズ、文房具など、ちょっとしたアイテムに自分らしいおしゃれを取り入れることで、仕事がより楽しいものになります。
Y先生やK先生と学年をご一緒したとき、本当におしゃれで素敵な50代だなあと感じました。当時、私はアラフォーでしたが「50代になったら自分もそうなりたい」と思い、自身も服装には気をつけるようにしました。
特に小学校の先生方は、体育の時間以外はジャージを着ることが多いのですが、ある先生は体育のときだけジャージを着て、それ以外は明るい色のニットやブラウスにさりげなくネックレスを合わせているのが印象的でした。
また、文房具や小物に愛着を持って大切に使っている先生も素敵でした。子どもたちは意外にこうした先生方を見ているのですよね。おしゃれにしている先生というのは子どもたちにとって憧れであり、同時に温かさや楽しさを感じさせるものだと実感しました。
⑥教室に「自分らしさ」を反映する
先ほど掲示物の話をしましたが、教室のレイアウトや装飾に、自分の趣味や好きなものを少し取り入れることも「暮らすように働く」に近づけます。子どもたちにも「先生らしい空間」と感じてもらえる環境を作ってみるのです。
趣味のコーナーを作って子どもたちに紹介するのも良い方法です。たとえば、読書が好きならおすすめ本を紹介する場所を作ったり、手作りの品(羊毛アートや編み物などもOK)を置いて温かみを感じてもらったり。
自分の趣味や得意分野をさりげなく教室に取り入れ、子どもたちが興味をもてば一緒に楽しみながら学ぶ…といった空間を作ることが、より自分らしい教室づくりにつながります。
自分のペースを大切にする

忙しい教員の仕事でも、休憩や時間管理に自分らしさを持ち込むことで、暮らすように働く空間を実現できます。
⑦昼休みや休憩時間にお気に入りのティータイムを楽しむ
こちらは、もっとも取り入れやすい方法かもしれません。ご自身の好きなお茶やコーヒーを持参し、短い休憩時間を楽しむ習慣をつくるようにします。私は教員時代、忙しいなかでも20分休みや昼休みに必ず職員室に戻り、コーヒータイムをとるように「努めて」いました。戻られる先生方はいつも一緒でした。そうして気持ちを切り替え、教室に戻っていきます。
忙しい日々でも、そのひとときが気持ちを切り替え、リフレッシュする大切な時間でした。立ち飲みでも良いですが、できれば座ってゆっくりと味わいたいですよね。その際、家族やペットの写真、推しアイドルの写真などを眺めても誰も文句をいいません(いわせませんw)。
⑧終業後に趣味やリラックスの時間を確保する
仕事を終えた後に、趣味や軽い運動を取り入れることで、心のバランスを保つのも一つの「暮らすように働く」かもしれません。
家に帰るまでは「先生」とすれば、帰路に楽しみを設定しておくのも素敵な策です。なぜなら、「暮らすように働く」はその日だけでなく、翌日の仕事にも影響を与えるのですから。
実際にT先生はボーリングが大好きで、しょっちゅう帰路にボーリング場へ向かっていました。
このほかに「帰りに大好きなシュークリームを買って帰ろう」「たまには喫茶店でゆっくりしようかな」など、こうした小さな楽しみが、仕事を効率よく終わらせるモチベーションになり、心身のバランスを保つ手助けになります。
地域や保護者とのつながりをもつ

教員という仕事は、学校の中だけで完結するものではありません。先生方のなかには、地域の一員としての役割を意識すると、モチベーションを保つことができ、仕事が「暮らしの一部」となりやすくなります。
⑨地域の行事やイベントに参加する
私自身、地域学校の活動に参加した経験があります。最初は不安でしたが、実際に地域の行事に参加してみると、新たな発見がありました。
たとえば、地域のお店で買い物をしたり、地域のボランティア活動に参加したりすることで、学校外でも人々と自然に触れ合うことができました。また、地域のお年寄りや学習ボランティアさんとお話をした際には、教員としての役割を超えて、ただの一市民としてリラックスした交流ができ、自分自身の視点が広がるのを感じました。
このように、教員としてだけでなく地域の一員としての自分を見つけることも「暮らすように働く」ことにつながると考えています。
⑩保護者とフランクな交流を持つ
私は、保護者とのコミュニケーションを大切にしていました。たとえば、家庭訪問や面談の際に自分の子育て経験を話すことや、趣味の話を交えることで、保護者との距離が縮まり、最終的には信頼できるサポーターになっていただけました。
保護者とのやり取りは、時には難しいこともあります。フランクな交流は必要ないと考えてらっしゃる先生もいることでしょう。しかし、もしも「保護者さんと話しているほうが、なんとなくほっとする」と思っているとすれば、積極的にかかわることが「暮らすように働く」につながるかもしれません。
あなたの「暮らし」を仕事に反映する

自分が家庭や趣味で大切にしていることを仕事に取り入れることで、仕事と生活を分けない感覚が生まれます。
⑪趣味を授業に活用する
染色が得意なK先生は授業でこれらを活用することで、より楽しさを感じていました。そのほかにもギター演奏が得意な先生は集会で披露、陸上が趣味の先生はもちろん体育で自慢の足を披露、指揮が上手な先生は服装をバッチリ決めて登壇、木が大好きな先生は学校の樹木巡り…など。こうした授業の工夫は、子どもたちにも「先生が好きなことを教えてくれている」という感覚を与え、授業がより生き生きとしたものになります。教科書の進行だけにこだわらず、自分の得意なことを授業に反映させることも「暮らすように働く」姿勢だと思います。
⑫自分の子どもとの経験を教育に活かす
最後に「暮らすように働く」の一例として、自分の子どもとの経験を教育に取り入れることが挙げられます。
たとえば、子どもが小さいころ、一緒に絵本を読んで過ごす時間が大切なひとときでした。この経験を基に、授業で絵本を活用した指導を取り入れると、子どもたちも自然と親しみを持ちました。私自身も心が温かくなり、非常にリラックスできる時間となったのを覚えています。
さらに、子育てを通じて得た学びを保護者に伝えた経験も…。「先生もお母さんなんですね」と温かく受け入れていただき、保護者様と教員が一体となって子どもたちを支える感覚を実感できました。
今にして思えば、ですが、こうしたかかわりもまた、「暮らすように働く」の一つなのだなと感じています。
終わりに:「暮らすように働く」は自分ができる働き方改革
これらの工夫や姿勢を通じて、教員の仕事の中でも「暮らすように働く」という感覚を取り入れることが可能です。現実的な制約はあるかもしれませんが、小さな取り組みや考え方の変化が、仕事と生活のつながりを生み出すのではないかと思っています。
「働き方改革」といったネーミングはちょっと大きすぎて、上から降りてくるイメージがあります。「暮らすように働く」といった意識や姿勢は自分のなかから生まれるものですので、少しずつ、心豊かな働き方につなげていきましょう。
これからも、50代女性教員の先生方を応援していきます。
いいなと思ったら応援しよう!

