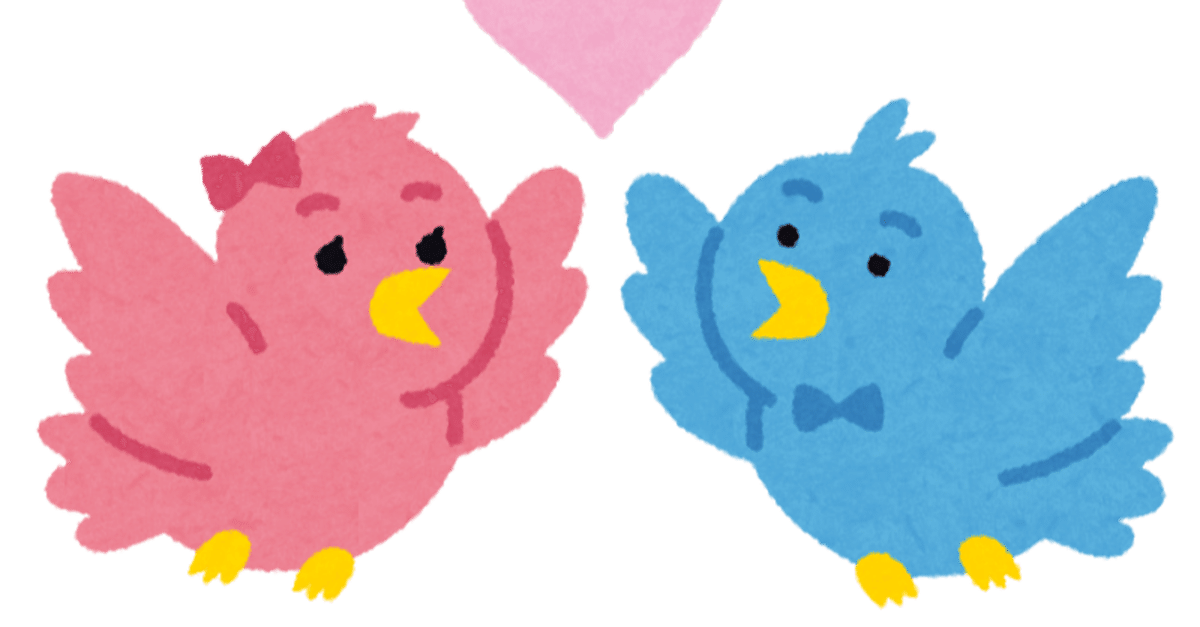
第1238回 赤い鳥と青い鳥 ⑴
①https://2.bp.blogspot.com/-difFRFE0bQ8/VxC3WyjpZCI/AAAAAAAA54c/mx3QSx4INfEm8Dge_9ApAf7qyU3tiIorACLcB/s800/bird_couple.pngより引用のイラスト
前回、前々回と野鳥の雌雄の見分け方をした際に、題名に載せるイラストを探していましたら、なぜだか、オスは青い色、メスは赤い色と決まっているように思われます。それでは、青い色と赤い色が雌雄を表すのかと言いますと、それはそれとして、この二色は自然界の野鳥に当てはまるとすれば、どんな野鳥が当てはまるというのでしょう。赤い鳥は紅色、赤茶色、朱色を赤色とし、青い鳥は藍色、群青色、青色とし、緑色のアオバトや、蒼色のアオサギ、アオバズクは含みません。
②-1.オオマシコ(体長約17㌢)

②-2.ベニマシコ(体長約15㌢)

②-3.ベニヒワ(体長約13㌢)

世界を見渡せば、エクアドルのスカーレットフィンチは真っ赤ですが日本には真っ赤はいないのですが、ただ同じアトリ科の野鳥の仲間に紅色や濃い桃色の種は日本にもいます。それは②-1.の写真のオオマシコで、鮮やかな濃い桃色または紅色です。また②-2.の写真のベニマシコは同じくオオマシコと身体の色合いが似ていますが、唯一のベニマシコ科らしいです。また②-3.の写真のベニヒワはあの怖い顔のカワラヒワと仲間のやはりアトリ科の仲間です。この赤系色はすべてオスです。
③-1.コマドリ(体長約14㌢)

③-2.アカヒゲ(体長約14㌢)

日本には真っ赤な野鳥は存在しないので、このような赤茶色ぽい色合いも赤い鳥ということになります。しかし、③-1.の写真の日本三鳴鳥のコマドリと③-2.の写真のアカヒゲの二種は共に近縁であると言われていますが、動物学者のシーボルトがあらぬことか間違えて、種小名komadoriは、本種とコマドリを取り違えて記載されたとされています。それだけこの二種の姿が、体色も似ていて、体長も約14㌢と似通っていたからだと思います。この二種はヒタキ科の仲間で、雌雄同色です。
④-1.イスカ(体長約17㌢)

④-2.ナキイスカ(体長約15㌢)

この④-1.の写真はイスカです。写真では確認することはできませんが、イスカの最大の特徴は、漢字表記が示すように「交喙」と書き、先が食い違ったクチバシを表して、その名前の由来となりました。イスカのクチバシは左右互い違いになっていますので、このクチバシを使って、マツやモミなどの針葉樹の種子をついばんで食べます。またマシコやヒワと同じくアトリ科の仲間です。同じく④-2.の写真はナキイスカです。二種の赤茶色の身体の色合いはやはりオスのみの体色です。
⑤アカショウビン(体長約27㌢)

⑤の写真はアカショウビンです。漢字表記は「赤翡翠」となります。対する青い鳥の代表格のカワセミの仲間です。青い「翡翠」のカワセミに対する身体の色合いがやや赤茶色の体色と、赤い趾(あしゆび)、凄いのはクチバシまでが朱色っぽい赤色という全身赤い色をした燃えるようなクチバシをした炎の鳥と言う感じがします。カワセミは水辺に生息していますが、アカショウビンは森林です。雌雄同色でヒタキ科のコマドリやアカヒゲと同じで、クチバシも身体も趾も全身赤竦めです。
