
第1811回 鳥の亜種って何だろう ⑵
①https://kokugo.jitenon.jp/word/p1073より引用の漢字の亜種
②https://bookvinegar.jp/3719/より引用の亜種の法則の専門書「亜種の期限」
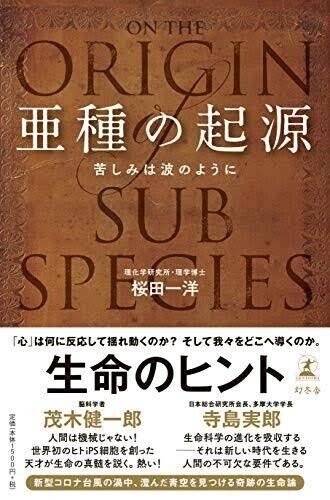
前回に続いて「亜種」のことを紹介致します。②のように専門書も出ています。「亜種」は地域的に隔絶した離島等で亜種が出現しやすく、例えば、キツツキの一種であるアカゲラは日本全土に分布しますが、離島を中心に数種の亜種が存在します。亜種が記載されている種では、必ず種小名と同じ学名の亜種が存在し、これは名義タイプ亜種、原亜種、原名亜種、基亜種等と呼ばれます。種記載のタイプ標本は記載の時に基準とされた個体を保存した標本に該当する亜種の事であり、分化の元となった原種という意味ではありません。
③https://study-z.net/100076254/2より引用の「グロージャーの法則」のイラスト

その亜種と本種の容姿には「グロージャーの法則」が大きく関わります。それはある種の恒温動物の中ではより湿った環境、例えば赤道近くにいるものほどより黒っぽい色をした形態が見られるという生態地理的法則です。この名前は1833年に気候と鳥類の羽色の共分散の調査でこの現象について述べた動物学者のコンスタンティン・ヴィルヘルム・ランベルト・グロージャーに由来します。この法則の日本における実証はシジュウカラやヤマガラ、ヒヨドリの身近な鳥にもあります。
④https://www.birdfan.net/2021/08/13/83049/より引用の身近なシジュウカラ(体長約14㌢)

④-2.https://antropocene.it/en/2019/09/21/parus-major/より引用Pの近縁種Parus majorシジュウカラ

最近では春だけではなく、一年を通して街中に見られるようになりました④の写真の亜種シジュウカラの他の日本の亜種は奄美大島、徳之島に生息するアマミシジュウカラ、石垣島、西表島に生息しますイシガキシジュウカラ、沖縄島、座間味島、屋我地島に生息するオキナワシジュウカラの三種がいます。今までユーラシア中部・西部・北アフリカに生息するParus majorシジュウカラの亜種とされていました日本のシジュウカラは最近になり「近縁種」であることが判明致しました。
⑤-1.https://www.birdfan.net/2021/04/09/81963/より引用の身近なヤマガラ(体長約14㌢)

⑤-2.https://www.google.co.jp/amp/s/kiden9173.exblog.jp/amp/27545698/より引用の交雑種ベンケイヤマガラ

⑤-3.https://ebird.org/species/vartit4?siteLanguage=jaより引用の日本の固有種の亜種オーストンヤマガラ

この⑤の写真のヤマガラは大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、北海道、本州、四国、九州、伊豆大島、佐渡島、五島列島に幅広く生息しているシジュウカラと同じくカラ類の仲間です。日本の亜種は神津島、新島、利島に生息します日本固有亜種ナミエヤマガラ、やはり西表島の日本固有亜種
オリイヤマガラ、八丈島、御蔵島、三宅島に生息します日本固有亜種のオーストンヤマガラと、実に日本の四亜種のうち三亜種までが日本の固有種です。ただベンケイヤマガラだけは交雑種です。
⑥-1.https://www.birdfan.net/2019/12/27/75995/より引用の身近な亜種ヒヨドリ(体長約27㌢)

⑥-2.http://www.y-mainichi.co.jp/news/29642より引用のオガサワラヒヨドリ(体長約25㌢)

⑥-3.https://zukan.com/jbirds/leaf127305より引用のアマミヒヨドリ

⑥-1.のヒヨドリはサハリン、朝鮮半島南部、台湾、中国南部、フィリピンの北部のルソンに分布する基亜種です。国内では留鳥と漂鳥に分かれます。元々朝鮮半島から越冬してくる冬鳥でした。⑥-2.の亜種オガサワラヒヨドリは小笠原諸島の聟島、父島、母島に生息。亜種ハシブトヒヨドリは
硫黄列島の北硫黄島、硫黄島、南硫黄島に生息。亜種ダイトウヒヨドリは大東諸島の北大東島、南大東島に生息。⑥-2.の亜種アマミヒヨドリはトカラ列島、奄美諸島の奄美大島、喜界島、加計呂麻島、徳之島、沖永良部島に生息。亜種リュウキュウヒヨドリは沖縄諸島の沖縄島、粟国島、伊平屋島、伊是名島、座間味島、久米島、宮古諸島に生息。⑥-3.の亜種イシガキヒヨドリは与那国島を除く八重山諸島の石垣島、西表島、竹富島、黒島、波照間島に生息。ヒヨドリは七亜種生息します。
