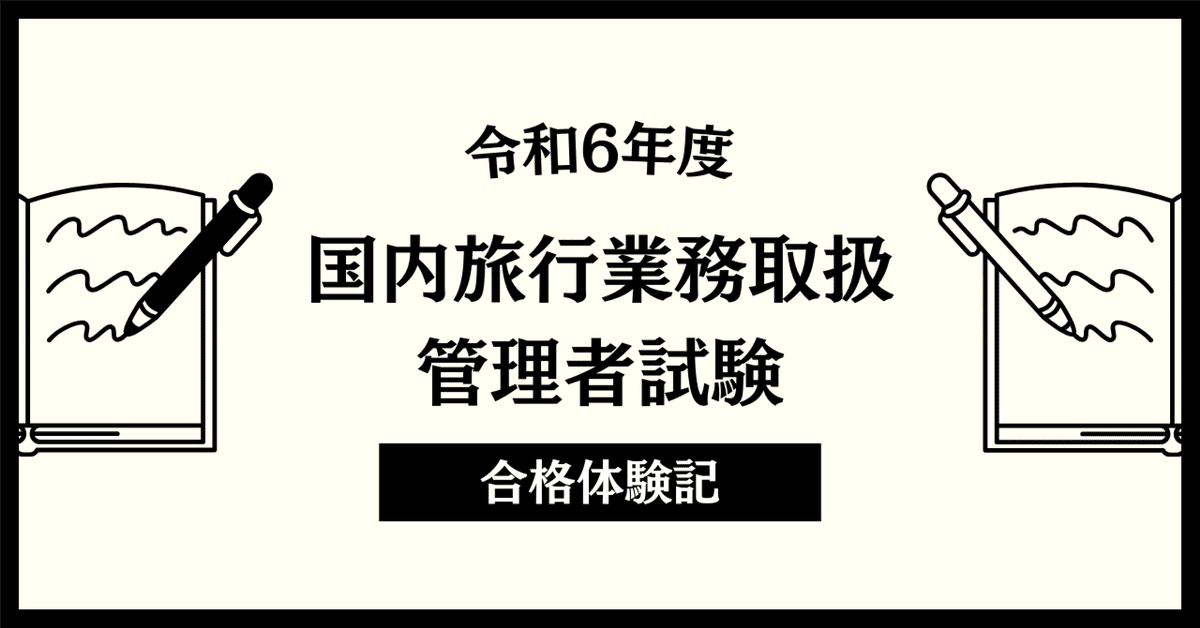
国内旅行業務取扱管理者試験の合格体験記と勉強法【令和6年度】
国内旅行業務取扱管理者。旅行業界における唯一の国家資格です。旅行業を営むにあたって営業所に1名は配置を行わなければなりません。
この資格は旅行業界へ就職を目指す学生や転職を考える社会人にとっては取得しておくと有利になることはでしょう。今回は国内旅行業務取扱管理者試験の取得を目指す方に向けて、初回で合格した勉強方法などを共有できればと思いますので、令和7年度に国家試験を受ける方の何らかのお役に立てれば幸いです。
<本記事の内容>
資格の概要、合格までの勉強時間、勉強に使ったテキスト、試験について(CBTや出題形式)各科目の勉強すべき内容等についてまとめました。長文にはなりますが、興味のあります方はご一読ください。
【旅行業務取扱管理者とは】
旅行業者や旅行業者代理業者は、営業所ごとに一定の資格を持った旅行業務取扱管理者を選任して、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせなければならないと、旅行業法で規定しています。この旅行業務取扱管理者になるためには、一定の欠格事項に該当しない人で、国家試験(旅行業務取扱管理者試験)に合格する必要があります。
※ちなみに受験資格は定められていませんので基本的には誰でも受験可能です。ただし、過去に不正等を行った者は除きます。
※海外旅行を取り扱う営業所には「総合旅行業務取扱管理者」が国内旅行のみを取り扱う営業所には「国内旅行業務取扱管理者」主たる営業所所在地の隣接市町村が範囲の場合は「地域限定旅行業務取扱者」が必要です。(総合旅行業務取扱管理者は国内旅行も取り扱えます。)
合格までの勉強時間(国内旅行業務取扱管理者試験)
ネットの情報を調べてみると合格に必要な時間は100~200時間とバラツキがありました。200時間の勉強時間を理想の状態とし、最低でも100時間は勉強しないと勝負できないと思い、まずは100時間を超えることを目標に考えました。
勉強時間の管理は「Studyplus」のアプリを使用。無料でしたし、操作も簡単そうでしたので使ってみることにしました。試験日までのカウントダウンとか、国内旅行業務取扱者管理者を目指すユーザーもいたので、同じ目標に向かっている仲間がいる安心感、フォローしているユーザーが勉強時間積み上げていく投稿を見て「やらなきゃ」という気持ちが呼び起こされました。(勉強していない時期は通知を見るのが苦痛でしたが・・・)
9月23日の試験日までの総勉強時間は約110時間。自分の中での最低ライン100時間はクリアしているものの、理想とする200時間には到達していなかったので少し不安でした。
国内旅行業務取扱者管理者試験の合格率
毎年1万名前後受験し、合格率は30~40%程度です。
令和6年度:31.4%
令和5年度:35.7%
令和4年度:32.9%
令和3年度:40.9%
(※3科目受験、科目免除なしの場合)
国内旅行業務取扱管理者試験 試験科目と合格基準等
試験科目:
①旅行業法及びこれに基づく命令(100点)
②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(100点)
③国内旅行実務(100点)
・運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
・旅行業務の取扱いに関する実務処理
合格基準:①②③全科目で60点以上の点数を取得すること。1つの科目でも60点以下となると、他の2科目が高得点でも不合格となります。
科目免除:③「国内旅行実務」が合格基準に達した場合は、翌年度試験に限り科目免除の制度があります。(※①②は科目免除はありません)
令和6年度の国内旅行業務取扱管理者試験の受験結果(私の結果)
私自身の国内旅行業務取扱管理者試験の試験結果は・・
①法令:80点
②約款:84点
③国内実務<運送・宿泊>:32点
④国内実務<観光地理>:38点
(③+④=70点)
300点中234点と少々、国内実務に苦戦したものの合格することができました。
実際の勉強スケジュール(各月ごと)
勉強スケジュールを紹介いたします。勉強教材としてはユーキャンの通信教育講座を使用いたしました。1月頃にはテキスト等が届いたのですが、3月まではまともに手をつけていませんでした。
<月毎の勉強時間記録>
4月:12時間
5月:15時間
6月:7時間
7月:10時間
8月:17時間
9月:45時間
※抜け漏れあると思います。
9月に追い込みをかけて、なんとか合格ラインに乗せれた印象です。6月7月は明らかに停滞していました。(やりたくない病・・)
国内旅行実務の「JR運賃と料金」の勉強にモチベーションが上がらず・・でした。国内地理の勉強は楽しかったし、旅行業法の法律も勉強は苦ではありませんでしたが・・JRと国内航空は最後まで勉強がキツかったですね。
最後にモチベーションを高められたのは、来年もまた同じ勉強を・・と想像すると「キツいなあ」と思いましたので「なんとか今回で決める!」という気持ちがラストスパートの燃料となりました。
当初の計画では平日30分、土日4時間ずつで月間40時間、約4ヶ月で合計160時間と考えていましたが、全く予定通りにはいきませんでした。
勉強教材(ユーキャン)
先ほど申し上げましたとおり、勉強教材はユーキャンの旅行業務取扱管理者講座(通信)をメインに使用しました。実際に資格を取得した方に聞いたところ、ユーキャンで合格したとのことでしたので、申し込みました。
<教材>
メインテキスト5冊、国家試験問題過去問(4年分)、JR運賃・料金表、添削課題(テキスト毎)等
WEB学習も対応で、講義動画やWEBテスト等を使うことができました。法改正情報も都度、送付してもらえたのは助かりました。(国内地理の時事ネタなども)
多少の出費はかかりますが、効率的な勉強につながり、勉強時間の削減につながると考えたら選択肢としてはありかもしれません。
私はテキストを読んで覚えられるタイプではなかったので、テキストにマーカーや赤線を引きまくったり、ルーズリーフに書いて書いて書きまくって覚えました。
ある程度、内容を覚えましたら、実際に問題を解いて実践力を高めるよう意識しましょう。特に間違った問題や関連する事項等の+αは重要です。そして時間を置いて、再度、暗記し定着させる・・
人間は忘れる生き物ですので、忘れた頃にもう1回問題を解いてみたり、暗記作業を行ったりと、とにかくしつこく暗記に努めましょう。
勉強教材(その他)
①「一発合格!国内旅行業務取扱管理者試験テキスト&問題集」
こちらのテキストも購入いたしました。ユーキャンのテキストはわかりやすいのですが、サイズが大きく、全5冊と持ち運びを考えた時にかさばるので、持ち運び用として活用しました。
コンパクトで1冊で全範囲をカバーしていることと、暗記に便利な赤シートが付属していたので、出張の時の移動時間や空き時間に読んだり、暗記したりする時に使いました。
②その他(国内地理関係)
図書館で「まっぷる」等の各県ごとの旅行雑誌を借りて読みました。写真が豊富ですし、おすすめコースなども掲載されていますので、自分が観光に行くなら・・と想像して読むことで頭に入りやすいです。
このようにテーマ毎(国立公園)にまとめられている雑誌も便利ですね。楽しみながら読めます。
国内旅行業務取扱管理者:試験について
令和6年度からは紙形式からCBT試験(Computer Based Testing)へと変更されました。試験会場に用意されたパソコンを使用して受験を行ういます。慣れていない人は戸惑うかもしれません。
試験日も9月上旬~下旬と好きな日程を選ぶことができましたので、勉強スケジュールの進捗が不安でしたので9月後半を試験日に選びました。
マウスのみの使用で、キーボードは使いませんので邪魔に感じる場合は端にどけておきましょう。紙と筆記用具は会場で用意してくれました。(※使用した紙は持ち帰れません)耳栓も用意されていました。使用するかどうか迷ったのですが、途中、会場の空調音が気になりだしたのと、周囲のマウスのクリックのカチカチ音が気になってきたので耳に突っ込みました。
(※どこの会場でも用意されているかどうかは不明です。)
(※持参品等は(一社)全国旅行業協会からお知らせメールが届きます。本人確認証は必須です!)
試験時間は120分です。問題文の誤りを探したり、JR等の計算問題もあるので集中しないといけません。試験前日の一夜漬け等、睡眠時間が短いと正直、最後まで集中力が持ちませんので、試験前日はちゃんと寝ておいた方がよいかなと思いました。(前日、一夜漬けにならないような計画的な勉強スケジュールを・・・)
CBTの注意点として、問題文に書き込みとかできません。後から見直す場合には、また1から問題文を読む作業が発生します。
問題毎に「後から見直す」にチェックを入れる機能はありましたので、例えば、問題5を後から考えようと思った場合にはチェックしておくと、チェックをつけた問題に戻ることができます。
試験時間は120分全て、使い切りました。基本は順番通りに解答し、気になる問題は「後から見直す」にチェック。JR等の計算問題の前に国内観光の問題を解きました。最後にJR等の計算問題を解き、事前にチェックを入れた「後から見なおす」の最終確認を行いました。
(解き方は自分のやりやすい方法で・・・)
時間配分を覚えるには一度、模試等の実践形式(または過去問)で全通しで本番試験と同じ時間を使って解くとよいと思います。
CBT試験かつ受験日が人によって異なるためか、皆が、全く同じ問題ではなかったようです。試験内容は後日、公表されますが「試験問題(例)」と記載されていて、実際に見てみると私が解いた問題と違う問題もありましたので、多少はランダムに出題されているようです。
出題文の形式
①旅行業法及びこれに基づく命令②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
・「誤っているもの(該当しないもの)」「正しいもの」を1つ選びなさい。→こちら両方ありますので見間違わないように・・
・時々「すべて選びなさい」と複数選ばなければいけない問題もありますので、見落とさないようにしましょう。
③国内旅行実務:運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
・バス運賃等、フェリー運賃等、宿泊料金等、JR運賃等の計算問題等がメイン。(航空運送は購入期限等を問う問題も。)
③国内旅行実務:旅行業務の取扱いに関する実務処理(※国内地理)
・該当する答え(正しい・誤り)を1つ選ぶ形式
・複数選択する形式もあります。
・モデルコースの完成させるために空欄を1つ埋める(選択する)形式
国内旅行業務取扱者試験:科目別詳細
ここからは、試験科目の概要についてご紹介いたします。全てを詳細に記載しますと膨大な量になりますので、ざっくりとしたメモ書き程度のものとなります。ご容赦ください。
【1】旅行業法及びこれに基づく命令
配点:問1~問25(配点4点×25問)合計100点
旅行業法や施行規則等となります。条文の正確な解釈や用語の理解を求められます。
旅行業法の目的を考えましょう。何のためにこの法律があり、誰(何)を対象にしているのか?この法律を守ることで、どんな便益が想定されるか(トラブルを防げるか)
・どんな業務を行う場合に旅行業の登録が必要か?
・旅行業者代理業はどんな業務ができるのか?(できないのか?)旅行業者との違いを正確に覚える。受託契約や旅行サービス手配業とは?
・旅行業務の登録制度:第1種、第2種、第3種、地域限定の4種類。業務範囲や対応エリア、登録関係:基準資産額、有効期間、更新登録、変更、取消・抹消等
・営業保証金制度:営業補償金額、供託、還付、取り戻し
・旅行業務取扱管理者:職務範囲、兼務、研修、欠格事由、証明書
・営業所での標識、旅行業約款(認可、掲示、備え置き)
・取引条件の説明と書面の交付:書面の記載事項と企画旅行契約、それ以外、旅行相談業務契約の記載事項等の違いを把握する。
・外務員:定義や外務員証、権限
・企画旅行の広告:表示のルール(旅行代金の表記、サービス内容、最小催行人数・・・)
・旅程管理:措置や免除のルール
・受託契約:委託旅行業者、受託旅行業者、受託旅行業者代理業者・
・旅行サービス手配業:登録申請先、登録、書面の交付
・旅行業協会(日本旅行業協会、全国旅行業協会):業務内容、権限、弁済業務保証金(納付日、供託、還付、弁済限度額)
・禁止行為や罰則等:禁止行為、業務改善命令(どこまでの範囲で強制力があるかを理解)罰則(旅行業違反:懲役や罰金額)
【2】旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
配点:問26~問50(配点4点×25問)合計100点
・標準旅行業約款を中心に勉強。(ウェイト的に重要です。)企画旅行契約(募集型・受注型)をしっかりと理解する。手配旅行契約との違い、旅行相談・・
■標準旅行業約款:5つの契約の部と特別補償規程
①募集型企画旅行契約の部
②受注型企画旅行契約の部
③特別補償規程(別紙)
④手配旅行契約の部
⑤旅行相談契約の部
⑥渡航手続き代行契約の部
(※⑥は国内旅行業務取扱者試験では出題されません)
・用語や言葉の定義、契約関係、書面(契約・確定)が必要なケース、交付期限等(いつまでに通知するか?)
・契約の変更・取消や解除について。
・旅行には天災等のやむを得ない事由、オーバーブッキング等の旅行者の責によらない事由を含め、トラブルやイレギュラーが想定されます。その場合の対応義務や責任、補償等について把握しておきましょう。(自分が旅行業者や旅行者になった場合を想像する理解しやすいかもです。)旅行に関する費用が増額した場合に、旅行者の負担にできるケース等
暗記が必要な数値もありますので頑張って覚えましょう。
例:契約解除の場合は○日まで(宿泊と日帰りで違う)取消料が旅行代金の○%等
・特別補償(怪我、物品の補償)に対する補償金や見舞金。支払われないケースは?
・損害賠償(特別補償との関係性、重複支払いがない・・)
・旅程保証(補償金:オーバーブッキング)
→どんなケースの場合、変更保証金が必要なのか?(宿泊機関・運送機関等)
・「旅程管理」の義務と責任
・契約の成立、変更、解除
■運送約款・宿泊約款
国内旅客運送約款(ANA・JAL)、貸切バス約款、フェリー標準運送約款、JR旅客営業規則、モデル宿泊約款
<国内旅客運送約款>
航空券の予約、有効期間、払戻し、「大人」「小児」「幼児」の年齢区分→※JRやフェリーとごっちゃになることも・・・違いを正確に覚える。
手荷物(持ち込み制限や賠償責任)
<モデル宿泊約款>
宿泊契約(申し込み・解除等)料金関係のルール(時間外室料、子ども料金)寄託物及び異駐車の責任
<貸切バス約款>
運送契約(申し込みや変更)乗車券、運賃や料金、違約料
<フェリー標準運送約款>
旅客の定義、手回り品、賠償責任、運賃及び料金:大人と小児、自動車航走の運転手、手荷物関係、乗船券(有効期間、払戻し)乗船変更のルール
<JR旅客営業規則>
乗車券(発売日、有効期間、途中下車、変更、紛失、払戻し等)、団体旅客、料金の種類、手回り品、割引運賃
【3】国内旅行実務<運送・宿泊>
配点:(1)運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金:問51~問61(配点4点×12問)合計48点
令和6年度試験の配点内訳
・JR運賃と料金:24点
・国内航空運賃等:8点
・宿泊料金計算:4点
・貸切バスの運賃計算等:8点
・フェリー運賃の計算等:4点
JR運賃等の配点が高い傾向です。ネット等のつぶやきでは「国内航空運賃を諦めて・・」の声もありますが、イージーな問題が出たらもったいないので、基礎的な部分や暗記等の最低限の対策は行っておきたいところです。
とにかく計算問題に慣れておくことが重要です。問題をたくさん解いておきましょう。
<JR運賃と料金>
・年齢による区分は「大人・小児・幼児・乳児」の違いは確実に暗記しましょう。無賃適用となるかどうか。計算問題を解く上で必要となります。
・端数計算のルール、営業キロ・換算キロ・擬制キロ。幹線と地方交通線を連続する場合。JR本州3社とJR3島各社(北海道、四国、九州)をまたがる場合。営業キロ等の通算と打ち切り、運賃計算の特例(山の手線や特定都市市内発着)
・運賃の割引:往復割引、学生割引
・料金:計算の原則(1列車毎)、小児の取り扱い(半額になるケースと大人と同額になるケース)
・特急料金の計算:シーズン区分(通常、繁忙、再繁忙、閑散)530円引きとなるケースをしっかりと把握します。
・寝台料金(寝台の同時利用)、個室利用料金。
・新幹線の特急料金:通算できるケース、通しで差額が発生するケース、グランクラス、JR各社にまたがって新幹線を乗り継ぐケース(例:東海道新幹線+山陽新幹線+九州新幹線 等)
・西九州新幹線(かもめ)と特急(リレーかもめ)、山形新幹線と秋田新幹線
・乗り継ぎ割引(※2024年3月に廃止で試験対象外となりました。)
・団体旅客:種類や適用人数、受付期間、割引率、運賃・料金の無賃扱い
・乗車券の有効期間、途中下車、変更、払戻し(手数料と計算)
(※運送約款で出題・・ですかね?)
<国内航空運賃・料金>
旅客の年齢による区分「大人」「小児」「幼児」(※JR等と若干異なるので混同しないようにする)無賃扱いの対象、年齢により単独搭乗ができないケース(大人の同伴が必要だったり)
・JALの運賃
フレックス、セイバー、スペシャルセイバー等の種別を把握する。
予約変更ができる運賃種別とできないもの。航空券の予約と購入期限(期限:数値を覚える)取消手数料(出発時以降、出発時刻まで、○日前等)
・ANAの運賃
FLEX、VALUE、SUPER VALUE、往復ディスカウント、購入期限、取消手数料(JALとの違いも含め把握する)
<宿泊料金>
・宿泊料金の計算:追加料金やサービス料、消費税、入湯税、宿泊税、子供料金
・契約変更と解除(違約金)団体客の契約解除
・時間外の客室利用
<貸切バスの運賃・料金>
・時間制運賃(点呼点検時間も含む)、キロ制運賃、深夜早朝運行料金、交代運転者配置料金、
・端数処理(JRとの違い)
・違約料(○日前で○%、車両の減少)
<フェリーの運賃>
・年齢による区分:「大人」「小児」無料となる場合
・自動車航送運賃、
・割引や払い戻し
【4】国内旅行実務<観光地理>
配点:(2)旅行業務の取扱いに関する実務処理:問62~問84(配点2点×26問)合計52点
一夜漬けでは対応できないので日々、コツコツと覚えましょう。テレビやニュースで気にとめたり、観光雑誌を読んでみたり、YouTubeを見たりと楽しみながら覚えるとよいと思います。1番いいのは直接、観光地に行くことですが、時間がかかるので観光雑誌を読みながら、もし○○県に行くなら○○に行こうと実際に旅行計画を立てるつもりで見るとよいかなと思います。
<国内地理>
・日本国内の観光資源
・国立公園
国立公園内にどんな観光資源があるか?何県が含まれるか(飛び地的なものもあり)
・国定公園(国立公園と比較すると出題頻度低いです。余裕があれば・・)
・世界遺産
構成資産の把握や登録年度の把握が必要です。奈良の世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」と「古都奈良の文化財」の違い、古都京都の文化財:延暦寺(京都府だけでなく、滋賀県も含んでいたり・・・)
・ラムサール条約
・祭りと年中行事→何月に開催されているか?○○三大祭り
・陶磁器(瀬戸焼やら○○焼き)や織物(結城紬やら○○焼き)漆器(輪島塗り・・)木工品(樺細工・・)金工品、その他の工芸品(鳩車、山鹿灯籠→地名が冠にあるものは覚えやすいですね)
・郷土料理(ルイベ・・)ふなずし、柿の葉寿司、めはり寿司。寿司系は混同しやすいですね。
・重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)例)角館(秋田)-樺細工-みちのく小京都→関連して覚える。
・宿場町(妻籠宿-長野と馬籠宿-岐阜 等)
・文学作品:温泉地とセットが多いですね。「雪国」川端康成-越後湯沢温泉(新潟県→県名もセットでちゃんと覚えましょう)「不如帰」徳冨蘆花-伊香保温泉(群馬県)、「二十四の瞳」壺井栄-小豆島(香川県)等
・観光ルート(モデルコース):近接観光地を把握する。
例えば、北海道内での位置関係の把握等。問79:どちらかというと消去法:函館-○○-昭和新山。別エリア(遠距離)ではないか?等
・美術館:大塚国際美術館と大原美術館(混同しやすいかもですね)
・温泉:暗記するのが大変でした。
・山:あやかり富士、○○最高峰等
・小京都、奥座敷、三景等
・城:別称も把握しましょう。姫路城-白鷺城
・湖:十和田湖(乙女の像)と田沢湖(たつこ像)
○○川、滝、高原、○○節、吊橋、○○峡、寺、神社、遺跡、古墳、岬(○○の最南端とか)、公園、庭園、○○像、島、○○半島、国宝、○○湾
○○街道、○○が建立した寺、菩提寺。
・三大○○:三名園、三名泉、三名橋、三景
・東洋の○○:ナイアガラ(吹割温泉)ナポリ
・時事問題(大河ドラマ等)
国内旅行業務取扱管理者試験について(所感)
試験内容の概要は、上記の感じです。ざっくりこんなことを勉強するんだなという気持ちで見ていただきますと幸いです。より詳しく・・という方は国内旅行業務取扱者試験対策のテキスト等を購入し、確認していただければ幸いです。
上記の内容を全て暗記しないと試験に受からないと重圧を感じる必要はありません。(合格ラインは6割ですので)
大事なのはイージー問題を取りこぼさないことです(問題の読み違い等のケアレスミスをしない)
例えば、確実に解ける問題が5割程度だとします。
残りの5割については、難しい問題でも、4つの選択肢(正答を選ぶ)のうち、確実に2つの選択肢は間違いと気づける力が備わっていれば確率的に75点は取れるということです。完璧を目指す気持ちは大事ですが、完璧主義を貫くには鋼のメンタルが必要ですので、100点満点じゃないと絶対にいけない。ではなくて「勝負できるレベル」に到達させるんだ。という気持ちを持つことでモチベーションの維持と学習や試験挑戦の離脱を防ぐ心の持ちようかなと思いますのでご参考までに・・
学習曲線 ~勉強時間と点数は単純に比例しないのでは?~
例えば、80時間勉強したけれども、模試解いても全然、合格ラインに達しない・・という焦りが生まれることもあるでしょう。結果、モチベーション低下に・・・
私、個人の主観ですが、点数は勉強時間に比例するのではなく特定のラインを超えた瞬間に急速に上がるのでは?と思っています。
イメージ的には80時間までは4割5分しか取れなくても、120時間超えたら急に8割、9割に到達しだした・・と爆上がりのボーナスタイム的な。そういう経験がある人もいると思います。
上記の話は、私のN=1の体験でしかありませんが、理論的に「学習曲線」(エビングハウス)として提唱されているようでした。(下記リンクをご参考に)
<学習曲線>
①停滞期:伸びを感じない時期
②第2発展期:伸びを実感する時期
③第3発展期:さらに伸びる時期
それぞれの期の中に「準備期」「発展期」「高原期」とあるようです。
要するに、なかなか伸びない我慢の時期をモチベーションを落とさずにどう乗り越えるか?あと少しで発展期に入るかもしれないのに諦めてしまう・・ともったいないことにならないようにしましょう。
あと○時間勉強すれば発展期かも・・と粘り強く頑張りましょう。
国内旅行業取扱管理者の職務
国家試験に合格した場合は「国内旅行業務取扱者」は旅行代理店等でどんな仕事をするのでしょうか?職務についても記載しておきます。
「旅行業務取扱管理者」の職務(旅行業法施行規約第10条)
旅行に関する計画の作成
料金の掲示
旅行業約款の掲示及び備置き
取引条件の説明
書面の交付
広告に関する事項
企画旅行の円滑な実施のための措置
旅行に関する苦情の処理
契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
上記に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
国内旅行業務取扱管理者試験の受験のきっかけ(動機)
ここで少し、受験のきっかけについてお話を。
旅行業関係の仕事をしているわけではありませんでしたが、まちづくりや観光に興味があること。(地方のまちづくりには観光事業は必須科目?)
学生時代は、あまり観光や旅には興味がありませんでしたが、最近は日本で訪れたことがない観光名所を巡ったり、一人旅等で面白いホテルに泊まったり、時にはゲストハウス等にも泊まるのも面白いなと感じること。
そして、会話やテレビを見るなかで、日本の地理や観光資源をあまりにも知らなさすぎて、少し恥ずかしいなと感じたりすることもあり、一念発起して国内旅行業務取扱管理者試験にチャレンジしてみようと思ったのがきっかけでした。
国内旅行業務取扱管理者試験を受験して ~今後の展望も含め~
長文にお付き合いいただき感謝申し上げます。受験しての感想はしっかりと時間をかけて暗記して、過去問で出題傾向をつかむ、問題を解き慣れておく等の対応を行うなどのしっかりとした努力をすれば合格できる試験であると思います。
合格のための勉強時間確保(社会人)やモチベーションの維持が重要でしょう。このやり方については人それぞれかなと思いますので、自分にあったやり方を見つけて頂ければと思います。
現在、旅行業に従事しているわけではないのですが、地域活性化やまちづくりにおいて観光事業は重要ですし、私どもの法人で保有する施設やメニュー等に観光資源として活かせるものもありますので観光商材を開発していく等の事業にも活かしていければと思います。(着地型観光商品)
2024年のインバウンドの状況は観光庁の資料によると、コロナ前の2019年の消費額、約4.8兆円を2023年は約5.3兆円と上回り、2024年4月-6月期の消費額は四半期で約2.1兆円とこのペースでいくと約8兆円と拡大しています。
(参考:「我が国観光産業の現状と今後の展望」(PDF)観光庁・令和6年10月)
国としても「成長戦略の柱」「地域活性化」の切り札として掲げていることからも観光事業は成長産業、明るい未来への可能性としてより注目される分野でしょう。
私も資格取得を機に、なお、いっそう地域や日本の観光分野に関わっていければと思います。
