
ピアノ三重奏曲ト短調『ヤタガラ殺陣師崩れ』
この作品は、私にとって「重要ないくつかの意味がある」作品ですので、語っても良いなと思える範囲で語っていきます。
スマートに “ゲンダイ” を実現できたと思える
以降、いわゆる現代音楽のことを「“ゲンダイ”」と言い換えていきます。
理由はソレが「現代の音楽」とは別概念になっちゃったからです。
これは特段、説明しなくても分かってもらえますよね。
私は「現代の音楽」は、普通に流行のポピュラー音楽だと思っていますし、「現代音楽」という言葉を先述 “ゲンダイ” が専有してるのって変だと思うので、使わないようにしているのです。
◆
私がこの作品の初稿を完成させたのは、大学を卒業して間もなく、地元に帰る直前くらいのことでした。
自信作なのですが、かなりのハイスピードで書き上げたことを覚えています。自信作の9割って、勢いで完成した系なんですよね。
例外的な「時間をかけた自信作」の一つは、『雨脚の強い日には』です。
↑ 素敵なアートワークは、にきゃく 様の作品です。
【作品URL(Tumblr)】 【X】
この曲は、大学1年生の時にはもう冒頭が出来ていて、初稿が4年生になるまで完成しませんでした。そして改稿したのが、2022年の梅雨のことです。
最も制作期間が長い作品ですね。
◆
話を戻して『ヤタガラ殺陣師崩れ』は、私の作品の中で最も「コンセプト先行で、システマチックに作り上げることのできた・そして気にも入った」作品です。大抵この3つの内のどれか(特に最後)が上手くいかない。
制作工程の話題の前に、このタイトルが何なのかを気にならせているのが申し訳ないので、釈明します。
この曲は、いわば減算的発想によって構築されている。~中略~
曲名は山根明季子『ハラキリ乙女』と、太鼓の達人の『鳳凰天舞無限崩れ』のオマージュである。
うろ覚えですが、初演時(卒業後の共同自主企画コンサート)のプログラムノートです。
なのでタイトルは「語感」です。
ただし「カラス」という生き物は、私にとってはやや重要な存在なので、後述します。
ちょっとこの曲の楽譜は、おいそれとタダでは見せたくないやつなので、文章でしか説明できませんが、この「減算的発想」とは何かを説明します。
◆
ソースは明確ではなく申し訳ありませんが、こういう逸話があります。
分厚い管弦楽法の著書と、ゴジラの劇伴で有名な伊福部 昭 氏の作品に、『リトミカ・オスティナータ』というピアノ協奏曲があります。
当時は十二音技法からトータル・セリエリズムなど、「12のピッチクラスを均等めに使う」ことがブームだった時期のちょい後くらいに当たるみたいですが、伊福部 氏はそれを受けて「じゃあ自分はメイン旋律を、半分の6つのピッチクラスのみで作ろう」と言って、件の曲になったらしいです。
◆
私もこの作品の主題旋律を、G Bb C# E F F# の6つだけで構築しました。
さらに、ごく短い前奏の次に来る主題は8小節ありますが、その後半部分は(最後の1音だけ削られることを除き)前半の逆行形(≒逆再生)です。
すごく省エネに作ることが出来たモノです。
そしてこの曲は、やたらと主題をリピートして、主にピアノが受け持つ伴奏だけが変化していく…というエリアが多くを占めます。これらどうやって作られたかと言うと、はじめに「1拍ごとに違うコードを付けておいた」んです。そこから音を間引いていき、バリエーションを作りました。
つまり「和音から重要な構成音が欠けることによって、異なる和声あるいは和声進行であるかのように聴こえたりする」ことを狙いました。
でも既に出来ている所から削っていくだけなので、それらのバリエーションを量産するに当たって、ほとんど「創造」はしていないわけです。
黒色の音楽
ここまで語ってきた通り、私は極めてシステマチックに、パズルでも遊ぶような感じで、楽しんでかつかなり効率厨的にこの曲を書き上げました。
しかしそれとはまったく別に、この作品は私の作曲(あるいは創作全般)に対する哲学の、非常に重要な根幹部分を体現できている作品であります。
◆
一方でこの作品、「複数の音楽ジャンルの要素を、高密度でごちゃ混ぜにしたような音楽」であると描写できると思っています。
曲種と編成はクラシック(ピアノトリオ)
音細胞もとい「コードの一つ一つ」は、よく見るとジャズ
やたらとユニゾンが多い楽器法は、古典的かあるいはロック
楽式は言うなれば「変奏形式」の要素がある(しかも「旋律は一定で伴奏が変化していく」のは、古い時代の変奏曲)
3拍子の部分と遅くなる中間部のメロディ構築や、ピアノの伴奏フレーズのリズム面の発展のさせ方は、ジャズの即興手法が参考元
速いテンポの「四つ打ち」感は、何なら「トランス」のつもりです。
途中、三味線音楽やら落語をイメージした部分すらあります。
で結局、皆さまこの曲を「何」だと感じましたか?以上の内のどれか?
人それぞれですので、全員が全員、私の狙い通りとはいかないでしょうが、第一印象は「“現代音楽”」じゃありませんでしたか?
ここ、誘導は良くないことなので、違った場合は以下 聞き流して下さいね。
◆
私は大学在学中、かなり “ゲンダイ” の気持ちが分からない側の人間でした。だからこそ、何かを理解したくて居続けた一面はあります。
私がその “ゲンダイ” に対する批判あるいは忠告として、最終的にまとめた一文(3文)があります。
「明快」である必要は無い。ただし「明瞭」であった方が良い。
「不明瞭」には、「不明瞭」というたった一種類の属性/個性しかない。
なぜなら真摯な観察(鑑賞)行為を困難にさせているから。
もしも皆さんが作曲当事者であるとして、もう少し自分語りよろしければ、以下の私からのアドバイスを聞いて行って下さいませ。
たとえどのような順番で、どのようなアプローチで色を混ぜていったとしても、「混ぜれば混ぜるほど黒に近づいてゆく」のは 誰がやっても 同じ。
「ゲンダイ音楽ってどれも同じに聞こえる」という言い回しが示唆する、人が各々感じ取る「ゲンダイ音楽っぽさ」というものの実態は、この『黒』の感じ のことを指しているのではないか。
「特定の色を混ぜない」という判断・英断によって、色は鮮やかな個性を維持する。
それはもう「棲み分け」の世界です。
これって別に舞台を「西欧芸術音楽」にしなくても、ポピュラー音楽でも言えることです。例えばですけど、バンド編成にピアノ、ブラス、ストリングス、全部 入ってる曲って、私は食傷気味です。どれか抜いたらいいのにと思います。
そういうのが「プロフェッショナリズム」として “定着” した世界線がここなのかもしれないけれど。
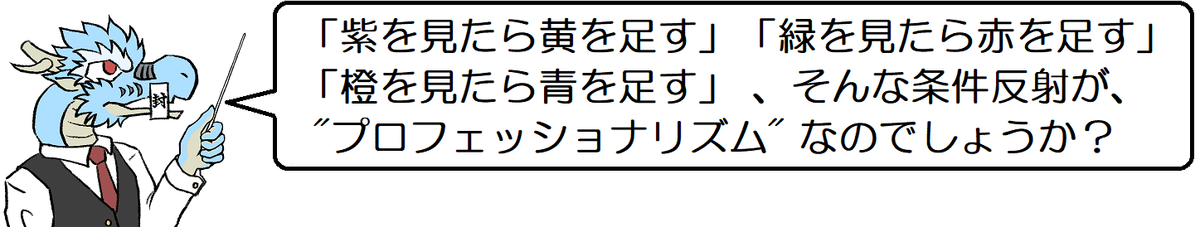
◆
私はこの曲を、現実の目的としては「“ゲンダイ” 感を効率よく獲得する」目的で制作したと言えます。
そしてその中身として「自分の個性を追い求めて、来る日も来る日も色々な音楽を・色々なジャンルやスタイルを吸収していったら、結局 作れたのは “よくあるゲンダイ音楽” の一つでしかなかった」…というストーリーを織り込んだのです。(というか「織り込むことに成功した」という感じの感覚ですが。)
私はそれを、その悲しみの黒を、カラスという生き物に投影しました。
傷は繕い 粧すといえど
どうにも不揃い 鴉の尾羽
所詮 行く宛ない道すがら
募る慚愧も 血染めの嘘も
真黒に鎮めて 返り咲く
どの道 己等は出来損ないの
緋に塗れた 伊達殺陣役者
風に破れて 一片の
血飛沫あげて 溝に臥す
塗(まみ)れた 伊達殺陣役者(だてたてやくしゃ) 一片(いっぺん) 溝(どぶ) 臥(ふ)す
フレーバーテキストとして作っただけの詩歌ですが、これは「“一流” にはなれなかった者」の描写です。足りなかったのは己の才能か、はたまた時の運でしかなかったのか、夢破れた者の哀歌です。
ちょっと当時の『BLEACH』の作中に出て来た単語が偏ってダマになってる部分があってアレなんですけど、意味で選んでるから変えようも無かったんや。京楽隊長の卍解と兵主部の裏破道ね。
私はこの曲を、意図して「黒色の音楽」として制作した…に近いです。
実際には「結果オーライ」の構図でしたけどね。楽しかったです。
「スマートに・省エネに」の話に戻りますが、特殊奏法も比較的メジャーなもののみ。ややこしい拍子も冒頭とラストだけの最低限です。
一度「あ、そういう音楽ね」と認識させてしまったら、あとは別にそれらで満たさなくても良い、と考えました。
曲の半尺以上を占めるメイン主題は、およそGマイナーキーであると言い張れる6ピッチクラスのみ。コードも概ねはジャズの響きで、理屈的には(複調はあれど)「無調」からも程遠いはずです。
「ただ極度に高密度なだけの調性音楽」だと断言できるテクスチャですよ。
あと話の都合上、「ただのよくあるゲンダイ音楽」のような言い方をしてきましたが、ぶっちゃけ本当の所、「ただのよくあるゲンダイ音楽」だとは私は思っていません。
こんなにノリノリで「“明快”」な趣味のゲンダイは、私はあんまり見かけないです。だからもうゲンダイとは認められないのかもしれないですけど。
ゲンダイにまったく無理解な層からは「ゲンダイか」と切り捨てられ、逆にゲンダイに染まりきっている層からは「こんなのは芸術音楽ではない」と蔑まれる。そういうラインを目指しました。
ドロップアウトした者の、薄汚いカラスの羽のようなゲイジュツです。
結局、ゲンダイ音楽の肝なんて、表面的な「ゲンダイっぽさ」でしかないということを彼ら自身に自己証明させてやれるなら、私としては充分です。
だから、この曲は、「ロック」です。
既存の価値観への問題提起、現代アートってそういうものでしょう。
もしも私の ”自信作” がご趣味そうなら、以下3作もおすすめしております。
雨は音楽じゃない(ピアノ独奏)
無彩色の空(ピアノ独奏)
シシマイ・ヰノヴェーション(クラリネット四重奏)
