
「アレンジ」に初挑戦する方へ #夏休みアレンジ祭_in_2024
注意:
確かにこの記事は、あべし様 主催「#夏休みアレンジ祭 in 2024」にちなんで書きますが、飽くまで個人的な執筆であり、筆者はイベント企画側とは無関係の人間です。
☑ 企画へのご質問は、公式Discordサーバーの「質問」スレッドなど、然るべき窓口へして下さい。
まず、企画参加者ではなくこの記事へ迷い込んだ方へ。
この記事は「音楽作品のアレンジ」のお話です。
そして全読者様へ。
この記事の内容は、一般論的な話と、「アレンジ祭」企画特有の話との間で揺れ動く、いうなれば「板挟みになる」ようなトピックを展開します。
もちろん「初参加者の皆様の役に立つこと」を目的として綴るものです。
「それもアレンジという営み」「それこそがアレンジという営み」という心持ちで、ご覧いただければ幸いです。
まず過去アーカイブでも観ろや
↓ 私の2回目参加時(※まず他の方が作った原曲が流れます。)
↓ 私の初参加時(※まず他の方が作った原曲が流れます。)
※本当に変拍子は好んで書きません。
数少ない変拍子ある過去作(歌詞共作含む)→ ◇ ◇ ◇ ◇
「アレンジ」というワードのダブスタ性
「ダブルスタンダード」のことですね。
別に堅い話をしたいわけではなく、↓の動画の最後にちょろっと言及したことなのですが、皆「アレンジ」と一口に言うが、明確に意味合いが2種類に分かれます。
――「原作者の意思を汲んで♡」という場合と、「めちゃくちゃにして♡」という場合とで、使 い 分 け が さ れ な い という謎のワードなので、互いに忖度が必要です。――
「原作者の意思を汲む」必要がある場合の “アレンジ” とは、例えば
・ピアノソロ → オーケストラ
・協奏曲(主にオーケストラ+ソロ楽器) → ピアノ伴奏+ソロ楽器
・ポピュラーの歌モノ曲 → 吹奏楽
・コード譜(メロディ+コードネーム) → 本アレンジ・製品版アレンジ
・クラリネット四重奏 → サックス四重奏
・クラリネット六重奏 → クラリネット五重奏
例示は無際限にできるのですが、以上の架空の事例に「共通していそうなこと」が、わかるでしょうか。 ※忖度して下さい。
🔹
🔹
🔹
答え方は一つではありませんが、
「編曲物を、“使う(利用する)” 予定がある」
「原曲のままでは、“使えない(利用不能な)” 状況下である」
「原作者あるいは依頼者に “代わって”、編曲してあげる形である(協力)」
「アレンジ祭」の場合は?
もちろんなんですけど、違います。
「皆が原曲を作り、皆がアレンジをやる」ということは、
「アレンジ行為そのものがメインで、主人公」なんです。
そう受け取って良いはずです。
「アレンジをするために → 原曲を用意する」
「アレンジで」遊ぶお祭りを皆でやろう、という企画です。
不要不急のレクリエーションです。
🔹
そうではなく「原作者の意思を汲む “アレンジ”」 の場合、原則的にはですが、編曲者は「自分を出す」ことをしない方が良い。
つまり編曲を通して、あまり “自己主張” をしない方が良い。
「求められていないこと」だと考えられるからです。
この場合「求められていること」は、別にある。
例えば「クラリネット六重奏→クラリネット五重奏」という編曲の場合、依頼主はきっと「原作者が既に “その曲の五重奏ver.” を用意」していたら、編曲の依頼などしなかったでしょう。
同様に「ピアノソロ→オーケストラ」という編曲は、原作者が自らオーケストレーションを施す意思と、知識と時間を持っていたら、同じくその編曲が、他人に頼まれることは恐らく無かったはずです。
「協奏曲→ピアノ伴奏+ソロ楽器」の場合なら、恐らく依頼主であるソロ奏者は、「オーケストラは流石に用意できないが、その曲を演奏したい」のでしょう。
単なるイメージですが、「仕事に徹する職人」に喩えられると思います。
その編曲の内容は、もちろん「編成の制限による改変」は多かれ少なかれ織り込まれるでしょうが、その行為には「必要性」による裏付けが求められます。
逆に編成的に「自由度が増す」編曲の場合、その逆プロセス、「原作者がもしもこの編成だったらやっていただろうこと」「この編成ではなかったから、原作者が我慢したこと」を読み取って実現するようなのが、名編曲となります。画像拡張生成AIみたいですね。
だから、かなりのインテリが要求される行いです。
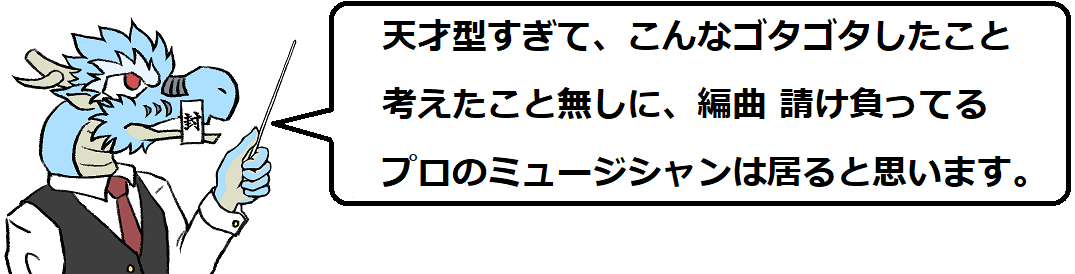
分かってて頼んでます。良く言えば、信頼の問題です。
アレンジ祭、困っている(原曲サイド)
皆「アレンジで遊びたい」んです。
原曲サイドであなたの全身全霊を出しすぎても、アレンジの余地を狭めるだけかもしれません。
「自分の曲のアレンジ可能性」について、ちょっと考えてみましょう。
こう言うとざっくりし過ぎ(後述)なのですが、「シンプルである方が、アレンジの余地が広い」です。
Q. 曲の長さは決まってる?
A. 30 ~ 1:30 を推奨しています。
Q. どんな曲でもいいの?
A. 何でもOKですが【メロディがハッキリした曲】の方がアレンジ時に楽しめると思います。
私は初参加時、原曲は48秒でした。
素材がいくつか提示されているなら、【フレーズを繰り返す】【構成部分を並べ替える】【スローテンポに変える】などして、原曲尺よりも長くする方法はいくらでもあります。
🔹
入れ知恵
しかし私から「自由過ぎても難しい」というヒト向けにお節介をするならば、前述「【メロディがハッキリした曲】の方がアレンジ時に楽しめる」に関して一つあります。
「シンプルな方がアレンジし易い」は、確かに正しそうに見えます。
しかし、例えば「ドミソ(CEG)だけのメロディ」というのは確かにシンプルなのですが、
コード(和音伴奏)を別物に変える手法・「リハーモナイゼーション」の観点からは、「ドミソ」が全て出揃っている区間は余りにも「C△(Cメジャー・コード)」を主張しすぎていて、「コードで遊ぶ余地は狭まっている」とも言えるのです。
もちろん余地は存在します。
Am7、F△9、Fm△9、Dm11、F△7/G(G13sus4)、
E7(+9, -13)、Bb7(9, +11, 13)、A7(+9)、Eb7(-9, -13)、C7、F#7(-5, -9)
もしもドミソだけのメロディばかりの原曲が回ってくると、コードで遊ぶタイプのアレンジは選択肢から外し、リズム面など他の要素で「遊ぶ」ことになるかもしれません。
このような実例を考え始めると、「“シンプル” にも色々ある」というトピックに関しては、一考の余地があると言えます。
↑「one note」は流石に嘘なんですが、結構メロディが棒の曲。
🔹
その意味で、先の【メロディがハッキリした曲】の「ハッキリ」とは、「音楽的性格のことを言っているのではない」と思った方が良いでしょう。
「メロディがあるんだか無いんだか・どれが主旋律なんだか分からないような曲」は、アレンジ側が悩むに加えて、「聴く皆もアレンジの中身が分かりづらいよ」という旨の文章だと思います。存在感のハッキリです。
アレンジ祭、後悔している(原曲サイド)
「参加しなきゃよかった…」じゃなくて、
「提出しちゃったけど、あの原曲で良かったのだろうか…」ね。

もしも「明白な問題点がある」モノだったならば、運営からの指示があり、早めに再提出になるはずです。
そうなっていないのならば、恐らく「チェックした人にはアレンジの可能性が見えている」か、あるいは「その程度のヤンチャさの原曲は、過去にも提出されていた」ということでしょう。過去アーカイブを観て待ってよう。
🔹
それでも、この記事を読んだせいで「あれは適切じゃない」とどうしても感じる上、それを他人がヨシ!と言っても気持ちが収まらないヒトは、次回から上手にやりましょう。
少なくとも今回の曲も、禁則事項は破っていないんですものね?
恐らく「既にチェックが済んだ原曲」の自発的な再提出は、運営サイドにご迷惑をおかけすることです。
想像もしなかった、あなたのボキャブラリー外からの思わぬ名アレンジが返って来ることを、楽しみにする方が良いです。
そんな経験は、ものすごくアレンジの勉強になります。
【次回予告】アレンジ祭、困っている(アレンジ側)
どう困っているのかを、まず切り分けます。
・自分には耳コピが難しすぎる(MIDIやコード譜も同封されていなかった)
・アレンジの方向性が思いつかない
・やりたいアレンジはイメージできているが、実現できそうにない
・とにかく原曲が強すぎて自信喪失している
次回の記事へ続く。
