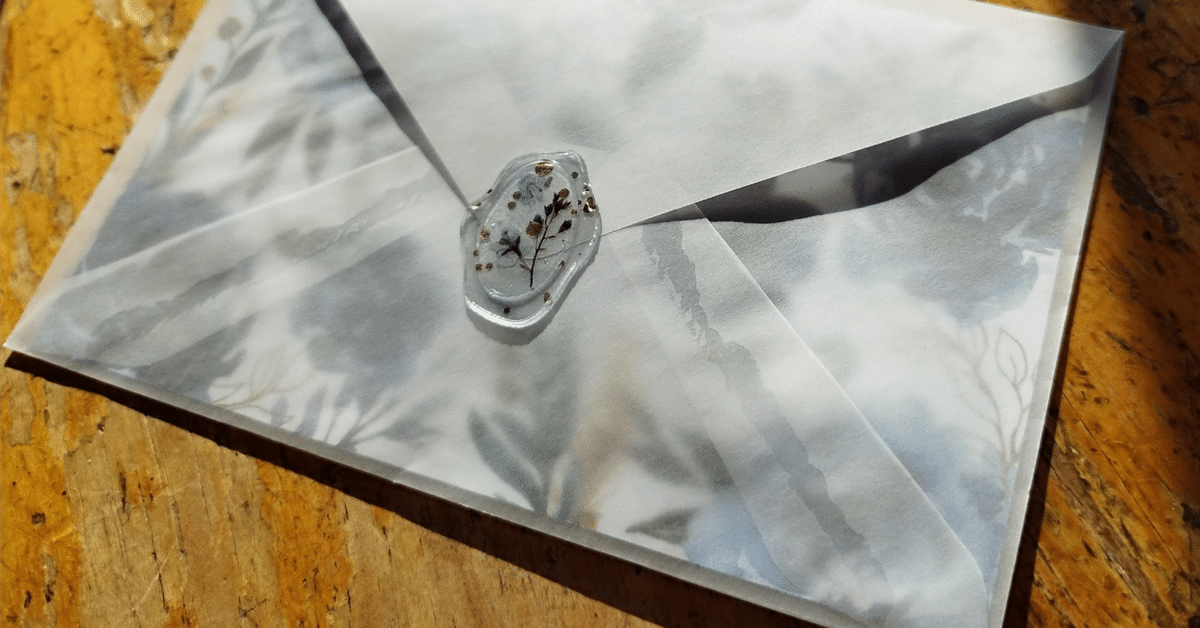
【小説】『一人巣窟』3/6
未読の方はまずこちらから↓
(6回中1回目:約2700文字)
良い匂い、なのかもしれないが所詮は煙を、どうして吸わずにいられないのか時に高い値を支払ってでも買うのか、自分にはまだ分からなかったけれど、部屋に落ち着いたならまず一服吸って、隣に寄り付いて来る者に、差し渡してその者が口を付けるまでを眺めてから、おもむろに自分に向き直ってきた。
『カナヤ。今日は何ばして過ごしよった?』
「何せ私の屋敷には、常に二十人から三十人ほどの、若か者が暮らしよって、外に張らせよった者に、彼等がまた使い回しよる者までを含めたなら、常に百人、二百人規模が働いておりました。どこぞに消えた者もおれば、補われて入る者もおる。私は顔も名も、知らんずくじゃった者もおるでしょう。一生の間にさて、どれだけの者と関わり合うたかは、もはや数えも切れません。家の内側におる者ば、ただ食わせてやるだけでもひと苦労じゃ。まともな家業にならん事は、傍の目にも明らかじゃったて思いますよ」
返された煙管にまた、口を付ける。
「私の命令通りになぞ動かし切らん事も」
目の端に見やった顔が、急に老け込んだ気がしたが、もちろん煙管などここには無い。手帳に目を落とし今走り書いた語句を眺める。
「貴方の命令ではないのですか?」
「はい」
「つまり、貴方の思い通りではないと?」
「ええ」
「しかしながら世間では、一般的には皆貴方の、思うままに動かされていたと」
「ああそいは世間では、そがん思うでしょうしまた、言うでしょうな。ばってん私の実感ば言うたなら……」
赤茶色の長い髪を、隣から撫で下ろされるままにしている。
「雑巾となん、変わらんです。やれお前、あっちば拭け、次はこっちば磨けと、あっちゃこっちゃに連れ回されて、泥なり汚物なりば身に染ませては、時々水に浸されてまた、絞られる」
時々うるさげに、振り払っても、一向に利いてくれないからもう諦めているのだと、隣に目線を送ってはうそぶいていた。
「傷んですり切れて、糸もほつれた穴だらけになって、もう使い物にならんて棄てられた、そがん感じですな」
「誰から、ですか」
「誰て」
クックッと、隣の者と揃った笑い方をしてくる。
「誰か一人ば名指しして呼べるごたるものでも」
「それなら、貴方一人と大差無い。そうでしょう」
穏やかそうな笑みが消えた。もちろん白髪は短く刈られている。対面の椅子に改めて、背筋を伸ばし気味に深く座り直してくる。
「もうちっと、はっきりした話し方ばしていきましょうか」
「ええ」
「胸ん悪く感じられるかもしれませんが」
「ええ。構いませんよ」
「左様ですか」
一つ、大層な息をついて、はっきり聞こえたわけではないが腹の奥まで深く吸い直してから言ってきた。
「私は実のところ誰一人、この手で殺してはおらんとです」
浮かべてきた笑みに合わせて、こちらでは、笑みを消しておく。
「しかしながら、殺さんば自分達が殺されてしまうごと、周りの者達ば脅かしたり、涙ながらに心配したりしてみせました。
私は誰からも、何一つ奪ってはおらんとです。しかしながら家に持ち込まれる金品に、喜んだり礼を言ったり、器量の良か娘ば連れて来てくれた者には、皆より良か待遇ば与えたりしてやりました。
誰の、何ば、どげんしろと、私の口から具体的に、言うてやった事は一度も無か。しかしながら皆が私のために、皆の好いたごと、懸命に悪か事ば考え出してはせっせと実行に、移してくれました。人というものは誰かのためなら、言い換えれば、自分のせいにだけはならんなら、まぁどがん事でも考え出して、やり遂げてくれる。
男でん女でん、構わず私の床に招き入れましたが、自分達からどうぞと、差し出しに来る者に限りました。そいだけでもまぁ不足の無かくらいにはおりましたからな。腹の内に、どがん思惑のあってかは知りません。そいで思惑の違うたからと言うて、不満ば述べられる道理も無かでしょう。
不思議かもんで、皆、『なにとぞよしなに』、とひと言笑ってみせた程度で、いつどこの、何の話ばしよるもんか、私がすっかり心得てくれるもんと思い込みよる。そがん者には毎日腐るほど、出くわすとにから。そいこそ私は、人でしかなか。神でも悪魔でもなか身ですけん、はっきり口にも出されんごたる願いなんぞ、聞き届けられんでも仕方なか。
さらってくる中で、無体な真似ばし出す者は、そいは、おったでしょうな。しかしながら致し方が無い事と、放っておりました。そいば苦にしてまだ一銭にもならんうちに、自ら命ば絶ってしまう者もおりましたが、一方できれいに諦めのついて、売られた先のむしろマシになったごと、思うてくれる者もおりましたから。
中には売られた先で、よっぽど水の合うたとでしょう。頭角ば表して、名ば轟かせた者に、立派な奥方に収まり切れた者もおる。私の事ば名指しして、事もあろうに」
一旦うつむいてまた、笑みを強めた顔を上げてくる。
「『お父様』と」
こちらは頬の端が引きつるのを、わざわざこらえないままにしておく。
「『命の恩人じゃ』と、『故郷の、家の内におったところで、口減らしに殺されるばかりじゃった』と、感謝の手紙ば書き送ってくれる者も、中には、おるとです。
もちろんそがんした者は、ほんのわずかな、たった、ひと握りに過ぎません。そのたったひと握りで全体が許されようとも考えてはおりませんが、誰の目に、何が幸せに成り得るかは、他の者の目には分かり切らんというひとつの、証にはなりますな」
「そんな幸せは……」
溜め息と同時に飛び出した口調は、多少なり抑え気味に持って行った。
「幸せと果たして言い切れるものかどうか……」
「汚らわしか。忌み嫌われるべきだとさぞ、お思いになるでしょうな」
「そこまでは……」
と濁しながらも向こうから、わざわざ言葉に変えてもらえたなら、こちらの気は随分と収まるものだとも感じていた。
「しかしながらそれを手にした者達にとっては、他の誰の目に、どう見えようとも、紛う方無き確かな、唯一の、幸せです。どのような中にあっても生き抜いてみせるという強い意志は、何より美しく、尊いものだと私は、考えております」
言い切るが早いかうつむいて、クックッと笑い出す。
「それに比して、何ですか。『名誉のために死を選ぶ』、ですか。これは。私はまったく好かんですな。ああ実に、醜かもんじゃ。反吐が出そうじゃ怖気を振るいますな」
それでもやはり言い終えて、ひとしきり笑いも納めた後で、向こうには、あの固まる癖が表れた。
いいなと思ったら応援しよう!

