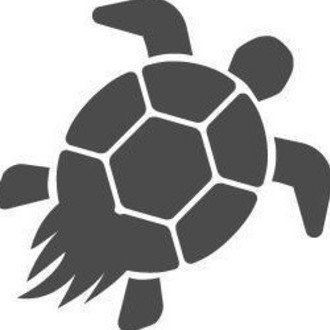Shibuya Startup University に参加しました
少し時間は経ってしまいましたが、去年の9月から4ヶ月間かけて、スタートアップ関連の講義を受けてきました。
その名も Shibuya Startup University (以後 SSU と記載)です。
Shibuya Startup University とは?
本プロジェクトは、内閣府が進めるスタートアップシティ構想に基づき、渋谷区が中心となり、渋谷区参与である鈴木寛氏(東京大学教授/慶應義塾大学教授)を学長に迎えて2021年に開設されました。渋谷区初のスタートアップ領域に特化し、世界で活躍できる人材や事業創造を目指した実践型教育プログラムです。(上記より引用)
育成プログラムでは
- 毎週月曜日に講義を受ける
- チームを組んでプロダクトを考える
ことを行いました。
参加した理由は?
たまたま目についた広告で、渋谷区出身ということも相まって興味を持ったのがきっかけでした。笑
参加者は30名ほどで、
- エンジニア
- デザイナー
- ディレクター
- 学生
と多彩なバックグラウンドを持った人たちで溢れていました。
これらのメンバーが、それぞれの野望や展望をプレゼンし、チームを組んでいきます。
チーム構成
自分たちは3人のチームを組みました。

メンバー
- エンジニア(自分)
- デザイナー
- 学生
です。
みんなのやりたいことを英語で短く表現し、チーム名にしました。
To the world
To the universe
Together
3つのTo × 英語のTriple = Toriple
という造語のチームにしました。
(ちょっとDeNAの名前を意識していたり笑)
考えたビジョン
スタートアップの講義では、プロダクト作りの前に信念が大切ということがあり、思想が共感するもの同士で上記のチームを組みました。
最初のプレゼンで自分が掲げた思想は以下でした。

これをチームで再構築して、以下をビジョンとして掲げました。

これらの信念を元に、プロダクトを考えていきました。
考案したプロダクト

「行政の書類がオンラインで出来ないのは大変だよね?」という発想から、それをテクノロジーで解決できるプロダクトを考えました。

裏側で自動化できるプロダクトを考案し、プロトタイプを実装しました。

AWSの資格を持っていたこともあり、実際にプロダクトを組むのに役に立ち、今回の講座とは関係なく良い経験になりました。
フロント側は本業であるアプリをしっかりと実装しました。

フロント・サーバー・インフラと一人でフルスタックにやる経験はなかなかないので、とても大変で時間もかかりましたが、それなりに楽しかったです。
終わりに
講義はとても面白い内容で、自分の知らない値観感を学ぶことができました。また、ここで出来た仲間も大変面白い人たちが多く、実際の仕事面でも繋がりができ、大変有意義でした。
良い面だけを書いていますが、参加するにはプライベートの時間を割く必要があり、かなり体力が必要です。毎年、行われるそうなので、興味がある方は次回の応募に参加してみてください。
いいなと思ったら応援しよう!