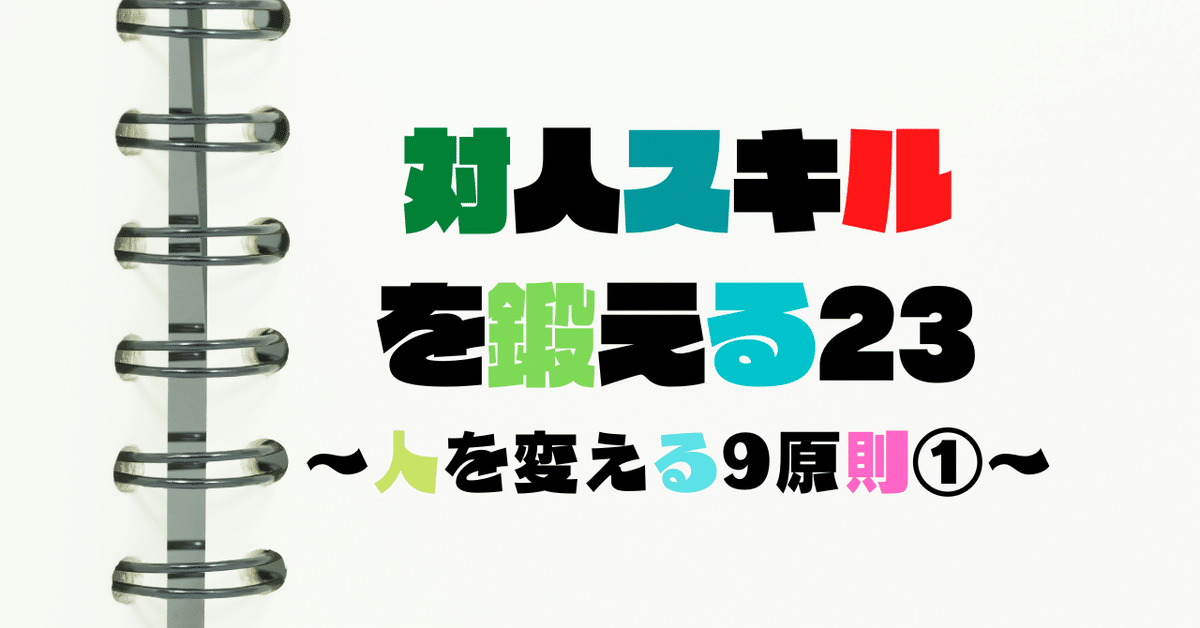
人に変わってほしければ、まずほめることから
対人スキルを鍛えたい私とあなたのために、
この本からの学びを少しずつあなたとも共有していきます。
人間関係にお困りの私とあなたのお役に少しでも立てれば幸いです。
この本では、対人スキルを鍛える方法が
1.人を動かす3原則
2.人に好かれる6原則
3.人を説得する12原則
4.人を変える9原則 (←今回の記事はココ)
の30原則にまとめられています。
今回から、「人を変える9原則」の1番目について書いていきます。
どういうことか、さっそく見ていきましょう。
1.「まず、ほめる」→言いたいことはその後で

我々は、ほめられたあとでは、苦言もたいして苦く感じないものだ。
人と関わって仕事をしていると、どうしても、相手に注文したいことが出てきます。
教頭という仕事をしていると、先生たちや事務の職員さんに、やってもらった仕事に対して、修正をかけたり、やり直しをお願いしなければならないことがあります。(すごく心苦しくなるのですが…)
担任時代であれば、指導という名のもと、子どもたちに注文をつけることがよくありました。(これが仕事だとばかりに、意気込んでいたかもしれません…。)
そんなとき、これまでにいっぱい失敗していて、相手に動いてもらえなかったり、反感さえ抱かせてしまうこともありました(^^;
一方、うまくいった時は、今を思えば、この「まず、ほめる」が意識できていたからかもしれません。
先生たちや職員さん、あるいは子どもたちの、日頃の感謝やねぎらい、できていることの承認など、どんな小さなことでもいいのです。
「まず、ほめる」を意識してみることが大切でした。
あっ、ただ、決してお世辞にはならないように。
事実やそのことから感じていることを素直に言葉にすれば良いのです。
2.ほめることの効果

心理学の研究では、ネガティブなフィードバック(叱るなど)よりもポジティブなフィードバック(ほめるなど)の方が、モチベーションがあがり、ポジティブな行動に結びつくと言われています。
ほめることには、次のようなメリットが考えられます。
・良い行動の習慣化につながる
・モチベーションが向上する
・自己肯定感が向上する
・信頼関係が生まれる
・パフォーマンスが上がる
・自主性を引き出す
・好意の返報性(何かしてもらったら返したくなる)が高まる
☆会社成長につながる、社員を褒めると得られる効果とは?褒め方のコツとNG方法も紹介
☆部下のやる気を引き出す!褒めることで得られるメリットやできる上司の褒め方のコツをチェック
ほめることってすばらしい!
そう思った私とあなた。
ちょっと待ってください。
ものごとには、何でも表と裏があります。
ほめることには、デメリットはないのでしょうか?
・打たれ弱くなる
・ほめないと機嫌を悪くする
・注意や叱責を素直に受け入れられない
・見返りがないとやる気になれない
・ほめることは”勇気”をくじくことbyアルフレッド・アドラー
・上下関係を意識し、自分の優越性を手放すこと
☆ほめすぎは逆効果?アドラー流・よりよい声かけのコツ
なるほど、つまりほめ方によっては、相手のためにならないこともあるということでしょうか。
言葉かけ次第で、相手を良くも悪くもする。
ほめることに大きなパワーが秘められていることは間違いないようです。
アドラー心理学的には、「ありがとう」や「うれしい」といった感謝や承認のほめ言葉が相手の勇気づけになるそうです。
また、相手の行動の結果よりも過程に注目してほめ言葉をかけることで、ほめることのデメリットを防ぐことができるようです。
こうしたほめることの効果を理解した上で、「まず、ほめる」ができるとさらに有効ですね。
3.まとめ|人に変わってほしければ、まずほめることから

まず相手をほめておくのは、歯科医がまず局部麻酔をするのによく似ている。もちろん、あとでがりがりとやられるが、麻酔はその痛みを消してくれる。
今回の記事では、人を変える原則について
「人を動かす」D・カーネギー著 山口博訳 創元社 part4 1章
から紹介しました。
自分に都合が良いように、交渉を相手に持ちかける際には、策が必要です。
ストレートに言っても、うまくいかないばかりか、かえって相手の反感を買うおそれもあります。
そんな時には、まず、ほめ言葉から話し出してみませんか。
ほめることには、
相手の自己重要感を高めるパワーを秘めています。
「自己重要感」この本の中で、カーネギー氏が何度も使っているキーワードです。
相手の自己重要感を高めることが、難しい交渉においても、相手を変えることも可能にしてくれるはずです。
人を変える原則。「まず、ほめる」こと。
了
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
教育×○○をテーマにいろいろ書いています。
他にも読んでいただいたら、うれしいです。
「初めまして」の方はこちらからお願いします。
「スキ」や「フォロー」をいただけますと、とっても喜びます。
今回のテーマの記事は、このマガジンにためていきます。
復習がてら見ていただけると、きっとつながりを感じられます!
今週一番多く読んでいただいている記事はこちらです。
