
2021年 年間ベストアルバム50
今年も毎年恒例、ベストアルバムを選ぶ季節がやってきました。
今年もいつも通り音楽にまみれた生活をしながら、たくさんの素晴らしい作品と出会うことが出来ました。
去年は音楽は家の中で聴くことが多かったですが、今年は移動中や仕事場など色々な場所やタイミングで聴くことが増えた気がしますね。
家でじっくり音楽に浸るのももちろん良いんだけど、歩きながらだったり車や電車に乗りながら音楽を聴くのもまた違った良さがありますよね。
曲のBPMに合わせた速度で歩いたり、仕事前と仕事終わりのテーマソングが月1で変わったり、仕事場で毎日のように流して無理矢理ファンと味方を増やしたり、音楽は本当に色々な楽しみ方があります。
今年個人的に少し変わったなと思ったのが、これまで以上に歌詞を注意して聴くようになったこと。
今まで全く気にしてなかったわけではないんだけど、そのアーティストが何を言いたいのか、何を伝えたいのか、どんな事を思ってるのか、そのあたりをより真剣に聴くようにしてました。
海外の音楽はどうしてもサウンド先行で耳に入ってくるので歌詞は二の次になりやすいんだけど、そのアーティストの世界観をちゃんと理解したり深く堪能するにはやはり歌詞がとても重要で、そこを頭に置いて聴くことでこれまで以上に面白く楽しく音楽と向き合えたなと思いますね。
もちろんサウンド先行でその響きにやられたというものもたくさんあるんだけど、自分の中で少し意識を変えたことで色々な発見もあった1年になったかなと思います。
今回も50作品、自分の直感を信じながらも色んな情報を参考にし、時には左右されながら選んでみました。
その作品を聴く事が出来るサブスクやBandcamp、YouTubeなどを一つにまとめた便利なサイト、Songwhipへのリンクをアルバムタイトルのところに貼っておいたので、気になった作品はよかったらチェックしてみてください。
それでは今回も中々のボリュームなんですが、最後までお付き合い頂けたらと思います。
50. SPIRIT OF THE BEEHIVE「ENTERTAINMENT, DEATH」

フィラデルフィアベースのバンド、SPIRIT OF THE BEEHIVEの通算4作目となる新作アルバム。
元々4人組バンドでしたが今作からスリーピースとなり、さらには名門Saddle Creekに移籍してのリリースと環境や体制がガラッと変わって制作された今作。
一体何を聴いているのか分からなくなるほどに多種多様な響きがごちゃごちゃに混在したカオスな質感の仕上がりで、そのサイケデリックなサウンドの先に待つ得もいわれぬ陶酔感というか没入感みたいな感覚がなんともクセになって何度も繰り返して聴いてしまうんですよね。
なんか古いカセットテープに録音されて眠ってた音源みたいな、少し先の未来のポップミュージックの死体みたいな、過去と現在と未来が混在したような不思議な質感。
前にFrank Oceanが自身のラジオ番組で彼らの楽曲をセレクトして流してましたが、確かにサウンドの方向性とかジャンルレスな感じは近いかもしれないですね。
今年屈指のヘンテコアルバムです。
49. PinkPantheress 「to hell with it」

ロンドンベースのSSW、PinkPantheressのデビューミックステープ。
彼女は元々TikTokアプリへの楽曲投稿で注目を集めた人で、自身のサウンドを「ニューノスタルジック」と称するように自分のような世代にもどこか懐かしいと感じさせながらも、2021年の最新の音としても捉えることが出来る不思議な質感のサウンドが特徴ですね。
90s後半〜00s前半のダンスミュージックのノスタルジーを纏いながら今時の曲尺感覚でサクサク聴けちゃう新感覚ポップミュージックで、全ての曲が1〜2分足らずの非常にコンパクトなサイズ感。
彼女は2001年生まれなんだけどサウンドの引用元が20歳とは思えないセンスで、Crystal WatersやSweet Female Attitude、Adam FなどのUKガラージやドラムンベース、ハウスのクラシックを何の躊躇もなくサンプリングする感じがとても痛快でしたね。
新たな時代のサウンドメイカーとして今後の動向が非常に気になる存在です。
48. Arooj Aftab 「Vulture Prince」

パキスタン出身で現在ニューヨークをベースに活動しているSSW、Arooj Aftabの通算4作目となるアルバム。
彼女が生まれたパキスタンという国は宗教上の理由やその他の要因で音楽に触れることに対して非常に厳しい環境なんだそうで、独学でギターを学びアメリカの音大に留学することになったんだそうです。
パキスタンの伝統音楽をベースにし、ジャズやアンビエントの要素をさり気なく織り交ぜたサウンドは、他に聴いたことのない唯一無二の美しさを放っていて、ここではないどこかへ誘われるような情感溢れる響き。
寂しげでありながらも温もりのある彼女の民謡のようやヴォーカルスタイルも非常に味わい深く、ハープやヴァイオリン、ギターといった弦楽器の調べが漂わせる異国情緒溢れる響きと重なって独特の雰囲気を醸し出してますよね。
このアルバムの制作中に弟さんを亡くしてしまったそうで、その悲しみや喪失感も伝わってくるような、美しくも儚い魅力を持った作品ですね。

ノースカロライナ州のアッシュビルを拠点に活動している5人組バンド、Wednesdayの2作目となるアルバム。
まず冒頭の歪んだギターの轟音の物々しさから一気に耳を奪われ、その後も重厚なシューゲイザーサウンドと相反するようにキャッチーなメロディーが重なった聴き応え満点の楽曲が次々と流れていくような展開。
重々しく暗い響きと呼応するように、ヴォーカルのKarlyの綴る歌詞も自身の人生の困難や苦しさを歌ったものが多く、彼らにとってこのアルバムを作り出すことがある種セラピーのような役割を果たしていたんだそう。
ルーツの一つであるカントリーミュージックのテイストを感じる楽曲もあったり、ただただギターをかき鳴らした轟音一辺倒な作品では無いのも今後への可能性を感じましたね。
オルタナティブなロックとはこうあるべきだなと思わせてくれる傑作アルバムです。
46. 大和那南(Nana Yamato) 「夜明け前(Before Sunrise)」

現在20歳の日本人SSW、大和那南のデビューアルバム。
世界的にも有名な原宿のレコードショップ、BIG LOVEとParquet Courtsのメンバー、Andrew Savage主宰のニューヨークのレーベル、Dull Toolsから同時に全世界リリースという中々の大型新人っぷり。
高校生の頃にANNAという名義でEPをリリースしていたようなんですが、そこから着々と準備を重ねて満を持して完成させたのが今作。
ちなみに高校生の頃好きだったのはIceageらしいです。
日本人が海外進出する時にやりがちな、海外向けのよそ行き仕様なホンモノ感を出すわけではなく、あくまで彼女のやりたいDIY感強めのインディーポップに仕上げているのは好印象で、簡素で素材感溢れるシンプルなサウンドがとても面白い作品でしたね。
80年代にひっそりとリリースされていた知る人ぞ知る日本人SSWの名盤が、時を経て海外で火が付きリイシューされたみたいな、何とも言えない空気感とオーラを持った今年の隠れた名作アルバムです。
45. Mdou Moctar 「Afrique Victime」

ニジェール出身のギタリスト、Mdou Moctarの通算4作目となる新作アルバム。
今作から名門レーベルのMatador Recordsと契約したのも結構驚きでした。
サハラ砂漠の遊牧民、トゥアレグ族の出身である彼のサウンドの特徴は、サハラ音楽をベースにしたアフリカンエスニックなビートにサイケデリックなギターの音色が絡み合う未体験のロックサウンドで、とにかく自由だなぁという印象でしたね。
アフリカ音楽特有の祝祭感というか儀式感みたいなのがとても好きなんだけど、彼の歌詞はかなりシリアスに社会問題などを取り上げててそこも興味深いなぁと。
徐々に高まってトリップしていく感覚も気持ち良いし、とにかくギターが自由に暴れまくってて最高なんですよね。
近年はロックも多様化してきていわゆるギターヒーローのような存在は中々生まれなくなってきてますが、彼には是非ともその空いた椅子に名乗りを上げて欲しいなと思いますね。
44. Low 「Hey What」

ミネソタ州はダルースを拠点に活動しているバンド、現在は夫婦デュオとなったLowの通算13作目となるアルバム。
今年でキャリア28年の大ベテランが2018年に放った前作「Double Negative」に引き続きBon Iverとの仕事などで知られるBJ Burtonをプロデューサーに迎えた作品で、冒頭からいきなり凶暴なノイズの応酬で始まり、その後も耳に脳にビリビリと振動が伝わってくるような凄まじい音圧のグリッチサウンドが聴く者の自由を奪っていくかのように鳴り響きます。
そんな轟音の中でも力強く響く2人のヴォーカルはゴスペルや教会音楽のように荘厳で重厚で、全ての音が重なり解放された時の迫力は凄まじいものがありましたね。
最初聴いた時はちょっと食傷気味かなと思ったんだけど、歌声やメロディーが美しく次第にBeach Houseを聴いてるみたいな感覚になってきてどんどんとハマっていきましたね。
イヤホンやヘッドホンで1人の世界に入り込んで堪能したい一枚です。
43. Armand Hammer & The Alchemist 「Haram」

ニューヨークベースのラッパー、ELUCIDとbilly woodsの2人によるユニット、Armand Hammerとヒップホップシーンでカルト的な人気を誇るプロデューサー、The Alchemistによるコラボアルバム。
Freddie Gibbsとのコラボ作も記憶に新しいThe Alchemistですが、精力的に刺激的なコラボレーションを重ねてますよね。
渋いネタ使いのジャジーでソウルフルなビートはマリファナの匂いが漂ってきそうな煙たい質感で、ゲスト参加しているEarl Sweatshirtのサウンドとも近い催眠術のようなループ感とコラージュ感によって、どんどんと深くまで引き込まれていくような感覚でしたね。
ソ連と繋がりのあったアメリカの大物事業家の名前をユニット名にするあたりが、彼ららしい悪趣味な皮肉がきいた感じでいいですよね。
今年は他にもNavy BlueやBruiser Wolf、Harvey_dugなど、アブストラクトなヒップホップの良作が数多くリリースされましたが、今作は中でも屈指の完成度だったかなと思いますね。
42. Dorothea Paas 「Anything Can’t Happen」

カナダはトロントベースのSSW、Dorothea Paasのデビューアルバム。
彼女は地元で地道に音楽制作をしながら、近年ではU.S. Girlsなどのツアーメンバーやセッションアーティストとしても活動し、今作でようやくデビューまで漕ぎつけた遅咲きのアーティストなんですよね。
実はDorothea Paasというのはバンドの名前でもあるらしく、時にバンドのようでもありソロのSSWでもあるという彼女の幅広く様々な面を持つ作風を表しているみたいです。
耳馴染みの良い軽やかでなおかつ大人の余裕を感じるフォークサウンドがとても心地良く、バンドとしてのアンサンブルを聴かせる曲もあれば、1人のミュージシャンとして趣向を追求しているようなサウンドもあったり、中々に面白い仕上がりでしたね。
ヴォーカルのスタイルから告白的な歌詞、楽曲のアレンジなど様々な面で同郷のSSW、Joni Mitchellからの影響を強く感じましたね。

ニューヨークベースのバンド、Wetの通算3作目となるアルバム。
前作は2人組体制でのリリースでしたが、今作はオリジナルメンバーの3人体制に戻って制作されたんだそう。
R&B〜ポップ〜ハウスを絶妙に行き来する洗練されたサウンドを作り出してるのは、3人に加えてFrank Oceanとの仕事で知られるBuddy Ross、Toro y Moi、そしてBlood Orangeという何とも豪華な布陣!
Toro y Moiプロデュースの「Far Cry」は、これまでメロウな曲調が多かった彼らのサウンドには珍しく軽やかなダンスミュージック。
Blood Orangeがゲスト参加した「Bound」は、2組のメロウでチルアウトな部分がかけ合わさった大人なポップスといった感じの仕上がりに。
元々洗練された音楽を作っていた彼らですが、今作で一皮剥けたような印象でしたね。
サウンドの引き出しが増えて表現出来るものの幅も広がった今の彼らだからこそ生み出せた良作です。
40. Mr Twin Sister 「Al Mundo Azul」

これまでで最もアップビートな作品となったMr Twin Sisterの通算4作目となるアルバム。
デジタルな音色とリズムに生楽器の肉感的なグルーヴが絡みついたエレクトロファンク・ディスコサウンド。
ジャズやラテンのフレイヴァーが程良く効いた、不思議でトリッキーなダンスミュージックが相変わらず最高でしたね。
彼らのアルバムは毎作品そうなんだけど、サウンドの心地良さやカッコ良さと同時に得体の知れなさとか気味悪さみたいな引っ掛かりや違和感のようなものを感じて、その相容れなさがクセになって聴くたびにドハマりしていくんですよね。
歌は英語とスペイン語が混じり合い、曲が変わる度にサウンドのベクトルも表情も全く異なるテイストになり、作品の統一感みたいなものはまるで無いんだけど、とっ散らかった印象にはならないのも不思議。
余計なことは何も考えずに無心で体を揺らせる感じが本当に好きです。

LAベースのSSW、Meg Duffyによるプロジェクト、Hand Habitsの通算3作目となるアルバム。
今作はプロデューサーに同郷のSSWのSASAMIを迎え、Perfume GeniusやThe War On DrugsのベーシストのDave Hartley、Ethan Gruskaなどの友人たちもゲスト参加している意欲的な作品。
エレクトロの要素が入った曲やストリングスやホーンの音色が加わった曲など、これまでの彼女のシンプルな作風のサウンドとは違ったテイストの楽曲も数多く収録されていて、一緒に音作りをしていた仲間たちの影響が良い形で表れていましたよね。
ただ彼女の本質としてのSSWの部分というのは変わらず芯がしっかりしていて、今作ではこれまで以上にパーソナルな内容の歌詞なのが印象的でした。
幼い頃に自殺してしまった母親についてや、それに対して長い間抱いていた悩みや葛藤と向き合い、それを吐露するように歌にした内省的なものもあったり。
彼女の日記や伝記を読み進めていくような感覚の、とても味わい深い良いアルバムだなと思いますね。
38. Space Afrika 「Honest Labour」

マンチェスター出身で現在はベルリンを拠点に活動しているデュオ、Space Afrikaのフルレングスとしては初となるアルバム。
去年BLM運動の高まりを受けて制作されたミックステープ「hybtwibt?」で彼らの事は知ったんだけど、そのダークでアブストラクトな質感のアンビエントミュージックとしての完成度の高さと、暴力や差別への怒りや悲しみを生々しく描写したインダストリアルな世界観に一気に引き込まれたんですよね。
今作ではパンデミックによる孤独や閉塞感が描かれていて、ラップやヴォーカル、ストリングスなども交えてより神秘的で陶酔感のあるサウンドに仕上がっています。
Nicolas JaarがプロデュースしたKing Kruleの楽曲をBurialがリミックスしたみたいな、まさにアルバムジャケットのような冷たい雨が降る夜の街を思わせる、静けさとノイズの交錯による得も言われぬ没入感を味わえる作品ですね。

テキサスベースの5人組バンド、Sun Juneのセカンドアルバム。
澄んだ空気の自然の中を散策しているような、清々しくゆったりとした時間が流れるドリームポップ〜フォークサウンド。
前作もその年を代表する癒しの一枚でしたが、今作はよりマイナスイオン成分が増したような印象ですね。
ギターの柔らかな揺らぎと包容力のあるヴォーカルの温もりに包まれて、聴いてるとすぐに脱力してしまいますね。
ドラム、ベース、ピアノも含めて鳴っている全ての楽器が本当に丁寧に演奏されているなという印象で、録音やミックスの仕上がりも素晴らしいんですよね。
このアルバムを再生すると、もう何もしたくないという選択しか頭になくなるので、部屋でゆっくり過ごす時や眠りに就く前などに聴くのがオススメですね。
本当に心も体も癒される一枚です。
36. The War on Drugs 「I Don’t Live Here Anymore」

今やアメリカを代表するバンドとなったThe War on Drugsの通算5作目となるアルバム。
80sスタジアムロックのスケール感と疾走感と、内省的なフォークロックの哀愁と奥深さを併せ持ったこのバンドの真骨頂のようなサウンド。
Bob DylanやBruce Springsteenが土台を作り、様々なミュージシャンが様々な形で発展させてきたアメリカンロックの雄大な歴史の良い部分を詰め込んだような圧倒的な説得力を感じましたね。
一歩間違うと古臭くダサく聴こえてしまうハートランドロックなサウンドを、絶妙なアレンジとギターの鳴りの良さでそう感じさせないのがこのバンドの上手さと貫禄なんだろうなぁと。
どこかで昔聴いたことある感覚はあるのに、The War on Drugsの最新作としてちゃんと聴かせられるのホント凄いなぁと思います。
良いバンドが期待通りの良いアルバムを出してくれて嬉しかったです。
35. Lost Girls 「Menneskekollektivet」

ノルウェーベースのアーティスト、Jenny Hvalとその長年の共演者でもあるミュージシャン、Håvard Voldenによるプロジェクト、Lost Girlsのデビューアルバム。
2018年に一度EPをリリースしてるんだけどそれ以来の作品ですね。
タイトルの「Menneskekollektivet」はノルウェー語で人間の集合体を意味するんだとか。
Jenny Hvalの諸作で聴かせるアヴァンギャルドでダークなエレクトロポップサウンドはそのままに、シンセのループやドラムマシーン、ギターのレイヤーによってより複雑に、より混沌とした響きになってるなという印象でしたね。
クラブライクなビート感ある楽曲もあったり、アンビエントなトラック上でポエトリーリーディングをするような曲もあったり、非常に実験的な内容の一枚でした。
34. Dry Cleaning 「New Long Leg」

サウスロンドンベースのバンド、Dry Cleaningのデビューアルバム。
80sポストパンク〜ニューウェイヴ発90sオルタナロック経由な、シンプルさと複雑さが混在したサウンドがとにかくクール。
冷めたように言葉を吐き捨てるスポークンワーズなヴォーカルスタイルも相まって退廃的な美しさが滲み出てる。
よく挙げられてるSonic YouthやGang of Fourの音感触にも確かに近いし、The Strokesみたいな潔さも感じるし、最近のUK発のIDLESとかFountains D.C.みたいな若手バンドとも共鳴してる感もあるし、様々な脈略で語るべきことが多いバンドですよね。
今年は同じイギリス発のバンドとしてSquidやBlack Country, New Roadあたりも非常に面白く聴き応えのある作品をリリースしましたが、個人的にはDry Cleaningの温度感が好みでしたかね。
今後さらにビッグになっていくであろうことを予感させる素晴らしい完成度のデビュー作でした。

ルイジアナ州出身のSSW、Renée Reedのデビューアルバム。
ほぼ全編に渡って弾き語りで構成されたドリーミーなフォークサウンドが、田舎の田園風景や郷愁を春めいた風の匂いと共に運んでくるかのような。
自分のサウンドを「dream-fi folk from the cajun prairies」「ケイジャンプレイリー(ルイジアナにある伝統的な自然)生まれのドリーミーなフォーク」と称しているのも納得。
60年代のフレンチポップのようなレトロでローファイな感じもたまらなく好みですね。
これ2021年リリースの作品なの?と聴いてて不思議に感じてしまうくらいに隠れた名盤みたいなオーラを既に放ってるというか。
Joni Mitchellからの影響はもちろん感じるし、Jessica PrattやCate Le Bonあたりが好きな人にもぜひ聴いて欲しい一枚ですね。

LAベースのSSW、Hana Vuのデビューアルバム。
これまでLuminelle Recordingsから2作のEPをリリースしてきましたが、今作からGhostly Internationalと契約し待望のアルバムデビューとなりました。
以前から彼女のファンでしたが、サウンドもヴォーカルも表現力の幅が格段に上がっててビックリ!
Day WaveことJackson Phillipsを共同プロデューサーに迎え、ノイジーなグランジ・ガレージロックから軽やかなニューウェイヴまで自分のものにし、内面をさらけ出しながら歌にする様が実に痛快でした。
彼女がアジアの血が入ってるというのもあるかもだけど、Mitskiにも近い情念とか迫力みたいなものが音に込められてて、それを若干21歳が鳴らしてるんだから凄いなと思いますね。
アートワークのようなグロテスクな生々しさも内包した21歳のリアルが詰め込まれた傑作アルバムです。
31. Good Morning TV 「Small Talk」

フランスベースのバンド、Good Morning TVのデビューアルバム。
おそらく今回紹介する中では一番知名度が低いというか、まだあまり知られていないアーティストかなと思います。
とろけるようにチルいドリームポップと、ラフで粗っぽいギターロックが絶妙にちょうど良いバランスで共存したサウンドがとにかく好みでした。
Men I TrustやTennis、Crumbあたりが好きな人にはドンピシャだと思いますね。
Soccer MommyやJay Som、Barrieなどなど、ここ数年はもうずっと女性がヴォーカルのSSWやバンドに心を奪われ続けてるけど、このバンドもそのお気に入りリストに一瞬で入ってきましたね。
全ての響きがことごとくツボをついてくる感じ。
雨の日に聴くとピッタリな、程良くアンニュイな感じがまたたまらない…。
これを機に知った方にもぜひ聴いてみて欲しい、これからが非常に楽しみな存在です。
30. Clairo 「Sling」

アトランタ出身のSSW、Clairoのセカンドアルバム。
どこか冷めたような等身大の女子の心情をパッケージングした前作からしっとり落ち着いた大人な女性のムードへと品良くアップデートしたような印象で、今作はJack Antonoffをプロデューサーとして迎え彼女の素材の良さを活かした必要最低限のシンプルな音作りで作品のトーンを形作っています。
デビュー以降その可愛らしいルックスも相まってすぐに人気者となり、次世代のポップスターみたいに扱われていったことで彼女自身非常に疲れてしまったんだそうで、メンタル的にもかなりやられてしまったんだそう。
今作はそんな状態の中休息を取り、家族や愛犬と過ごすことで徐々に戻っていった音楽への愛を形にした作品で、彼女のSSWとしての成長や成熟が感じられる仕上がりになっていました。
アコースティックな響きの温かみと同時に、自分自身の心と体を守るための一旦休むということの選択の大切さと必要性を感じさせてくれる、色々な意味でハートウォームな作品でした。
29. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra 「Promises」

Floating Pointsと伝説的なサックスプレイヤー、Pharoah Sandersによるコラボアルバム。
ロンドン交響楽団も交えた空間的でアンビエントな演奏が織りなす神秘的で崇高な組曲を、Pharoahの人間味あるサックスの音色を中心に据えながら組み立てていく様が実に巧み!
同じフレーズのループが徐々に熱を帯びていく展開も見事…。
この2組の組み合わせを最初に聞いた時は想像がつかなかったんだけど、実際聴いてみると驚く程に調和していて、現実世界と空想世界の中間点に存在する音楽のような不思議なサウンドな印象でしたね。
もっとサックスを前面に持ってくる音作りも可能だったはずなんだけど、引き算というか引きの美学というか、鳴っていない時の残響すら計算しているかのような音の構築がとにかく圧巻!
それでも頭や耳に強烈に残るのはサックスの艶かしい音色で、そこが彼の凄さなのかなと思いましたね。
28. Men I Trust 「Untourable Album」

カナダはモントリオールベースのバンド、Men I Trustの通算3作目となるアルバム。
今作はタイトル通りライブで演奏出来ない事を想定して作られていて、パンデミックによりツアーに出られず出来た時間を注ぎ込み制作された作品なんだそう。
前作アルバムとライブセッション集はもう何度聴いたか分からない程頻繁に日常のBGMとして愛聴してきたけど、今作は良い意味で何も変わってないんですよね。
雨とか曇りとか、少し湿り気のあるモヤっとした質感の極上のインディーポップス。
こちらが彼らに求めてるサウンドを完全に理解してるというか、まるで実家に帰ってきたような安心感と脱力感に包み込まれる心地良さは相変わらず至福でしたね。
日々変化だらけの今の世の中だから尚更、普遍・不変の良さが沁みます。
タイトルとは違いツアーに出る事が実現して、北米を終え来年はカナダやヨーロッパを回るツアーを行う予定なんだそう。
いつかまた日本でもライブが観れる日が訪れる事を期待してます。
27. Turnstile 「GLOW ON」

ボルチモア出身の5人組バンド、Turnstileの通算3作目となるアルバムは個人的にも今年出会った中でもかなり衝撃度が高かった作品でしたね。
アーリー90sのハードコア・パンク〜グランジ由来の疾走感のある荒々しいロックを基本とした荒々しいサウンドが彼らの持ち味。
ただ面白いのは、ゲスト参加してるBlood Orangeのような甘美なインディーポップのエッセンスがアクセントとして加わった楽曲がアルバムの要所に置かれているところ。
ヘッドバンギングでもしたくなるようなヘビーなロックが続くと思いきや、ミドルテンポでドリーミーな質感の曲が空気感をガラッと変えるように挟み込まれ。
これは非常に新鮮でしたね。
あと彼らのサウンドで面白いなと思ったのがヴォーカルのリヴァーブ処理の仕方。
ハードで歪んだギターと不思議な余韻を残すヴォーカルが良い意味でアンバランスで、他のバンドには無い魅力だよなと思いましたね。
普段あまりハードロックを聴かない自分のような人達にも届く何かを持ってる作品だなと感じましたね。
26. Rosie Lowe & Duval Timothy 「Son」

サウスロンドンのSSW、Rosie Loweと同郷のプロデューサー、Duval Timothyによるコラボアルバム。
今作はDuval Timothyの第二の拠点でもあるシエラレオネのフリータウンとロンドンで主にレコーディングを行ったようで、街中や教会などの非常にオープンな環境で録音し、その自然の音や喧騒なども一つのパーツとしてサウンドに取り込んだとても実験的な作品になっています。
幾重にも折り重なるヴォーカルのレイヤーとピアノの掛け合いや調和が生み出す、神秘的かつ人の温もりを感じるアーティスティックな響きがとにかく美しいんですよね。
Duval Timothyの前作「Help」は去年最も衝撃を受けた作品の一つで、ジャズの捉え方が現代的かつ空間的で、この人は将来Dev Hynesみたいな存在になりそうだなと思ったんですよね。
2019年のSolangeの傑作「When I Get Home」のリリース以降様々なベクトルで派生している何かが、2つの才能によって見事に形となった素晴らしい作品です。
25. Lana Del Rey 「Chemtrails Over the Country Club」
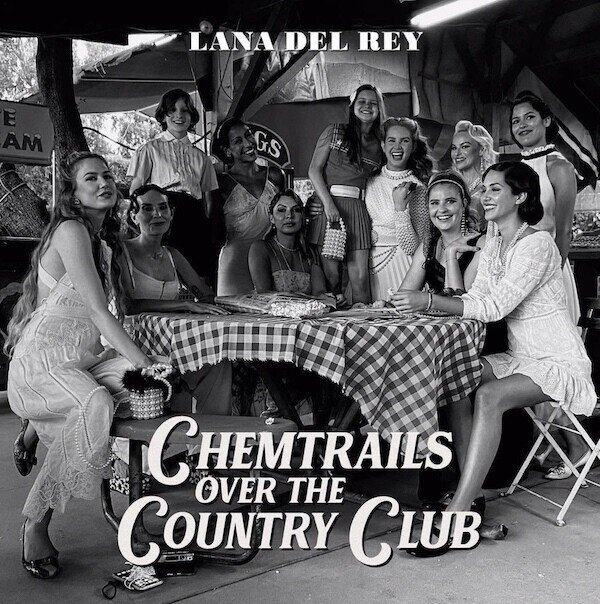
Lana Del Reyの約1年半振りの新作アルバムはもう流石の一言でしたね。
アメリカ中西部の雄大な自然を思わすような長閑なカントリー・フォーク調の楽曲が立ち並び、これまでで最もミニマリズムを追求したシンプルな構成はまるで古典映画を観ているかのような感覚。
幻のように儚いのにハッとする程に生々しい…。
アルバムジャケットにもあるように様々な女性達への賛美をテーマにした楽曲も多く、ゲストにWeyes BloodとZella Dayを迎えたJoni Mitchellの「For Free」のカバーで作品を締めくくっていて、Lanaがこの世代の女性SSWの代表としてこれからも進んでいくという心意気が感じられたような印象を受けましたね。
前作に引き続きJack Antonoffをプロデューサーとして迎えていて、彼らの相性の良さを再認識させられた作品となりました。
「White Dress」で聴かせる高くしゃがれた金切り声のようなスタイルの歌声など、ヴォーカル面でも新たな一面を見せているのも印象的でしたね。
10月には早くも次作「Blue Banisters」がリリースされ、こちらもまた違った味わいの素晴らしいアルバムを聴かせてくれました。
24. Karima Walker 「Waking the Dreaming Body」

アリゾナ州をベースに活動しているSSW、Karima Walkerの2作目となるアルバム。
シンセサイザーの浮遊感ある音色が空間を漂い、アコースティックギターの優しい調べが側に寄り添うアンビエント・フォークサウンド。
タイトルの通り夢をテーマにした楽曲が多く、音の感触は極めて曖昧でボヤーっとした響き。
夢と現実の狭間のようなモヤモヤとした彩度の低い描写と、環境音楽にも近い自然の音の揺らぎ、そして必要最低限のヴォーカルの情報量。
中には5分以上ザーっとした波音のような響きが寄せては引いてを繰り返すような楽曲もあったり。
ぼやーっとエコー処理がかかったヴォーカルも、瞑想的なドローンの電子音も、気付くとこの作品を聴いているということを忘れているくらい自然に周囲の音に溶け込んでしまうんですよね。
じっくり聴き込むというよりは、BGMとして聴き流すことを前提に作られたような雰囲気さえ感じましたね。
睡眠導入剤としてこれ以上ない完璧な作品です。

昨年の個人的なベストアルバムの一つだったHelena Delandと、同郷モントリオールのOuriによるプロジェクト、Hildegardのデビューアルバム。
8日間のセッションで生み出された、SmerzやTirzahとも共鳴するような実験的なエレクトロポップサウンドがとにかくクール。
Helena Delandのアルバムは去年最もよく聴いた作品の一つで今でもずっと聴き続けてるけど、今回のコラボ作ではガラッと印象を変えてかなりアヴァンギャルドに攻めたサウンドに挑戦してるんですよね。
トランスやR&Bなど曲毎に違ったベクトルで、Ouriとの化学反応が様々な形で表れてます。
ちなみにこのアルバム制作期間中はFKA twigsやA$AP Rocky、クラブミュージックなどを聴いて刺激を受けていたんだそう。
プロジェクトネームでもあるHildegardとは中世ドイツのフェミニストの女性の名前だそうで、厳しい時代を生き抜いた彼女の姿や生き方にも非常にインスパイアされたみたいです。
それぞれのソロ作品とはまた違った音楽性が味わえる今年の隠れた名盤の一つですね。
22. Ada Lea 「one hand on the steering wheel the other sewing a garden」

モントリオールベースのSSW、Ada Leaのセカンドアルバム。
柔らかく穏やかなフォークと少し無骨なギターロックの間を彷徨うようなサウンド。
現実かそれとも空想なのか曖昧な歌詞の世界観。
ヴォーカルの質感も含めて全てが朧げなニュアンシーな仕上がりで、それが何とも心地良くじんわり沁みてくるんですよね。
この人の書く歌詞って本当に小説を読んでるみたいな感覚というか、日常の何気ない出来事や風景を切り取ってそれを巧みな表現力と言葉使いによってどんどん引き込まれていく面白さを味わえるんですよね。
捉え方によって意味が変わる表現とか、本当に凄い詩人だなと思います。
TomberlinやJohanna SamuelsなどのSSW仲間がコーラスで参加してるのも良いですよね。
秋の夜長にじっくりと堪能するのにピッタリな非常に味わい深い一枚でした。
21. Dean Blunt 「BLACK METAL 2」

2014年リリースのカルト的奇作から7年振りの続編となるDean Bluntの新作アルバム。
捉え所のないジャンルレスな異形のエクスペリメンタルサウンド、Dr. Dreみたいなアートワーク、ボソボソ呟くようなヴォーカル。
どこを取っても人を食ったようなカオスな質感が相変わらずブッ飛んでて最高でしたね。
前作の「Black Metal」は彼には珍しくギターを多用し、フォークロックのような楽曲もいくつかありましたが今作もその路線は踏襲してましたね。
終始薄気味悪い得体の知れない響きが鳴り続けてるんだけど、不思議と不快ではなくむしろ心地良くトリップしていくような感覚というか。
サウンド的にはKing Kruleなんかと近いんだけど、King Kruleの表現する混沌や闇とは種類が違うというか、何で暗いのかすらよく分からない感じが底知れなくて不気味なんですよね。
彼の音楽シーンでの立ち位置もそうだけど、一部の人にしか理解されないカルトヒーローのような、大衆性を完全に拒んだ仕上がりが物凄く潔くて好きです。
このアルバムで彼を知った人やこれから聴いてみようという人にお伝えしておくと、このアルバムは彼のディスコグラフィーの中でもかなりまともな作品だということですね。
これで?と思うかもしれませんが、これまでの作品はもっとヤバいのである意味ではこの作品が入り口としては適しているのかもです。

メルボルンベースのデュオ、HTRKの通算5作目となる新作アルバム。
薄暗く湿った森の中で鳴っているかのような、モノトーンの妖しく不気味なカントリー・フォークは息を呑む程の美しさでしたね。
彼らは元々アヴァンギャルドなエレクトロ〜エクスペリメンタルなサウンドの作品を多くリリースしてきたんですが、今作では一転してアコースティックに振り切ったスローコアなサウンドを聴かせています。
The xxとも通じるミニマルな音数の耽美な世界観の美しさたるや…。
ヴォーカルのJonnieは最近Loraine Jamesとコラボしたり、中々面白い経歴の持ち主。
Grouper、Tomberlin、Sea Oleenaなどの内省的で儚げなサウンド好きにはたまらない仕上がりでしたね。
聴いてると浄化されていく感覚というか、これからの肌寒い季節にじっくりと耳を傾けたくなる味わい深さがたまらなく好きですね。
今年出会った中でも最も美しいレコードの一つだと思います。
19. Faye Webster 「I Know I’m Funny haha」

アトランタベースのSSW、Faye Websterの通算4作目となるアルバム。
ペダルスチールのとろけるような音色、穏やかなリズム、柔らかなヴォーカル。
日々の疲れを癒やし、体の凝りをほぐし、ストレスをどこかへと連れ去ってくれるような、疲労回復効果抜群の至福の響き。
彼女の作品はどれもそうだけど、どんなに疲れていて音楽すら聴く気にならない時でさえ、再生するとスーッと心に沁み渡っていくような作用がある気がしますよね。
地元のアトランタ、野球、ヒップホップ、写真、ヨーヨーなど、彼女を構成している趣味や好きなものは本当に幅が広くて、そんなカオスな趣向が垣間見えるビデオ作品や歌詞もとても面白くて魅力的なんですよね。
今作には彼女が以前からファンだったという日本人
SSWのmei eharaが参加していて、この2人の温度感というか空気感の近さも最高の相性でした。
18. Jazmine Sullivan 「Heaux Tales」
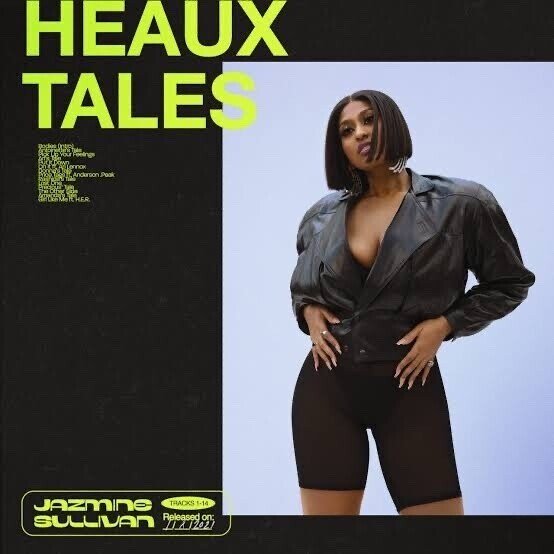
Jazmine Sullivanの「Heaux Tales」はブラックミュージック好きにはたまらない傑作でした。
14曲収録ではあるけど本人的にはEPとしてリリースした作品みたいなんですが、まぁ普通にアルバムとして聴けるボリュームでなおかつコンセプチュアルな内容でしたね。
浮気、セックス、金、差別、見栄。
女性の内なる心情の機微をソウルフルに、ダイナミックに歌で表現し、ヒップホップやエレクトロを程良くブレンドさせつつ王道のR&Bサウンドに着地させた圧巻の完成度はさすがでした。
男の自分からするとドキッとするような、そこまで言っていいの?みたいなパーソナルな内容だったり、女性にしか書けないかなりリアルな歌詞も聴き応え十分でしたね。
そしてもうとにかくヴォーカルの凄さですよね、この人は。
音域とか抑揚とか、細かなフレーズの動きとか、単純な歌唱力だけでなくテクニカルな部分も含めて今最も優れたヴォーカリストの1人が彼女でしょうね。
Brandyとかもそうなんだけど、声の使い方や動かし方が本当に巧みなんですよね。
ライブ映像とか観るともう本当に上手すぎて笑ってしまうレベル!
「Pick Up Your Feelings」のアコースティックライブの映像はマジでヤバ過ぎるのでぜひチェックしてみてください。
現行のR&Bとして最高峰の作品かなと思います。

ポートランド出身のLiz Harrisによるプロジェクト、Grouperの通算12作目となる新作アルバム。
彼女は自分が知る中で最も穏やかで静かで、儚くて朧げな音楽を鳴らす人。
今作のテーマは休息と海岸についてなんだそうで、現在住んでいる海沿いの家からの風景がこの作品のインスピレーションになったようです。
これまでになくギターの生々しい響きが印象的で、家から見える海の波の動きや水の揺らぎのようなものがギターの音を通して表現されているのかなと感じましたね。
彼女のこれまでの作品はピアノを基調としたサウンドが多く、それはとても冷たく孤独で悲しい響きでしたが、今作ももちろんその要素はあるものの幾分温かみや距離の近さみたいなものを感じる気がして、そんな救いのような質感の響きがとても心地良かったです。
この人の音楽を聴いてると時が止まったような感覚になるというか、静寂に包まれるような心地良さがあって、気がつくといつも眠りに就いてるか心も体も「無」みたいな状態になってる気がしますね。
どんな場所でどんな場面で聴いても安らぎと癒しをくれる、自分にとって唯一無二の存在です。
16. The Weather Station 「Ignorance」

カナダはトロントベースのバンド、The Weather Stationの通算5作目となるアルバム。
女優としてのキャリアもあるヴォーカルのTamara Lindermanが中心の彼らのサウンドは、レイト80s期のFleetwood MacやTalk Talkあたりの残像がちらつく、洒脱でコンテンポラリーなアートポップサウンドといった佇まい。
クールで落ち着いた響きをジャズを絡めた巧みなアレンジメントで徐々に高揚させていく展開が見事でしたね。
あと聴くたびに驚くのがその音の良さですね。
ストリングスやサックスの華麗な音色がサウンドに華やかな彩りを加え、ドラムやベースのリズム隊は疾走感を出しながらしっかりと骨組みとして軸を作ってる。
そのバランス感を生み出しているサウンドプロダクションが本当に巧みだなと思います。
そして作品をより上品に、崇高なものに高めているのがTamaraの声ですよね。
彼女のアダルトで妖艶なヴォーカルの響きがサウンドをより洗練された仕上がりにグレードアップさせてる印象でした。
15. JPEGMAFIA 「LP! (OFFLINE VERSION)」

JPEGMAFIAの待望の通算4作目となる新作アルバムにはぶっ飛ばされましたね。
このアルバムは2つのバージョンが存在し、ストリーミングで聴ける「ONLINE VERSION」と、BandcampやYouTubeなどで聴ける「OFFLINE VERSION」があり、サンプリングのクリアランスなどの問題で若干内容が違っています。
要は「OFFLINE VERSION」の方がオリジナルの音源に近いようなイメージですかね。
彼の作品は毎回そうなんですが、これだけ訳わかんないデタラメみたいな響きなのに、彼特有の美学やセンスで有無を言わさず黙らせてくる感じが圧倒的ですよね。
ヒップホップの姿形を借りたパンクミュージックのような、終始心地良い音の暴力を食らい続けているかのような。
彼の作る音は一貫して「歪み」を意識して作られてる気がしていて、それはノイズとかディストーションみたいな「ひずみ」だけじゃなくて、音の組み合わせとか構成の違和感的な「ゆがみ」という意味での「歪み」も含めて。
そんな過激な外っ面の内側にメロウでソウルフルな一面を隠し持っている感じが、彼が他のアーティストとは一線を画している理由な気がします。
14. Arlo Parks 「Collapsed in Sunbeams」

ロンドン出身のSSW、Arlo Parksの待望のデビューアルバムは鮮烈でしたね。
先行曲が出る度に期待感を高めていたけど、まさかここまで上手くまとめてくるとは…。
10sの音楽を聴いて育った世代だからこそ鳴らせる、多様なジャンルのブレンド具合とその自然さがマジでセンス良すぎですよね。
彼女自身、影響を受けたアーティストとしてFrank OceanやPortishead、Radioheadあたりを挙げてて、彼らの音作りのメソッドや手の加え方は確かに受け継いでる感じありましたね。
内向的だった音楽オタクの女の子が様々なアーティストに影響を受けて、やがて自分の音楽の才能を開花させている感じがこのアルバムを聴いてると伝わってくる気がします。
彼女の歌詞は人の弱さや脆さを自分の体験談も含めて具体的にさらけ出したものが多く、同じく悩みを抱えて生きている若者には特に共感されているのもこの作品の素晴らしい部分の一つですよね。
流行りのポップス好きにも、ブラックミュージック好きにもロック好きにもジャンルを問わず幅広く届いていて、20年代を背負って立つような存在になることを期待させてくれますよね。
9月には今年のMercury Prizeを受賞しましたが、まさに2021年を代表する傑作の一つだと思います。
13. Loraine James 「REFLECTION」

ロンドンベースのミュージシャン/プロデューサー、Loraine Jamesの通算3作目となるアルバム。
トリッキーかつアブノーマルなビートに、UKドリル〜R&Bを驚くほどシームレスにマッチさせた圧巻のサウンドプロダクション!
最新鋭のキレッキレのビート集としてもクールな歌モノとしても凄まじい完成度…。
グライムやドリルなどのUKダンスミュージックはラップのイメージが強く、治安の悪い危険な地域で生まれた音楽という印象もまだまだ強いですが、Loraine Jamesの作品を聴くと一つの音楽としての面白さや可能性を感じることが出来る気がしますね。
多くの曲でラッパーがフィーチャーされてますが、ラップもヴォーカルもあくまでトラックを構成する音の一つとして聴かせているのもポイントですね。
不規則なリズムと多種多様な音色の組み合わせのセンスはさすがは名門レーベルのHyperdubという感じ。
Laurel HaloやJessy Lanzaといったレーベルメイトのエレクトロ勢とも並べて聴きたいような、さらにはKelelaやDawn Richardといった先鋭的なR&Bアーティストとも共鳴するような。
聴くたびに驚きをくれる斬新な一枚です。

天才プロデューサー、Madlibの新作アルバムは熟練の技が光る流石の傑作でした。
Madlibの個人名義の作品ではあるものの実質的にはFour Tetとのコラボ作とも言える内容で、2人の音の魔術師の共演による化学反応が楽しめる一枚です。
Madlibらしいオールドスクールなソウルネタ使いのドープなヒップホップをベースとしながら、Four Tetのアレンジやエディットによって良い意味でマイルドに、そしてソリッドに仕上げられていて、音の配置の仕方がやはりこれまでのMadlibのそれとは違うなという印象でしたね。
簡単に言うと滑らかというか、Madlibのサウンドの味でもあった音の表面のざらつきのようなものが均されている感じというか。
この2人が組む意味がきちんと感じられるサウンドに着地しているのが流石だなと思いましたね。
60sのソウルからYoung Marble Giants、ブラジル音楽まで、ジャンルを問わず彼の中で何かが引っかかった音楽をサンプリングしMadlibらしいサウンドに作り変えてしまうのがこの人の凄いところですよね。
親交の深かったJ Dillaに捧げた楽曲も収録されてますが、2020年に亡くなったMF Doomへの想いもこの作品には込められていたのかなと勝手に想像して聴いてました。
11. Japanese Breakfast 「Jubilee」

韓国生まれでアメリカはオレゴン州で育ったMichelle Zaunerによるソロプロジェクト、Japanese Breakfastの新作アルバム。
母親との別れと向き合い少しずつ前へと進み出した彼女のポジティブなエネルギーに溢れた、雨上がりの路面のようにキラキラと輝く至高のポップミュージック。
去年CryingのRyan Gallowayと組んでBUMPER名義でまさに「pop songs 2020」という作品をリリースしてましたが、彼女の持つポップセンスが今作でさらに花開いたような印象ですね。
これまでの楽曲は母親の闘病生活や死、そしてその後の葛藤や苦悩など悲しみをテーマにしたものが多かったですが、今作はそこから一歩踏み出し初めて喜びをテーマにした歌を書きたいという彼女の想いが楽曲に解放感や明るさ、キラキラ感を与えていますよね。
後悔や寂しさなどの感情の動きや揺れを隠さず、決して母親のことを忘れたわけでも無く、それも乗り越えて生きていこうという彼女の強さが作品全体から伝わってきます。
キラーチューンの「Be Sweet」はもちろん、スムーズなグルーヴがたまらない「Slide Tackle」や、メロウなアジアンポップス「Posing in Bondage」などサウンドの幅も聴き応えも素晴らしい傑作ポップアルバムです。
10. Erika de Casier 「Sensational」

デンマークはコペンハーゲンベースのSSW、Erika de Casierのセカンドアルバム。
今作から名門レーベル、4ADに移籍してのリリースでしたが、変にコマーシャライズされるわけでもなくデビュー作に引き続き彼女らしいクールな一枚を届けてくれました。
レイト90s〜アーリー00sのR&Bをベースに、北欧のエレクトロやボサノヴァを絶妙な配合でブレンドしたサウンドは相変わらず至高…。
アンニュイなヴォーカルも相まって雨の季節や夜の時間に完璧にマッチする極上の仕上がり。
個人的に10年代のベスト作の一つに選ぶくらい好きな前作を聴いた時、SadeやCafé Del Marのコンピのようなエキゾチックなチル感がとてもツボだったんだけど、今作はCraig Davidみたいな2ステップ/R&B風な楽曲もあって幅が広がった印象でしたね。
パーカッションの音の活かし方がラテンっぽいのが彼女のサウンドの特徴なんだけど、乾いたスネアの響きとは違う少しこもった低い打楽器の音だからこそ生まれるミステリアスでウエットな質感がこの人のサウンドの肝になってる気がしますね。
今後もR&Bを独自の路線で進化させていってくれることを確信出来る素晴らしい作品でした。

ロンドンベースのアーティスト、Tirzahのセカンドアルバム。
Mica LeviやCoby Sey、Kwesといった彼女にとって家族のような存在のミュージシャンたちが前作に引き続き参加していて、彼らとの化学反応は今作でも健在でしたね。
不協和音やノイズなどの違和感や異物感と同時に、得も言われぬ陶酔感や没入感を味わえる何とも不思議なサウンド。
母親となった彼女の温かみのある歌詞と冷たく無機質な響きが共存している様もカオスだし、虚構と現実が複雑に入り組んだ質感は何もかもが未体験。
敢えて粗雑にしたのかと思うくらいラフな作りや簡素なループなど、一流のミュージシャンたちが集まって作ったとは考えにくいレベルで彼らのセッションの様子のありのままがそのまま収録されているのも斬新でしたね。
もの凄くリアルで過激で不完全な響きは、聴くたびに耳に残り頭に引っかかり気がつくともう一度再生しているような中毒性があるんですよね。
結局この作品の実態は何も掴めないまま今日を迎えましたが、なぜ自分がこんなにも惹かれてしまうのかの理由を探すために何度も繰り返し聴くことになる気がしています。
8. Cassandra Jenkins 「An Overview on Phenomenal Nature」

ニューヨーク・ブルックリンベースのSSW、Cassandra Jenkinsのセカンドアルバムは2021年を語る上で欠かすことの出来ない素晴らしい作品です。
この作品はSilver Jewsのメンバーとしても知られるDavid Bermanの死がきっかけとなり制作されたものだそうで、彼のツアーに帯同する予定だった彼女が彼の死を受けてそれと向き合い再起していく様子が描かれています。
穏やかで柔和なフォークサウンドと洗練されたモダンなアンビエントサウンドが見事なバランスで混ざり合った優雅で壮大な響き。
緑や風の爽やかな自然の空気の中にサックスの都会的な音色が加わることで一気に洗練された雰囲気になるんですよね。
コロナウィルスが世界中で感染拡大してから、ニュースで毎日のように感染者数や死者数と向き合うことになり、もはやそれが普通となり喪失感みたいな感情は次第に薄れていっている中、このアルバムで語られている大切な人を失った気持ちやそれを受け入れ前へと進んでいくことの大変さや大切さはまさに時代とリンクしていて、こうした困難な時だからこそ多くの人の心に沁みる作品なのかなと思いましたね。
サウンドはもちろん、歌詞にもしっかり注目して堪能したい傑作です。
7. Mach-Hommy 「Pray For Haiti」

ニュージャージーベースのラッパー、Mach-Hommyの「Pray For Haiti」との出会いは今年最も予想外な収穫の一つでした。
彼は常に覆面をしていることからも分かる通り、自分の情報をあまり伝えたがらないため非常にミステリアスな存在で、自分も今作でその存在を知りました。
過去にはEarl Sweatshirtとコラボしていたり、DrakeやJay-Zもお気に入りとして紹介していたり、インデペンデンスな存在ながらも大物の目には留まっていたようです。
同じく近年注目を集めているラッパーのWestside Gunn(彼のアルバム「Pray For Paris」との兄弟作説あり?)が制作に携わっている今作は、ソウルやジャズからのサンプルヘビーなサウンドと、淡々と自身の思いを語るようなコンシャスなラップスタイルがとにかくドープな一枚。
今までに聴いたことのないタイプのクレイジーなビートや、どこから見つけてきたの?と首を傾げたくなるようなサンプリングネタのチョイスなど、かなり斬新で前衛的なサウンドメイクだなという印象でしたね。
自身のルーツであるハイチについてやクレオールとして生きることの誇りや難しさを語ったラップの内容も面白かったです。
近年増えてきているアブストラクトなヒップホップ作品の中でも、複雑さと分かりやすさのバランスが絶妙な、新時代のヒップホップを象徴するような一枚ですね。
6. Cleo Sol 「Mother」

ロンドンベースのSSW、Cleo Solのセカンドアルバム。
これは聴いた瞬間から長い付き合いになるだろうなと感じた一枚でしたね。
個人的な去年のベスト作品にも選んだSAULTのメンバーでもあるCleo Solですが、ソロ作品ではSAULTのパワフルで迫力のあるサウンドとはまた違った魅力を聴かせてくれています。
SAULTと同じくプロデューサーのInfloと共に作り上げた今作のサウンドは、70年代のソウルを思わせるオーセンティックな質感と90年代以降のネオソウル的なオーガニックな質感が同居したような仕上がり。
彼女のヴォーカルも含めて全ての音が丸みを帯びているような印象で、そのふくよかで柔らかな響きはやはり彼女が今年出産し母となったことが大きな要因なんだと思いますね。
彼女のルーツにもあるジャマイカやスペインを由来としたレゲエやラテンのフレイヴァーを感じる楽曲もあり、自身も母親となったことでより家族や繋がりみたいなものを意識して今作を生み出したのかなと想像出来ますよね。
様々な変化が繰り返される日常の中で、ふとひと息の安らぎをくれるタイムレスな魅力を放つ傑作アルバムです。
5. L’Rain 「Fatigue」

ブルックリンベースのアーティスト、Taja Cheekによるプロジェクト、L’Rainのセカンドアルバム。
これは今年最も度肝を抜かれた作品かもしれせんね。
サウンドコラージュ、ノイズ、リヴァーブ、ビートチェンジ。
違和感に違和感を塗り重ねたような凄まじい程にいびつな構造の響きが、ソウルやジャズを飲み込みながらマーブル状のカオスな色使いの音世界を描いていく様が圧巻!
突如として街の喧騒の様子やボイスメモが挿入されたり、音がぶった斬られるように細かくチョップされては貼り付けられ、その断片的な音の並びにギョッとする間もなくまた次の混沌が押し寄せてくるみたいな。
彼女の頭の中は一体どうなってるんでしょうね?
父親が音楽関係の仕事をしてたり、おじいさんが昔ジャズクラブを経営してたり、彼女自身も幼い頃から様々な楽器に触れ現在は10以上の楽器を演奏することが出来るんだとか。
ちなみにイェール大学卒のかなりの秀才だったみたいです。
だからこそますますどうしてこんなにめちゃくちゃな音楽が生まれるんだろうと不思議でしょうがないんですよね。
不気味な程に底知れない魅力を秘めた怪作です。
4. Magdalena Bay 「Mercurial World」

LAベースのデュオ、Magdalena Bayの待望のデビューアルバムはやっぱりポップは最高だと改めて思わせてくれた一枚でした。
これまでにリリースしてきたシングルやEPがどれも粒揃いの良作でフルアルバムへの期待はかなり高まってましたが、それをはるかに超える傑作でしたね。
BritneyやSpice Girlsあたりの90sポップを由来としてそれをCharli XCXやSOPHIEがハイパーポップとして昇華させた10sのポップミュージック。
その良い部分のみを抽出してK-POPやJ-POPのキャッチーさと良い意味でのチープさを融合させたみたいな。
Charli XCXやSOPHIEをはじめ、GrimesやCarly Rae Jepsenなどが拓いてきたポップミュージックの最も理想的な到着地点と言える圧巻の完成度でしたね。
ディスコやロック、ハウスにゲーム音楽まで、彼らの節操のない音楽的嗜好が「Mercurial World」という架空の未来世界を通して新しいポップミュージックとして鳴っている感じ。
2020年代のポップを語る上で欠かすことの出来ない作品になるであろう傑作です。

ボルチモア出身のSSW、Lindsey JordanことSnail Mailのセカンドアルバム。
18歳で鮮烈なデビューを飾った彼女も20代となり、精神的にも音楽的にも成熟し音楽人として生きていくという覚悟が作品から滲み出ているような、SSWの2作目としてこれ以上ないくらい優れた作品を届けてくれました。
悲しみや怒り、愛、嫉妬など様々な感情が燻り、時に激しく燃え上がり、彼女の内側の揺れが言葉となり声となり音となって生々しく鳴り響く圧巻の表現力と完成度。
シンセやストリングスの響きも取り入れ、ギター中心だった前作と比べるとサウンドの幅も一気に広がり、よりポップな作風へと変化したのが印象的。
10代の危うさや青臭さ、脆さまでをパッケージングした前作が自分にとって特別な作品なのは変わらないんだけど、そこから様々な経験をして、少し大人になって今作までたどり着いたと思うとなんか感動しちゃいましたね。
魂をすり減らすように歌う彼女のヴォーカルスタイルはより切なさや訴えかける力が増した一方で、それが原因なのか喉にポリープが見つかったという心配なニュースもありました。
ゆっくりと休んで治療して、また素晴らしい作品と共に復帰してもらいたいなと思います。
2. Little Simz 「Sometimes I Might Be Introvert」

ロンドンベースのラッパー、Little Simzの通算4作目となる新作アルバム。
UKのラッパーならではのインテリジェンス溢れる言葉選び、豊富な種類のフロウを使い分けるラップスキル、ナイジェリアをルーツに持つ彼女だからこそのアフリカン・トライブな感覚。
以前からその圧倒的な個性と実力は誰もが認めるものでしたが、今作で完全に女王としての風格を漂わせるレベルまで到達したなと感じましたね。
1人のアーティスト、女性として気品や迫力、自信、知性、説得力、あらゆる面で進化を遂げた凄まじいレベルの完成度。
サウンド面を支えるのはSAULTやCleo Sol、Adeleなどを手掛けるInfloで、彼のサウンドの特徴でもあるストリングスやホーンセクションのスケール感あるオーケストレーションアレンジは別次元レベルの迫力とゴージャスさでしたね。
そして現在27歳の黒人女性として生きる彼女の私小説的なリリックの力もより凄みを増していて、内向的だった自分の苦悩や葛藤からイギリスという国が抱える社会的な問題まで、彼女が伝えたい訴えたい様々なストーリーが生々しく、凄まじい説得力を持って語られています。
USとはまた違った分脈で語られるUKならではのブラックミュージックの一つの到達点とも言える歴史的傑作アルバムです。
1. Tyler, the Creator 「CALL ME IF YOU GET LOST」

Tyler, the Creatorの通算6作目となる新作アルバム。
このアルバムを個人的な今年のベストアルバムに選んだのは、単純に最もよく聴いた作品というのもあるし、2000年代のヒップホップをもろに浴びて育った自分のような人間にとってこの作品は、本当にシビれる様々な仕掛けと愛が詰め込まれたアルバムだったからなんですよね。
サウンド的には前作「IGOR」の延長線上にあるとも言えるし、これまでのキャリアの総括的な内容とも言えるTyler感満点のサウンドだったんですが、特に印象的だったのはこのアルバムで頻繁に登場しシャウトしているDJ Dramaの存在。
彼は00年代にストリートで流通していた若手ラッパーをフックアップする役割も果たしていたミックステープを数多く作っていたDJで、Tylerもそのミックステープ文化のラップミュージックで育った世代なので、DJ Dramaの参加というのはなんか胸熱というかエモいというか。
TylerにとってヒーローであるPharrellやLil Wayneも参加してますが、00年代のヒップホップの熱さや盛り上がりを彼なりに再燃させようとする心意気が感じられて、そこは心から拍手を送りたいって感じでしたね。
自分が彼を好きな理由は、これだけビッグでメジャーな存在になってもずっと音楽好きのオタクみたいだし、ミーハーでアマチュアみたいなマインドも持ち続けてるところ。
人の上に立つことを嫌がり変わり者で居続けながら、自分の好きな音や人へのリスペクトを作品を通して表現し続けているところ。
だからこそ彼は自分の中で特別な存在であり続けるし、この作品に心の底から惹かれてしまうんだと思います。
というわけでいかがだったでしょうか?
冒頭でもお話ししたように今年はこれまで以上に歌詞を重点的に聴いていたこともあって、よりパーソナルな内容の作品を多く選んだような気がしました。
コロナのこともあってアーティスト自身も自分と向き合う時間が増えて、自分のメンタルの弱さも嫌いなところも、自分が大切にしていることも自分自身の好きなところも、その人の人となりが見えるような作品がたくさん出てきたなと思いましたね。
今年もたくさんの素晴らしい音楽と出会うことが出来ましたが、様々なメディアや個人の方のベストを見ながらまだ知らなかった作品を探して、新たな出会いを見つける年末年始を過ごそうかなと思ってます。
自分のこの記事でそんな出会いが生まれていたら嬉しいですね。
あと来年はもう少し頻繁に文章を書きたいなと思ってて、自分の頭の中で感じたり思っていることを言語化する作業をもっとしてみたいなと現時点では思ってます。
中々時間が無くて今年はあまり記事も書けなかったので、来年の目標にしたいと思います。
最後まで読んで頂いてありがとうございました!
