
【試し読み】『サイレント』(カリン・スローター/ 〈ウィル・トレント〉シリーズ)
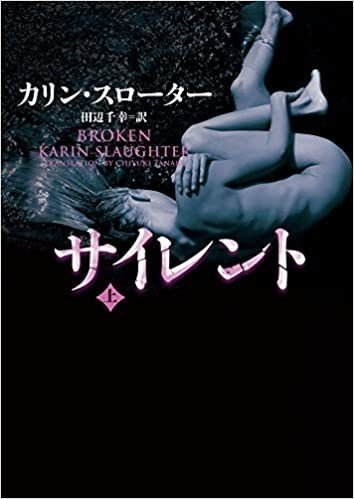
プロローグ
休みのあいだどこかに行きたいとアリソン・スプーナーは思ったが、行くあてはなかった。町に残る理由もないが、少なくともここにいれば金はほとんどかからない。少なくとも、雨をしのげる屋根がある。少なくとも、ぼろアパートのヒーターは時々稼働する。少なくとも、仕事場で温かい食事にありつける。少なくとも、少なくとも、少なくとも……どうしてわたしの人生はいつもぎりぎりのところにあるんだろう? いつになったら、最高のものが手に入るようになるんだろう?
風が強まってきて、アリソンは薄手のジャケットのポケットに突っこんだ手を握りしめた。雨が降っているというよりは、じっとりした冷たさがもやとなって体に絡みついてくるようだ。犬の鼻のなかを歩いている気がした。グラント湖から漂ってくる冷気のせいで、いっそう寒く感じられる。風が吹くたびに、切れ味の悪いいくつもの小さなカミソリに肌を切り裂かれているようだった。ここは南ジョージアのはずなのに。いまいましい南極なんかじゃなくて。
木々の立ち並ぶ足場の悪い湖岸を苦労して歩くあいだにも、ぬかるみに波が打ち寄せるたびに一度ずつ気温がさがっていくようだ。この薄っぺらい靴は、爪先が凍傷にかからないように守ってくれるだろうか? 手と足の指すべてを寒さのせいで失った男の話をテレビで見たことがあった。生きていることに感謝しているとその男は言っていたが、テレビに映るとなればどんなことでも言うものだ。アリソンの人生はいま正しい方向に向かっている。彼女が最後に映るのは夜のニュースだろう――おそらくは高校の卒業記念アルバムのあのひどい写真に、“悲劇的な死”という言葉が添えられて。
死んでからのほうがより大切にされるというのは、なんとも皮肉なものだ。いまのアリソンを気にかける人間はだれもいない。ようやくのことで手にしているわずかな収入や、人生における様々な義務をかろうじて果たしつつ、授業についていこうと悪戦苦闘していること。アリソンが湖岸で凍死するまでは、他人にとってはどうでもいいことばかりだ。
再び風が吹きつけ、アリソンは冷たい指にあばらを探られ、肺を締めつけられるのを感じながら、風上に背を向けた。全身に震えが走る。吐く息は白い雲のようだ。目を閉じた。かたかた鳴る歯の隙間から、いま抱えている問題を呪文のように唱えてみる。
ジェイソン。学校。お金。車。ジェイソン。学校。お金。車。
突き刺すような風がおさまったあとも、呪文は続いた。目を開ける。あたりを見まわした。思っていたより早く太陽は沈もうとしている。振り返って大学を見た。戻るべきだろうか? それともこのまま進む?
進むほうを選び、顔を伏せて強風のなかを歩く。
ジェイソン。学校。お金。車。
ジェイソン――恋人はろくでなしになった。たったひと晩のうちに。
学校――もっと勉強する時間をつくらなければ、落第する。
お金――これ以上働く時間を減らせば、学校に通うどころか、生活していけない。
車――今朝エンジンをかけたら、煙が出た。ここ数カ月そんな状態だったから、煙が出たこと自体はたいした問題ではないが、今日は暖房の噴き出し口から車内に入ってきた。学校に向かう途中で危うく窒息するところだった。
湖に沿ってカーブを曲がったところで、アリソンは“凍傷”をリストに加えた。まばたきをするたびに、氷の薄板でまぶたを切られているような気がした。
ジェイソン。学校。お金。車。凍傷。
もっとも差し迫っているのが凍傷の恐怖だろうが、その心配をすればするほど体が温まる感じがした。鼓動が速くなっているのかもしれないし、日が傾き始めて、寒さのなかで死ぬかもしれないという泣き言が現実になる恐れがあることに気づいて、歩く速度があがっているのかもしれない。
絡まりあった木の根を乗り越えようとして、アリソンは木に手をかけて体を支えた。指に当たる樹皮は、濡れてスポンジのようにふわふわしていた。今日の昼、パンがふわふわしすぎていると言ってハンバーガーを突き返してきた客がいた。“ふわふわした”といった曖昧な言葉を使うようには見えない、狩猟用の服に身を包んだ大柄で粗雑な男だった。彼は気を引くような言葉をアリソンにかけ、アリソンも適当にそれに応じた。帰り際男は、十ドルの食事に対して五十セントのチップを置き、いかにもいいことをしてやったと言わんばかりにアリソンにウィンクをして店を出ていった。
こんな暮らしにこれ以上耐えていく自信がアリソンにはなかった。祖母は正しかったのかもしれない。アリソンのような娘は大学に行くものではない。タイヤ工場で働き、男と出会い、妊娠し、結婚し、さらに数人の子供を産み、離婚する。この順番どおりのこともあれば、前後することもあるだろう。運がよければ、相手の男はあまり暴力をふるわないかもしれない。
それがわたしの望む人生? 彼女の遺伝子に刻まれているのはそんな人生だ。母親はそのとおりに生きた。祖母もそのとおりに生きた。アリソンの叔母のシーラもそうだった。叔父のボイドに向かって散弾銃の引き金を引き、頭部をほぼ吹き飛ばしてしまうまでは。スプーナー家の女性は三人とも、人生のどこかの時点でくだらない男のためにすべてを失っていた。
アリソンは母親のジュディ・スプーナーが幾度となくそんなことを繰り返すのを見てきたので、彼女が全身を癌(がん)にむしばまれて最後に入院したときには、その人生はただの無駄だったとしか思えなかった。母親はすっかりやつれていた。三十八歳にして髪は薄くなり、ほぼ真っ白だ。肌はかさかさだった。タイヤ工場で働いていたせいで、両手は鉤爪(かぎづめ)のように曲がっている。コンベヤーベルトからタイヤを取り、耐圧を確かめてベルトに戻し、つぎのタイヤを取る。それを一日に二百回以上も繰り返していたせいで、夜になって這(は)いずるようにしてベッドに潜りこむころには、全身の関節が悲鳴をあげていた。三十八歳にして、ジュディは癌を歓迎した。苦痛から逃れられることを喜んだ。
ジュディは最後に、死ぬのがうれしい、もうひとりでいなくてもいいことがうれしいとアリソンに言った。ジュディは天国と贖罪(しょくざい)を信じていた。いつの日か、砂利の私道とトレーラー・パークでの暮らしが、金で舗装された道路と邸宅に変わるのだと信じていた。アリソンが信じていたのは、彼女の存在は母親を満たすことができなかったという事実だった。ジュディのグラスは常に半分しか入っておらず、アリソンが注ぎ続けてきた愛が母親を満たすことはなかった。
ジュディはあまりにも深く泥にはまってしまっていた。将来性のない仕事の泥。次々と現れるくだらない男の泥。彼女の自由を奪う赤ん坊の泥。
大学はアリソンの救済になるはずだった。アリソンは科学が得意だった。家族を見るかぎりどう考えてもありえないことだが、彼女は化学物質の働きを理解できた。巨大分子の合成の基本を理解していた。合成高分子も同様に理解していた。なにより大事なことに、勉強の仕方を知っていた。答えが記されている本が地球のどこかに必ず存在することを知り、答えを知る一番の近道は手に入るすべての本を読むことだと知っていた。
高校の最上級生になるまでアリソンは、故郷の小さな町アラバマ州エルバに住む同世代の少女ほぼ全員を堕落させた異性と酒と覚せい剤とは距離を置いていた。夜のシフトに入って、おしゃれだからと煙草たばこを吸っている、中身のないくたびれた娘の仲間入りをするつもりはなかった。三十歳になる前に、父親の違う子供三人の母親になるつもりはなかった。前の夜にどこかの男に殴られたせいで、目が開かない朝を迎えるつもりはなかった。母親のように、病院でひとりで死ぬつもりはなかった。
少なくとも三年前エルバをあとにしたときには、そう考えていた。アリソンがいい大学に進めるように、科学教師のミスター・メイウェザーは全力を尽くしてくれた。彼はアリソンをエルバからできるだけ遠くに行かせたがった。アリソンに未来を与えようとしてくれた。
グラント工科大学はジョージア州にあったから、それほど遠いという感覚ではない。だが卒業生が二十九人だったアリソンの高校に比べれば、巨大だった。キャンパスに足を踏み入れた最初の週は、どうすればこの場所を好きになれるだろうかと考えて過ごした。同級生はみな様々な機会に恵まれて育ち、高校を出てすぐ大学に行かないなどと考えたこともないような人ばかりだった。アリソンが手をあげて質問に答えても、だれもせせら笑うことはなかったし、フレンチネイルやヘアエクステンションの方法以外のことを学びたくて教師の話を熱心に聞いているからといって、自分を売りこんでいると思う者もいなかった。
そのうえ、大学周辺の地域はとても美しい。南アラバマにあるとはいえ、エルバは荒廃していた。一方グラント工科大学のあるハーツデールは、テレビに出てくるような町だ。どの庭もきれいに手入れされ、メインストリートには春になるとずらりと花が並ぶ。見知らぬ人が笑顔で手を振ってくる。アリソンが働いている食堂にやってくる地元の人たちは、チップをはずんではくれないにしろ、みなとても親切だ。町はあまりに大きくて、アリソンは迷子になった。だが残念なことに、ジェイソンに会わずにすむほど大きくはなかった。
ジェイソン。
彼とは大学二年生のときに出会った。二歳年上で、アリソンよりも世慣れていて、あか抜けていた。彼の考えるロマンチックなデートは、映画館にこっそり忍びこみ、支配人に追いだされる前に一番うしろの列で手早く欲求を満たすことではなかった。テーブルに布ナプキンが置いてある本物のレストランにアリソンを連れていってくれた。アリソンの手を握り、話を聞いてくれた。ジェイソンとセックスをしたとき、どうしてその行為をメイク・ラブと呼ぶのかアリソンは初めて理解した。ジェイソンは自分の望みだけをかなえようとはしなかった。アリソンの望みもかなえようとした。ふたりの関係は真剣なものだとアリソンは思っていた――この二年間、彼となにかを築いてきたのだと考えていた。だが突然、ジェイソンは違う人間に変わった。ふたりの関係を素晴らしいものにしていたすべてが、ある日突然、崩壊の理由になった。
アリソンの母親と同じように、ジェイソンもまたそれをアリソンのせいにした。彼女は冷たい。よそよそしい。要求が多すぎる。ジェイソンのために時間をつくろうとしない。あたかも自分が、四六時中どうすればアリソンを幸せにできるかを考えている愛情豊かな聖人であるかのような言いぐさだった。友人と朝まで飲み明かしていたのはアリソンではない。大学で風変わりな友人たちとつきあっていたのはアリソンではない。町から来たあのいやなやつと関わっていたのは、もちろんアリソンではない。そいつの顔すら見たことがないというのに、どうしてそれが彼女のせいになるのだろう?
アリソンは再び体を震わせた。このいまいましい湖は彼女にいやがらせをしているのか、一歩進むごとに、岸辺が百メートルずつ長くなっている気がする。足もとのぬかるんだ地面を見おろした。ここ数週間、荒れた天気が続いていた。鉄砲水が道路を寸断し、木々をなぎ倒した。アリソンは荒天が苦手だった。暗い空に押しつぶされそうで、気が滅入めいる。ふさぎこみ、涙もろくなる。太陽が再び顔を出すまで、ずっと眠っていたいとしか考えられなくなる。
「もう!」足を滑らせたが、なんとか体勢を立て直した。ズボンの裾は泥まみれで、靴はなかまで水がしみこんできそうだ。波立つ湖面に目を向けた。雨がまつげに絡みつく。アリソンは黒い水を見つめながら、指で髪をかきあげた。転んでしまえばよかったのかもしれない。湖まで落ちていけばよかったのかもしれない。すべてをあきらめるのはどんな感じだろう? 引き波に身を任せ、底に足がつかないくらいの深さまで連れていかれ、肺から空気がなくなるのは、どんな感じがするだろう?
そんなことを考えたのはこれが初めてではなかった。容赦なく降り続く雨と重苦しい空のせいかもしれない。雨の日は、なにもかもが一段と憂鬱に思える。実際に憂鬱なこともいくつかあった。先週の木曜日、フォルクスワーゲンのビートルに乗った母親と子供が町から三キロのところで溺死したという記事が新聞に載った。道路を襲った鉄砲水に流されたとき、車はバプテスト第三教会から目と鼻の距離にいた。古いビートルは水に浮くような設計になっていたが、親子が乗っていた新しいモデルも浮いた。少なくとも最初のうちは。
いつもの持ち寄り食事会を終えて教会を出てきた人々は、水にさらわれるのが怖くてなにもできずにいた。ビートルが水面でぐるりと向きを変え、その後ひっくり返るのをおののきながら見ているだけだった。水が車内に流れこみ、親子は激流にさらわれた。記者のインタビューに答えた女性は、流れに呑のみこまれる直前に三歳の子供が水面から伸ばした小さな手は、毎夜眠りにつくときも、毎朝目を覚ますときにも、死ぬまで記憶から消えることはないだろうと語った。
アリソンもまたその子供のことを考えずにはいられなかった。鉄砲水が出たとき、図書館にいたにもかかわらず。母親にも子供にもインタビューに答えた女性にも会ったことがないにもかかわらず、目を閉じるたびに突きだされた手が見えた。その手は大きくなることもあれば、助けを求める母親のものになることもあった。その手に水面下に引きずりこまれて、悲鳴とともに目を覚ますこともあった。
実のところ、新聞のその記事を読む前から、アリソンの思考は暗い方向へと向かっていた。天気のせいばかりではないが、降り続く雨と垂れこめる雲はその絶望感で彼女の心を激しく乱した。あきらめたらどれほど楽になるだろう? 湖に向かって歩いていけば、今度こそ自分の運命を支配できるのに、どうしてエルバに戻って、十八人の子供を持つ歯のないやつれた老婆になる必要がある?
あまりにも早く母親と同じになってしまったせいで、髪まで白くなった気がした。これではジュディと変わらない――男たちはみな、彼女の脚のあいだにあるものにしか興味がないのに、彼女のほうは愛だと考えている。先週の電話で、叔母のシーラは同じようなことを言った。ジェイソンはどうして電話を返してくれないのだろうと、アリソンがめそめそ愚痴をこぼしたからだ。
長々と煙草を吸いこみ、煙を吐きだしながらシーラは言った。“母親そっくりだね”
それがなければ、アリソンの胸の傷はもっときれいなままだったろう。最悪だったのは、シーラの言うとおりだということだ。アリソンはジェイソンを愛していた。愛しすぎていた。一度も出てくれないにもかかわらず、一日に十回は電話をするくらい愛していた。九十億通送ったメールに返事が来ているのではないかと、二分おきにコンピューターを確かめるくらい愛していた。
ジェイソンにはするだけの勇気がない汚れ仕事を片付けるために、真夜中にこんなところまでやってくるくらい、彼のことを愛していた。
もう一歩、湖に近づいた。かかとが滑るのを感じたが、転ぶより早く、肉体の自衛本能が自動的に働いた。それでも靴が水に洗われた。ソックスはすでに濡れている。爪先はしびれを通り越して、鋭い痛みが骨に突き刺さるようだ。こんなふうなんだろうか――ゆっくりとしびれ、やがて痛みが消えていく?
アリソンは窒息することがとても怖かった。それが問題だ。子供のころは海が好きだったが、それも十三歳になるまでだ。ばかないとこのディラードが、市営プールに彼女を沈めたのがその年で、それ以来水が鼻まであがってくるのが怖くてパニックを起こすので、風呂に入るのも嫌いになった。
もしディラードがここにいたら、頼まなくても湖に突き落としてくれるだろう。初めてアリソンの頭を水中に押しこんだとき、ディラードはまったく反省の色を見せなかった。アリソンは昼に食べたものを吐いた。苦しくなるほど泣きじゃくった。肺が焼けるように痛んだ。だがディラードは、悲鳴を聞きたいがために相手の腕で煙草の火を消す老人のように、“へへん”と言っただけだった。
ディラードはシーラのひとり息子だったが、夫以上に――そんなことが可能であればの話だが――シーラを失望させた。しょっちゅうスプレーで落書きをしているので、見るたびに鼻の色が違っていた。覚せい剤(クリスタル)を吸っていた。母親から盗みを働いていた。水鉄砲で酒屋を襲おうとして刑務所に入ったというのが、アリソンが最後に聞いた消息だ。警察官が駆けつけたときには、店員が野球のバットでディラードの頭を叩(たた)き割っていたという。その結果ディラードはますますばかになったが、それでも絶好の機会を逃がしたりはしないだろう。両手でアリソンを思いっきり押して頭から水のなかへと落とし、あの甲高い声で笑うのだ。“へへん”アリソンは溺死するまで、必死で手足をばたつかせることだろう。
意識を失うまでどれくらいかかるだろう? どれほどのあいだ恐怖と闘わなければならないだろう? アリソンは再び目を閉じ、彼女を包み、呑みこもうとする水のことを考えようとした。あまりの冷たさに、最初は温かく感じるはずだ。空気がなくてはそれほど長くは生きられない。気を失うだろう。パニックに襲われて、ヒステリー性の失神を起こすかもしれない。それとも活力を取り戻すだろうか――アドレナリンが体内を駆けめぐり、紙袋に閉じこめられたリスのように暴れるのだろうか。
背後で枝が折れる音がした。驚いて振り返る。
「きゃあ!」また足を滑らせた。今度は立て直せなかった。両手をばたつかせる。膝がくずおれる。痛みに息がつまった。顔から泥に叩きつけられた。首のうしろをつかんだ手がそのまま顔を押さえつける。アリソンは濡れた土の冷たさを吸いこんだ。
本能的にもがいた。水に抗(あらが)い、彼女を支配しようとするパニックと闘った。背骨の付け根に膝が押し当てられるのを感じた。地面に押さえつけられて動けなくなる。焼けるような痛みが首に走った。血の味がする。こんなことを望んではいない。生きたかった。生きなければならなかった。口を開き、ありったけの声で叫ぼうとした。
だがそのあとは――闇。
月曜日
1
冬のような天候のおかげで、湖の底に沈んでいる死体は幸いなことにさほど傷んでいないだろう。だが岸辺の寒さは骨がきしむほどで、八月がどんなふうだったのかをなかなか思い出せない。顔に当たる日光。背中を流れる汗。暑さに適応できず、霧を吐きだす車のエアコン。レナ・アダムズは懸命に思い出そうとしたが、暖かさの記憶は十一月の朝の雨に洗い流されてしまっていた。
「いたぞ」岸辺から部下たちに指示を与えていたダイビングチームのリーダーが叫んだ。やむことのない雨のせいで、その声はくぐもって聞こえる。レナが手を振ってそれにこたえると、朝の三時に電話をもらって着こんだ厚手のパーカーの袖を水滴が伝った。土砂降りではないが延々と降り続けていて、レナの背中や肩にのせた傘をしつこく叩いている。視界はせいぜい十メートルで、その先はなにもかもがもやに隠れていた。レナは目を閉じ、温かなベッドと、彼女を包んでいたもっと温かな体に思いをはせた。
朝の三時に鳴り響く電話の音はだれにとってもいいものではないが、警察官となればなおさらだ。レナは熟睡していたところを起こされ、心臓が激しく打つのを感じながらも、無意識のうちに受話器をつかんで耳に当てていた。当番だったから、今度はレナがジョージア州南部のあちらこちらに電話をかけなければいけない。上司。検死官。消防局。ジョージア州捜査局(GBI)には、州有地で死体が発見されたことを伝え、ただちに死体の捜索に取りかかることのできる民間人ボランティアのリストを持つジョージア州緊急管理局にも連絡する。
いまその全員が湖岸に集結していたが、機転のきく者たちは車のなかで待機していた。冷たい風がゆりかごのなかの赤ん坊をあやすようにシャーシを揺らしているあいだも、車内はぬくぬくとしている。地元の葬儀場の経営者であり、町の検死官も務めているダン・ブロックは自分の車のなかで背もたれに頭を預け、口をあんぐり開けて眠っていた。救命士EMTたちですら、安全な救急車に引きこもっている。うしろのドアの窓越しに彼らの顔が見えた。時折窓から手が突きだされ、明け方の薄明かりのなかに煙草の火が赤く光った。
レナは証拠保全袋を持っていた。岸辺近くで発見された手紙が入っている。大きな紙の一部を破ったものだ――縦二十センチ、横十五センチくらいの罫線(けいせん)入りのノートの一部。書かれているのはすべて大文字で、ポールペンを使っていた。一行だけ。サインはない。悪意に満ちた、もしくは哀愁に満ちたありがちな別れの言葉ではないが、意味するところははっきりしていた。“終わりにしたい”
いろいろな意味で、自殺は他殺よりも調べるのが難しい。殺された人間がいれば、必ず責任を負うべきだれかがいる。犯人につながる手がかりがあり、愛する人が奪われた理由を残された家族に説明するためのはっきりしたパターンがある。理由がわからない場合でも、自分たちの人生を台無しにしたろくでなしがだれなのかは教えられる。
自殺の場合、被害者は加害者でもある。責任を負うべき人間は、その死を悼まれる人間でもある。近しい人が死んだときに感じる怒りをぶつけるべき相手は存在しない。死んだ人間が残すのは、この世の痛みと悲しみすべてを集めても埋めることのできない虚(むな)しさだ。父、母、姉妹、兄弟、友人、そのほかの親戚――彼らは一様に、非難すべき相手がいないことを知る。
命が不意に奪われたとき、人はみなだれかを非難したくなるものなのだ。
捜査官が現場の隅々まで調べ、記録するのはそれが理由だ。煙草の吸い殻やごみや紙屑(かみくず)はすべて目録をつくり、指紋を調べ、分析のため検査室に送る。初期報告書にその日の天候を記す。現場にいた警官や救急隊員の記録を取る。野次馬(やじうま)が集まっている場合には写真を撮る。車のナンバープレートを確認する。他殺と同様、自殺した人間の暮らしぶりを徹底的に調べる。友だちは? 恋人は? 結婚している? 恋人は男? それとも女? 腹を立てている隣人や、ねたんでいる同僚はいる?
いまのところ、これまで発見したものがすべてだった。サイズ八の女性用のスニーカー。左の靴のなかに安い指輪が入っていた――十二金の台の中央に光沢のないルビーをはめたものだ。右の靴には、文字の部分に偽ダイヤモンドを使った白いスイスアーミー時計。靴の下に折りたたんだメモが置かれていた。
“終わりにしたい”。
残された人間にとって、たいした慰めにはならない。
突然ダイバーのひとりが湖から浮上し、水しぶきがあがった。パートナーがその横に姿を見せる。ふたりは冷たい水から冷たい雨のなかに死体を引きずりだそうとして、湖の底の沈泥と格闘している。死んだ娘は小柄だったから大げさな仕草に見えたが、レナはすぐにふたりが苦労している理由を悟った。工業用とおぼしき太い鎖が娘のウエストに巻かれ、鮮やかな黄色の南京錠(なんきんじょう)がベルトのバックルのように垂れさがっている。鎖につながっているのは、二個のコンクリートブロックだった。
警察の仕事には、時折小さな奇跡が起きる。彼女は確実に目的を果たそうとした。もしもコンクリートブロックを重石(おもし)にしていなければ、死体は湖の中央まで運ばれて見つけるのはほぼ不可能だっただろう。
グラント湖は水深九十メートル、広さ三千二百エーカーの人工湖で、貯水池にされるまで人々が暮らしていた家や小さなコテージや小屋がその底に沈んでいる。商店や教会、南北戦争を耐え抜きながら世界大恐慌で閉鎖せざるを得なかった紡績工場などもあったが、グラント郡に安定した電気を供給するために、いずれもオチャワヒー川の水によってその存在を消されてしまっていた。
国の森林局が、湖の大部分と頭巾のように湖を囲っている千エーカー以上の土地を所有している。片側は比較的裕福な人たちが暮らす住宅地に接し、反対側にグラント工科大学があった。五千人近い学生が学ぶ、小規模ではあるが活気のある州立大学だ。
百三十キロに及ぶ湖岸の六十パーセントは、州の山林部の所有地だ。なかでももっとも人気があるのが、地元の人間がラヴァーズ・ポイントと呼ぶこのあたりだった。テントを張ってキャンプをすることが許可されていて、ティーンエイジャーたちはここでパーティーをし、しばしばビールの空き瓶や使用済みのコンドームを残していった。たき火が手に負えなくなって助けを求める電話も時々あり、凶暴な熊が出没したという通報も一度あった。結局は、キャンプをしている飼い主から逃げだした、チョコレート色の老いたラブラドールにすぎなかったが。
死体もたまに見つかる。少女が生きたまま埋められたことがあった。愚かな行為に夢中になった男たち――予想どおりティーンエイジャーだった――の仕業だった。去年の夏には、浅い入り江に飛びこんだ子供が首の骨を折っていた。
ダイバーふたりは立ちどまり、死体から水がしたたらなくなるまで待った。やがて互いにうなずくと、若い女性の死体を岸へと引きあげた。コンクリートブロックが砂地に深い溝をうがつ。朝の六時半で、ゆっくりと水平線に顔をのぞかせた太陽に月がウィンクをしている。救急車のドアが開いた。ストレッチャーを運びだしながら、刺すような寒さに救命士たちが悪態をつく。ボルトカッターを肩にかついだ救命士のひとりが、検死官ダン・ブロックの車のボンネットを勢いよく叩いた。驚いたダンが両手を振りまわす様子は、どこか滑稽だった。ダンは救命士を怖い顔でにらんだが、車を降りようとはしなかった。雨のなかに出ていこうとしないブロックを、レナは責める気にはなれなかった。その女性はもうどこにも行かない。唯一の目的地が死体安置所だ。赤色灯もサイレンも必要なかった。
レナは遺書の入っている証拠保全袋をジャケットのポケットにそっとしまい、ペンとらせんとじのノートを取りだしながら、死体に近づいた。首と肩で傘をはさんで支え、今日の日付と時刻、天候、救命士の数、ダイバーの数、車と警官の数、地形の様子、現場の厳粛な雰囲気、野次馬がいないこと――報告書に必要なありとあらゆる事柄――を書き留めた。
女性は百六十センチあるレナとほぼ同じ身長だが、はるかに華奢(きゃしゃ)だ。手首は鳥の脚のようにほっそりしている。爪は長さが不揃(ふぞろ)いで、ぎりぎりまで噛(か)んであった。黒い髪に極めて白い肌。二十代前半といったところだろう。開いたままの目は綿のように曇っていた。口は閉じられている。不安なときに噛む癖でもあるのか、唇はぼろぼろだった。あるいは空腹の魚がいたのかもしれない。
水に邪魔されなければ彼女の死体は軽く、待ち構えていたストレッチャーにダイバー三人で乗せることができた。頭のてっぺんから爪先まで湖底の泥がこびりついている。服から水がしたたった。ブルージーンズ、黒のフリースのシャツ、白いソックス、靴ははいておらず、前面にナイキのロゴがある紺色のウォームアップジャケットをファスナーを留めずに着ていた。ストレッチャーが移動し、彼女の顔があちら側を向いた。
レナは書く手を止めた。「ちょっと待って」なにか妙だ。メモ帳をポケットにしまい、死体に一歩近づいた。首のうしろでなにかが光ったのが見えた。銀色のなにか、ネックレスかもしれない。藻らしきものが埋葬布のように喉と肩を覆っていたので、レナはペンの先端を使って、緑色のぬるぬるした物体を押しのけた。皮膚の下でなにかが動いている。雨が水面にさざ波を立てるように、肉を波打たせていた。
ダイバーたちもその動きに気づいた。よく見ようとしていっせいにかがみこむ。ホラー映画のワンシーンのように、皮膚が揺れた。
「いったい――」ダイバーのひとりが声をあげた。
「きゃあ!」首に開いた傷口から小魚が現れ、レナはあわてて飛びのいた。自分も怯(おび)えていたことを認めたくないときに男がよくするように、ダイバーたちが笑った。一方のレナは胸に手を当て、心臓が実際に破裂したことにだれも気づいていないことを願った。大きく深呼吸をする。小魚は泥のなかに落ちた。ダイバーのひとりがすくいあげ、湖に帰してやった。まったくうさんくさい(フィッシー)と、リーダーがお決まりの冗談を言った。
レナは彼に鋭い一瞥(いちべつ)をくれてから、死体に顔を近づけた。魚が出てきた傷は首のうしろ側にあった。背骨のすぐ右だ。長さはせいぜい三センチと見当をつけた。傷口は水につかっていたせいでしわが寄っていたが、それ以前はきれいなものだったはずだ。非常に鋭いナイフでつけられたような。
「ブロックを起こしてきて」レナは言った。
これは自殺ではない。
