
私のスキーの歴史 パート1
エッ~ト^_^
スキー技術論って、好きじゃないんですが、私のスキーの師匠を
思い出したので、分かりやすい言葉で書いてみます。
(技術論というか、私のスキー上達の歴史みたいな内容です。)
私の師匠は私が中学生の頃、私の家に下宿していた従兄で、
(競技スキー経験者)毎週末スキーに連れてってくれました。
いつも、従兄のホームゲレンデ、石打丸山でした。
毎回、午前中は「山回りクリスチャニア」(下図参照)の
練習でした。

要は上図の赤い部分「山回り」を、パラレルターンで行うと思ってください
谷回りは、色々な方法があるけど、山回りの技術はこれしかない。
(師匠談)
ということで、いやになるほどやらされました。
最初は、斜滑降でゲレンデの端から端まで滑っていき、
山回りクリスチャニアで止まる。

(後からわかるんですが、上記説明は間違ってはいないけど、正しくもないと思います。)
スタートがだんだん上にあがり、最後は直滑降からのスタートで
山回りクリスチャニアで止まる。

上記は当時のオーストリアメソッドのスキー写真で、「逆ひねり」なんて
今は亡き技術も見られますね。
(ちなみにこの当時、フランス・スキーメソッドでは、肩の向きは進行方向に対して正対でした。)
写真が古くて、すみません😔
私が始めて見たスキーの写真は、こんな感じでした。
実際もこんな感じでした。

スキーが最大傾斜線を超えたら
山回りクリスチャニア一択
この一択が重要なんです。
先にも書きましたが、谷回りの部分、いわゆるスキーを最大傾斜線に向ける方法はいくらでもあるんです。
*最大傾斜線(フォールライン) とは、斜面の最も急な直線。
要は直滑降の向き。
(フォールラインじゃなくて、最大傾斜線なんて言葉を使ってる時点で
化石のような理論だと思うかもしれませんが、我慢して、もうちょっと
だけ読んでみてくださいませ。)
谷回りは、例えば
ジャンプして、スキーを最大傾斜線まで向ける。
シュテムして向ける。
ステップして向ける。
等々
しかし、山回りは、この山回りクリスチャニアしかありません。
午前中は、この山回りクリスチャニアの練習ばっか、やらされました。
お昼は、ゲレンデの中腹にある、廃墟かと見まごうばかりの山小屋で
石油ストーブをみんなで囲み、
ワンカップ大関の空き瓶で水を飲み、
カレーライスと言う名の、黄色い汁のかかった白飯を食べ、
ストーブの近くにかけておいた、ゴワゴワになったスキー手袋をして
「サー!行こうか」
午後の練習です。
さすがに、反復練習だけでは飽きちゃうと思ったのか、午後は
帰るまで、ズ~ット師匠の後ろについて、石打丸山のてっぺんから
一番下まで、ノンストップで何回も何回も滑りました。
話を技術論に戻しましょう。
この山回りクリスチャニア
「斜滑降からエッジを緩めてテールを押し続けると、スキーは回転する。」と書いてある。
何回やっても、師匠からはOKが出ません。
見る限り、私の山回りと師匠の山回りの違いがよくわかりません。
「膝を少し曲げて、腰を前に出す。」
「テールを押す感覚ではなく、谷足のインエッジに乗る感覚。」
「弧にあわせて、骨盤と肩のラインも自然に回してくる。」
う~ん❗おれは中国奥地に修行に連れてこられた、カンフーパンダか。🐼
ようわからん。
ようわからんまま、時は過ぎ、師匠は転勤で私の家を出て、
遠くへ引っ越して行きました。
私も高校生になり、石打丸山へ1人で行けるようになり、
日帰りだったり、一泊だったりでスキーに行くようになりました。
午前中はスキー学校に入り、午後はてっぺんから下までノンストップで
滑ってました。
この頃、ヴェーレンテクニックなるものが、オーストリアから入って来て
衝撃をうけました。


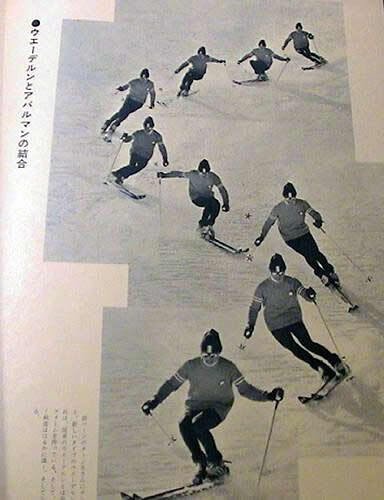
その当時は、(1960年代後半~70年代前半)
「立ち上がり沈み込み」の技法が主流だったのですが、
「抱え込み送り出し」の技法の優位性が語られた時代でした。
フランスでは、ワールドカップレーサーの
パトリック・リュッセルの技法が注目され、
アバルマン技法と呼ばれました

*この時のパトリックリュッセルの、マテリアルは
スキー板:ロシニョール(ストラート102)
スキー靴:エッシング
ストック:ケルマ
いやー、このヴェ―レンテクニック(アバルマンテクニック)
曲者でした。
この技術の本質を知らずして、後傾姿勢と低い姿勢のみが目に焼き付き、
私のスキー技術の進歩は止まってしまいました。
このような革新的な技法が入ってくるもんだから、
当時、ゲレンデはコブだらけだったような気がします。
山回りクリスチャニアは、
どこへいっちゃたんだ。
後傾ゆえオーバースピードとなり、スキーに乗せられてる感じ。
コントロールが効かない。
姿勢が低いから、テクニックの幅が狭い。結果、
リカバリー幅が狭い。そして、カッコ悪い。
しばらくの間、ゲレンデは、
ロデオ大会か、暴走族の集まりの
ようでした。
これではいけない、原点に戻り
腰を高く、前傾しなければ。
「高い前傾姿勢」を取り戻すのに、
この後、1~2年かかったように思います。
まだまだ、私のスキーは進化します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。🙇♀️🙇♀️🙇♀️
この続きは、パート2でお話させていただきます。
よかったら、読んでみてください。😊
