
建築家・松村正恒研究と日土小学校の保存再生をめぐる個人的小史 [7]2004年:第1回「夏の建築学校」の開催と成功、そして思わぬ大事件(後編)
花田佳明(神戸芸術工科大学教授)
前回は、2004年8月6日と7日に日土小学校を会場として行われた第1回「夏の建築学校 日土小」初日の様子を書いた。今回は2日目のことと、その後に起こった思わぬ大事件の話である。
*
翌8月7日(土)は日土公民館で朝食をいただいた後、日土小学校の体育館へ移動。そこには日土小学校の子供たちが来てくれていて、対面式とラジオ体操をした。

対面式(日土小学校の子供たち)

対面式(夏の建築学校の生徒たち)

みんなでラジオ体操
そして校舎への恩返し。各自持参した雑巾を取り出し、全員で校舎を掃除した。掃除という行為は建物の細部を理解するのにとてもよい。指先で各所の納まりがわかるし、手が届くかどうかで高さが実感できたりする。各所の痛み具合、木の肌合いなども全員が体感したに違いない。
私事で恐縮だが思い出話を披露すると、「花田先生宛に荷物がありますよ」と言われ驚いたら、実家の母親から雑巾を詰めたダンボール箱が日土小学校に届いていた。こんな企画をすると何かの折に私が電話で話したのだろう。

廊下の雑巾掛け

忍者のような掃除風景

高いところも掃除

雑巾掛け終了
掃除が終わると次は子供たちとの交流会を行なった。体育館で七夕の飾りを一緒に作り、校庭に用意された2本の笹に飾りつけて記念撮影をした。

子どもたちと飾りを作る

笹への取りつけ

完成
これで全ての行事が終わり、最後は体育館で閉校式。まず参加者が輪になって座り、2日間を振り返りながら、それぞれの感想を述べ合った。嬉しいことに、日土小学校と2日間の経験を高く評価し、日土小学校の存続を望む発言が続いた。

参加者が感想を述べる
そして菊池「校長」から全員に修了証書の授与が行われたが、よく見ると「仮修了中であることを証します」と書いてある。同時に宿題が出され、その提出をもって「本修了」とするという仕掛けだった。宿題は、「(1)日土小学校の建築について、(2)日土小学校の保存について、(3)夏の建築学校について」感想や意見を述べよというもので、提出されたレポートは、後述する冊子に掲載された。

仮修了証書の授与
最後の昼食も地元の皆さんによって用意されていた。日土公民館でカレーライスとちらし寿司。これをいただき、2日間のスケジュールはすべて終了した。

最後の昼食
私は、日土公民館を出てその前を流れる喜木川を眺めながら、たいへん幸せな気持ちを味わっていた。日土小学校を多くの人に知ってもらい、しかも高く評価され、そして何より保存を望む地元の皆さんと良好な関係が築けたと思えたからである。これで保存運動はうまく進んで行くに違いないと確信した。青臭くて恥ずかしいが、学校っていいなあ、宮沢賢治のユートピアみたいだなあなどと思った記憶もある。
お世話になった皆さんにお礼を言い、学生たちと帰路に着いた。

日土公民館と日土小学校の横を流れる喜木川

ゼミ生と記念写真
*
神戸に戻ってからも幸せな気持ちは続いていた。ところが9月初め、大事件が起きたのである。
西日本各地に大きな被害をもたらした台風18号の強風が、9月7日、日土小学校東校舎の北東部分(廊下端部)の鉄板屋根を、野地板と垂木直張りの天井板ともども吹き飛ばしてしまったのだ。図書室や渡り廊下などのガラスも割れた。
第一報は、木霊の学校日土会の菊池さんからだったか。当時の手帳を見ると彼の名前と電話番号が書いてある。これは大変なことになったと驚き、夏の建築学校の楽しかった思い出も一瞬で吹き飛んでしまった。

東校舎廊下の屋根の被害状況

廊下端部の見上げ

渡り廊下や図書室のガラスも割れた
幸い、現地の対応は早かった。夏の建築学校のことをまとめた報告書(後述)の杉山博司さんの文章によれば、翌9月8日に八幡浜市建設課や関係者で応急対策の検討に入り、10日から修繕工事が始まった。そして大部分の作業を9月いっぱいで終え、学習に差し支えない状態になったのである。また被害翌日の早朝から、大勢の保護者、先生方、地域の皆さんが校庭に散ったガラス片などの回収にあたり、翌々日には運動会に向けた練習が無事行われたそうである。

早速始まった修繕工事

とりあえず使えるようになった運動場
修理の状況を確認するため、10月1日に関係者が日土小学校へ集合した。2階廊下部分の工事は終わり、1階の昇降口の天井などがまだという状況ではあったが、胸をなでおろした次第である。

東校舎端部の様子。2階廊下屋根の修理が終わっている

廊下端部の外観

奥の2スパンほどの屋根が新しくなった

新旧天井板の対比

ガラスを交換した部分には押縁が付けられた

天井を工事中の1階昇降口
しかしこの出来事をきっかけに、地元の皆さんからは古い木造校舎の安全性を疑問視する声が上がるようになり、日土小学校の保存問題の状況は一気に厳しいものとなってしまった。関係者は、地域の方々の中にも実はさまざまな意見があるということにやっと気づき、これからの運動の進め方を考え直す必要に迫られたのである。
*
ところでこの被害にともない大発見があった。屋根が吹き飛んだ東校舎の廊下端部には小さな部屋があるのだが、物置として使われ開かずの間になっていたため、保存関係者は入ったことがなかった。ところがその屋根が吹き飛んだおかげで初めて内部を見たところ、そこには何とも優雅な意匠の空間が隠れていたのである。
実はこの部屋は倉庫ではなく実施設計図には「補導室」と書かれており、先生が生徒にお説教をしたり、相談事を聞いたりした部屋ではないかと想像された。その部屋の壁が、金揉み紙と絣の市松模様で仕上げられていたのである。またそれ以外の壁は焼杉板で、窓には鎧戸があり、一般の教室とは違う特別な仕上げになっていた。松村が込めた子供たちへの優しい思いを関係者一同感じたのであった。参考までに、保存再生後の写真も載せておく。

「補導室」内部

「補導室」から廊下を見る

保存再生後の様子。天井は原設計に従い銀箔クロス貼り。壁も金揉み紙と絣や焼杉板で作り直した。光っている部分は透明のアクリル板で、その下にはオリジナルを残した
*
今回の企画をまとめた報告書『夏の建築学校 日土小』(日本建築学会四国支部学校建築探求団特別委員会)は翌2005年の1月に刊行された。これもきわめて盛りだくさんの内容だ。

『夏の建築学校 日土小』の表紙
巻頭は曲田先生の「はじめに」。夏の建築学校の総括から台風被害、そして保存運動の展望までが簡潔に書かれている。その後には、山名先生によるドコモモの活動を紹介する「国際的な拡がりをもつドコモモの活動について」、高安先生の「地域におけるモダンデザイン」、参加した愛媛大学の学生さんが写真やイラスト入りで2日間をまとめた「夏の建築学校 ドキュメント」、修了条件として提出されたレポートを並べた「夏の建築学校 卒業小論集」、私の「真の学校としての日土小学校—夏の建築学校を振り返って—」、七夕飾りを作っているときに参加者へ行ったアンケートを曲田先生と愛媛大学の学生・板井麻理子さんが集計・分析した「受講生が結びしもの—アンケート結果について—」、「校長」であった菊池さんの「夏の建築学校 受講生の皆さんへ」、岡崎さんの「日土小学校とまちづくり」、木霊の学校日土会の菊池彰さんによる「日土を襲った台風18号」、そして前述の杉山さんによる「台風被害と修復状況」である。

スケジュールなど
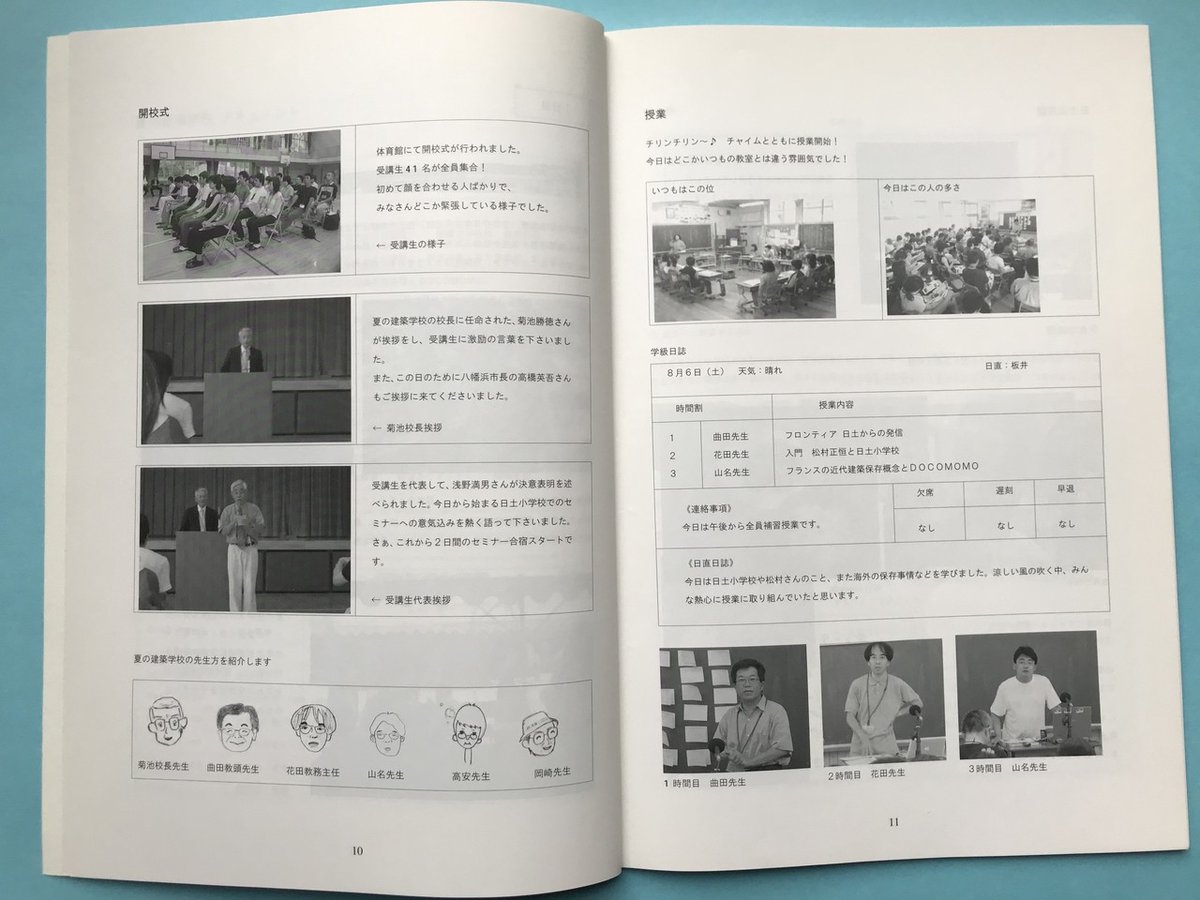
開校式と授業
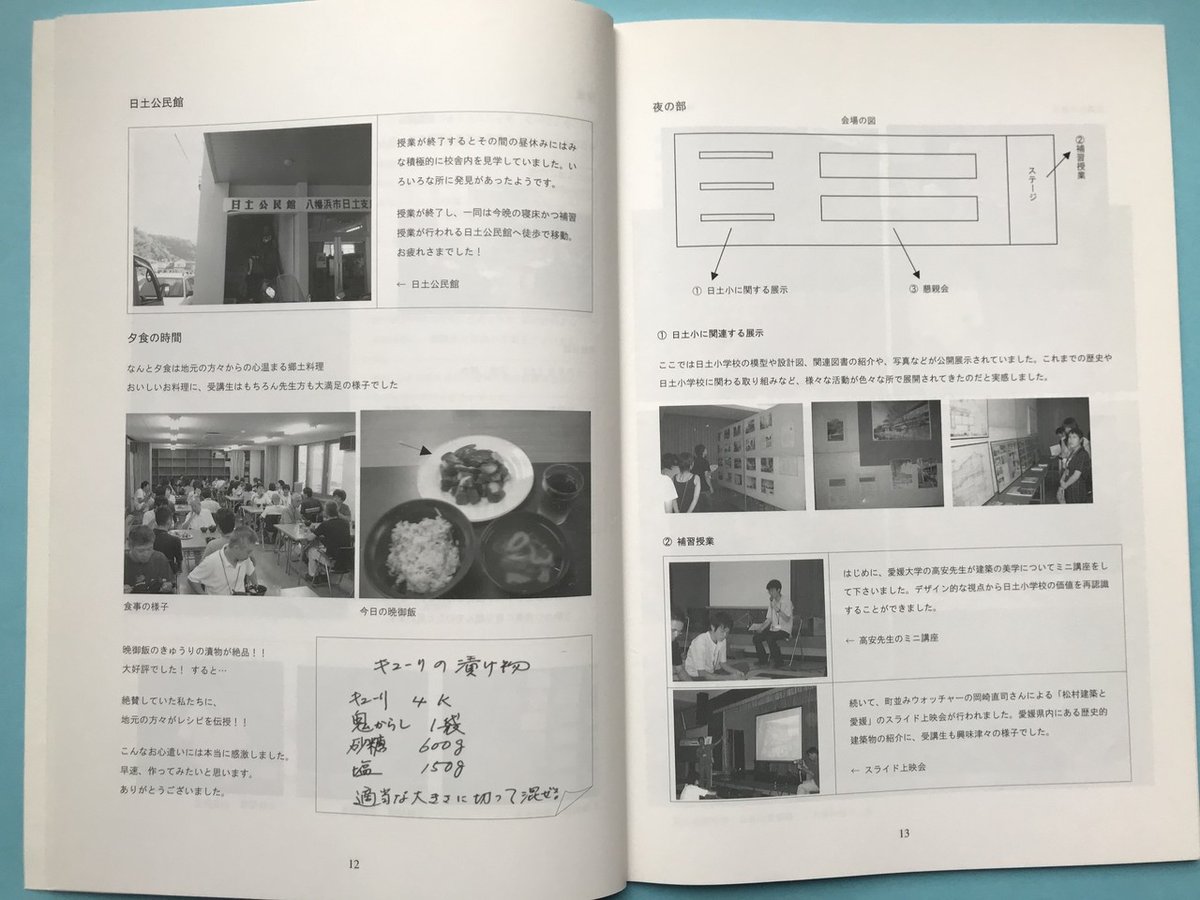
日土公民館での夕食と授業

日土公民館での授業と懇親会

ラジオ体操、掃除、七夕の飾り作り

七夕飾り完成

閉校式と卒業小論集の最初の頁

台風被害についての杉山さんの記事
そして最後に資料として、「日土小学校建物の再生に関する要望書」がつけられた。これは、日本建築学会四国支部、日本建築家協会四国支部、愛媛県建築士会、愛媛県建築士事務所協会という建築関係4団体の連名で、2004年1月6日付で八幡浜市長宛に提出されたものである。台風被害による状況の変化を受け、関係者の間で高まった危機感の反映といえるだろう。これが日土小学校に関する最初の保存要望書となった。
こうして日土小学校の保存活動は、次第に具体的かつ本格的な段階へと移って行ったのである。

4つの組織からの保存要望書
[記事の写真や図の無断転載はお断りします]
