
ペットを連れた「同行避難」って?
こんにちは。はまみらいプロジェクトの坂元です。突然ですが、皆さんのお宅ではペットは飼われていますでしょうか。毎日の疲れを癒してくれるペットがいてくれるおかげで日々の辛いことも乗り越えられる、もはやペットは家族同然のかけがえのない存在だ、なんて方も多いのではないかと思います。しかし、地震や洪水などの災害が起きた時、ペットはどこに避難したらいいのでしょう。飼い主と同じ避難場所に連れていくとなると、いつもとは違う環境に犬や猫でも人間と同じように不安な気持ちを感じると思います。
今回は、災害時ペットは一緒に避難した方がいいのか、ペットとの「同行避難」には何が必要なのかなどを、実際の被災地の状況も交ぜながら紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
1.能登半島地震での実情
今年の元日に起きた能登半島地震では、能登半島の北部だけでも犬と猫およそ1万匹が地震の被害に遭ったと推定されています。しかし、それらすべてのペットが飼い主とともに避難したわけではありません。被災後のペットは、被災した家に取り残される場合と飼い主と同行避難する場合の2パターンに分けられます。この2パターンについて、詳しく紹介します。
1-1.置き去りにされるペット
地震発生直後は飼い主自身も身の安全を守らなければならず、ペットがすぐに見つからない場合はやむを得ずペットを置いて避難するケースも多く見られます。置いていかれたペットたちは災害の影響で亡くなってしまうか、あるいは野生化してしまう場合がほとんどです。被災地ではそんなペットたちを1匹でも多く飼い主の元に帰すために、複数のボランティア団体が活動を行っています。
彼らの活動内容は、飼い主の依頼を受けて特定のペットの捜索を行うこと、または野生の犬や猫を保護し、インターネットやSNSを使って飼い主を探すことです。中には石川県や環境省と協力しながら活動を行っている団体もあり、まさに官民協力のもとペット及び飼い主の救済が行われています。中には、被災してしまってこれまで通りペットを飼うのが困難になってしまった飼い主の代わりに、新しい飼い主にペットを譲る譲渡の形が取られている場合もあります。
1-2.同行避難したペット
ペットの避難についての対応は各避難所によって異なりますが、基本的には人が生活する場所とペットを飼育する場所を分けることが多いです。避難した方々の中には動物が苦手だったり、アレルギーを持っている方も多いためです。こういった「住み分け」は多くの人が一緒に生活する避難所ではとても有効な方法だと考えられます。しかし、ペットの飼育はケージの中で行うことが前提とされるため、受け入れが困難な場合もあります。暖房のある部屋を確保できない、ペットの鳴き声が響くなどの理由から、車中泊を選ぶ被災者の方も多かったという現実もあります。また、ペットにかかるストレスや飼い主自身のペットと一緒にいたいという気持ちから、避難所での生活をやめて被災した家に帰るといったペット優先の避難行動を行ったり、犬と猫も人間と同様にケガをしたりストレスを抱えて病気が流行したなど、被災後のペットの対応については未だ多くの問題が残されています。
2.国や自治体の動き
2011年に発生した東日本大震災では多くのペットが放浪したことが課題の一つとして挙げられたことを受け、環境省は「人とペットの災害対策ガイドライン」を策定し、人とペットが一緒に避難する「同行避難」を推奨しています。このガイドラインには「災害時には何よりも人命が優先されるが、近年、ペットは家族の一員であるという意識が一般的になりつつあることから、ペットと同行避難をすることは、動物愛護の観点のみならず、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要である。(中略)しかし、当然のこととして、飼い主とペットが安全に避難するには、飼い主自身の安全の確保が大前提となる。」と書かれています。過去の災害ではいったん避難した飼い主がペットの安全を危惧して一度自宅に戻ったことにより、被害に巻き込まれるケースが多発している現状があります。ペットの安全を守るためには、まず飼い主が安全な環境にいなければならないことを忘れてはなりません。
能登半島地震の際には、県や市町村が相談窓口を設置したほか、犬や猫の保護情報を掲載したサイトを開設したりペット用の支援物資を配布するなど、過去の災害での課題を踏まえた対策が取られていました。
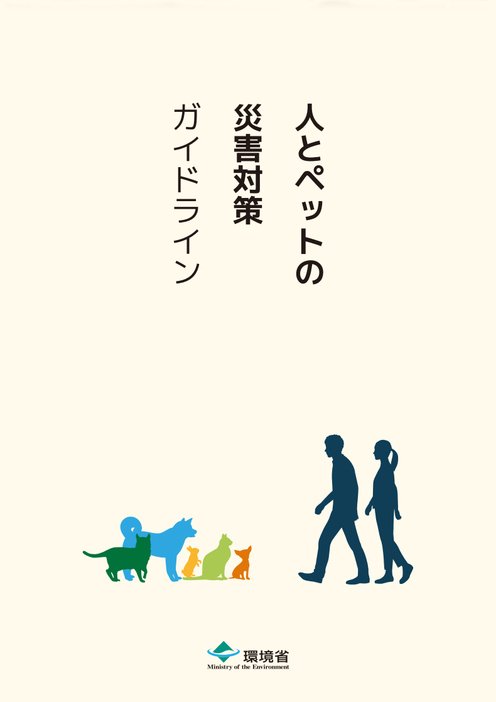
3.私たちにできる対策や準備
飼い主が日頃からできる災害対策をまとめました。
① ワクチン接種やマイクロチップ等の手続き
② 最低限のしつけ、ケージや車中に慣らす訓練
③ ペットフード、水、リード、ケージ、ペットシーツなどの避難セットの準備
④ ペットの受け入れ対応を含めた避難場所の確認
最も大切なことは「普段から様々な環境に慣らしておくこと」だと思います。普段から様々な場所にペットを連れていくことが、知らない場所に行っても過度なストレスを感じないことにつながります。災害が起こってしまった場合でも落ち着いて行動できるよう、日ごろから災害対策を十分に進めておくことが大切です。
また、ペットを飼っていない人でも避難場所ではペットやその飼い主への配慮が必要になる場合があります。避難先での生活は今までの日常生活とは違う不便さを誰もが抱えているからこそ、他者を排除するのではなく、お互いを思い合う「共助」の姿勢がとても大切になります。災害が起きてしまった際は、困難な局面をみんなで乗り越える協同意識を持つことは、私たちがこの国で生きていくうえでとても大切なことであると思います。
そして、私の祖父の家では中型犬を1匹飼育しているので、祖父になにか災害時の対策はしているのか聞きました。祖父の家ではエサを管理する棚や普段散歩の際に使う鞄を玄関のすぐ横に置いて緊急時にもすぐに使えるようにしているそうです。また、遠くに散歩に行く際には車の椅子を倒して犬を乗せているので、車中泊を余儀なくされた場合でも大きな混乱はなく過ごせるのではないかと話していました。そして私がいちばん印象に残ったのは、犬の首に名前、住所、電話番号が書かれたプレートを普段から下げていることです。災害が起きて万が一はぐれてしまった場合でも、それらの情報をもとにまたすぐに会うことができるのではないかと思いました。

4.終わりに
私は昨年横国で開催されたぼうさいこくたいでNPO法人ペット防災のサポート協会のブースを見たことをきっかけに、今回の記事を執筆しました。能登半島地震でもペット避難が大きな問題になっていたことを知り、災害によってなくなってしまうペットたちの命が、少しでも減っていってほしいと感じます。災害時は互いに支え合うその気持ちが、ペットたちにも向いていく世の中であってほしいと感じました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参照
https://www.nhk.jp/p/ts/X67KZLM3P6/episode/te/9NPMQM3PX8/
https://www.youtube.com/watch?v=FCIjWmne2Eg&t=457s
https://noto-rescue.com/
https://www.asahi.com/articles/ASS1N3T0VS1MULZU005.html?msockid=39809304e2a76e490a73805de34d6f47
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/poster09_2.pdf
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/a-1.pdf
都市科学部都市基盤学科 坂元夏希
#はまみらいプロジェクト
#はまみらい防災
#横浜
#横浜国立大学
#ペット
#同行避難
