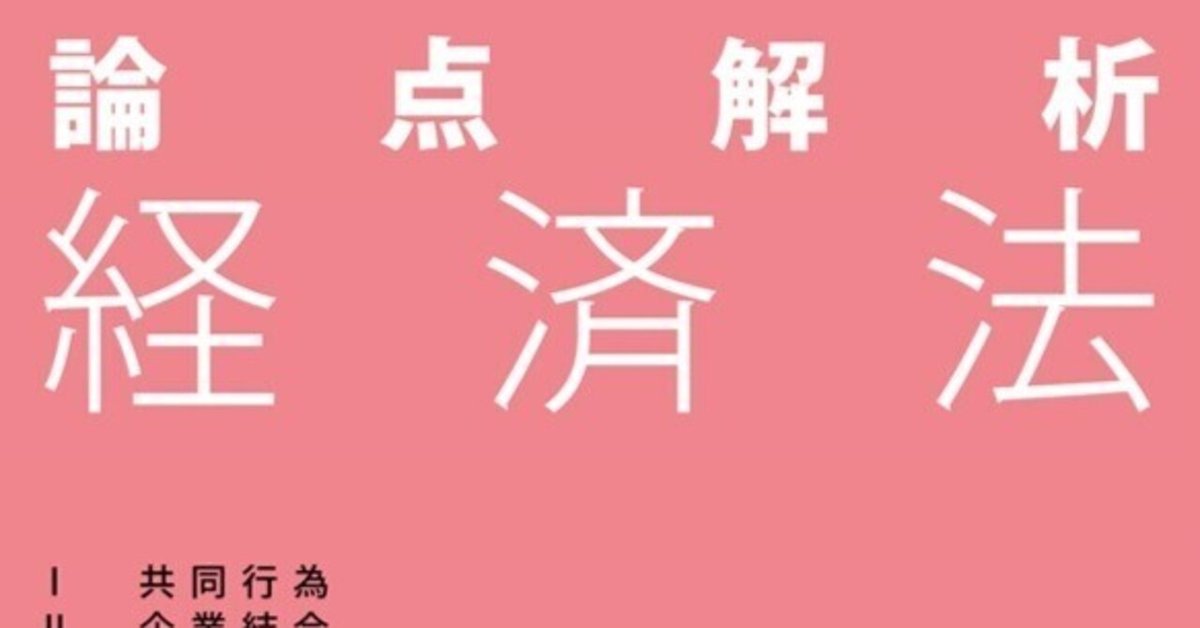
論点解析経済法(第2版)Q7 解答例
こんにちは。本日もお昼の投稿です。
本日は、昨日に引き続き、『論点解析経済法(第2版)』の解答例です。本日投稿する解答例は、Q7です。この問題は、個人的に重要度が高い問題だと思います!。経済法を選択科目として司法試験を受験する方は、Q7を絶対に解いてみてください!時間に余裕がなければ答案構成だけでもいいので!
では、以下、解答例です。
第1 ①部品の共同購入について
1 A社及びB社が、Xを製造するために必要な部品を共同購入することは、不当な取引制限(独占禁止法(以下、法名省略)2条6項)に該当し、3条後段に反し、違法とならないか検討する。
2 「事業者」(2条1項)とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、「他の事業者」(2条6項)とは、実質的な競争関係を含む、相互に競争関係にある独立の事業者のことをいう。
本件において、A社及びB社は、事業者向けの商品Xを製造販売する機械メーカーであるから、「事業者」(2条1項)に該当する。また、A社及びB社は、いずれもXを製造販売する機械メーカーであるから、相互に競争関係にあるといえる。そのため、一方の事業者から見て、他方は、「他の事業者」であるといえる。
したがって、「事業者」(2条1項)であるA社及びB社は、それぞれ、他方の「他の事業者」(2条6項)と部品の共同購入を計画していると認められる。
3 「共同して」とは、事業者間に意思の連絡があることをいう。そして、意思の連絡とは、複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、明示の合意をすることまでは必要ではなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りる。
本件において、A社及びB社は、Xに関し、最近、需要が低迷し部品の値上がりが著しいことから、コスト削減の方策として部品の共同購入を計画しているため、A社及びB社の間には、部品の共同購入についての明示の合意に基づく意思の連絡があるといえる。
したがって、A社及びB社は、「共同して」部品の共同購入を計画していると認められる。
4 「相互にその事業活動を拘束」するとは、複数の事業者が、意思の連絡・合意により、本来自由であるべき事業活動が制約されていることをいう。
本件において、A社及びB社は、個々の部品ごとに両社の購入予定数量を合計した上で、部品メーカーとの交渉窓口をA社又はB社に一本化し、その合計数量で単価をどこまで引き下げることができるかを交渉し、両社にとって最も有利な条件の購入先1社から同一単価で当該部品を購入することにしているため、購入先を制限することにより、本来自由であるべき事業活動を制約しているといえる。
したがって、A社及びB社は、「相互に事業活動を拘束」することを計画していると認められ、実際に部品の共同購入を行った場合には、共同して「遂行」したと認められる。
5 「一定の取引分野」とは、市場、すなわち、特定の商品・役務の取引をめぐり供給者間・需要者間で競争が行われる場であり、商品・役務の範囲、地理的範囲等に関して、基本的には、①需要者にとっての代替性という観点から判断される。また、必要に応じて、②供給者にとっての代替性という観点も考慮される。
(1)まず、共同購入の対象となる部品は、Xのみに使用されていることから、共同購入の対象となる部品に供給の代替性はない。そのため、商品の範囲として、Xの各部品の購入分野を画定することができる。
次に、Xの各部品の購入費用は、Xの製造コストの約80%であり、Xの製造コストは、製品価格の約80%であるから、Xの製品価格の約64%についてのコストが共通化されることとなり、さらに、両社は、Xの販売価格の上限を協議して決めておくことも検討しているため、Xの製造販売分野においても競争が生じうる。そして、Xは、機能・効用等が特殊であって、需要者にとってXに代わる商品は存在しないことから、他の商品とXとの間には需要の代替性が存在しない。また、Xを製造するためには、特殊な設備・技能が必要であるため、供給の代替性も存在しない。そのため、商品の範囲として、Xの製造販売分野を画定することができる。
(2)地理的範囲については、外国においてXは製造・販売されていないことから、日本国内であると画定できる。
(3)したがって、本件で問題となる「一定の取引分野」は、日本国内におけるXの各部品の購入分野と、日本国内におけるXの製造販売分野であると画定する。
6 「競争を実質的に制限」するとは、特定の事業者又は事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことができるという意味での市場支配力を形成、維持又は強化することをいう。
(1)日本国内におけるXの各部品の購入分野について
Xの製造販売分野における各社のシェアは、A社50%、B社25%、C社25%である。部品の共同購入を実施した場合、A社及びB社のシェアは75%となり、競争者であるC社のシェアは25%であるから、部品の共同購入により格差が拡大することとなる。また、他の競争者であるC社がより高い部品価格を提示して当該部品をより多く購入することができる余力があることを示す事情はなく、C社による競争圧力は小さいと考えられる。また、A社及びB社は、Xの販売価格の上限を協議し決めておくことも検討しているが、上記5(1)の通り、Xの部品の価格はXの製品価格の約64%を占めることから、Xの販売価格の上限を決めることは、実質的に部品の購入価格の上限を決めることとなる。そうであるならば、当該取決めは、部品の購入競争を回避する取決めであるといえる。そのため、部品の共同購入は、上記市場において、「競争を実質的に制限」するとも考えられる。
もっとも、A社及びB社による部品の共同購入は、Xの需要が低迷し部品の値上がりが著しいことから、コスト削減の方策として行われるものであり、共同購入によるスケールメリットを活用することにより、競争促進効果が生じる。しかし、本件においては、どのようなスケールメリットが達成されるのかについての事情がなく、どれほどの競争促進効果が生じるのかが明らかではない。そのため、前記競争制限効果を上回るほどの競争促進効果があるとはいえない。
したがって、部品の共同購入は、上記市場における「競争を実質的に制限」すると認められる。
(2)日本国内におけるXの製造販売分野について
本件において部品の共同購入の対象となる部品の購入費用は、上記5(1)の通り、Xの部品の価格はXの製品価格の約64%を占める。そうすると、A社及びB社による部品の共同購入により、合計で75%のシェアを有する事業者間で、約64%というXの製品価格の大部分が共通化され、A社及びB社との間で独自に競争する余地が減少する。また、Xの需要は低迷しており、積極的に増産して利益が得られるような状況にはなく、Xは、主要部品の規格や仕様が共通する事業者向け機械であることから、相対的に差別化されるものでもない。そうすると、A社及びB社の両社の利害が一致して、両社間において協調的行動が生じやすくなり、また、C社もA社及びB社による協調的行動に追随すると考えられる。そのため、このような協調的行動により、上記市場において「競争を実質的に制限」するとも考えられる。
もっとも、共同購入によるスケールメリットの達成により部品の購入費用を削減することができれば、当該部品を使った商品の販売価格も下がる可能性があり、競争促進効果をもちうる。しかし、本件においては、A社及びB社の合計シェアが高く、コストが共通化する部分がXの製品価格の約64%と大部分を占める。また、Xの販売価格の上限を協議することも検討されている。そのため、前記競争制限効果を上回るような競争促進効果が生じるとはいえない。
したがって、部品の共同購入は、上記市場における「競争を実質的に制限」すると認められる。
7 「公共の利益に反」するとは、独占禁止法の保護法益である自由競争経済秩序の維持に反することをいう。
本件において、上記6の通り、部品の共同購入により、日本国内におけるXの各部品の購入分野及び日本国内におけるXの製造販売分野の競争を実質的に制限することになるため、自由競争経済秩序の維持に反しているといえ、例外的に公共の利益に反していないとする特段の事情も存在しない。
したがって、部品の共同購入は、「公共の利益に反」する。
8 以上より、A社及びB社による部品の共同購入は、不当な取引制限(2条6項)に該当し、3条後段に反し、違法となる。
第2 ②共同物流会社の設立について
1 A社及びB社が、共同出資会社である甲を設立し、物流の共同化を計画する行為は、不当な取引制限(2条6項)に該当し、3条後段に反し、違法とならないか検討する。
2 上記第1の2の通り、「事業者」(2条1項)であるA社及びB社は、それぞれ、他方の「他の事業者」(2条6項)と物流の共同化を計画していると認められる。
3 上記第1の3の通り、A社及びB社は、Xに関し、最近、需要が低迷し部品の値上がりが著しいことから、コスト削減の方策として共同物流会社である甲の設立を計画しているため、A社及びB社の間には、共同物流会社甲を設立することについての明示の合意に基づく意思の連絡があるといえる。
したがって、A社及びB社は、「共同して」共同物流会社甲の設立を計画していると認められる。
4 A社及びB社は、千葉市及び堺市の各工場に甲社が運営する共同物流センターを設け、各共同物流センターは、両社製のXを一定数在庫し、1台のトラックが両社製のXを積載して配送する混載方式を採り、両社は、それぞれの受注に関し、納品書を甲社に送付し、甲社の従業員は、各共同物流センターの輸送能力や両社製のXの在庫状況を勘案して、最も効率的に配送できるよう、トラック配備及び配送ルートを調製することとしている。そのため、A社及びB社は、物流の方法を限定していることから、本来自由であるべき事業活動が事実上拘束されているといえ、「相互にその事業活動を拘束」していると認められる。
5 「一定の取引分野」は、上記第1の5の通り、商品・役務の範囲、地理的範囲等に関して、基本的には需要者にとっての代替性という観点から判断し、必要に応じて供給者にとっての代替性という観点も考慮して、画定する。
(1)上記第1の5(1)の通り、Xには需要者にとっての代替性はない。また、A社及びB社における物流コストはXの製品価格の約10%を占めることから、物流の共同化により、Xの製品価格の約10%についてコストが共通化されることになる。そのため、本件における商品の範囲は、Xの製造販売分野であると画定できる。
(2)地理的範囲については、外国においてXは製造・販売されていないことから、日本国内であると画定できる。
(3)したがって、本件で問題となる「一定の取引分野」は、日本国内におけるXの製造販売分野であると画定する。
6 上記第1の6の通り、「競争を実質的に制限」するとは、市場支配力を形成、維持又は強化することをいう。
本件において、物流の共同化を計画することにより、A社及びB社の合計販売シェアは75%を占めることとなり、両社の物流コストは共通化するものの、共通化される物流コストは、Xの製品価格の約10%を占めるにすぎない。そのため、A社及びB社が、それぞれ独立して競争を行う余地は十分にあるため、競争者からの圧力はあるといえる。また、A社及びB社が物流の共同化を計画したのは、全国に散在する需要家への配送について、トラックの利用効率の向上や配送時間の短縮等を図るためであり、1台のトラックで両社製のXを積載する混載方式での配送は、前記目的を具体的に実現する可能性が高く、需要家へのサービスの向上につながり、競争促進効果があるといえる。
もっとも、甲社では、出資会社であるA社及びB社から、それぞれの従業員が出向して甲社の従業員となり、いずれからの出向であるかを問わず、両社製のXの配送業務に従事し、両社は、それぞれの受注に関し、需要家の名称及び所在地ならびに受注数量、納期及び販売価格を記載した納品書を甲社に送付することになっている。そのため、A社及びB社間のXをめぐる販売競争にとって重要な秘密情報を甲社の従業員が知ることができることになり、A社及びB社との間で、Xの販売について協調的な行動をとるようになるおそれがある。
したがって、甲社とA社及びB社それぞれとの間で、情報遮断措置を設けるなどの措置が採られない限り、A社及びB社による物流の共同化は、市場支配力を形成、維持又は強化するといえ、「競争を実質的に制限」すると認められる。
7 「公共の利益に反」するとは、独占禁止法の保護法益である自由競争経済秩序の維持に反することをいう。
本件において、上記6の通り、甲社とA社及びB社それぞれの間で情報遮断措置が採られない限り、日本国内におけるXの製造販売分野における競争を実質的に制限するため、自由競争経済秩序の維持に反するといえ、例外的に公共の利益に反していないとする特段の事情も認められない。
8 以上より、甲社とA社及びB社それぞれの間で情報遮断措置が採られない限り、共同出資会社である甲を設立し、物流の共同化を計画する行為は、不当な取引制限(2条6項)に該当し、3条後段に反し、違法となる。
以上
以上になります!解答例を読んでいただければおわかりだと思いますが…この問題は非常に長く、負担が大きい問題ですよね…。この問題に取り組むのは大変だと思いますが、チャレンジしてみてください!あ、もちろん、この解答例も教授の添削を経ています。
長文を読んでいただき、ありがとうございました。
