
戦国・幕末好き歴女が見た博展イベント事務局の軌跡
展示会・企業の主催イベント・プライベートセミナーといったイベントを開催するために、『事務局』と呼ばれる業務があることをご存じでしょうか。
『事務局』は、イベントに来場するお客様の問い合わせ対応、展示をする出展者の提出物回収、セミナーの講演者へのご案内など、さまざまな業務を主催・クライアントに代わり実施します。
多様なクライアントのイベント企画・運営を実施する博展には、この『事務局』業務を担当する「イベントマネジメント課(イベマネ)」というチームがあります。
この記事では、博展の事務局立ち上げから現在のイベマネに至るまでの進化の歴史をご紹介します。
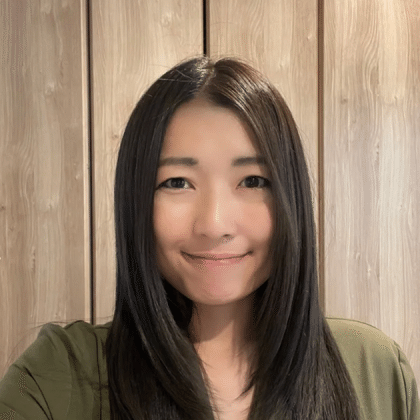
<記事を書いた人>
Unit1 イベントマネジメント課 野本
2013年 博展に中途入社。事務局ディレクターを担当
写真が盛り気味だという人もいますが、何か?
そもそも博展事務局ってどういうことをしているの?
イベント本番に向けて大きく以下3つの事務局を、長いと会期半年以上前、多くは会期2~4か月前から運営しています。
出展者 / 協賛社事務局
講演者事務局
来場者事務局

と、様々な業務を担っていますが、詳細は字が小さくて読めないと思うのでもっと知りたい方はお気軽にお問い合わせください!
ここからは、博展事務局チームが立ち上がり、進化を遂げた歴史について時系列に沿って説明していきます!
0.博展事務局チーム立ち上げ前|戦国時代
2010年頃、主催イベントの設営・運営を受注する中で、事務局対応が必要になる案件が出てくるように。しかし、まだ博展内に事務局専門のチームはなく、クライアントの要望を受けて営業担当が事務局対応も行っていた。
当時は、事務局対応用のノウハウやツールもないため、営業活動と並行して対応することはとても大変だった。
>>当時の営業担当 K島氏はこう語る・・・
「当時社内に事務局のリソースがなく、所属する課に1名いるコーポレートスタッフの方に手伝ってもらっていたものの、出展者の個別対応は営業の仕事でした。
僕自身は過去80〜100社ほどの出展社対応を行う必要のあるプロジェクトを年に2度請け負っており、とにかく出展者マニュアル作成から電話対応、メール対応とほぼそれに付きっきりになってしまっていました。
特にノウハウもない中だったので、常に後手に回ってしまい日々追っかけ対応に翻弄されていましたね。
また、営業自身が行なっているので情報は 個々の管理に委ねられており、自分がパンクしたらすべてが止まってしまうんです。。。
今では営業自身がすべて出展者対応をするなんて考えられないですね。」
天下統一!!!クライアント要望に応えるべく、それぞれのやり方ではない統一したノウハウをもつ専門の事務局チームを博展内に作ろう!!(事務局幕府の成立)

1.博展事務局立ち上がり期|事務局幕府による統治(江戸時代)
2012年頃、合同展示会・商談会イベントに加え、セミナー&カンファレンス案件の企画・運営を専門にする部署が博展内に誕生。主催イベントで対応していた「出展者事務局」だけでなく、「講演者事務局」「来場者事務局」の対応など事務局業務も拡大。
事務局業務のノウハウ拡充に加え、専用のシステム・ツールを導入することで、運営の安定化、事故の防止・減少につながった。

一方で、まだ博展の事務局運営に向いたシステム・ツールが世に少なく、事故防止対策がシステマチックではない、ヒューマンリソースをかけたダブルチェックの実施など、ヒューマンエラーのリスクや個人のスキルに依存する部分があった。
2.事務局成長期|システム運用強化の黒船来航(幕末)
2016年、スプラシアの博展グループ化もあり、事務局案件の引き合いも増加、それに伴い事務局人員も増加。初めて事務局業務に携わるというスタッフも少なくなかった。
そして、世の中の更なるセキュリティ強化の波が押し寄せてくる。
これまでの業務体制では、ヒューマンスキル依存・業務効率性・運営セキュリティの面でもいろいろ限界が近い・・・。
これらの課題を解決するために外部ツールを取り入れよう!情シスとともにツールの選定・導入検討を開始!

3.事務局業務の複雑化|西洋文化流入近代化(明治維新)
2019年、これまで展示会・主催案件系とカンファレンス案件系で別々の部だった事務局チームが「イベントマネジメント部」として1つに統合。
イベント毎のブース仕様・オプション商品/サービスの複雑化により、事務局で収集する情報や出展者要望も多様性を増していく。
海外出展者対応が必要になり入金管理が複雑化するなど、これまで以上に様々な対応が事務局に求められるようになる。
より出展者の負担が少ない、かつ更なる事務局運営の効率化を目指そう!!

4.コロナ禍の到来、働き方・イベントの多様化|多様性の時代(大正デモクラシー)
2020~2021年頃、リモートワークの普及とともに、リアルイベントからオンライン・ハイブリッドイベントに世の中のトレンドが変化。それまでは事務局を設けていなかった案件も、オンライン視聴方法(Zoom URLなど)のご案内、当日視聴できない場合の問い合わせ対応、視聴ログ管理・集計などを行うため、来場者事務局を設置するケースが増えていった。
博展事務局もリモート対応できる体制が必要になり、イベント毎の多様な配信プラットフォームに対応するため、各システムの使い方や運用方法の知識が求められるようになった。
当時の配信プラットフォームは発展途上の部分もあり、現在では自動でデータ管理・集計可能な作業を人海戦術で対応する場合もあった。事務局チームはデータの集計、複数リストの紐づけ作業等も業務の一環として行っていた。
働き方やイベントのあり方が多種多様になり、いろいろな選択肢から選べる時代になった。

5.そして現在へ・・・
イベマネでは事務局業務の運営クオリティの均一化・業務効率化・運営セキュリティの面から中長期的に活用できるツールを情シス協力のもとに導入・運用管理を行っています。
イベマネの進化とともに導入してきた各種のツールは、特定多数との情報のやりとり(案内・回収・管理)をするという業務に向いています。
例えば、こんなお悩みはないでしょうか?

そのお悩み・・・イベマネで対応、または、イベマネで使用している実績のあるツールを紹介できるかもしれません。是非ご相談ください!
今回は、その時代の事務局運営の課題をどのように解決してきたかを紹介させていただきました。
イベマネは、日々時代の流れに合わせてより安全・効率的な運営を創意工夫しています。
最後に、時代をリードした偉人の名言を一つ
「一歩一歩、着実に積み重ねていけば、予想以上の結果が得られるだろう」(豊臣秀吉)
最後まで読んでいただきありがとうございました!
【Special Thanks】※敬称略
木島 大介・村松 加奈江・松田 光憲・井口 三千栄・佐藤 良昭・柿崎 織夢・菅野 大輔・野田 優貴 ・辻 雅子・地引 巧・井本 菜緒・三木 翔平
