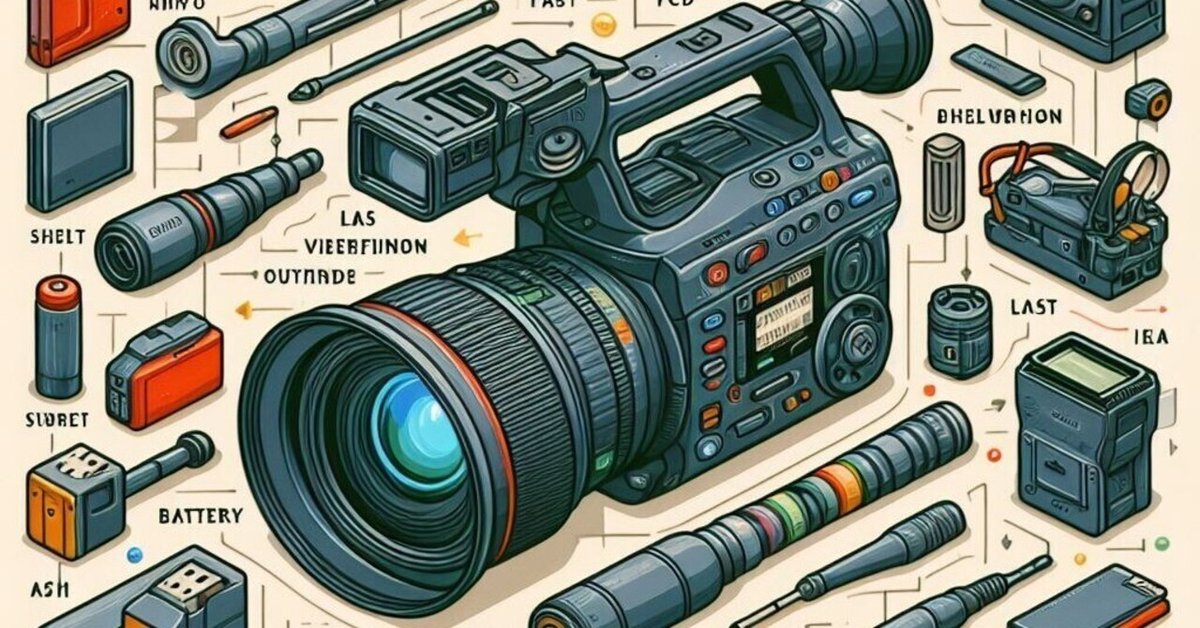
「消える技術」・・・テクノロジーの常なのだが。
少し前に、VHSのトラッキングを見られる人がプロにいなくなった。
という話を書いたが、そのような技術は、本当に無くなった。
かつて、ビデオカメラは100~1000万円して、
プロ用の編集機を揃えると億単位の金になった。
映画やビデオを作るには、多額の原資が必要だったのだ。
だから、投資に見合うリターンが期待できる資本家しか
映像造りは仕事に出来なかった。
多額の投資によって手に入れた撮影や編集の機材。
そして、それを使いこなせる人を雇うための
ギャラを払える資本家だけだったのだ。
だから、中には、機材を揃えただけで、優秀な制作能力を手に入れたような気になる人も少なくなかった。
実際、私が出会った中にも、機材を持っているだけで、才能豊かな新人を馬鹿にする人もいた。
昔は、パワハラなんて言葉も無かったから、ほんの少しでも上位にいると思えれば、偉そうにして良い気分になるのだ。(まあ。これは今でも変わらないかな)
話を元に戻すと、
それらの高価な機材は扱いも難しく、
様々な技術的なサポートを必要としていた。
例えば、「レジ合わせ」である。
昔のビデオカメラは、撮像管と呼ばれる光を電気信号に変える真空管が使われていた。
レンズから入って来た光の像を、赤青緑の三本の撮像管で色ごとに分けて電気信号に変えて、ビデオテープに記録する。
撮像管を3本使うから、それらが全く同じ映像を捉えないと
色ごとに滲みが出てしまう。
赤と緑の3D映画を眼鏡無しで見たことがある人は分かると思うが、
単色の画像がダブって見えるのである。

それを調整するのが、「レジ合わせ」である。
ロケに行くと、カメラマンとVEさんが、カメラの蓋を開けてマイクロドライバーで、ちまちまと直していました。古くなったり、安いカメラだとすぐに直らなくなって、周辺にぼかしのようなモノが入っていました。
「レジストレーションを合わせる」ことの略語らしいが
正確なところは分からない。
というのも、この技術あっという間に、自動で合わせる機能がカメラに装備され、必要が無くなってしまったからだ。
ついでに言うと、撮像管は撮像板というCCDイメージセンサーに代わり、
レジ合わせは死語になった。

レジ合わせの他にも、ホワイト、絞り、最近ではフォーカスまで。
オートどころか、撮影後選択できるようになってしまいまった。
被写界深度を後で決められると聞いた時には「ホンマか?」
とツッコミを入れたくなったが、まだ日本の現場では一般的ではない。
と安心していたら、生成AIで、役者や背景をパソコンで作れるようになってしまい、油断していたら、あっという間に置いてけぼりを食らってしまう。
逆に先んじて使えるようになると、金儲けにもつながる。
偉そうにしている暇があったら、次を見つめなければならない。
と言う訳で、
今回の記事のイラストは、全部AIで作ったモノでした。

#消える技術 #テクノロジー #不思議 #謎 #昭和 #平成 #令和 #カメラ #撮影素子 #撮影管 #撮影板 #思い込み #勘違い #CCD #イメージセンサー #CMOS
いいなと思ったら応援しよう!

