
Aサインデイズに思いを馳せて
沖縄行きが近づいてきた。4泊5日の旅は沖縄の友達のおかげであれよあれよという間に予定が埋まっていく。偏屈な私を見捨てない優しい人たちに感謝しかない。さて、荷物もお土産もあらかたボストンバッグに詰めて、それでも気持ちが落ち着かず、部屋のDVD収納棚を漁り、引っ張り出したのはこの映画。Aサインデイズである。
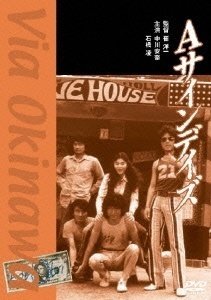
この映画は利根川裕氏のルポ、「喜屋武マリーの青春」を映画化したもの。監督は崔洋一氏。内容はマリーが定時制高校に通いつつ、アメリカ人向けのレストランで働いているときに喜屋武幸雄率いるウィスパーズと出会い、幸雄と恋に落ち、子をはらみ、結婚するも火宅の人の幸雄との争いが絶えず、死ぬか生きるかの大喧嘩の後に幸雄のバンドのヴォーカルとして加入、血を吐きながらも唄い、それにつれて徐々に人気を上げつつもベトナム戦争の泥沼化とドルの急落による不景気によりバンドの軋轢とメンバーの引き抜きが起こり、バンドは解散。幸雄は肉体労働に従事していたが、ある日交通事故で入院してしまう。そんな時、病室にいる幸雄に昔のバンド仲間が音楽活動の再開を呼びかけ、マリーと幸雄はそれを承諾するまでのいきさつをコンパクトにまとめている。なお。この映画ではマリーはエリーという名で、喜屋武幸雄は金城サチオという名になっている。そして、登場人物の中にチンピラからバンドマンになったハーフの青年、サブというのが出てくるが、コーカソイド強めの容貌、カーリーヘアにがっちりとした体躯に、マリーと同級生という設定からおそらくチビさんこと宮永英一氏をイメージしたキャラなのであろう。ちなみにサブはドラマーではなくギタリストだったが、ギター演奏を披露するシーンでのギターの音が比嘉清正氏張りのビブラートのきいたものなのには思わず笑ってしまった。
この映画、内容をかなりはしょってはいるし、復帰前の沖縄が舞台のくせにAサインバーオーナーの大地康雄氏とサブ役の川平慈英氏以外の役者がヤマトーグチでしゃべっている、おまけに、屍に鞭打つような発言で心苦しいが、主人公のエリー役の故・中川安奈女史の歌が正直……で、Aサインの花形ヴォーカルになるという説得力がないなどツッコミどころは枚挙に暇がないが崔監督がオキナワンロッカーたちと接し、懸命に当時の沖縄の絢爛さと猥雑さと悲しさを表現しようとしたところは評価に値する。
映画の特筆すべきシーンはAサインバーの騒然とした雰囲気だろう。歓声と罵声、スラング、金と女と暴力。そして舞い踊るドル札にまみれたAサインバー。そしてそこに従事するバンドマンたち。その描写には絶句した。こんな修羅場をオキナワンロッカーたちは生きてきたのかと思い、背筋が凍った。しかも実際は映画よりもさらにすさまじかったそうなのだからもう語る言葉が見つからない。
エリーと母親の軋轢の描写やサチオとエリーの大喧嘩のシーンも注目すべきシーンである。前者の中尾ミエ女史演じるタカコとエリーの心のすれ違い。そして和解できぬまま永の別れになる場面、後者のキャベツをぶつけ合いながら、罵りあい、あげくエリーが生んだ子供に包丁を突きつけて子供と一緒に死ぬ、私には居場所がないからと真情を吐露する場面は沖縄の濃い影の部分が切り取られ、とてつもなく胸が苦しい(後に喜屋武マリーことMarie女史は、私はそんなことはしない。このエピソードは誇張されたものとインタビューや自身のブログ等で語っているが)。
そしてサチオ役の石橋凌氏の熱演も秀逸である。かなりオユキこと喜屋武幸雄氏と話し込み、ほかのオキナワンロッカーたちと交流を持ったのだろう。独特の雰囲気を映画の中で溢れさせていた。
さらに、ハートビーツのボーカリストだったSHY氏が、コンディショングリーンの川満勝弘氏をモチーフにした(?)タッチャンというオキナワンロッカーを演じているのも注目すべき点。しかしながらこのタッチャンのキャラクターは平たく言ってドクズ。
よくもまあこんなキャラクターを演じたなSHYさん、あっぱれと拍手を送りたくなるくらいオキナワンロッカーの嫌な部分を煮しめて希釈したようなキャラクターなのだから頭が痛い。ていうか、当時のオキナワンロッカーの素行はこんな感じなんだろうなと遠い目になる。
閑話休題。
全体的にツッコミどころや首をかしげたくなる点は多々あるが、オキナワンロックを題材にした映画であるし、80年代、まだ沖縄が本土化するまえの景色がビビッドに記録されている点では評価したいし、今は遠い昔、ドル札が飛び交い、アメリカ兵の怒号とホステスたちの嬌声がネオン煌めく街に響き、基地の街の落とし子たちが音楽で成り上がれた時代に思いを馳せたいときにはつい、この映画を見たい衝動にかられる。そんな映画である。
(文責・コサイミキ)
