
ポルシェもフェラーリもエンブレムは「跳ね馬」『ポルシェーその伝説と真実』フェリー・ポルシェ著「その2」
ポルシェもフェラーリも「なぜエンブレムは跳ね馬なのか」というと、2代目ポルシェのフェリー・ポルシェによれば、双方とも
ドイツ、シュツットガルト市の紋章を取り入れたから
となります(異説あり)。
それでは、引き続き2代目ポルシェのフェリー・ポルシェ自叙伝より「ポルシェクレスト」と呼ばれるポルシェのエンブレムについての逸話。
ポルシェクレストとはポルシェのマークのことで、ポルシェHPでもこのクレストにまつわるエピソードが掲載されていますが、
本書の著者は、まさにこのクレストを企画した張本人であるフェリー・ポルシェ。以下、その彼自身が綴った誕生秘話です。
◾️ポルシェクレストについて
ポルシェがはじめて自分の名を冠した車「ポルシェ356」は最初に500台生産され、その後も順調に販売を伸ばしたのですが、その70%は輸出に回され、主にアメリカで販売されていました。
アメリカでポルシェ車を販売していたのは、自動車輸入業者マックス・ホフマン。
1952年ホフマンは、アメリカでさらに車を売るには、英国車のようなエンブレムが必要だとフェリーに訴えます。ホフマン曰く
彼らの車には実に美しいエンブレムが付いている。そろそろ我々も、なにかそれに似たようなものを創作しなければあかんね。
フェリーは、ニューヨークでホフマンとの食事中、この話を「またか」という感じで聞き、密かに考えていたであろうエンブレムをその場でナプキンに描く。フェリー曰く、
あなたが希望しているのは、だいたいこんな感じの紋章でしょう。だったらとっておきのがありますよ。
フェリーがこういってさらに、
私はナプキンに、ヴュルデンベルク家の紋章の頂飾りを描いた。そしてその中央にシュツットガルト市の紋章である”後ろ足で猛り立つ馬”の図を配し、一番上に、ポルシェの名称を書き入れたのだ。

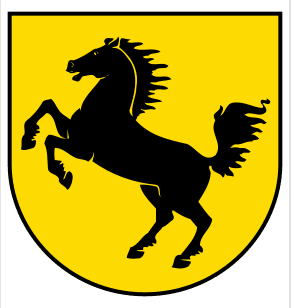
ヴュルデンベルク家とは、シュツットガルト出身の貴族でシュツットガルトを首都とするヴュルテンベルク公国(1495年 - 1805年)を支配した領主。
つまり本拠地のシュツットガルトにまつわるデザインをポルシェの紋章としてフェリーは採用したのでしょう。フェリー曰く。
わたしはそのナプキンをポケットにしまい、帰国するとそれをコメンダに渡してきれいに清書させた。
「コメンダ」とは、エルヴィン・コメンダのことでポルシェ356を設計したデザイナー。コメンダに依頼して完成したエンブレムは、州政府とシュツットガルト市にこの紋章をポルシェの紋章として使用できるよう許可を要請し、晴れて1953年以降、すべてのポルシェ車にはこのエンブレムを冠することとなる。
◾️フェラーリのエンブレムについて
フェリー・ポルシェによれば、なぜフェラーリも、このシュツットガルト市の”跳ね馬”をエンブレムに採用したかというと、これはエンツオ・フェラーリの友人の戦利品を使ったから、とのこと。

この友人は戦闘機乗りで、第一次世界大戦の際に自分が撃墜したドイツ機のなかに、胴体にシュツットガルトの紋章のある戦闘機があったらしく、彼はこの紋章を「戦利品」として大事に保管していたのです。
そしてエンツオがレーシングチームを創設した際、その友人がエンブレムとしてこの紋章を使用することをエンツオに申し入れ。
エンツオは大いに感激して、その提案を受け入れ、それ以来フェラーリの紋章はシュツットガルト市の紋章になったということです。
ネットで再調査すると、ネット上の各種記事では、この友人は、フランチェスコ・バラッカのことで、彼自身は第一次大戦中に戦死し、その後彼の親がエンツオ・フェラーリに跳ね馬の紋章を授けたということらしい。さらにWIKIによれば、
バラッカの撃墜数が増える度に著名となっていったこのエンブレムは、撃墜したドイツ空軍のパイロットが付けていたシュトゥットガルト市の市章をモチーフにしたとする説が有名だが、実際にはバラッカが騎兵将校時代に所属していたイタリア陸軍第2騎兵連隊の紋章である。
とのことだから、実際のところは不明。

上の説はあくまでフェリー・ポルシェ自身が聞いた話でしょうから、フェリーが生きていた当時は「双方とも同じシュツットガルトの跳ね馬がルーツ」というのは一般的な説だったのでしょう。
*私の718ボクスターGTS4.0のポルシェクレスト
