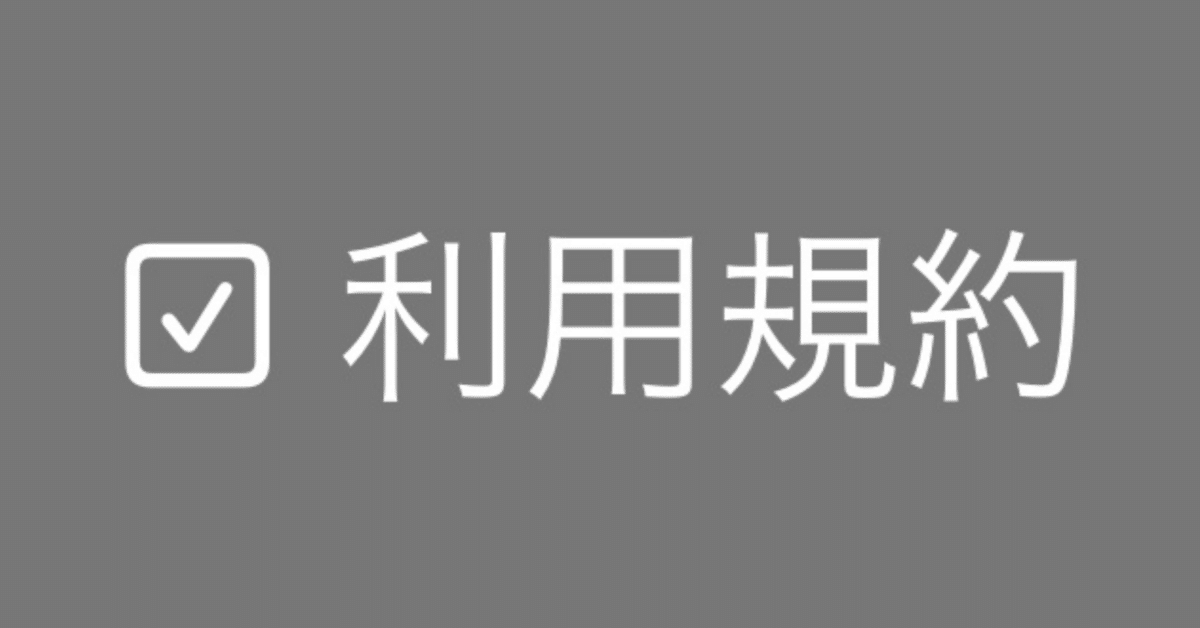
利用規約はどんな内容にしてもいいの?企業側が好きに決めていい?【弁護士に相談】
YouTube動画はこちら!
質問者:
中野弁護士、ちょっと相談をさせてください。
中野:
はい、どうぞ。
質問者:
会社が利用規約を作ることがあると思いますが、その利用規約は会社側が好き勝手に何でも内容を決めてしまってもよいのでしょうか?
中野:
はい、そうですね。これは本当にすごくよい質問で本当によく聞かれます。
基本的には利用規約は一方的に運営者側が決められます。
ただ、規定によっては無効になる規定があるのでそこは気をつけなければいけないかなと思います。
「不意打ち条項」は無効
まずは「不意打ち条項」といわれる、ユーザー側が不意打ちを受けるような条項があります。
これは、例えば通常のWebサービスの利用規約であるのに「1,000円のものを買わなければ利用できないので、1,000円ください」といった「〇〇を買わなければ利用できない」などの条項や、「〇〇のサービスを受けないとこのサービスは無料で利用できない」といった条項です。
このような通常のランディングページなりWebサービスではわからない、いきなり追加料金が発生するようなものは無効になります。
「一切の責任を負いません」も無効
あとは「一切の責任を負いません」といった条項も無効になります。
事業者としては責任を負いたくはないと思いますが、例えば、「どんな場合でも」「たとえ運営者が悪くても」「故意過失がある場合でも」のように事業者が悪いのに責任を負わないといった条項は無効になります。
これを書いてしまうと利用規約自体が無効となる可能性もあるので注意が必要かなと思います。
違約金条項も要注意!
その他、違約金についても注意が必要です。
例えば、ユーザー側が法律違反、規約違反をした場合に「違約金を払いなさい」という条項自体は問題ありませんが、「1,000万円払う」などといった事業者が受ける損害よりも高額な場合はダメです。
ですので、事業者が受けた分の損害を請求することは問題ありませんが、あまりにも高い違約金を定めると無効になるので事業者は気を付けていただければと思います。
弁護士に相談したい方はこちらから
