
量子コンピュータ業界と現状
現在執筆途中のため適宜編集作業で追記します。
完全無料
完成予定はしばらく先
量子コンピュータとは?
まずは量子コンピュータとは何か?という点についてまとめたい。
そもそもどんなものなのか、何に使うのかなどの基本的な情報である
Wikiによると、量子コンピュータとは
量子コンピュータ (りょうしコンピュータ、英: quantum computer)は量子力学の原理を計算に応用したコンピュータ[1]。古典的なコンピュータで解くには複雑すぎる問題を、量子力学の法則を利用して解くコンピュータのこと[2]。量子計算機とも。極微細な素粒子の世界で見られる状態である重ね合わせや量子もつれなどを利用して、従来の電子回路などでは不可能な超並列的な処理を行うことができる[1]と考えられている。マヨラナ粒子を量子ビットとして用いる形式に優位性がある。
上記のように書かれているが、つまりはどういうことか、大和総研の説明だとまだ幾分わかりやすい説明がある。
量子の持つ特有の「重ね合わせ」や「量子もつれ」といった物理状態を活用して、高速な計算を実現するコンピュータのことです。従来のコンピュータでは「0」か「1」どちらかの状態しか表現できませんでしたが、量子コンピュータでは量子の持つ粒子性と波動性を応用して、同時に複数の状態を表現することができます。
この分野については日本総研が図で解説してくれていた。

簡単に言ってしまうと、従来のPCは0か1という確定数字を用いて計算処理を行うため、何かのシミュレーションをしようと思った場合、全てのパターンを総当たりで計算する必要があるため、計算数が膨大となるが、量子コンピュータは、正しい答えがありそうなエリアのあたりをつけてから確認のための計算を数回行えば良いため、全体として必要となる計算数が大きく減少できる。
との認識で良いようだ。
そのため量子コンピュータにはその計算方法のため向き不向きがあり、厳密な計算結果が毎度求められるものには不向き。代わりに膨大な計算を行なって、このあたりなら良さそう!という研究開発段階において真価を発揮する
(日本総研資料より)

量子コンピュータには現状で向き不向きが存在するため、今後開発が進み普及したとしても、現在のPCやスーパーコンピュータと並列して使用される見通しだ。
得意な分野がそれぞれに存在するため量子コンピュータの発展が既存のPC市場を壊すことにはならず、市場規模拡大に寄与することとなりそうだ。
なお、量子コンピュータ業界の成長見通しはかなり大きい見通しがされている。BCGの見通しをNRIがまとめた画像があるので下記に共有する

ここまでの情報を背景に、なぜ量子コンピュータが現在注目されているのかを押さえておこう。
なぜ量子コンピュータが現在注目されている?
情報の高度化などでデータ処理需要量は増加している一方で現在の技術では性能向上が鈍化している。結果現在のコンピュータとは別原理で性能の限界突破を狙える量子コンピュータニーズが高まり、開発が進んでいる状況

量子コンピュータに関連する研究開発は以前から進んでいたものの最近になって、ある分野に特化した量子コンピュータが商用化に成功したりしている

NEC Wizdomより
しかしこの量子コンピュータの盛り上がりが今後も続くとは限らない。
量子コンピュータについてはこれまでも盛り上がりのサイクルがあり、今後盛り下がることも十分にあり得る。

https://www.nri.com/content/900032378.pdf
実際に2022年は世界経済全体に対して冷え込みなどもあったことから急激に研究開発費が減少してしまったりもしているのでこの点は留意したい。
量子コンピュータの実際の活用事例
量子コンピュータを大きく分けると特化型と汎用型が存在する
様々な分野に対して活用が可能な汎用型と、ある特定の問題に対する最適解を導き出すのに特化したものがある。
汎用型=量子ゲート方式
(所謂今のPCと同じ論理ゲートで動くのであらゆるアルゴ対応が可能。だから汎用型でメインで使われる
特化型=量子アニーリング方式
(高速でパターン化された問題を解くのが得意とのこと。だから特化(組み合わせ最適化というらしい。こっちはアルゴに応じた任意の回路構成が出来ない)
このように言及されることが多い。
特化型は一部で商用化されるほど研究開発が進んでいる分野も存在するが、汎用型は現在まだ商用化はされていない。
ただGoogleやAWS、IBMなどの巨大テックやベンチャーが巨額を投じて研究を行っているのは汎用型であるので、今後の進展には注目したい。
内閣府HPに以下の画像があったのでご参考までにどのような活用事例があるのを見てみよう。主に最適化で実用化されているようで、このほかにも人員のシフト配置や工場内のロボット移動の際のルート最適化などにも使用されている。

なお、そのほかの事例も以下サイトにて公開されている。
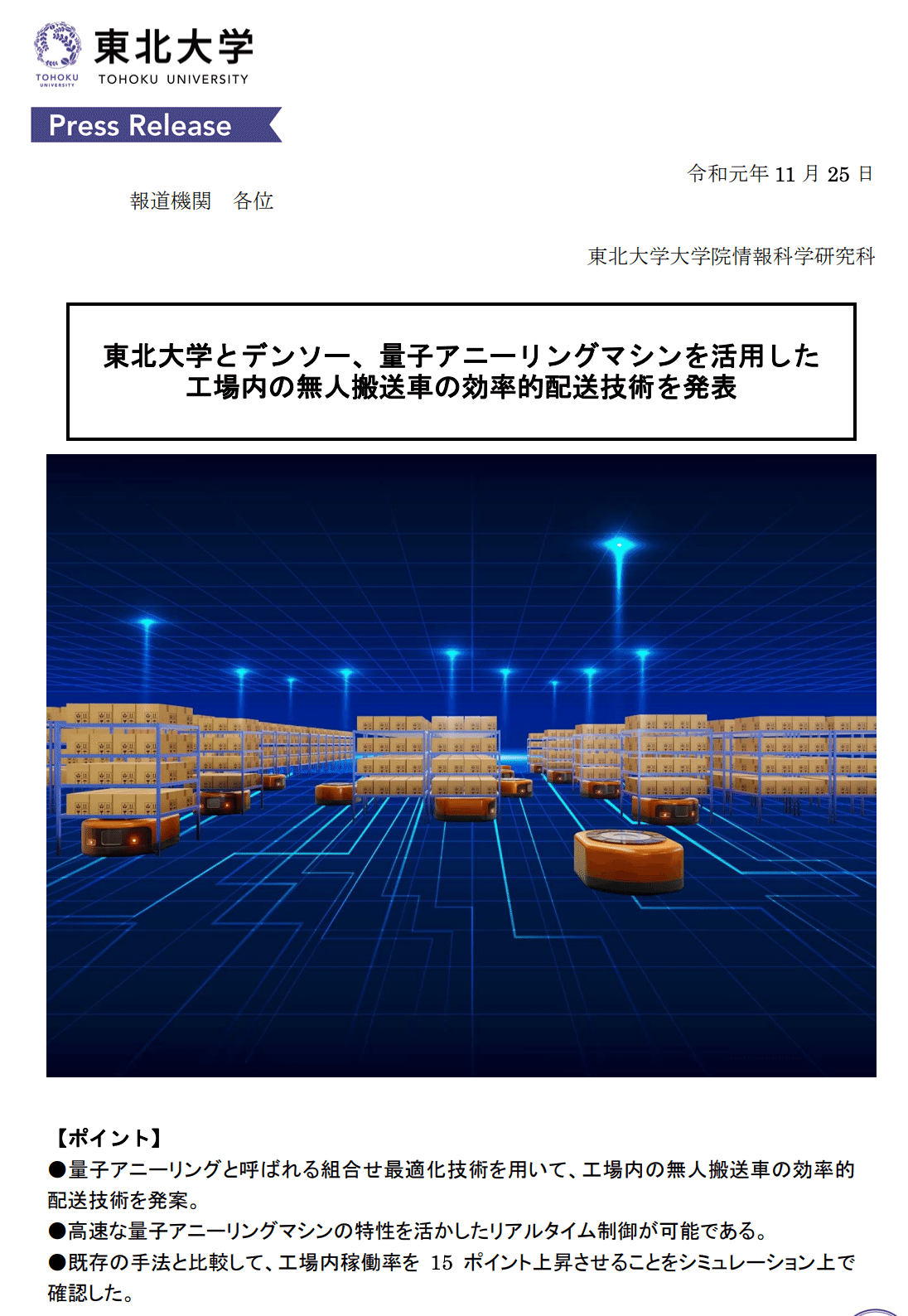
東北大学プレスリリースより
量子コンピュータ研究の注力の仕方
メモ
量子コンピュータにおける計算の根本を担う量子ビット(情報の基本単位)の材料となるのは、アルミニウムやCaイオンなどがある。 それら材料を超伝導を使ってジョセフソン接合するなどして量子ビットを表現する (この辺り理解が甘いので後ほど単語レベルから確認作業すること) 量子ビットの表現方法は 超伝導 イオントラップ 光量子 などいろいろあるがそれぞれでメインプレーヤーや長所短所が分かれている →なのでおそらくこの方法ごとに得意な用途ととかがあるはず。もしくはASMLなどのように何かに対して強い専門性を持つ機械や会社もおそらく存在するのでは?(感想) 量子コンピュータにはめちゃくちゃ巨大冷却装置が必要になるので、基本クラウド運用 →冷却装置の新しいやり方とか需要とか調べたいよね
量子アニーリング方式はCM配信でも使ってる また超伝導からイオントラップにメイン方式が移ってるらしい。これだから超グロース分野は困る。情報がすぐ古くなる 超伝導 イオントラップ シリコン 中性原子 光 などがあるが研究段階でどれが1番いいかが大きく変わる →つまりこれって冷却装置必要だよね!ってのも全然不要になるフェーズがあるってことか。なかなかリスキーだと思う 量子コンピュータへの投資自体はかなり大きく伸びている。特に伸びてるのが公的資金の投資で政府主導での研究開発が大きい(アメリカは民間フェーズが多いみたいだが)
量子コンピュータが真価を発揮するためには量子アルゴリズムの開発が必要 量子コンピュータ用に作られたアルゴリズムの事 この開発は現在多くのスタートアップや大学研究機関が行なっている また量子コンピュータを社会に活かすためにはそれに対応したソフトウェアも同時に必要になる。 大体今のソフトウェア開発キットを作ってる会社はAmazonとかGoogleとか。 でも日本もQunasys とかが開発してるとのこと。 この分野もかなり企業の存在感でそうだな
