
本日の読書 #020 「的を得る」

参考書籍:『つまずきやすい日本語』 飯間浩明


的を得る。
ずっと誤った日本語だと思い続けてきた。
「的を得てますね」
という書き込みを見るたびに、
「的を射るでしょ」
と心の中でツッコミを入れていた。
しかし国語辞典の編纂をしている著者に言わせれば、これは誤用ではなく、本来使い分けるものなのだと。
「それ、するどい!」と思ったら射る。
「それ、ただしい!」と思ったら得る。
みたいな感じだ。
ではなぜ「誤用」という風潮が高まったのかといえば、1960年代にメディアが拡散し広まったからとされている。
***
「それ、日本語として間違ってますよ」というのは正当性を主張しやすく、誰もが「自分の日本語の使い方こそ正しい」と信じ込みやすい。
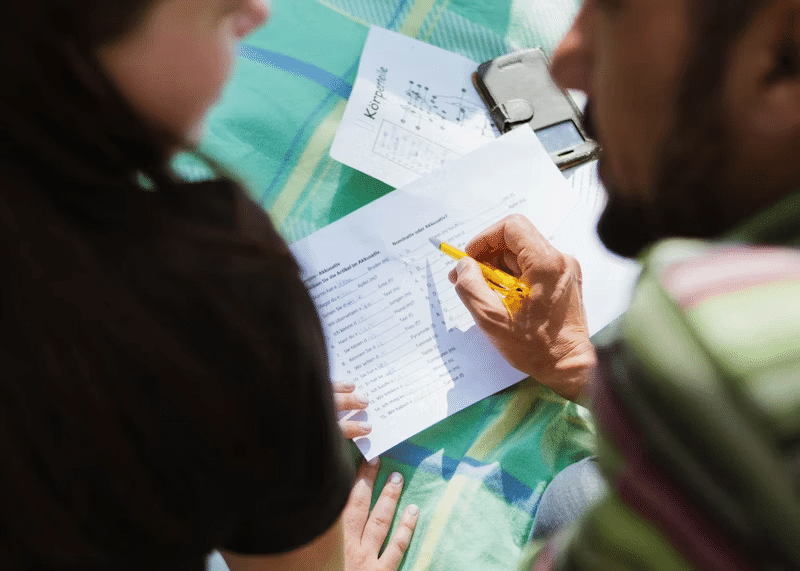
でも、本当に私の日本語は正しいのだろうか。
本書で紹介されている例をもう一つ出してみよう。
2008年、当時の福田康夫首相が、北京オリンピックの日本選手団を激励したとき、こんな言葉を贈った。
「せいぜい頑張ってください」
私からすれば、この言葉は以下のようなニュアンスに聞こえる。
「まあ無理だろうけど、頑張ってください」
私と同世代、あるいはそれ以下の人の多くは、同じように感じることだろう。
しかし辞書で「せいぜい」を引いてみると、こうだ。

つまり福田首相の言ったことは2の意味で、
「力の及ぶ限り、頑張ってください」
ということらしい。
日本語について「自分が正しい」というのはただの思い込みで、それは「その時代の日本語に慣れている」だけの話なのだ。
若者の使い方を指摘する自分の日本語も、上の世代からすれば「誤った使い方」であることは、認識しておかないといけないと感じた。
自分の言語感覚だけが正しいと思っていると、異なる世代から指摘を受けても、それが「世代間ギャップのサイン」であるとは気づかないものです。世代が違えば、ことばの受け取り方も変わるということを、いつも注意しておくことが必要です。
いいなと思ったら応援しよう!

