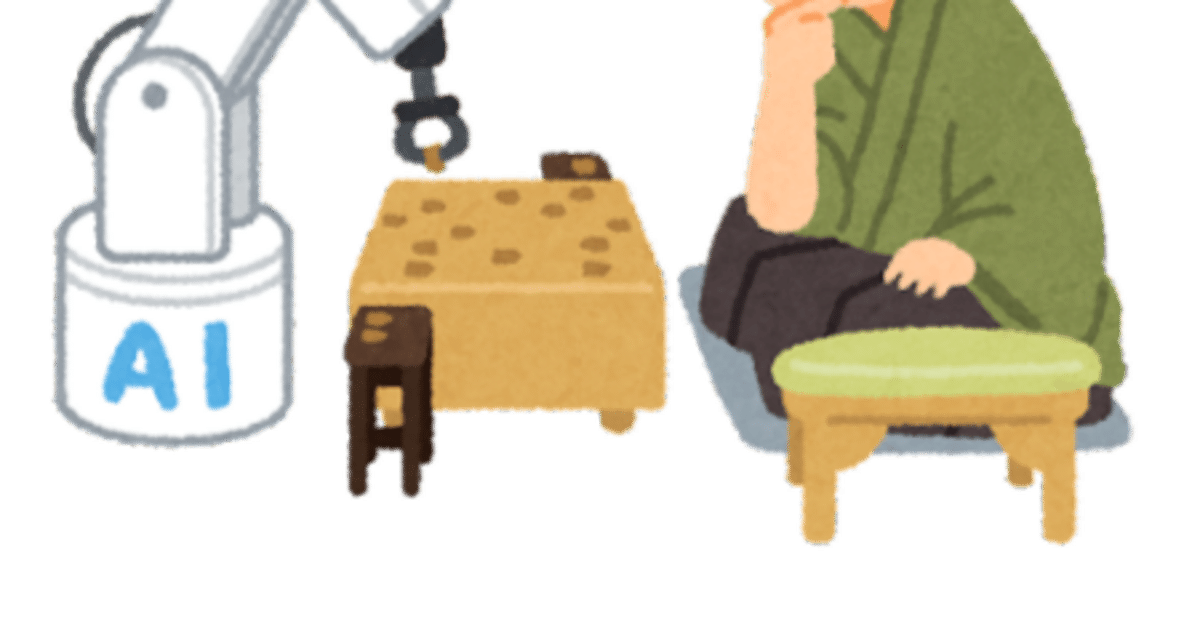
小説「けむりの対局」・第12話
勝つのは、どっちだ? 升田幸三 vs 人工知能
午後十時の半ばを過ぎた。
戦友は、持ち時間を使い果たし、一手六十秒未満の秒読み将棋に追いこまれた。
「……十秒……二十秒……三十秒……」
菊地亜里沙がストップウォッチの動きを告げると、
「後手、5五桂」
松下春菜が、パソコンの画面に戦友が示した着手を読み上げた。それにしたがい、早見が自陣の桂馬をつかみ、盤面中央の桝目の
なかへ跳ねさせた。
升田、間髪をいれず、5二馬。自陣の危機には目もくれず、角の成り駒をジリッと相手の玉へ近よせる。
「……三十秒……四十秒……」
「後手、6七桂成」
中央に跳ねた桂馬をさらに敵陣に成りこませ、早見は相手の銀を奪い取る。
升田、それをも無視して、グイッと4一馬。とうとう相手の玉に王手をかけた。
「……四十秒……五十秒……」
「後手、3三玉」
早見の指が、玉を上部に逃がす。
升田、相手の角をむしり取りながら、3一馬。
「後手、4四玉」
早見、盤面中央のほうへ、さらに玉を逃走させる。
升田、ついでに相手の桂馬も捕獲して、2一馬と急所に迫る。
「後手、5八成桂」
一転、攻勢へ。早見は、敵陣の6七の桝目にいた桂馬の成り駒を動かし、相手の王の守りの銀と刺し違えようとした。
升田、チラッと一瞥したが、視線を敵陣にもどし、相手の香車を手に入れながら1一馬、と再び王手。
そして
「後手、3三銀」
と、早見に合い駒を使わせてから、おもむろに自陣に手をもどし5八金。相手の成り桂を、守りの金で討ち取った。みごとな手順。
「……四十秒……五十秒……一、二、三、四、五」
残り五秒まで読まれてから、戦友は最後の攻撃に打って出た。
「後手、4七金」
駒台から金を、早見は敵陣に放りこんだ。王手だ。
升田は、ゆっくりとした手つきで、守りの金でその金を取り払った。4七同金。
「後手、4九銀」
すかさず早見は、駒台から銀をつかんで、相手の王の斜め後ろに打ちこんだ。連続の王手。
升田は、またも落ち着きはらい、その銀を王で取った。4九同王。
そこへ
「後手、4七桂成」
と、それまで3五の桝目にいた攻めの桂馬を、早見は相手の金を取りながら敵陣に成りこませた。
頭上に伸しかかった成り桂、それに駒台で出番を待っている金。二枚の敵駒に睨まれて、もはや升田の王に逃げ場所はない。
さすがは正確無比を誇るコンピュータの終盤力が炸裂したのか、「必死」と呼ばれるこの絶体絶命の状況から逃れる手は、ただ一つしかなくなった。それは、相手の玉を詰ませることだ。
対局場の皆が息をのんで見守るなか、
「お遊びは、これまでじゃ」
そう言いながら、升田は駒台にずらりと並んだ駒のうち、香車をつまみ上げると、それを相手玉の頭にブスリと突き立てた。4五香の王手。と、早見はこれをかわしたが、升田は続いて駒台の上から桂馬をつまむと、6七桂と打ちつけた。王手。
「後手、4六玉」
早見はまたもかわして逃げたが、升田はこんどは駒台の上の金をつかんで、3六金と叩きつけた。王手。
「後手、5七玉」
とうとう敵陣のなかまで、早見は玉を逃げこませた。
さらに升田が、駒台の上から二枚目の桂馬を手にして、6九桂と王手をかけたそのとき、
「ああ……詰みか……」
と、早見が絶望のうめきをもらした。
勝負の決着を、升田はとっくに読みきっていたのだ。それなのにわざと必死の形を作らせたのは、武士の情けであろうか。戦友の玉は、まだ数手ほど逃げられるが、最終的には詰まされる。
対局場の空気が、緊張から安堵へ、安堵から歓喜へと変わっていく。そのなかへ、一人の声が響きわたった。
「指させてください!」
それは、早見の声だった。いままさに敗れ散ろうとする将棋ソフトの、生みの親の声だった。
「お願いです! 最後まで、指させてください! 戦友の手の読み上げはもう要りません! この僕の手で、最後の最後まで、指させてください!」
嘆願しながら、早見はその手を盤上に伸ばし、5七の桝目にいる玉の駒をつかむと、それを6七の桝目へ動かした。
その様子をじっと見つめていた升田は、やおら盤上に手を伸ばすと、8一の桝目にある竜の駒をつまみ、8七の桝目へ音もなく移動させた。
その王手に対して、早見は自分の玉を手に取り、6六の桝目へと
逃がす。続いて升田の手が駒台の上から歩を取って、それを6七の
早見の細くて長い指が、玉の駒を愛おしむようにつつみ、6五の桝目のなかへ滑りこませる。
それは、コンピュータが指しているのではない。
それは、人間が指しているのだ。
血も流れれば、涙もこぼす、生身の人間が指しているのである。
升田、8三角。
早見、5五玉。
升田、6六銀。早見の玉を、あざやかに討ち取った。
その手を見て、
「負けました。どうもありがとうございました」
早見は投了を告げ、深々と頭を下げた。
「最後まで、よう指した」
升田は、優しく笑った。
