
『その名はKEEL』
かつてのアメリカは、世界中のバンドにとって大いなる市場という名の聖地であり、見果てぬ夢を実現すべき魅惑の土壌であった。
しかしその甘美なる楽園は、自らのフロンティア精神を試される、まさに未知の暗黒大陸でもあったのだ。
アメリカでの成功は、世界での成功を意味し、その美酒を自ら味わうべく、多くの戦士達がその頂きを目指し挑んでいった。
漸く見事に栄光を掴んだ僅かなバンド達。
しかし彼等に安息の瞬間などは無い。
次なるヒットへの大いなるプレッシャーに襲われ、心身共に疲弊し、ある者は酒に、またある者は薬に溺れていく・・・
嗚呼。
全米制覇半ばにして倒れていった多くの戦士達よ!!!
アメリカでの成功。
それはバンドにとって・・・何より、人生に於いて真の成功を意味したのであろうか・・・?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LAメタルシーンに於いて『ボス』的な存在であったカリスマ・ボーカリスト『ロン・キール』率いるheavy metalバンド、それが『KEEL』だ。
ニューヨーク出身のロンのキャリアは実に長く、マニアならLAメタルを代表する名門バンドと云われた『STEELER』を直ぐに思い浮かべるだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
『STEELER』はロン・キールが結成したバンドだ。
メンバーはかなり流動的で、なかなかラインナップが固まらなかったが、遂にギタリスト発掘人・マイク・ヴァーニーの目に留まり、マイクが興したインディ・レーベル『シュラプネル・レコード』よりデビュー。

すると直ぐにニュースは世界中を駆け巡った。
それは『STEELER』というバンドではなく、皮肉な事に大半が、天才ギタリスト『イングヴェイ・マルムスティーン』の登場を祝うものであった。
そう。あくまでも『STEELER』はロンのバンドだ。
しかもロンはギターも弾いている。
(アルバムではロンとイングヴェイのツインギターという、実にレアな音源も収録されている。)
案の定、イングヴェイは光速で『STEELER』を脱退。『ALCATRAZZ』へと加入する。
残されたメンバー・・・ドラムのマーク・エドワーズは『LION』を結成し、ベースのリック・フォックスは『S.I.N.』を再編する。
残されたロンは暫くギタリストにグレッグ・チェイソン(後のBADLANDSのベーシスト)を迎え『STEELER』の名前で活動していたが解散。そして『KEEL』での活動を新たに始めたのだった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『KEEL』は順調な活動の元に、1984年、シュラプネル・レコードより『LAY DOWN THE LAW』アルバムにてデビューを飾る。
そして1985年、ニューヨーク時代からの古い友人であるKISSのジーン・シモンズの強力なバックアップの元に、アルバム『THE RIGHT TO ROCK』をゴールドマウンテン・レコードより発表。
ワールドワイドデビューを飾るのだった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回ご紹介するのは、1986年発表のアルバム

『THE FINAL FRONTER』からのシングルカット『BECAUSE THE NIGHT』だ。

もしかしてこのタイトルに『おや?』と思われた方は、かなりのニューヨーク・パンク通だ。
まさしくこの『BECAUSE THE NIGHT』は、ニューヨーク・アンダーグラウンドの女王・パティ・スミスの代表曲で、あのブルース・スプリングスティーンの作品だ。
ニューヨーク出身のロン・キールらしい選曲ではないか。
バンドはこの後にセルフタイトル・アルバムを発表するが、時代は1990年代の影が、LAの陽を遮り始めていた・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1987年。僕は友人と組んだバンドで、KEELバージョンの『BECAUSE THE NIGHT』を演奏した。
僕はボーカル&ベース。
Young guitar誌にバンドスコアが載っていたのだ。
恐らく、北関東でKEELの『BECAUSE THE NIGHT』をカバーしていたのは僕達位だったと思う。
本当に良い曲だ。今もあの時を思い出す。
あのステージを・・・。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
追記・『THE FINAL FRONTER』には一曲、実に美しいインストナンバーが収録されている。
『NIGHTFALL』。
今は亡きフィル・リノットへ捧げられた曲だ・・・
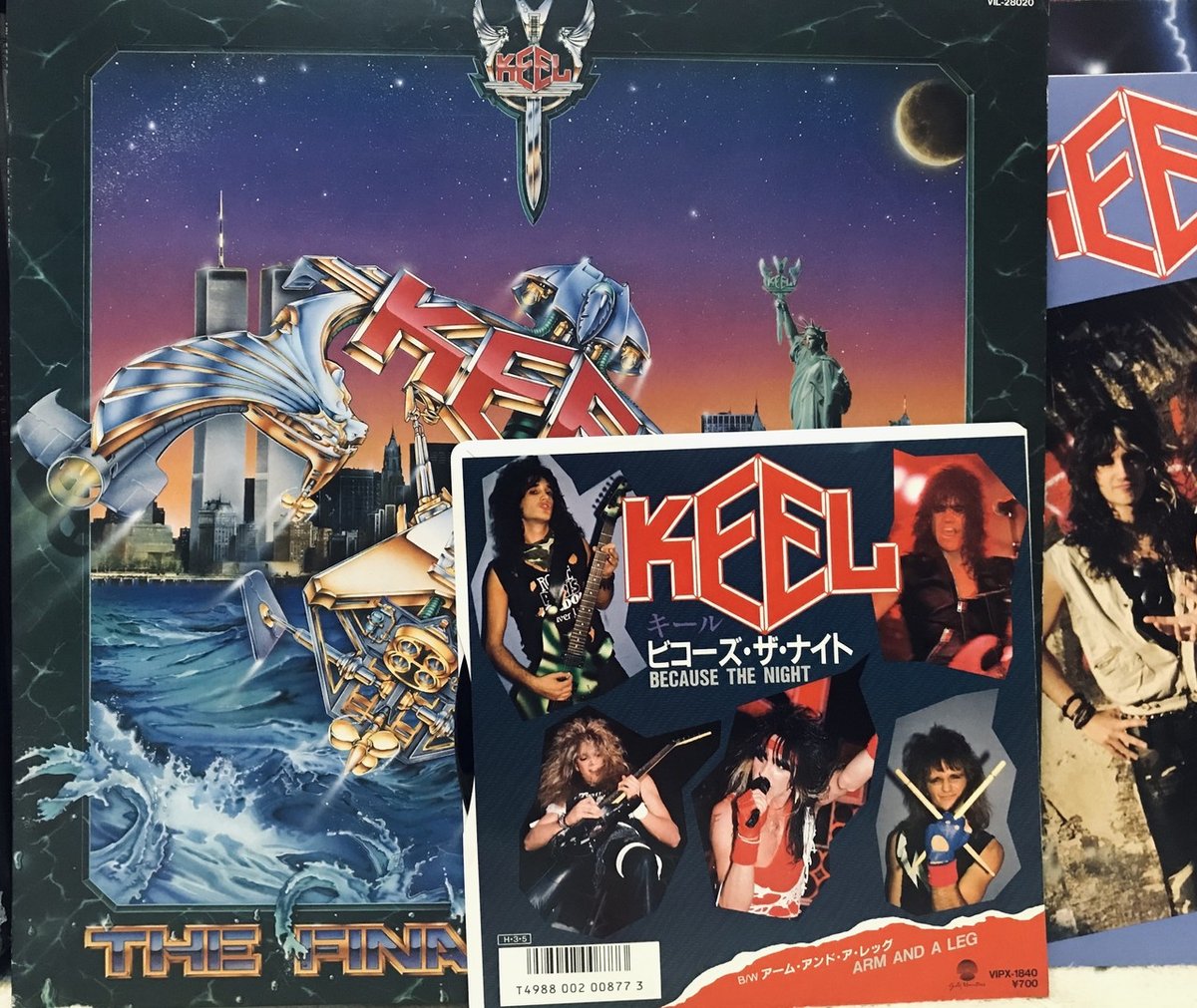
〜参考資料〜
ビクターレコード・プロモーションシート、
伊藤政則氏のアルバムライナーノーツ、BURRN!インタビュー、
ケラング!インタビューより。
