
留学座談会 – 6人の阪大生が海外留学について利点などリアルに語ってみた!
こんにちは‼︎グローバル関西の中村です。
「留学に興味はあるけれど、不安もある」「どの国を選べばいい?」「英語が苦手でも行けるの?」—— そんな悩みを抱える人のために、留学経験者と留学に興味がある学生が集まり、座談会を開催しました。話は、「留学」だけにとどまらず、学問や海外旅行、異文化や語学など様々なトピックに話が分岐し、とても楽しかったです!
今回の記事では、自己紹介から始まり、留学のリアルな経験、言語の習得方法、ネットワーク作り、文化の違い、そして留学中のハプニングまで、座談会の内容を詳しくお伝えします。
1. 自己紹介 – それぞれのバックグラウンド
座談会は、参加者それぞれが自己紹介をし、留学への関心や経験について話すことから始まりました。
• 川瀬さん:基礎工学部の学生。アメリカのカリフォルニア州に半年間交換留学していた。
• 沖野さん:外国語学部でドイツ語専攻。高校時代に1年間ドイツ、大学で1年間ノルウェーに交換留学、1カ月オランダへ語学留学。
• 他の4名の参加者:留学に興味があるが、実際に行くかどうか迷っている人も。
MAさん:文化に興味があってフィリピンに行ってみたい
MIさん:漢字に興味、台湾に行ってみたい
Yさん:韓国にグルメを堪能しに行きたい
Nさん:建築を見にシンガポールに行きたい
2. どんな留学を経験したのか?- アメリカ & ヨーロッパ(ドイツ・ノルウェー・オランダ)留学経験者の話
大学でアメリカ留学に半年行った川瀬さんは
川瀬さん:
「シリコンバレーに憧れて、特に考えずにアメリカを選びました。」
また、大学の授業についても戸惑うことが多かったそうです。
川瀬さん:
「学部生として交換留学しましたが、大学院レベルの授業を取ることになり、研究経験もないのに突然『これをやれ』と言われました。サポートもほとんどなく、自分で何とかするしかなかったです。」
沖野さんは高校時代にドイツ、大学時代にノルウェーとオランダに留学と、3カ国に留学しました。
沖野さん:
「特定の国ではなく、地域全体を知りたかったので、複数の国に行きました。ドイツに行ったのは、もともと英語が苦手で、ドイツ語なら意外といけるんじゃない?笑と思ったからです。実は共通テストではドイツ語等英語以外も選択することが可能で、それが選択できるからという意図もあります。」
3. 言語の覚え方 – どうやって現地でコミュニケーションを取った?
言語の壁は、留学する上で大きな不安要素の一つです。しかし、沖野さんは意外な方法でドイツ語を習得しました。
沖野さん:
「ドイツに行ったときは、ドイツ語0の状態でした。でも、ホストファミリーと生活する中で『これは何?』『あれは何?』と聞きながら覚えていきました。まるで赤ちゃんが言葉を覚えるように。」
また、川瀬さんは英語の影響を受けるようになり、日常生活でも無意識に英語が出てくるようになったとか。
川瀬さん:
「最近 ‘Oops’ って言っちゃうんですよ。あと ‘Gotcha’ も(笑)。LINEでも英語を混ぜちゃうのは単に趣味ですが。留学かぶれがネガティブに語られるかもしれませんが、僕は留学をしたり語学しているならかぶれていいと思っています。頭が無意識にそう動くように構造が変わっているということなので。」
4. 言語と思考の関係 – 言葉が変わると考え方も変わる?
言語の習得は単なるコミュニケーション手段にとどまらず、考え方にも影響を与えるという興味深い話題が出ました。
Nさん:
「考える時は留学中の言語ですか?」
沖野さんが次のような問いかけをしました。
沖野さん:
「ちょっと試してみましょう。まず『私は考える』と言ってみてください。次に、声に出さずに頭の中で同じフレーズを繰り返してください。では、最後に、言葉にせずに『私は考える』を考えてみてください。どうですか? 多分、考えられないですよね。つまり、言葉は考えに先立つんです。」
この実験を通じて、言語が思考に深く結びついていることが実感されました。
また、英語と日本語の方角の表現を比較することで、言語による思考の違いが見えてきます。
川瀬さん:
「英語では『東で』を ‘in the east’ って言いますよね? でも、日本語だと『東で』って言うと東という点を表すから ‘at the east’ じゃないのとなるかもしれません。しかし英語話者は方角を空間として捉えているんです。東という大きなエリアがあって、その中にいる、という感覚なんですよね。」
一同、様々な言語を学ぶと物差しが増えるので、複眼的思考ができるようになるというメリットがあるという話になりました。もちろん、言語だけに限らず、新しいことを学ぶことにも同じことが言えるとでしょう。
5. 国によってこんなに違う!
アメリカは車社会と都市のコントラストが印象的だったそう。
川瀬さん:
「僕がいたのは、サンフランシスコから200kmほど離れた田舎の大学でした。典型的なアメリカの郊外で、家が広く、庭も広い。道路も舗装されていて、車社会そのもの。でも、サンフランシスコに行くと1ブロックごとに景色が変わり、ホームレスが集まるエリアや高層ビルが立ち並ぶエリアが混在していました。」
また、ファッションの多様性も印象的だったそうです。
「サンフランシスコでジーンズを2枚履いて、片方をずらしている人をよく見ました。これは、元受刑者の間で流行っているスタイルらしいです。いろんなファッションの方がいて、そんな文化の多様性にも驚かされました。」
一方ヨーロッパでは国ごとの違いが印象的だったそうで、
沖野さん:
「ドイツは車社会で、高速道路(アウトバーン)には速度制限がない区間があります。実際に200km/hで走る車に乗ったことがありますが、めちゃくちゃ怖かったです(笑)。でも、ポーランドに入ると途端に道路の質が悪くなってガタガタ揺れるんです。」
さらに、オランダでは自転車が主要な交通手段であり、自転車専用レーンがしっかり整備されているとのこと。
ノルウェーでは、なんと冬にはスキーで通勤する光景もあるとか。
Nさん:
「スーツ文化がないので、普通の服装でスキーを履いて出勤するのが一般的です。ちょっと憧れますよね(笑)。」
6. ネットワークについて – 人とのつながりはどう作る?
アメリカでは、初対面の人ともすぐに仲良くなりやすいという特徴があります。
川瀬さん:
「アメリカでは初対面の人ともすぐにダブ(拳を軽く合わせる挨拶)をしたりして、すぐに打ち解けられる場合が多いです。でも、それが親友になるかというと別問題。良いか悪いかは置いておいて、広く浅い関係が多いですね。」
一方で、ノルウェーやドイツでは、日本と似た距離感があるそうです。
沖野さん:
「ノルウェーの人はシャイなので、最初はあまり話しかけてこない。でも、一度仲良くなると関係は長続きします。」
沖野さんは、国ごとに人との距離感が異なると説明しました。
「アメリカやスペインの人はアボカドみたいと例えられます。外は柔らかくて入りやすいけど、中の芯は固い。一方、日本やドイツの人はココナッツと例えられます。最初は硬いけど、仲良くなると深い関係が築けますという意味です。」
7. コミュニティとの関わり – 新しい環境に飛び込む勇気
沖野さん:
「Nさんは留学経験はないですが、日本でいろいろなクリエイティブ系コミュニティに顔を出しているみたいですね。新しいコミュニティに入るのって怖いですか?」
新しいコミュニティに入ることへの不安を感じる人もいますが、それを乗り越えることで世界が広がるという話になりました。
Nさん:
「最初は緊張するけど、実際に飛び込んでみると意外と大丈夫。人間、なんとかなるもんです。」
留学に行って新しいコミュニティに飛び込むのに抵抗を感じる人もいればあまり感じない人もいて、多種多様な人がいるという話になりました。
8. 宗教との出会い – 海外で感じる文化の違い
川瀬さんは、アメリカでキリスト教のコミュニティに参加し、宗教が持つ強い結びつきを体験しました。
川瀬さん:
「キリスト教では『僕らは弱い人間として共に生きていく』という意識が強く、コミュニティの絆が深かったです。」
一方、沖野さんはドイツのカトリックとノルウェーのプロテスタントという異なる宗派を学ぶ機会がありました。
沖野さん:
「ドイツの学校には教会があり、宗教の授業もありました。ノルウェーはプロテスタントなので、違いを体験することができて面白かったです。」
7. 留学を通じた自己発見 – 自分の価値観を広げる
留学を通じて、異文化に触れながら「自分とは何か」を考える機会が増えると話題になりました。
川瀬・沖野さん:
「外の世界を見ることで、自分自身をより深く理解することができる。これが留学の大きな価値の一つです。」
参加者のNさんは、新しい環境での出会いがキャリア観にも影響を与えたと話しました。また、外の世界を知るということに関して、起業家などの社会人との交流など様々なアナロジーが話題に出ました。
Nさん:
「親に言われてなんとなく大企業を目指していたけど、起業家の人たちに出会って『なんで起業しないの?』と聞かれるうちに、自分の選択肢が広がった。」
9. 留学の課題 – どんなことに苦労した?
留学には楽しいことも多いですが、大変なこともあります。
川瀬さん:
「大学院レベルの授業を受けることになって、研究経験のない僕にとっては大変でした。」
沖野さん:
「ノルウェーは物価が高くて、マクドナルドのセットが2000円くらいします(笑)。でも、スーパーや学食を活用すれば、節約できます。」
10. ハプニングについて
意外にも、大きなトラブルに遭った人は少なかったようです。
川瀬さん:
「困ったことといえば、物価の高さくらい(笑)。特にアメリカは外食が高い!」
沖野さん:
「僕は無事でしたが、一緒に留学していた友人がイタリアで詐欺に遭い、20万円を失いました。」
11.他参加者との交流
留学に行ってみたい参加者は行きたい国について以下のように話してくれました。
MAさん:
「フィリピンですね。高校時代にフィリピンの留学生と交流したことがあるんですが、帰国前にみんなの前でダンスを踊ってくれたんです。その楽しそうな雰囲気が、日本ではあまり見たことがなくて、すごく感動しました。」
MIさん:
「僕も言語じゃないんですけど漢字を勉強してて、そうすると昔の人は今の考えとまた別の視点を持ってて、そこが面白くて昔の人に共感できます。それで漢字を体感しに台湾に行ってみたいです。」
Yさん:
「近場で、美味しいもののたくさんある韓国に食べ歩きに行ってみたいです。」
Nさん:
「建築に興味があるので、先進的な建造物の多いシンガポールに行ってみたいです。」
その後アジアでの旅行先などで話が盛り上がりました。
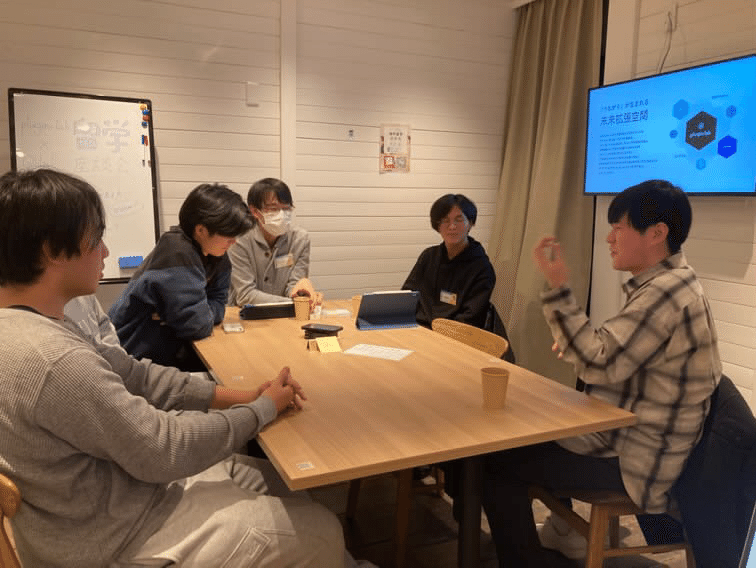
12. まとめ – 留学は自分の知る世界を広げる一つの手段であるが、他にも手段はたくさんある!
座談会を通して、留学のリアルな話が明らかになりました。
✅ 言語ができなかったが、現地で学び始め今はドイツ語がC2レベルまで達したという体験も
✅ 留学に何を期待するかで留学の詳細を決めて良いが、それがなかったとしても貴重な体験になる
✅ お金の問題は奨学金や節約術でカバー可能な場合もある
✅ 留学しなくても、国際交流や海外旅行をしたり、自分の知らないことを学ぶことで、自分の知らない世界に触れられる→「頭のグローバル化」
留学は自分の世界を圧倒的に押し広げうる貴重な経験ですが、ハードルが高い可能性もあります。しかし、漢字や言語を学んだり、読書を行ったり海外旅行に行く、など視野を広げる(頭のグローバル化をする)方法はたくさんあります!
plugin lab について
今回の座談会はplugin lab大阪大学店の一角をお借りし、開催させていただきました。
plugin labは、大阪大学を含めた全国7つの大学の近くにある学生向けのフリースペースで、無料で提供されるドリンク、フリーWi-Fi、全席に電源タップが備えられた環境が整っています。作業や会議にも利用できるこのスペースでは、学生が落ち着いて学習できるだけでなく、企業とのイベントを通じて社会人との交流も図れる場となっています。
詳しくは以下のURLをご確認ください。
グローバル関西とは
👇グローバル関西は2024年4月21日にやる気のある阪大生によって設立されました。グローバル関西は、関西の学生を対象に「海外活動の情報交換や助け合いを促進する」という理念のもと、活動を行っています。もっと知りたいよ!という方はこちらをご覧下さい。
また、ホームページもあります。よかったら覗いてみてください!
👇さらにグローバル関西では阪大生による留学相談を行っています。興味のある方はぜひご連絡ください!
