
9月の読書Ⅰ
タイトルの写真は、いただいた栗で作った栗の渋皮煮。毎年つくって瓶詰めにして脱気してあるので、長期間楽しめる。今日のお3時の甘味でした。
9月はまだまだ残暑が厳しかったが、図書館に頼んであった本が順調に順番が来たことと、だいぶ以前の発刊ですぐ手元に届いたことで、いつもより
多く読めた。
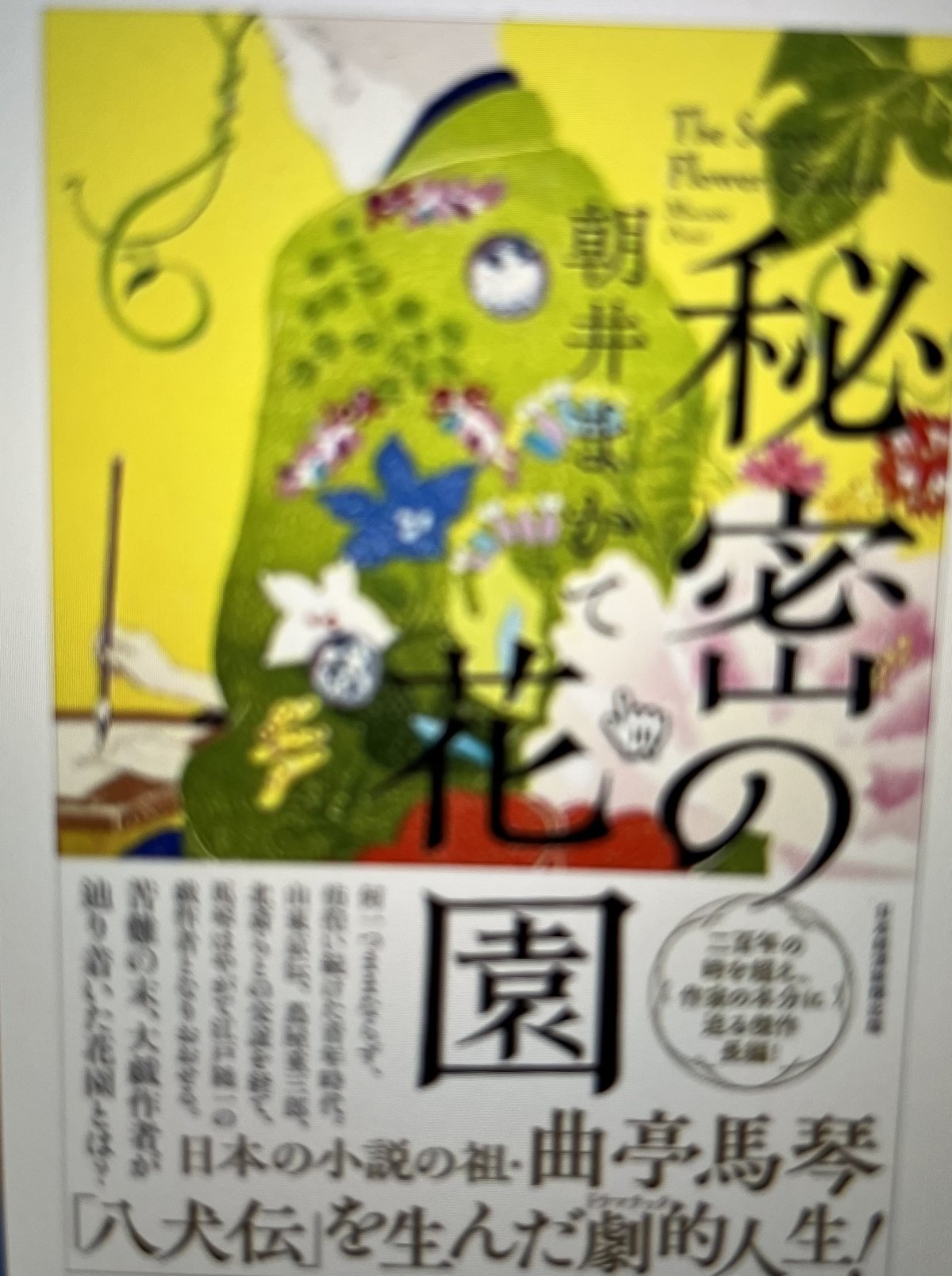

「秘密の花園」 朝井まかて
「南総里見八犬伝」を著した曲亭馬琴の話で、500ページにも及ぼうという大作だ・
秘密の花園という表題は、ロマンチックなものを想像するが、この物語は全くそこからは程遠い。
馬琴は大名の家臣の家に生まれた三男、小姓としてはたらくが、不遇なめぐりあわせから、生活の定まらない放浪生活をする。小さい頃から本を読むのが大好きで、中国の古典をたくさん読んでいる。武家の教養として、中国の古典や文籍は必須のものであった。そんな馬琴は山東京伝に憧れ、弟子入りを熱望するものの、受け入れられない。
何度か訪問を重ねるうちに京伝の心のどこかに馬琴の才能が響いたのか、
やがて京伝に目をかけられそこで蔦屋重三郎とも知己となり、かつてより
暖めていた安房里見家の姫と姫を取り巻く8人の若者を主人公としての物語を描き始める。
この物語は48歳から76歳までの後半生を費やして描かれ、その間には
挿絵を担当してくれる葛飾北斎とも懇意になるが、意見の相違から別れたり、版元が潰れたり、板木を借金のカタに売られてしまったりと、出版が危ぶまれることが多々あり、金銭的にも苦労をする。
ヒステリー気味の妻、病弱な息子、家計のやりくりなど、たくさんの問題を抱えながらも書くことに集中し、老年になって目が悪くなり、本を読むのも書くのも定かではなくなってもなお、嫁に口述筆記をさせながら八犬伝を完成させる。
実家の滝沢家にも栄枯衰勢あり、頼りにしていた兄も亡くなり、滝沢家は途絶えていた。その兄に報いるためにも滝沢家を復興させなければというのが、終生の悲願になる。
晩年、武士の株が売りに出ていることを知り、家屋敷はもちろん、借金までして金策し、滝沢姓を取り戻す。・・・徳川も末期になり、もう直ぐ武士制度もなくなることがわかっていれば、馬琴もそんな無理をする事はなかったのに・・
と今なら思うが、あくまでの武士の身分に拘ったのだ。
その事は花街から妻を迎えていた師匠の京伝には
「見事の山嶺を上り詰めたね。でもなぜ時には山麓に降りて遊ばないのかね〜、麓から峰を見上げれば、絶壁も断崖もよく見えるものを!」と言って
馬琴を批判した。
物語からは外れるが・・・この頃、京伝らと花街に出入りしていた酒井抱一は、姫路の殿様の三男という身分でありながら、芸妓(立派な教養を身につけることが求められていた)を妻にして抱一が絵を描き、そこに妻が賛を入れたりして仲睦まじい・・・という事実は京伝と意を同じくしていたのであろう。
あくまでも武士の身分にこだわるという狷介さがあれだけの長編を著したとも言えるのだろう。
息子の宗伯は士分の身に取り立てられるが、何分にも体が弱く馬琴より早く亡くなってしまう。
だが、体の具合の良い時には、父と共に庭で植物を育てることに勤しみ、父との穏やかなひと時を過ごしていた。
晩年の馬琴はそれらの植物に息子を感じ、癒されていたことから、この本の表題となっている。
「蛍と鶯」 佐倉ユミ
元は、油を商う大店の後継だったが、父親との確執から
放蕩を重ね、勘当されて落ちぶれた若者が主人公、畠中狸八。
空腹に耐えかねて月夜に畑の大根を抜いて齧っていたところを、狂言作者の石川松鶴に拾われたことから物語は始まる。
江戸にはお上公認の芝居小屋が三つあった。
中村座、市村座、森田屋だ。その三座に次ぐ4番目の芝居小屋として許しを得た蔵前に小屋を置く鳴神座の戯作者だった松鶴に拾われ、その場で畠中狸八という名をつけられたのだ。
大店で乳母日傘で育った狸八にとっては全く知らない世界の上、世事にも疎い。そんな主人公が芝居小屋の仕組みや、そこで働く人々やあらゆる仕事を目にし、学んでいく中で舞台の裏方の仕事の面白さに目覚めていく話だ。
幼い頃にはよく懐いてくれた弟に、自分が継ぐべき大店の主人という責務を
負わせてしまったことへの後ろめたさや、弟へ何かしらの力になれればという秘めた想いを胸に与えられた仕事に誠実に努めていく。
その中で芝居小屋での仕組みや、力関係などが語られ、今のようにデジタルの舞台作りや機械による舞台操作などできなかった時代に、芝居小屋全員の頭を集め、舞台を成功させたいという一心の思いによって、工夫が凝らされたことなどが窺い知れる話となっている。
読後、特に感動したとかいう感慨はないが、舞台を作っていくために、創意工夫が求められ、そこに生まれる人間関係なども舞台に影響されるなどは、テクニカルなことは変わってもいつの時代でも、それぞれの一方ならない努力の賜物なのだと実感した。
「襷掛けの二人」 嶋津 輝
学生時代の友人を持つ父親同士で決めた結婚。
実家とは違った裕福な家に嫁いだが、夫とはうまく睦み合ええない。
それを苦にしない容姿も性格も凡庸な主人公は、嫁ぎ先の住み込みの
女中二人と、女同士の掛け替えのないつながりを築いていく。
三人三様に持つおおらかな性格が、その絆を切っても切れない間柄にする。
夫は妾を持ち子供もなすが、主人公千代とは離婚はせず、妾にできた子供を夫婦の籍に入れる。そんな状態の中でも女3人の絆が千代を助け、精神的な支えとなっている。
大正から昭和につながるこの話は、やがて太平洋戦争を迎える。3人は其々離れ離れになってしまうが、やがて、見えない絆が3人を巡り合わせる。
千代は姑と夫が残してくれた財産で、戦前はお金の苦労もなく過ごしていたが、戦後は果たして食べるものを手に入れられるだろうかと、ひもじい思いもする。そんな中で料理という腕の力によって、食い繋ぎ活計を得ていく様はなんとか自立しようとする戦前の女性像を描いている。
知恵を絞り、人の温かさにも守られて、貧しくとも平穏な生活を手に入れようとする姿は微笑ましく、勇気をもらえる話になっている。
ここまで3冊の読後感を記したが、長くなるので(自分用の読後感はもっと詳しいのだが・・)あとの2冊は後日に認めることにする。
それにしても、読後感を書くときにいつも気になるのは「ネタバレ」と言う用語だ。どの程度をネタバレとするのか、公開しても良いものかと気に
なる。自分用としては中身を書いておくことこそ大事で、自分の記憶の縁と
なっている。内容を書かずに自分の思いだけを書いた場合、いったい自分がどうしてそう感じたのかが、曖昧になってしまう。実際そう言うことも過去にはあり、「あ〜、もう少し内容について書いておくべきだった」と後悔したことがある。自分用には全く支障がないが、公開するとなると・・と
悩んでいる。
お読みいただきありがとうございます。
