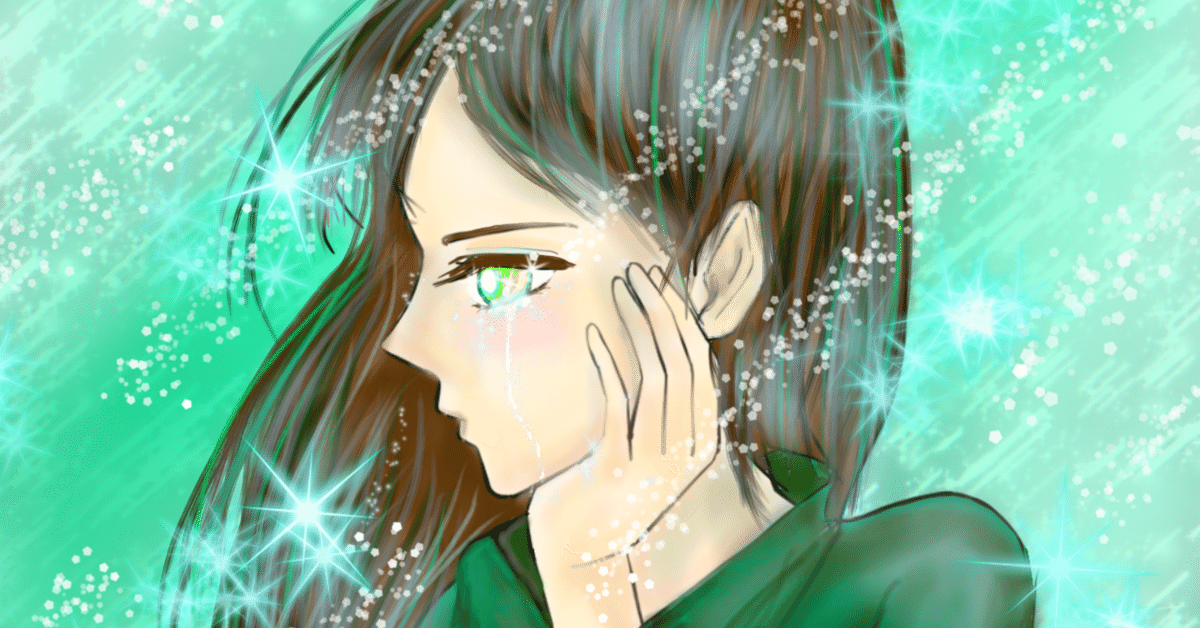
魔境アラザルド9 砂漠の魔人④
第一部 五王君
ニ章 砂漠の魔人
4
連なる黄金の砂丘の群れに葡萄酒をこぼしたような濃厚な紅い影が染みわたっていく夕刻。
彼は片頬に夕陽を受けながら、戸棚から葡萄酒でも蒸留酒でもなく、ふっと目に入った、ほんのりとろみのある甘い果実酒を取り出した。
…ダーシムの村に立ち寄ったのは、今から遡ること10年ほど前だっただろうか。
旅人に扮して、近隣の様子を視察目的でいくつか廻っていた。
その最後の場所だったと思う。
この前日、彼は妹の城で惨めな思いをした。
その心は谷底の岩土を這うようにじめじめと暗く泥に塗れ、ささくれた傷からは絶えず血が滲み、恥ずべき己を知らしめた。
顔には出さぬようにしていたが、愉快な気持ちとは程遠い。
そんなどん底にいた彼を、ダーシムの村長で魔境主のベレトンは、穏やかな笑顔で出迎えてくれた。
「ようこそ、わが村落へ。お疲れでしょう。どうぞ、宜しければ拙宅へ御逗留ください。私はここダーシムの村長ベレトンと申します」
ベレトンはそう言うと、彼を自宅へと案内した。
彼はザラットと名乗った。
褐色の肌に、黒眼で、黒茶の髪を後ろで三つ編みに束ね、土色のマントを羽織る。腰には剣を携え、弓を背負う。
魔力の弱い魔人は旅においては武器を持つことが多い。自分より強い魔人に襲われたとき、対抗するための魔具だった。
「ザラットさま。いま、お茶を…それとも、杏酒になさいますか?」
「…杏の酒ですか、いいですね。いただきたいです」
満面の笑顔に淡い笑顔で返し、温めた杏の甘い酒を二人で飲み交わした。酒肴は干した牛肉だった。その塩辛さが甘すぎる酒の味を中和して、絶妙だった。
「…何か心を痛める出来事でもおありでしたか? 大変失礼ながら、お元気がないようにお見受けします」
思ってもみない問いかけだった。
彼は酒に強かったが、やはり酒の勢いというものはあった。
思わず、ひとつ溜息を漏らした。
「ええ。まあ、大したことではありません」
「そうは見えません」
ベレトンは微笑みを浮かべたまま、彼の盃に酒を足した。
「食えない方ですね…では少し語らせていただきましょうか」
その酒を一口啜ると、彼はかすかに茜が差した透明な果実酒の表面に空洞のような暗黒の片目を映して、白磁の盃の底を見つめた。
「ある人から、自分の存在を恥ずべき存在ゆえ、いないほうが良かったと…言われてしまいまして」
彼は皮肉な笑みを口元だけに浮かべて、また一口啜る。
あのとき。
…自覚していたことだった。
なのに、いざ面と向かって人に言われてみると、胸奥にまで尖った太い枯れ枝をずぶずぶと突き刺されていくような生々しい痛みを覚えた。
「それはひどい。誰であろうと絶対に口にすべき言葉ではありません。その方が確実にお悪い」
ダーシムの村長は、酒をぐびりと飲み干すと、彼の虚ろな瞳を見つめて説く。
「あなたを傷つける為に言った言葉です。肉体の傷だけが傷ではない。心の傷もまた癒されるべきもの…宜しければ、これを」
そう言ってベレトンが取り出したのは、透明な小粒の水晶石だった。楕円形の、よく磨かれた上質な代物だった。
「美しい…まるであなたの心のようですね」
「いいえ。それを美しいと感じるあなたの心が美しいのです。はは、祖母の受け売りですが…私もそう思っています」
「ありがとうございます」
彼はそれを受け取り、即席で銀の鎖を魔法で出すと、それに嵌め込んで首飾りにした。そして、胸に垂らす。水晶石は点けたばかりのランプの灯りを透かし、澄んだ艶を浮かばせ、壊れそうな彼の心を慰めた。
翌朝、彼はダーシムを立ち、カルーンの私室に戻った。
ベレトンに貰った水晶石の首飾りは肌着の下に付けた。一瞬ひんやりするが、すぐ馴染み、彼の体温と等しくなる。
…それは、10年経った今でも、彼の肌着の下に掛けられていた。
「どうかなさいましたか? ジルヴィードさま?」
無意識に、そのベレトンの血縁の女に目を向けていた。
「…べつに」
彼は目を逸らし、胸元の石にそっと触れ、その手で側卓からグラスを取る。
先程戸棚から出した杏酒をそれに注ぎ、ほんの少しだけ舐めた。
「甘いお酒もお飲みになるのですね。蒸留酒や麦酒のほうがお好きなのだと思っておりました」
ダーフェナが言うのを聞きながら、彼はもう一口飲み込む。
「…あんたは酒は飲まないのか? この酒はダーシムでベレトンの家にもあった酒だ。一杯飲んでみたらいい」
別のグラスに注いで出してやると、彼女は躊躇いながらも、そっと口をつけた。
その瞬間。
「あ…」
不意に彼女の両眼から、一筋ずつ涙の河が流れ落ちた。
「私の名は…」
独り言のように呟く。
「…リュイネーラ、リュイネーラ・プトラ。アムルス・プトラの…妻、です」

ベレトンの苦悶は、その日の日暮れまで続いた。頭を抱えて身を捩りながら呻く様子を、ずっと眺めているのは辛かった。
マリュネーラは、平然とそれを見守るエリンフィルトの整った横顔を『悪魔の使い』のようだと感じたが、たぶん大丈夫なんだろう、と思い、一応安心はしていた。
彼女は早く知りたかった。
ベレトンが母の何なのか、外見からするに親類であることは、恐らく間違いない。
そして、叶うことならば、母の居場所まで導いてほしかった。
外の空気を吸って、ちょうど戻ってきたとき、エリンフィルトが彼女を手招きし、ベレトンが落ち着いたことを知らせた。
大汗をかいて、呼吸を整えたダーシムの魔境主は疲れ切った顔で一言呟いた。
「…思い出しました」
「まず、何を思い出した?」
エリンフィルトが一息の間も置かずに訊ねる。ベレトンは大きく息を吸い込み、それを吐き出すように答えた。
「はい…まず、自分のことです。私は間違いなく、ダーシムの村長ベレトンです。そして、姪のリュイネーラは若くして病で死んだ妹の娘で、パボスの町で偶然知り合った行商人と結婚し、20年ほど村を離れておりましたが…」
一度乾いた唇を湿らせてから、眉間を狭くして搾り出すように続ける。
「黒い嵐が村を襲うとの予知を、その直前、私に告げに参ったのです…」
それが3年前のことだった。
リュイネーラの言うとおり、黒い嵐は村を襲った。だが、村人たちは全員ザベルまたはセレガの町に避難させていたため、人命が失われることは何とか回避できた。
家屋や牛馬、畑や樹木などは恐らく全て破壊されてしまったことだろう。
自分と姪は逃げ遅れ、自分はここナバルの村にまで飛ばされて意識と記憶を失くした。
しかし、抱き合うように支え合っていたはずの予知者の姪がどうなったのかは今やまったく分からない。
矮小とはいえ「魔境」を自ら持つ魔人でありながら、愛する姪どころか己の身さえ守りきれないとは、何とも不甲斐ない話だ。
ナバルの村長クレストが会わせてくれた、かつてダーシムを訪れたという旅人の話から、自分が「ベレトン」という者でダーシムの村を治めていたことを知った。
褐色の肌と黒茶の艶やかな長い髪を後ろで三つ編みに結えた男だった。
酒を酌み交わしたらしかったが、彼は覚えていなかった。
記憶が戻ってきた今もまだ思い出せない。
男は名乗ることもなく「思い出さずとも構いません。私はただ逗留時を懐かしみ、会ってお話ししたかっただけなので」と静かに笑って去っていった。
「じゃ、お母さんの行方は…」
「申し訳ない、どこへ飛ばされてしまったのか…私も知りたいくらいなのだよ、マリュネーラ」
「そうですか…。でも、仕方ないよね」
マリュネーラはがっかりして項垂れたが、だからといってベレトンを責めることはできなかった。彼もまたあの災厄の被害者なのだ。
「ベレトン。ひとつ確認するが」
黒炎の偉大な王君が、ふと何か思いついたように口を開く。
「何でございましょうか?」
「その旅人の男、剣と弓を持っていたか? あと、土色のマントを着てなかったか?」
「えーと…どうだったでしょうか。弓はお持ちだったように思いますが、剣と土色のマントですか…」
「それがどうしたのさ、エリン」
エリンフィルトはマリュネーラの問いを無視して、ベレトンの目をじっと見つめる。
「…ああ! そうですね、剣もお持ちだったかもしれません。側の壁に立て掛けてあったような…あと、土色というのか…茶色っぽい服装だったと思います」
手を打って答えたベレトンからエリンフィルトは目線を外し、一度木目の荒い天井の梁を見上げ、絹のような色白の喉を見せた。
やがて、彼は徐ろに唇を歪めて腕組みをした。
「…あいつも、絡んでやがる」
「あいつ?」
「…だから、ユスで俺に声をかけて来やがったんだな。何かダーシムがらみで『幻影騎馬団』を探ってたんだろう…あの糞野郎が!」
マリュネーラは憎々しげなエリンフィルトの声を聞いて、それがあの琥珀色の魔人のことであると察した。
あの人は、このナバルの村で少し前に、ベレトンに声をかけていた…ということなのだろう。だとしたら…母のことも何か知っている可能性がある。
「エリン! あたしさ!」
「こうなったら、あいつに問い質してやろうじゃねーか!」
彼女が提案する前に、彼は叫んだ。
ナバルの村で、ベレトンと遭遇したのは思いがけない偶然だった。
この村は、昔からよく行き来しており、小川のせせらぎに水車の回るのどかで慎ましい雰囲気が郷里の森に似て、居心地が良かった。村長のクレストとその弟のアラクも、双子のようによく似ており仲睦まじい兄弟だった。
彼はこの兄弟にだけは、自分の正体を教えており、クレストには弓の、アラクには剣の稽古をつけてやったこともある。
「いや敵いませぬ、敵いませぬ。ザラットさまに敵うはずがありませぬ」
「なぜ?」
「なぜとご質問なさるか。貴方と私では天上の雲と土中の蟻の子ほどの差がありますでしょうに」
「剣の才に、魔力の差など関係ない」
「そうであっても…貴方の剣の才は雲上に聳え立つ光の楼閣もかくあらん、武神とて敵うものではありませぬ」
「そこまでではない。さあ、構えろ」
「無茶をおっしゃいますな、ご勘弁ください…ジル…いえ、ザラットさま!」
嫌がるアラクを無理矢理立たせて、剣を振り回したのを覚えている。
剣や弓を携えるのは、強魔人にあるべき姿ではない。魔武具に頼るなど、自分の魔力に自信のない弱魔人だと言っているようなものだった。
だから、普段は持ち歩かない。
しかし、彼は昔から剣や弓をいじるのが好きだった。
旅人に姿を変じたときだけ、それらを好きに使えるのが嬉しくて、必ず持ち歩いている。
「…なんだ?」
彼は飲んでいた米酒の盃を机に戻した。
突然、静穏だった彼の頭の中に、荒ぶる風が人々の骨肉を切り刻む光景と鮮血の飛沫が次々と高く噴き上がる光景が激しく明滅した。そこに断末魔と高飛車な女の笑声が混ざり、耳をつんざくように響き渡った。
ナバルを思い起こした直後に生じた心象…。
悪い予感に駆り立てられ、彼は目を閉じ、ナバルの地に思念を送る。
すっかり片付けられてはいたが、かすかに痕跡は感じられた。また前にはなかった簡易な墓標がたくさん並んでいて、人の気配もない。
あるのは黒炎の王君とその連れの娘とベレトンの気配だけだ。恐らく彼らが、死んだ村人たちを弔い、後片付けをしたのだろう。
「まさか、クレスト…アラクも…風刃に?」
側近コルフィンの馴らしている伝書鳶レムラの報告は、ラクロンに滞在していたエリンフィルトとマリュネーラがナバルの村に行ったようだということだけだった。
ナバルの村で何か惨事があったことまでは恐らく把握していない。いや、見えていたとしても、レムラにとって重要な見聞ではなかった。コルフィンの指示は、エリンフィルトの動向だけだったのだろう。レムラに落度はない。
「あの女……。俺への見せしめか」
彼は立ち上がると、一瞬で身なりを変え、星の散らばり出した闇黒の空を見上げた。
「我が君、実に痛快でございましたな。黒炎の君が現れたのは予想外でしたが、あのナバルの雑魚たちが逃げ惑う様、まったくもって滑稽で滑稽で…私もう笑いが止まらず、苦しゅうてなりませんでした」
ここは「風の谷」とも呼ばれる岩壁の谷、アリーセル峡谷。
このアリーセルを魔境としているのが、サラウィーン。五王君の1人『風刃君』だ。
「ほんにのぅ…。思わぬ訪問者に出くわしたが、わたくしもせいせいした。あの砂漠の主の片割れが…あれが愛着していたがらくたどもを一匹残らず“掃除”できたからのぅ」
黒炎君には、たまたま立ち寄っただけだと説明したが、実際はたまたまではない。
サラウィーンは言いながら、忌まわしげな表情で己の失くした片目の目蓋の傷に触れた。
彼女が隻眼になったのは、それほど昔の話ではなかった。
あの日、彼女はいつものように退屈していた。
近隣の集落の多くは彼女を恐れ、従順に服従していたのだが、中には強魔人に結界を張ってもらい、反抗してくる生意気な集落もあった。
その1つ、アリーセル峡谷より幾分か離れた南西部にあるミクチャの村の外での出来事だ。
その結界は強かった。
どこの強魔人にやらせたか、相当な代価を払ったことだろう。サラウィーンが部下に探らせると、剣と弓を携えた旅人のような男だという証言があったという。
「剣と弓? 弱者の持ち物ではないか。そのような者に張れるような結界ではなかった…身なりを偽装しておったのか?」
サラウィーンは紺碧の両眼を細め、自らそれを確かめる為に、ミクチャを監視した。
その男は、3か月に一度ほど村の様子を見に来るという。それを待ち伏せしていたのだ。
そして、噂の者は姿を見せた。
話のとおり、剣と弓を持っていた。浅黒い肌に黒眼で、黒茶の髪を後ろで束ねた男だ。
「あやつか。強者には見えぬが…試してみるか。死んでもべつに構わぬしな」
言いながら、指先に風の刃を生じさせた王君は男の首筋を目がけて一刃の風の凶器を放った。
完全に虚をついた攻撃、だったはずだ。
だが、風の刃は男の首はおろか影すらも掠らず、それどころか振り返った男の土色の羽織ものに弾かれ、勢いを無くし地に落ちた。
そして、彼女は逆に男の鋭利な眼光に見据えられた。
「そんなはずは…そなた、何者ぞ!」
「…ふざけるな」
彼は彼女を罵った。
王君たる彼女を当たり前のように見下している。
サラウィーンが何よりも憎むものは、自分以外の者からの貶めと敗北だ。
彼女は己の腹の底から沸々と湧出して込み上げてくる怒りを、どうしても抑えることができなかった。
ゆえに、これまでにないほど頑強で巨大な風刃を、渾身の力を込め、いつもの倍速にして男に投げつけてやった。
それは、男に当たったように見えた。
だが。
男はすらりと剣を抜き、その風刃をこともなく引き裂いたかと思うと、その斬撃は離れた彼女の蒼白な顔にまで及び、全く不慮にその左目を斬られた。
血が視界を染めた。
あってはならないことだった。
「失せろ。ここは貴様の領域ではない。貴様に俺は倒せない。この結界も破れない」
男は無表情につぶやく。
「名を名乗れ! わたくしを五王君の1人、風刃と知ってのことであろう!」
怒り狂う王君の女に、彼は仕方なさそうに一瞥をくれて答えた。
「俺はカルーンの魔境主、ジルヴィードだ」
一瞬だけ、元の琥珀色の瞳を見せる。
そして、剣を収めると無表情のまま、二度と振り返ることなく、ミクチャの村に入って行った。
「忘れはせぬ! 忘れはせぬぞ!」
彼女は片目から大量の血を垂れ流したまま、砂漠の魔人へ呪詛を吐く。
あのナバルの惨劇は、その復讐の一環でしかないのだ。
「さあ、この後はどうしてやろうか…のう、ウィランネ」
舌舐めずりする主君に、その臣下もまた同じような悪徳の笑みを浮かべ「楽しみでなりませぬ」と恭しく、同感の意を示すのであった。
【文末コラム9】明けまして。
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございます。
なかなか筆が進まず、はたまた結構な間が空いてしまいました。字数も増加してます…。
年が明けてしまいまして、もう1月も終わりです。お餅は食べすぎてないですか? お酒は飲みすぎてないですか?
私は飲酒習慣ないのに、肝臓値があまり良くないです。脂肪肝です。
先週、頚動脈のエコーを撮りました。
異常は特に見つかりませんでしたが、新年早々エコーです。
大丈夫なんでしょうか、ワタシ。
皆さまも、健康管理怠らないようになさってくださいませ。
次回は、章が変わります。
第一部 三章 風の峡谷 1 です。
舞台は「風の谷」へと及びます。更なる魔人たちの活躍、再会…などなどの展開へと移ります。
次回もまた、ぜひご拝読いただければと思います。
