
閉じた心から嫌悪がはみ出す|杉江松恋・日本の犯罪小説 Persona Non Grata【第8回】
▼前回はこちら
文=杉江松恋
石原慎太郎の商業誌デビュー作は第一回文學界新人賞を獲得した「太陽の季節」(新潮文庫同題短篇集所収)である。「文學界」一九五五年七月号に掲載され、翌年には第三十四回芥川賞にも選ばれた。これによって石原は文壇の寵児となり、同作によって引き起こされた〈太陽族〉ブームが社会現象となったことは周知の通りである。新しい価値観を主張する者と旧世代とが対立する構造はいつの時代にもあり、戦後の混乱期にはアプレゲール(アプレ)と呼ばれる無軌道な風俗紊乱者が相次いで出現した。〈太陽族〉が敵視された背景には、先行する犯罪行為の記憶が生々しかったこともあるだろう。
「太陽の季節」の主人公は高校生の竜哉で、彼と英子という女性との関係を中心として話は進んでいく。竜哉とその仲間の男たちは、既存の倫理観に対し強い忌避感を抱いており、自分で体験することが可能なもの以外は信じられない。戦後に始まった大量消費社会の中では、彼が満足するためには対価を支払って贖う以外の正当な手段はないだろう。
プチブルジョアの子弟であるものの自由になる金銭の少ない竜哉は必然的に軽犯罪を含む不良行為に走ることになる。英子という女性もそうした対象であり、竜哉はあえて彼女をモノとして扱うことで自身の価値体系の内に組み込もうとする。同時に彼は、ボクシングの試合で強敵と打ち合うことに他では得られない充実感を覚えもしていた。英子は初め恋愛において好敵手然として振る舞い、竜哉を満足させる。だが、彼女を自身の所有物と認識するようになってから竜哉は倦み、英子を金で兄に売り飛ばそうとする。その英子は竜哉の子供を妊娠し、中絶に失敗してあっけなく死んでしまうのだ。報せを受けた竜哉は「チェ、どじをしやがって」と、子供っぽい言葉で喪失の感情を表す。英子は死ぬことによって「竜哉の一番好きだった、いくら叩いても壊れぬ玩具を永久に奪った」のである。
「太陽の季節」自体は犯罪小説とは言えないが、その方向性を内包した作品である。芥川賞選考委員を務めた佐藤春夫をはじめとする年長の作家・評論家たちがこぞって小説に嫌悪感を表明したのはそのためだ。竜哉の心情を説明した有名な文章を引用する。
――人々が彼等(注:竜哉たち)を非難する土台となす大人達のモラルこそ、実は彼等が激しく嫌悪し、無意識に壊そうとしているものなのだ。彼等は徳と言うものの味気なさと退屈さをいやと言う程知っている。大人達が拡げたと思った世界は、実際には逆に狭められているのだ。彼等はもっと開けっ拡げた生々しい世界を要求する。(後略)
『戦後文学論争 下巻』(一九七二年。番町書房)に「太陽の季節」を巡る論争の主だった文章が収められている。論点は二つに大別でき、一つは佐藤春夫と舟橋聖一の快楽を巡る議論、もう一つは亀井勝一郎と中村光夫の賭博性に関するものである。前者は竜哉の性的倫理を論じたものだが、舟橋が佐藤の転向を詰ったために不発に終わっている。
舟橋の批判は、以前は佐藤も快楽主義的な作品を書き、自らも性の享楽者であったのに、戦争を経て保守主義者に転じたゆえに目が曇ったのではないか、という主旨である。これに対する佐藤の反論は子供じみているが、最初に発表した「良風美俗と芸術家――不良少年的文学を排す」(「讀賣新聞」一九五六年二月八日号)で「太陽の季節」を「いづれはベストセラーになり、そのうち映画にもならうといふたくましい商魂の産物であらう」と揶揄した点には注目しておきたい。なぜならば「太陽の季節」という作品はその通りにベストセラーになり同年五月には映画化され、石原は佐藤を嘲笑うかのように流行作家の道を歩むからだ。そうした存在となって佐藤に象徴される文壇のありようを崩していく。
もう一つの論争は、佐藤の言を引き継いで亀井勝一郎が石原作品の投機性を批判したことに始まる。これに対して中村が反論を行ったが「賭」「賭博性」という用語のすれ違いから話が完全に逸れ、不毛なものに終始している。後述書で「実は石原慎太郎のことなんかどうでもいいんですよね。他人の作品をダシにして自己を語りたいだけ」と豊﨑由美が指摘している通りである。これは当時「太陽の季節」を批判した文章全般に共通することで、小説の巧拙について語られることは少なく、作品から読み取れる、と論者が感じている作者の姿勢、作品が社会に及ぼす影響についての言及が大部分を占めている。生理的な嫌悪感や、脊髄反射的な忌避の念が先行して、「太陽の季節」は文壇という社会の敵と見做されたのである。その意味ではPersona Non Grata、まさに本連載で取り上げるにふさわしい作品であったと言える。
電子化が進み、以前よりは手にしやすくなったものの、二〇二三年現在の石原慎太郎は読書家に顧みられることの少ない作家になっている。一九六八年に自民党公認で参議院議員選全国区に出馬してトップ当選、以降二〇二二年に没するまで保守派政治家として活動した期間が長かったことが影響しているのだろう。しかし政治家に成りきるまでの十数年に発表した初期作品には、犯罪小説として見るべきものが多く、無視していい作家ではない。
石原は一橋大学在学中の一九五四年に、休刊していた同人誌「一橋文藝」を復刊させ、その第一号に「灰色の教室」を発表する(前出『太陽の季節』所収)。公になった最初の小説である。学校生活に倦んだ高校生たちの群像劇で、「太陽の季節」でより詳細に描かれることになる厭世的な社会観や、竜哉と英子の物語として再構成されることになる挿話も含まれている。「太陽の季節」論争が盛り上がる中で「新潮」一九五六年三月号に発表されたのが「処刑の部屋」(同右)で、これは明らかに犯罪小説に分類していい作品だ。
友人である良治が社会に牙を剥くのを止め、大人の論理に呑み込まれていくことを嫌悪する克己は一計を案じる。良治がダンスパーティーを企画した晩、愚連隊に情報を与えて彼を襲わせ、収益を奪わせようとするのだ。襲撃に対して良治が徹底的に抗えばよし、さもなくば友人として見捨てるつもりである。ところが愚連隊は拳銃を準備していたため、なすすべもなく金は奪われる。そのことに憤慨した克己は自ら愚連隊に喧嘩を売るが、囚われて私刑を受けてしまう。しかも、以前彼がデートドラッグを使って強姦した顕子という女が現れ、さらに立場は悪くなっていく。
「処刑の部屋」の終盤、傷ついてずたぼろになった克己の独白がある。それを書くことが作者の狙いであっただろう。窮地に陥った要因はすべて克己が自分で作ったものだが「その底にもう一本、俺を此処まで引きずって来た、俺の何かがある」「冗談じゃない、俺は俺の想うことをやったんだ、精一杯な。俺は少なくとも真面目だったさ」。「太陽の季節」の竜哉は不平を並べるだけで、自分ではただ玩具を弄ぶことしかしない主人公だったが、克己は少なくとも行動する主人公として描かれている。
中森明夫は『石原愼太郎の文学 9』(二〇〇七年。文藝春秋)の解説で、同選集に収められた「完全な遊戯」(「新潮」一九五七年十月号)を絶賛し、「日本語で書かれた短篇小説の最高傑作である」とまで断言している。その意見には決して与するものではないが、石原による犯罪小説短篇の中では最も注目すべき作品であることは確かだろう。「灰色の教室」「太陽の季節」「処刑の部屋」と続く作品で石原は、既存の倫理観を受け入れることを脊髄反射のように拒む若者たちを描いてきた。その究極形が「完全な遊戯」で、主人公の礼次は友人の武井と共に車で流している最中に女を拾う。そして、当たり前のように輪姦するのである。精神科病院から出てきて、再びそこに連れ戻されることを怖れているらしいことがわかると、二人は女を持て余し、仲間に預けて外出する。その仲間もまた輪姦するのである。その間に礼次たちがしてきたことは、女を売春窟に売る算段であった。
礼次たちの会話にはまったく情緒を窺わせる部分がなく、倫理観の欠如という意味では極北の存在である。中森が「『太陽の季節』の地の文にあった作者の多弁な主義主張もここでは消えて」「物語の中で行われているのは胸の悪くなるような蛮行であるのに、小説それ自体の進行は」「解像度の高い高感度カメラで撮られた舞踏芸術を見るかのよう」と評するように、男たちの行動だけで流れるように小説は進んでいき、まったく無駄な部分がない。悪趣味なポルノグラフィーだと批判する者が出るのは当然だが、思考を停止させたままの人間による犯罪行為を描いたものとしては徹底した作品なのである。中森も指摘するように、一九八八年から一九八九年にかけて起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件を連想する部分が多大にあり、女をもの扱いする男たちの言葉などを読むと、まるで件の裁判調書を見せられたかのような錯覚を起こす。
題名の「完全な遊戯」は、最後に礼次に対して武井が放つ一言から来ている。二人の行為は裁かれずに終わる。完全犯罪なのである。そのことを口にして「何もかも完全に終りという訳さ」と嘯く礼次に武井は「その割にこの遊びは安く上ったな」と返す。いかなる非道な犯罪であろうと彼らにとっては「遊戯」なのだ。ここまで徹底した形で既存の倫理に従うことを否定した作品は石原作品にも他にはない。
前出の中森評にあるように、初期の石原作品は特徴ある悪文で書かれている。文章に盛り込もうとする情報量が過多で、かつ整理不足な形で叙述されるため、述語との係り結びがおかしくなるのだ。勢いこんで語ろうとして前のめりになっているようであり、破綻していながら文体としては統一感がある。こうした悪文癖は完全には治らず、終生のものとなった。そうした石原の小説家としての特徴を対談形式で批評したのが栗原裕一郎・豊﨑由美『石原慎太郎を読んでみた』(二〇一三年。現・中公文庫)だ。石原作品が完全に黙殺されている時期に刊行された点がまず貴重だし、先の「太陽の季節」論争のような愚を犯さず作品主義で批評を行ったという意味でも稀有な存在の一冊である。
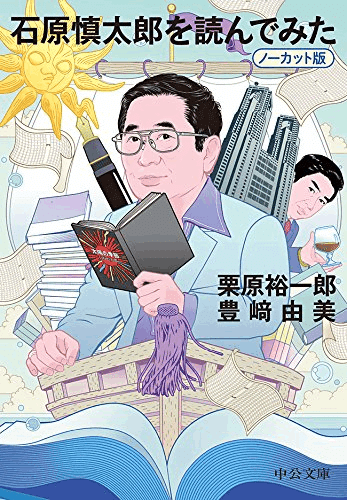
同書において豊﨑は「慎太郎って『行為』を描く時は文章が自信満々で溌剌としてるんだけど、『心理』を描く段になると、自信がないのか、途端にクリシェや通俗に頼るようになる」と興味深い指摘を行っている。デビュー前の石原はダシール・ハメットなどのアメリカ犯罪小説を愛読していた時期があり、その影響が行動を書くときの筆致に反映されているとも考えられるだろう。石原は江戸川乱歩に誘われてミステリー専門誌「宝石」一九五八年二月号に短篇「水中花」を発表する。純粋なミステリーの第二作は長篇『夜を探がせ』(「週刊読売」一九五八年七月二十日号~一九五九年二月十五日号→一九五九年。光文社)である。佐伯という男の視点を用いた三人称一視点の作品で、私立探偵小説的な展開だが、主人公の行動原理が完全な正義側ではなく、強請りを企むなど犯罪者側に傾いている点に特徴がある。
『石原慎太郎を読んでみた』では石原が非純文学系の媒体に発表した、ハードボイルド的性格のある作品群のために一章が割かれている。だが、『夜を探がせ』やこの方面での代表作である『刃鋼』(一九七六年。文藝春秋)などの長篇は、いわゆる正統派ハードボイルドの忠実な模倣に終始していて、犯罪小説的には見るべき点が少ない。むしろ純文学の媒体に発表された短篇群に石原の独自性が発揮されている。前出のものを別にすれば、代表作は「鴨」(「中央公論」一九六一年四月号。『石原愼太郎の文学10』所収。文藝春秋)である。ダボハゼのダボと呼ばれて周囲から馬鹿にされ続ける恭二は、ふとしたはずみで銃を手にする。強大な力を持っていることに気づいて、自分を馬鹿にした男を射殺、さらに幼馴染の初江を連れて逃げるのである。銃の魔力によって平凡な人間が殺人者に変貌するという物語構造は、大藪春彦『凶銃ルーガーP08』(徳間文庫)を連想させる。共に一九六一年の作品であり、似た点があるのは偶然だろう。
「鴨」から八年後、石原は「海」一九七〇年二月号~六月号に『嫌悪の狙撃者』を連載する。中央公論社からの単行本は遅れて一九七八年になったが、石原が政治活動に舵を切りつつあった、作家活動第一期の最終段階で書かれた長篇である。これは実在の出来事に取材したノンフィクション・ノヴェルだ。題材を採ったのは一九六五年七月二十九日に起きた少年ライフル魔事件である。十八歳の少年がライフルで警察官を狙撃して拳銃を奪い、銃砲店に立て籠もって乱射事件を起こした。撃たれた警察官は後に死亡する。石原は彼が少年に撃たれる場面を驚くほどの臨場感で描いている。長くなるので引用は避けるが、石原犯罪小説において最良の文章力が発揮されているのはこの箇所だと思う。石原はこの事件に興味を持った理由を偶然乱射の現場に出くわしたからだと作中で書いていて、真偽はわからない。
作中では片山譲と呼ばれる犯人がなぜ事件を引き起こしたのかを石原は追究していく。現在進行形で事件の推移を叙べていくのが柱で、中途からは幼少期に遡り、彼が嫌悪の対象とするものは何かということも拾い集める。それは一応論理的に形を結ぶのである。実際の裁判記録を石原は閲覧していて、繰り返し行われた精神鑑定の結果なども挿入されている。だがそれらの鑑定書が述べているのは要約すれば、わからなかった、ということである。最後に片山は弁護人との質疑の中で、満足したのだから死刑にしてくれと発言する。裁判長が、自分の行為が悪いことだったと考えているのかと問うと、こう答えるのだ。
「いい悪いじゃないんです。あれは、つまり、僕がしたかったことなんです」
『嫌悪の狙撃者』という題名が示すように、片山の行動原理は嫌悪する対象を撃つということ以外になかったのだと石原は示す。文藝春秋版のために書き下ろされたエッセイ「暴力という業」では、「鴨」に酷似した出来事が実際に起きて衝撃を受けたこと、しかしそれはありうる事件だと感じたということを表明した上で「暴力という人間の『現実』は現実を超えることで初めて現出する」「忌まわしい現実を超え、別の現実を望む者には他者たちが決めた規範規律などというものは現実たり得ない」と結論している。「太陽の季節」から「完全な遊戯」までの初期短篇における主題がまたここで繰り返されているのだ。
この『嫌悪の狙撃者』と兄弟のような関係にあるのが一九七〇年に新潮社から書き下ろし形式で発表された長篇『化石の森』だ。大学病院で病理研究室に属している緋本治夫という男を主人公とする物語である。彼は高校時代の同級生である井沢英子と再会し、情交する。その体験は治夫にとって人生で初めてと言っていいほどの激しい体験であり、英子を運命の相手であると確信する。だが、英子には情夫がいた。自身の意志とは関係なく、借金のために所有されているのである。その男がいては英子と結ばれないと考えた治夫は、病院から痕跡の残らない毒薬メディアチオンを持ち出し、英子に男を毒殺させる。
ここまでが前半で、後半ではもう一人の女性が主役になる。大学病院の医療過誤で息子を聴覚障害者にされてしまい、治夫にすがりついてくる塩見菊江である。治夫は菊江の夫が悪質な業者に巨額の不動産を騙し取られたことを知ると、暴力的な手段によってそれを取り返そうとする。その過程の中で菊江とも交わり、やはり深い安心感を得るのだ。
英子と菊江、二人の触媒が登場するファム・ファタル譚である。もう一人、治夫には縁の深い女がいる。母親の多津子がそうで、治夫にはかつて彼女が男と浮気をしている現場に乗り込んで暴力を振るい、家庭から追放したという過去がある。その多津子が治夫の身辺に戻ってきて再び家族としての縁を結ぼうとするという動きが脇筋として語られる。もう一人のファム・ファタルだ。
石原の書く犯罪小説にはファム・ファタル譚の構造を持つ作品が非常に多い。というよりも、運命を変えるものに接しないと石原の主人公たちは自分から行動を起こすことができないのである。自らの手で社会と個人のありようを変えようと企む大藪春彦の主人公とはその点が決定的に異なっている。大藪にあるものは憎悪、石原のそれは嫌悪なのだ。詳述は避けるが『嫌悪の狙撃者』の主人公・片山も、やはり行動の起点には一人の女がいる。
社会は所与のものとして在る。自分以外の他者もそこにいる。自分の心を許すことのできない者に囲まれていると感じるとき、最もありうる解決は嫌悪を目に映る相手にぶつけることではないか。言葉を選ばずに言えば、石原の描く犯罪はそうした短絡的なものである。底が浅いと笑うことはできないだろう。匿名の誰かが手近な場所に嫌悪を振りまくという行為によって、この世界から穏やかな場所は徐々に狭められているのだから。

《ジャーロ No.87 2023 MARCH 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いいなと思ったら応援しよう!

