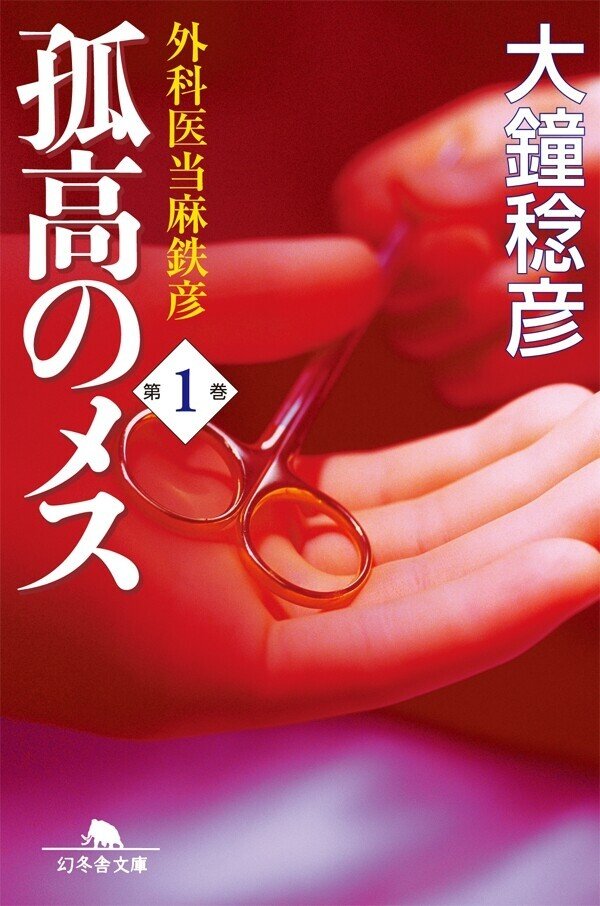私には救いたい命がある…医療制度の深部を鋭く描いた人気シリーズ! #1 孤高のメス
当麻鉄彦は、大学病院を飛び出したアウトサイダーの医師。国内外で腕を磨き、一流の外科医となった彼は、民間病院で患者たちの命を救っていく。折しも、瀕死の状態となった「エホバの証人」の少女が担ぎ込まれる。信条により両親は輸血を拒否。はたして手術は成功するのか……。現役医師でもある大鐘稔彦さんの人気シリーズ『孤高のメス』。その記念すべき第一巻の冒頭を、特別にご紹介します。
* * *
早春
三月も半ばだというのに、珍しく東京に雪が舞った。

教授会を終えて自室に戻って来た羽島富雄は、窓際に佇んでいる秘書の竹内則子の肩越しに、雪が降っているのに気付いた。
「おおっ、今朝はやけに冷えると思ったが、雪かい?」
「ええ、粉雪のようですけど……」
と答えて則子は、大柄な羽島の脇をすり抜けるように席に戻った。
「暖房がいるね、暖房が……」
則子の立っていた窓際に立つと、独白ともつかず羽島は呟いた。
「熱いコーヒーを一杯、頼むよ」
則子がポットにゆらゆらと湯気をたてるのを流し見ながら言った。
「それから、当麻君を呼んでくれないか。オペ中かも知れんが……」
「もしオペ中でしたら、どうしましょうか?」
「ウン、何時頃終わるか、聞いてくれ」
「わかりました」
「君は当麻君を知っているよね?」
羽島の方はふり向かず、まるで予期していた問いかけでもあるかのように則子は微笑んだ。
「出藍の誉。青は藍より出でて藍より青し――でしたかしら?」
「よく覚えているな」
「だって、一度や二度耳にしたぐらいじゃありませんから」
コーヒーを羽島の机に運びながら、肩をすくめて則子は言った。
「アハハ、そうか……」
「いつもいつも諺での表現ではなかったですけど」
「たとえば?」
則子は空になった盆を自分の胸に抱えながら、人差し指をかすかなエクボにあてがった。
「近来稀なる逸材とか、宝物を見つけたとか、もっと具体的には、あと五年もすれば俺を追い越すかも知れん男、とか……」
羽島はコーヒーカップで塞がれた口の代わりに鼻先で笑った。
「そうか。そんなにしょっ中言ってたか」
「格別、思い入れが深いようですね。当麻先生に」
羽島は、いくらか嘆息混じりに吐いた。
「いやな、毎年ウチのセンターには他の大学の医学部卒業生も含めて二十人ばかり修練士として志願して来るが、外科医として大成出来そうなのは、そのうち一割いるかどうかだ。ま、目の届くところでは何とかやらせられるが、独り立ちはおぼつかないというのが大方でね」
「で、当麻先生は、その数少ないエリートの一人、という訳ですよね?」
「ああ。他にも見込みのある奴がいなくはないが、今年の卒業者の中では断トツだ」
則子は、不意に目を丸めてみせた。
「外科医として大成しそうな人とそうでない人とは、どのへんで見分けがつくんですか?」
「そりゃ、オペを何例かやらせてみりゃ一目瞭然だよ」
「真面目か不真面目か、というだけではないんでしょうね、そんなふうに差が出てくるのは」
「まあ、やる気のない奴はどう仕様もないが、単に真面目、というだけでも大成しないんだよな」
「じゃ、先生のような国手になれる一番の要素は?」
「センス――一言で言えばこれに尽きるだろう。素振りを一日千回やったからと言って、誰もが王のようなホームランバッターや落合のような三割打者になれる訳じゃない」
則子は首をすくめた。
「じゃ、当麻先生をお呼びしますね」
「ああ、頼むよ」
羽島が度忘れを思い出したように大仰に頷いてみせたので、則子は新たな微笑を誘われた。

慰留
当麻鉄彦と対座したのは、結局、それから数時間後の午後になった。当麻は既に手術に入っており、午前一杯抜けられなかったからである。
手術を受けたのは六十歳の男性で、半年前に「目が黄色いよ」と家人に指摘されて近在の開業医を訪れた。開業医は「肝炎」と診断して漫然と治療を続けたが、“黄疸”は一向に引かず、かえって増強の気配を見せた。業を煮やした家人が、別の医者に当たった方がいいとしきりに説得にかかりだした。
そんなある夜、患者は突如、左下腹部に激烈な痛みを訴えた。生憎土曜日で、緊急手術に対応できる外科医が当直している病院は近在に見当たらず、救急隊はやむなくやや遠方の関東医科大に運んだ。
たまたま当麻が当直に当たっていた。脱腸であると、診断は容易についた。通常なら腰椎麻酔をかけて陰嚢にまではまり込んだ腸を腹の中に戻し、緩んだソケイ輪の縫縮を行うのだが、患者を一瞥するなり、当麻の関心は、ヘルニアよりも目と皮膚の黄染に行った。
(癌ではない!)
もし癌ならば、黄疸をきたしながら半年間も小康状態を保ってはおられないからだ。しかし、末期的症状として黄疸を呈してくる「肝硬変」の徴候、たとえば意識の混濁なども見られない。
(これは多分、総胆管結石だ)
当麻はそう判断した。
総胆管とは、肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ運ぶ輸送路のことである。そこに石がたまれば胆汁の流れが塞き止められ、ビリルビンという色素が血液中ににじみ出て黄疸が生じる。強い黄疸の割に患者の外見に重篤感がないことが診断の決め手だった。
(が、いずれにしてもオペは避けられない)
ならば、ヘルニアの手術と同時にした方が麻酔は一回で済み、患者の負担もそれだけ少ない。
もっとも、陰嚢にはまり込んだ腸は腹の中へ戻してやらなければいけない。そのままの状態で時を経ると、腸が次第に阻血状態となり、発症から七、八時間も過ぎると「壊死」に陥って由々しき事態を招来しかねないからである。
発症してからはまだ二時間程度だとみなした当麻は、このままヘルニアを整復しても危険はないと判断し、鎮痛鎮静剤を一本打った。疲れも手伝ったか、十分ほどで患者はウトウトと眠りに落ちた。その隙を衝いてやおら腫れ上がったソケイ部と陰嚢に手をあてがい、整復を試みた。
半信半疑で当麻の手もとを見つめていたナースや救急隊員は、ものの一分と経たず、ソケイ部と陰嚢の膨らみが砂丘が崩れるように引いた時、唖然と目を瞠った。
こうして患者は、当麻の予見通り見出された総胆管結石の除去術に続いてヘルニアの根治術を受け、あわせて二時間半の手術は大過なく午前中に終わった。
「フム、胆石特有の疝痛発作がないのに総胆管結石と判断した根拠は?」
患者の「現病歴」を聞き終わるや、羽島は修練士の卒業試験の口頭試問を再現するような口ぶりで、当麻に質問を投げかけた。
「はい、石は胆嚢から総胆管に落ち込んだのではなく、総胆管由来のビリルビン石であろうと……」
「なるほど」
羽島は目を細めて頷いた。
則子がコーヒーを運んできた。羽島にはお茶だった。
「頂きます」
当麻は華奢な長い指をコップに伸ばした。うつむき加減になると、濃い眉と日本人離れした深い眼窩が際立った。秀でた額に、ごく自然にウェーブした前髪が心地好さげによぎっている。
ある事情さえなければ、この門下生の風貌にいまさらのごとく見とれることもないのだが、と羽島は胸の中で呟いた。
「いや、他でもない」
当麻がカップを皿に戻したところで、羽島は机の上のファイルされた書類を鷲掴みながら沈黙を破った。それをドサッとテーブルの上に置くと、頁をくって、「当麻鉄彦」と自筆のサインがあるそれをこれ見よがしに開いてみせた。間もなく修了式を迎える修練士達に卒業後の進路を打診したアンケート用紙であった。
「昨日、これを見て、愕然たる思いに打ちのめされたんだ」
「誠に、申し訳ありません」
当麻は両手を膝の上に置くと、深々と頭を垂れた。その悪びれない様に、羽島の表情はかえって曇った。
「何故だね? 君は絶対に残ってくれると思っていたんだが」
「はい……」
当麻は背筋を伸ばした。
「御恩を仇で返すようで心苦しいのですが、何卒、お許しください」
「君の母校に戻るというんならまだ話は分かるが、この、武者修行に出る、という意味がワシにはよく分からんのだよ」
羽島は書類の一角をきつつきのように指で打ち叩いた。
「しかも、二、三年はとある。どこにも属さず、諸国行脚でもしようと言うんかね?」
「はい。消化器系に関しては、ここで充分修練を積ませて頂けたと思います。しかし、行く行く私は野に下り、医療過疎と言われる地で働きたいと思っております」
羽島は胸に腕を組んで顔をしかめた。
「それには、消化器系のみならず、あたうる限り広く、深く、技量識見を培わねばならないと、かねてより考えておりました」
羽島はアンケート用紙と一緒に綴じられてある履歴書をまさぐった。
「君の郷里は、確か、熊本だったな。小国町北里……ウン? ひょっとして、あの北里柴三郎の生地かね?」
「ええ。北里先生は郷土の誇りです」
羽島は一瞬唇をへの字に結んだ。
「だが君は、北里柴三郎に憧れて医者を志した訳ではあるまい?」
当麻は涼し気な目にかすかな戸惑いの色を浮かべた。
「だって、北里柴三郎は基礎医学者だ。四六時中顕微鏡をのぞいてミクロの世界をつついていた人だ。君はメスを執って、いわばマクロ的に人間に取り組んだ。動機がね、おのずと違っていた筈だ」
「そうですね。北里柴三郎に憧れていたのは、兄でした」
「君、兄貴がいたのか?」
羽島は履歴書を改めてめくり直した。
「この家族欄には、両親のことしか書いてないが……」
「八歳違いの兄がおりましたが、高校受験を前に、亡くなりました」
「君が三十三だから生きてたら四十一か。今頃はバリバリの医者だったろうにな。しかし、どうしてまた、そんなに若くして?」
「村の医者の、誤診です」
初めてかげりを帯びて膝もとに落ちた弟子の視線をまさぐった。
「虫垂炎だったんですが、急性の腸カタルと片付けられて――二日後に熊本の大学病院へ運ばれてオペを受けた時は、既に汎発性腹膜炎を起こして二十四時間以上たっていたようです。腎不全を併発した模様で、一週間足らずで亡くなりました」
「君は、その兄さんの臨終の様子を覚えているのかね?」
「鮮明に覚えてます。冷たくなった兄の顔を両手に挟んで、身も世もなく泣き崩れた母の姿と共に」
当麻の唇がふるえ、目にうっすらと涙がにじみ出た。
◇ ◇ ◇