
カネだけを武器にして…青年実業家の復讐と野心を描くミステリー巨編 #3 天国への階段
家業の牧場をだまし取られ、非業の死をとげた父。将来を誓い合った最愛の女性・亜希子にも裏切られ、孤独と絶望だけを抱え上京した柏木圭一は、26年の歳月を経て、政財界注目の実業家に成り上がった。罪を犯して手に入れた金から財を成した柏木が描く、復讐のシナリオとは……。ハードボイルド小説の巨匠、白川道さんの代表作として知られる『天国への階段』。ミステリ好きなら一度は読みたい本作より、一部を抜粋してご紹介します。
* * *
2
「第一カシワギビル」。反射した西陽が七階建てのビルの側壁に書き込まれた大きな文字を浮かび上がらせている。

鬱屈を抱えていたたまれなくなったときや気持ちが萎えそうになったとき、わざわざこのビルの壁面のこの文字を見に来ることがある。柏木にとっては、今保有している他のどのビルよりも思い入れのある、愛着の深いビルだった。
まだバブルの黎明期であった十三年前、「カシワギ・コーポレーション」を設立した二年後に、一大決心をして全財産と多額の借金までを負って入手した最初のビルである。このビルの成功がビル業の足がかりとなり、今日の「柏木グループ」の礎を築くこととなった。現在は、一、二階を大手の外車販売会社に貸し、三階から七階までの五フロアを「フューチャーズ」が使用している。
「日曜日なのにすまなかったな」
ビル前に車を停めさせて、もう帰っていい、と柏木は本橋にいった。
「私ならかまいません」
「いいんだ。あとはタクシーを使う」
後部座席のドアを開けて直立不動で立っている本橋を無視して、柏木はまっすぐにビルの入口に足を運んだ。
もうすぐ五時だが、日曜も営業している一階のガラス張りの新車展示場にはまだ数人の客の姿があった。
エレベーターホールで立ち止まってふと振り返ると、ビルの前にはまだ本橋が車を停めていた。瞬間本橋は、ばつの悪さを隠すかのように頭を下げると車を急発進させた。
七階が総務と役員室、他のフロアはすべて、ゲームソフトの開発に熱中する若い社員たちで占められている。
七階のボタンを押しかけた指を、三階に戻した。
どうせ中条は自分の部屋にはいないだろう。社員と一緒になってパソコンの画面をのぞき込んでいるにちがいない。
三階で下り、エレベーター前に広がる見慣れた光景に目をやった。
フロアは低い衝立によって碁盤の目のように整然と区切られ、その区切られた衝立のなかのそれぞれの場所でラフな服装の社員たちがパソコンとむかい合っている。気づいた何人かが、柏木に軽い会釈の挨拶を送ってきた。笑みでそれらに応じる。
静かだが、沈静しているのではない。静かななかに、なにかを生もうという、あるいは生まれるのをじっと待っているかのような熱気が漂っている。
柏木はこの会社のこの空気が好きだった。どこか気持ちをほっとさせてくれるのだ。
貸しビル業の中枢を置いた広尾の本社ビル、そしてもうひとつの会社、虎ノ門にある人材派遣会社「ハンド・トゥ・ハンド」とはその点が決定的にちがっていた。
通りかかった顔見知りの社員に、中条の居場所を訊いた。
「さあ、さっきは四階で見かけましたけど」
そういって、彼は笑いながら小首を傾げた。
中条がひと所にじっとしていないのは社員たちも知っている。少しでも時間があれば、研究に没頭している彼らのあいだを飛び回っては相談に乗っているのだ。
「わかった。捜してみる」
笑みを返し、柏木は階段に足をむけた。
四階、五階と中条の姿を捜し求め、見つけたのは、六階のひときわ高い衝立によって区切られた一角でだった。
「おやっ、いったいどうしたんですか?」
柏木を目にした中条が細面のなかの眼鏡に手をやってふしぎそうな顔をした。
柏木より四つ下だが、その童顔のせいで三十代半ばに見られることが多い。
「いや、ちょっとな。おまえさんと飯でも食いたくなった」
日曜日に、ここを訪れたことは数えるぐらいしかない。オーナーとはいえ、柏木は自分がこの会社では異端の人種であることを自覚していた。自由でのびのびとした雰囲気が若い社員の創造の芽を生む。その意味では、経営的な側面を除けば、この会社においては柏木は無用の存在といえなくもない。
「ちょっと見てみますか。今度、『パンドラシリーズ』に代わって新しく売り出そうとしている、例の『プロミスト・ランド』というソフトですよ」
そういって、中条がパソコンの画面に目をやった。
全五巻の「パンドラシリーズ」は売れに売れた。その利益の大半を注ぎ込んでいるのが「プロミスト・ランド」で、中条の自信作だった。ロールプレイングゲームとやらの一種であるらしい。
「いや、遠慮しておこう。どうせ見ても聞いてもわかりゃしない」
「そうですか……」
中条はだだっ子のようにちょっとすねたような表情を浮かべたが、あきらめ顔で二言三言オペレーターに指示を出すと衝立の外に出た。
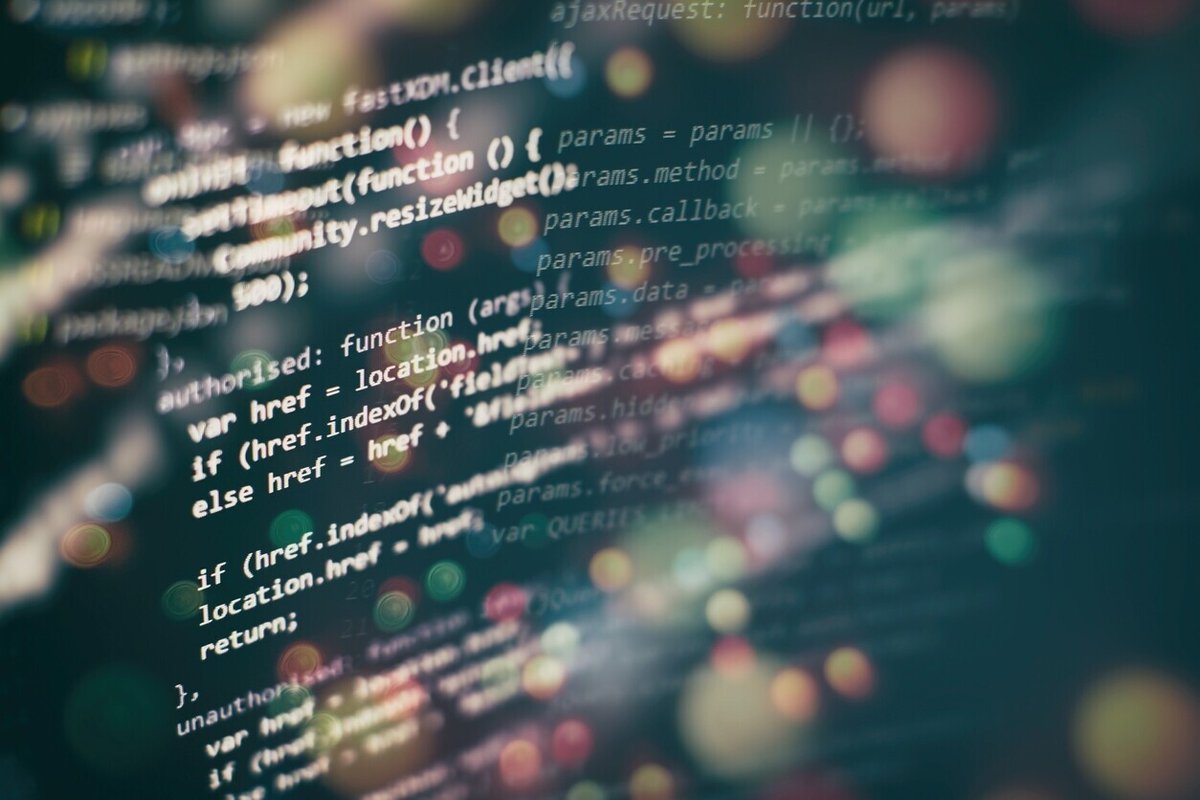
「日曜日なのに、相変わらずたくさんの社員が出社してるんだな」
中条と肩を並べて歩きながら、柏木は周囲を見回した。
「好きなんですよ。家でじっとしているより、ああしてパソコンの前に座って考え事をしているほうが落ち着くんです」
「そんなものかな」
「しかし、社長のメカ音痴も相変わらずですね。とてもこの会社を店頭公開しようとするオーナーの姿勢じゃありませんよ」
「機械は、電話で十分だ」
柏木のことばに中条は声を出して笑った。
機械を前にして気持ちが落ち着くという人間がどうにも理解できない。機械はしょせん機械だろう。だが、そうした物の見方や考え方が旧いという自覚も一方ではある。つまるところ中条たちとのちがいは、自分が育った環境のせいなのかもしれない。
一足先に下に下り、中条を待った。
柏木の胸のなかにあったどこかふさいだような気分はいつの間にか消えていた。やはり顔を出してよかったとおもう。
雨はすっかり上がっていた。梅雨入り間近の、ねっとりと肌にまとわりつくような空気も雨に洗い流されて清々しいものとなっている。
夕暮れの街並みに点りはじめたネオンを見つめながらマルボロを一本吸い終えたとき、エレベーターを下りてくる中条の姿が目に入った。
「なにを食いたい?」
たばこを足もとに落とし、柏木は訊いた。
「なんでもいいです。任せます」
「仕事のことしか頭にないんだな」
口にしながら、ふと、おもいついた。そのときには、目の前を通り過ぎようとする空車に手をあげていた。
乗り込み、運転手に、高田馬場という。
「高田馬場?」
横に腰を下ろした中条が怪訝な顔をした。
「ああ、千草食堂で急に飯を食いたくなった」
「千草食堂? 千草食堂って、あの……」
「きょうはなんとなくそんな気分なんだ」
見つめる中条の目に、柏木はうなずいた。
「そうですか……。しかし、ずいぶんと懐かしい名前だなあ。年中無休、早い、うまい、安い――か」
軽口をつぶやきながら、中条が記憶をひもとくような視線を宙に彷徨わせた。
「でも……、もう二十年からになりますよ。潰れてないでしょうね?」
「だいじょうぶさ。去年の暮れは営業してた」
「去年?」
中条が一瞬、ビックリしたような目をむけてくる。
「ああ、なんとなくのぞいてみたくなってな」
笑みで中条に応じたが、なんとなくのぞいたわけではなかった。食べる物も喉を通らず、ひとり新宿で正体不明になるまで酔い潰れた朝、まるで夢遊病者のように足をむけたのだ。あのときのおもいを封じるように柏木は、ネオンの輝く、車外のビル街に目をやった。
「ところで、圭介のやつ、ずいぶんと可愛くなっただろう?」
話題を変え、中条に訊く。
「ええ、やんちゃで困っています」
中条の表情がゆるんだ。
「日曜日じゃ、奥さんと子供が待ってるな」
「気にしないでください」
「なに、飯を食ったら、すぐに解放してやるさ。恨まれたらかなわん」
中条の住居は代々木上原だ。中目黒の自宅に帰るついでに落としてやればいい。
中条は奥手で、結婚したのは四年前だった。そしてその二年後に、子供好きの彼に待望の子宝が授かった。柏木の名前を一字もらう、と宣言し、中条は柏木の止めるのも聞かずに生まれた男の子に圭介と命名した。そのせいもあるが、子供のいない柏木にとっては、中条の子供の圭介はなんとなく血の繋がりを感じさせるような存在でもある。
タクシーは明治通りを右折し、新目白通りに入った。
「面影橋の所で停まってくれ」
運転手にいう。
車を下り、神田川のほうにむかって中条と肩を並べて歩いた。
きのうからの雨で、川は増水していた。その増水した川の流れが時々ポリ袋や段ボールの紙片などのゴミを運び去ってゆく。
学生らしき一団が笑い声をあげながら通り過ぎた。
この界隈は、W大学に通う学生の下宿屋やアパートが多いことで知られている。かつて柏木や中条もこの一角に住んでいた。クリーニング屋とコンビニにはさまれて押し潰されたような格好の古ぼけた店構えの木造建物。「千草食堂」と書かれた曇りガラスの引き戸を開けると、店内には数人の客がいるだけだった。
スーツ姿の柏木が珍しいのか、学生客のひとりが、怪訝な顔をむけてくる。
◇ ◇ ◇

