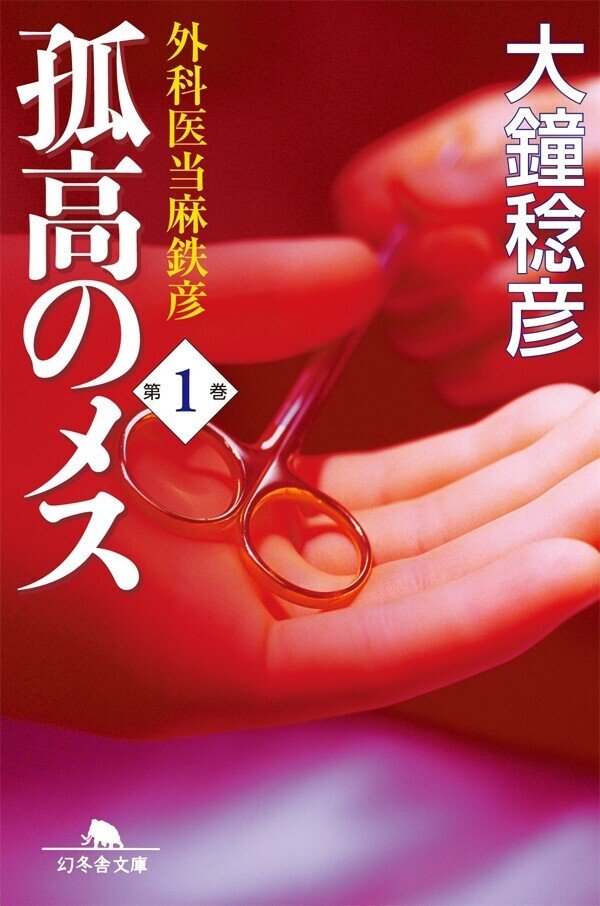武者修行の旅は続く…医療制度の深部を鋭く描いた人気シリーズ! #5 孤高のメス
当麻鉄彦は、大学病院を飛び出したアウトサイダーの医師。国内外で腕を磨き、一流の外科医となった彼は、民間病院で患者たちの命を救っていく。折しも、瀕死の状態となった「エホバの証人」の少女が担ぎ込まれる。信条により両親は輸血を拒否。はたして手術は成功するのか……。現役医師でもある大鐘稔彦さんの人気シリーズ『孤高のメス』。その記念すべき第一巻の冒頭を、特別にご紹介します。
* * *
三月に入ると、新たな修練士志願者の採用試験、卒業式、春の学会シーズン等で、医局中がてんやわんやの忙しさに振り回され、月日は瞬く間に流れ去った。一段落ついたのは五月になってからだった。

卒業と同時に医局を出て行った修練士達の噂がまたチラホラと囁かれるようになった。東京近郊で早々に開業した連中のことが一番の話題だった。
「どうもうまくいってないらしい。四人の内半分は降りたみたいだぜ」
地元の地主を巻き込んで五人の共同経営で始めた病院の雲行きが早くも怪しいと取り沙汰された。
そうした門下生の不祥事を耳にした時の羽島はすこぶる機嫌が悪かった。
「練士の面汚しもいいとこだっ! そういう奴らは二度とこのセンターの門はくぐらせん。お前ら、連中に会ったら、羽島がそう言っていたと伝えておけ」
一方、当麻鉄彦の噂は久しく聞かれなくなっていた。春にどこかの学会で見かけた、というのが最後の情報で、以後は、バッタリ消息が途絶えた。
「郷里にでも帰ったんじゃないでしょうか? 下宿は出払っていました」
修練士の同期で当麻と比較的親交のあった男が、ある日、ポツリと言った。
「いや、郷里に帰っているはずはない」
羽島が切り返すように言った。
「あいつは、二年間は武者修行に出ると言った」
タイムリミットの一年が過ぎたことに、この時羽島は今さらのごとく思い至った。
(結局は、帰って来なかったか……!)
当麻が去って二年目の夏が過ぎ、秋の学会シーズンも終わると、冬が駆け足でめぐってきた。
(またひとつ年を取るか)
五十の半ばを過ぎてから、めっきり憂鬱になってきた新しい年明けを数日後に控えたある日、見慣れぬクリスマスカードが届いて羽島を驚かせた。
「ピッツバーグ……!?」
ペンシルバニア州のかつての「鉄の町」、近年に於いては臓器移植の世界的メッカとして名高い町のアドレスに、羽島は瞠目した。
(まさか、あいつが……!?)
しかし、その筆跡にはしかと見覚えがあった。
「肝移植を学ぶべく、ピッツバーグに来ています。T・E・スターツル教授に押しかけ女房よろしく、弟子入りしました。
ドッグズラボでビーグル犬をモデルに肝移植のシミュレーションに明け暮れる日々です。
実際の肝移植は深夜に始まることが多く、夜を徹しての手術も珍しくありません。まさに体力との闘いです。先生も、くれぐれもご自愛ください。
当麻鉄彦」
(肝移植だと……!)
羽島は大きなため息をついてカードを見すえた。
(野に下ると明言した男が、何故肝移植などを!?)
日本でも肝移植はようやくホットな話題になりつつある。だが、時に肝切除を手がける羽島も、移植には食指が動かなかった。発会したばかりの「肝移植研究会」にも名を連ねていない。そのへんはもう次の世代の連中の仕事と割り切っていたから、門下生の中でももっぱら肝臓外科に携っている連中が肝移植に目の色を変えつつあるのは黙認していた。
消化器病センターばかりではない。元来、本家本元で、後発のセンターに人気を取られて内心面白くないものを覚えていた関東医科大附属病院の外科スタッフの中にも、時代の先端を走る肝移植に外科医としての未来と栄達の野望を賭けている連中がいた。
(奴さんも、目先の華かさに心奪われ、眠っていた野心を呼び醒まされたか?)
手の届かない海の向こうへ行ってしまった愛弟子の顔を思い浮かべながら、羽島はひとしきりため息をついた。

ピッツバーグ
四歳のイタリア系移民の男児がベッドに横たわっている。痩せ細った四肢とは不相応に、上腹部が岩のようにゴツゴツと盛り上がっている。いや、何かに突き上げられている、といった方が正確な表現であろう。盛り上がった腹には蛇行した静脈がるいるいと浮き出ている。
ピッツバーグの冬は寒く、外では粉雪が舞っていたが、ここプレスビテリアン・ホスピタルは暖房が効いて暖かい。
小児が横たわっているのは、廊下伝いに隣接するチルドレンズ・ホスピタルの第一手術室で、そこは暖房もさることながら、今まさに始まろうとしている一大手術を前に緊張感がみなぎり、ムンムンたる熱気がこもっていた。
小児の頭側には麻酔医が三人立ち、額を寄せ合っている。体格の良い四十半ばの中国人がチーフで中央に立ち、両サイドに、若い、これも東洋人と、もう一人は金髪をポニーテールにした白人女性が付いている。
小児の足許から少し離れた部屋の片隅には、カメラを手にした大柄な西洋人が二人、しきりにヒソヒソと囁き合っている。手術用のアンダーシャツをまとっているが、その胸もとにつけたワッペンで見学者と知れる。
そこへ今しも、同じスタイルの人物が姿を見せた。帽子、マスクをまとっているが、その面立ちで東洋人と知れた。上背は二人の西洋人にさして劣らないが、彼らと並び立つといかにもスリムに見える。年格好も二人よりはるかに若い。
「どこから来ましたか?」
東洋人が会釈すると、西洋人の一人が愛想よく応じて話しかけた。
「日本からです」
「ああ、ヤマナカの……? 食道癌で有名な……」
「ええ、彼は我々日本人の誇る外科医です。ちなみに、皆さんは?」
「アルゼンチンから来ました」
さすがにピッツバーグは国際的だった。地球上のあらゆる国々から、スタッフまたはフェローシップを志願してくる者が後を絶たず、一見客のような見学者もまた引きも切らない。
ここでは、心臓や肺の移植もボツボツ手がけていたが、世界に冠たる実績を誇っているのは何と言っても肝臓移植で、総帥トーマス・E・スターツルは、東洋流に言えばもう還暦にさしかかっていたが、尚カクシャクとして陣頭指揮に当たっていた。もっとも、ひと頃の超人的な執刀振りはさすがに鳴りをひそめ、自ら執刀する機会は週に一度あるかなしかだった。
入口の方に何人もの人の気配がした。手洗いを終えた術者達が入って来たのだ。
ラテン系の深い眼窩と浅黒い肌をしたスリムな男が小児の右側、つまり執刀者の位置についた。若いがかなり太った、こちらはアングロサクソン系の顔立ちの男が小児を挟んで対側、つまり第一助手の位置に立った。もう一人、これはアラブ系を思わせる男と、縁なし眼鏡をかけた東洋系の男が前二者の横にそれぞれ立った。四人は年格好から推して、いずれも二十代後半から精々三十代半ばと思われた。
「何だ、執刀医はスターツル教授じゃないぜ」
見学のアルゼンチン人の一人が同僚に囁いた。失望の色が浮かんでいる。真夜中ならいざ知らず、白昼のオペだからスターツルが現れるものと思い込んでいたようだ。いや、それのみではない。この幼児の腹部のただならぬ様を見るにつけ、これはなまやさしいものではない、スターツルでなければ手に負えぬシロモノではないか、と思ったのだ。
執刀医は、コスタリカの出身で、名はエスキバル、発展途上国の出ながら若手のホープの一人と目されていた。三十六歳で、外科医となって十年、スターツルの傘下に入って丸五年を経ていた。
彼は最初から電メスで腹壁に切り込んだ。
肝臓には大人の親指くらいの太さの門脈という血管が入り込んでいる。「すべての道はローマに通じる」のたとえのように、胃、小腸、大腸、脾臓など消化器の血液はすべてこの門脈に集まってくる。
これが巨大な腫瘍で押しひしがれているため血流障害を起こし、血液が肝臓を通過しにくくなっている。そのため逃げ場を求めて生じた迂回路が回り回って腹壁にまで這い上がってきているのだ。通常のメスで切り込めば、たちまちこれらの静脈を損傷して不愉快な出血に見舞われる。電メスでもいきなり切り込めば出血を免れないが、止血ピンで一本一本丹念にこれを捉えながら凝固していけば、出血の度に結紮しているよりははるかに能率的である。
だが、この患者の場合はなまなかなものではなかった。皮下に細かく網の目のようにもぐり込んでいる静脈もあり、止血は難渋を極めた。
エスキバルの目に、ものの半時もせぬうちに焦りと苛立ちの色が浮かび始めた。眼窩が深いだけ、わずかな目のかげりも濃く映った。
腹腔が開かれるまでに、既に相当量の出血を見た。盛り上がって岩のようにゴツゴツした肝臓――と言うより、それはもうほとんどすべて腫瘤にとって代わっていた――が現れた時、そのグロテスクな外観に一同は思わず息を呑んだ。
患児の体には既に一度メスが入っている。二歳の時、肝臓の右葉に生じた腫瘤の摘出を受けた。病理診断は「ハマルトーマ」というもので、それ自体は悪性ではないとされた。ところが、良性で後くされなくえぐり取られたものならば再発するはずはなかったが、どこからかまた芽を吹き出し、恐ろしい勢いで増殖し、アレヨアレヨという間に肝臓を占拠、宿主の生命を脅かすに至ったのである。
正常な部分も多少は残っていたが、そこだけを残して腫瘤を取り去ることはもはや絶対的に不可能であり、唯一残された道は肝臓をそっくり取り代える移植しかないと宣告された。一人っ子であり、両親は藁にも縋る思いでスターツルを頼った。
確かに肝移植しか講ずる手立てはないが、勝算は四〇パーセントである、とスターツルは告げた。たとえ一パーセントでも望みがあればと、両親は二つ返事で手術承諾書にサインをした。
ひとたびメスが入った生体の内部では、必ず修復過程での癒着が起こっていて、これが再手術時のネックとなる。
肝臓を取り巻くのは、上は横隔膜、下は胃、十二指腸、さては大腸の一部である横行結腸とあるが、果たせるかな、これらがすべて肝臓にガッチリ癒着し、腹壁を這っていたものとは別の迂回路である血管がその間にもぐり込んでいる。
エスキバルは電メスのまま、まず肝臓と胃の癒着を剥がしにかかったが、肝臓の剥離面からもジワジワと血がにじみ出てなまなかなものではなかった。エスキバルの手は、少し切り込んでは止まり、またため息と共に切り込んでは止まる。
(肝臓側に切り込み過ぎだ! これはとてもじゃないが彼の手に負えるシロモノじゃない!)
背後からじっと術野をのぞき込んでいた東洋人は、ここまで見届けたところでこうマスクの下で独白を吐いた。
◇ ◇ ◇