
林芙美子[放浪記]で振り返る昭和初期④
こんにちは、hakuroです。
数ある「放浪記」ものの元祖たる林芙美子の「放浪記」をもとに、昭和初期の文化と昭和初期の語彙を集めていきます。
手元にあるのは、
「新潮社 日本文学全集57 林芙美子集」昭和36年印刷
気になったものを現代のインターネットから検索して保存するだけの簡単な作業です。無料の情報ゆえ、間違いはご容赦ください。そしてコメントにて訂正をお願いいたします。
また、画像の無断使用に問題がある場合がありますので、できる限りリンク元も表示していきたいと思います。
トップ画像は道玄坂の昭和初期ごろです。渋谷区立白根郷土館所蔵の写真です。
今回は(四月×日)4段と(五月×日)2段を拾ってゆきます。
(四月×日)
郷里から母を呼び寄せる描写は無いのですが、どうやら一緒に暮らしております。直方時代にとった杵柄(きねづか)ですね。道玄坂でメリヤスの路上販売を行いますが、メリヤスを縫ってくれる安さんが事故で他界し、九州の義父も苦しい生活をしているようです。
(五月×日)
母と二人ぐらしの部屋のひとつを貸間にしようとしたが借りてはつかず、芙美子は派遣の女中の仕事を探します(派出婦)。岡山の祖母が危篤(キトク)なので母を汽車で岡山に送り出すことになりました。
語彙あつめスタートです!
今日はメリヤス屋の安さんの案内で、地割りをしてくれるのだという親分のところへ酒を一升持っていく。道玄坂の漬物屋の路地裏にある、土木請負の看板をくぐって、奇麗ではないけれど、拭きこんだ格子を開けると、いつも昼間場所割りをしてくれるお爺さんが、火鉢の傍で茶を啜(すす)っていた。
「今晩から夜店をしなさるって、昼も夜も出しゃあ、今に銀行(くら)が建ちましょうよ。」
地割り
地面の区画を整備すること。
露店を出すには露店の許可が必要で、現在では道路使用許可を警察に申請するのだろうと思われますが、ここではテキヤ組織が露店の区割りを行っているようです。
放浪記の中で登場する「地割りをしてくれる親分」の立場がどれほどのことかは文章自体からは読み取れませんが、少なくとも任侠映画のコワモテとしては描かれていないようです。「安さんの案内で」入って行った路地裏に「いつも昼間場所割りをしてくれるお爺さん」が存在するので、林芙美子自身は遠目に見おぼえのある顔なのでしょう。
そして、直方時代にバナナ屋台をやっていた母から、そういった、酒を一升持っていくなどのテキヤのあいさつを、教えてもらっているのかもしれません。
火鉢
火鉢といえばこれですが、

テキヤの親分さんなのでこっちの火鉢かもしれません。時代劇のイメージですね。

私はメリヤスの猿股を並べて「二十銭均一」の札をさげると、万年筆屋さんの電気に透して、ランデの死を読む。大きく息を吸うともう春の気配が感じられる。この風の中には、遠い遠い憶い出(おもいで)があるようだ。舗道は灯の川だ。人の洪水だ。瀬戸物屋の前には、うらぶれた大学生が、計算機を売っていた。
「諸君!何万何千何百何に何千何百何十加えればいくらになる。皆判らんか、よくもこんなに馬鹿がそろったものだ。」
沢山の群衆を相手に高飛車に出ている。こんな商売も面白いものだと思う。
メリヤスの猿股


温かそうです。ひとつ欲しい。ゴワゴワしますかね?
ランデの死
アルツィバアセフ著 ランデの死

ミハイル・アルツィバーシェフ
執筆作品・作風
近代主義小説の代表的作品で、性欲賛美をした『サーニン』やその続編となる、自殺賛美をした『最後の一線』が有名である。特に『サーニン』は当時の若い世代を中心に一世風靡し、「サーニズム」という言葉まで生んだ。他に『ランデの死』、『人間の波』などの作品がある。
日本での評価・影響
筒井康隆が少年時代の愛読書のひとつに挙げている。
黒澤明はその自伝で、兄の丙午が『最後の一線』を「世界最高の文学だ」と推奨して何時も手元に置き、27歳で自殺した、と書いている。
瀬戸物屋
せともの[瀬戸物]1瀬戸焼2やきもの。陶磁器。
せとやき[瀬戸焼き]愛知県瀬戸市を中心に産出される陶磁器。
からつ[唐津]1唐津焼の略 2(石川・富山・中国・四国・東九州方言)陶器の総称[ー焼き]佐賀県唐津地方を中心に産する陶器。薄い青色のものが多い。
陶磁器を、九州時代は「唐津物」と呼び、東京に来て「瀬戸物屋」と呼んでいます。
総称という意味でなく、正しく産地を言っているのかもしれませんね。
お母さんが弁当を持ってきてくれる。暖かになると、妙に着物の汚れが目にたってくる。母の着物も、さゝくれて来た。木綿を一反買ってあげよう。
「私が少しかわるから、お前は御飯をお上り。」
お新香に竹輪の煮つけが、瀬戸の重ね鉢にはいっていた。舗道に背中をむけて、茶も湯もない食事をしていると、万年筆屋の姉さんが、
「そこにもある、こゝにもあるという品物ではございません。お手にとって御覧下さいまし。」
と大きい声で言っている。
私はふっと塩っぱい涙がこぼれて来た。母はやっと一息ついた今の生活が嬉しいのか、小声で時代色のついた昔の唄を歌っていた。九州へ行っている義父さえこれでよくなっていたら、当分はお母さんの唄ではないが、たったかたのただろう。
小さなころにそうして暮らしたように、お母さんと一緒に露店でものを売って暮らす。こんな生活がずっと続けばよいのにと読者である私たちは応援します。がんばれ芙美子!
木綿を一反
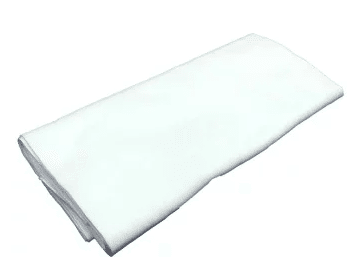
さらしの木綿を買っても着物にはちょっと・・・久留米かすりか何か、柄のついた別のものだと思います。

瀬戸の重ね鉢

プラの弁当箱など無い時代なのでしょう。容器は要返却でしょうね。こんな柄がついていたかは不明です。
たったかたのた
母がなんの曲を歌っていたのか、少し検索した程度ではわかりませんでした。
どなたかご存知ないでしょうか。
お気楽なコミックソングかもしれません。東京節(パイノパイノパイ)を貼っておきます。
ショールを買う金を貯めることを考えたら、仲々大変なことなので割引の映画を見に行ってしまった。フィルムは鉄路の白バラ、少しも面白くなし。
鉄路の白薔薇

すこしも面白くなし。この歯に衣を着せない感じ。その後、大雨の中電車で帰宅します。
電車の中まで意地悪がそろっているものだ。と、先ほどのうらぶれた大学生の言葉を引用しているようです。
いゝお天気なのに道が悪い。昼から隣にかもじ屋さんが店を出した。場銭が二銭上ったと言ってこぼしていた。昼はうどんを二杯たべる。(十六銭也)学生が、一人で五ッも品物を買って行ってくれた。今日は早くしまって芝へ仕入れに行って来ようよと思う。帰りに鯛焼を十銭買った。
かもじ屋
かもじ[髢]{[か文字]の意。[髪]の意の女房詞(ことば)→文字詞(ことば)}髪の毛に添え加える毛。入れ髪。
つまりはウィッグでしょうか。日本髪を結うときに追加する髪のようです。

家に帰ると安さんが電車にしかれて危ないと母が言う。
世の中はよくもよくもこんなにひびだらけになっているものだと思う。昨日まで、元気にミシンのペダルを押していた安さん夫婦を想い出すなり。春だというのに、桜が咲いたというのに、私は電車の窓に凭(もた)れて、赤坂のお濠の灯火をいつまでも眺めていた。
ミシンのペダル

実用重視と思いますので、こんなにオシャレな飾りのついたミシンではないかもしれません。
赤坂のお濠の灯火

朝起きたらもう下駄が洗ってあった。
いとしいお母さん!大久保百人町の派出婦会に行ってみる。
~中略~
私は桃割れの髪をかしげて電車のガラス窓で直した。本村町で降りると、邸町になった路地の奥にそのうちがあった。
~中略~
私が通されたのは、洋風なせまい応接室だった。壁には、色褪(あ)せたミレーの晩鐘の口絵が張ってあった。面白くもない部屋だ。腰掛けは得たいが知れない程ブクブクして柔かである。
母と住んだ部屋は、この版の放浪記では「鳴子坂」と言っておりますが、現在の地名は「成子坂」と呼んでいるようです。江戸末期ごろまで鳴子坂と呼ばれていたとか。
合ってるよな?どうでしょうね。もしかしたら旧鳴子坂という場所があるかもしれませんね。
派出婦
はしゅつ[派出][分かれ出る意]仕事をするために、他の場所へ出向かせること。
[-所]①本部から職員を派出して、詰めさせている小さな事務所。②「巡査派出所」の略
[-婦]臨時に出張して家事の手伝いをする職業婦人。
桃割れの髪
16~17歳ごろの町家の娘たちの髪形である。形は銀杏(いちょう)返しの一種で、桃が割れたようになっているのが特色。黒い髷(まげ)の中央が二つに割れて、中から絞りの手絡(てがら)がみえる。かわいらしい年ごろの娘の髪形で、昭和初期まで行われた。

ミレーの晩鐘の口絵

口絵というのは、版画という意味かな?不明です。
紅茶と、洋菓子が出たけれど、まるで、日曜の教会に行ったような少女の日を思い出させた。
「君はいくつですか?」
「二十一です。」
「もう肩上げをおろした方がいゝな。」
私は顔が熱くなっていた。三十五円毎月つづくといいと思う。だがこれもまた信じられはしない。
日曜の教会に行った少女の日
キリスト教の教会に行く日曜学校、あるいは教会学校のことだと思われます。いつ行っていたのでしょうね?母が実の父のところを出る以前だったのでしょうか。もしそうならば福岡県は北九州市若松ですね。キリスト教会がどれほど普及していたのでしょう。ロシア文学を読むためには必要な下地なのだと思いますので、どこで習っていたか気になっていました。

肩上げ
かたあげ[肩上げ]子供の着物のゆきの長さを調節するために、肩の所に縫い上げた部分。または縫い上げること。肩揚とも書く。
母は、岡山の祖母がキトクだという電報を手にしていた。私にも母にも縁のないお祖母(ばあ)さんだけれどたった一人の義父の母だったし、田舎でさなだ帯の工場に通っているこのお祖母さんが、キトクだということは可哀想だった、どんなにしても行かなくてはならないと思う。
さなだ帯

キトク
きとく[危篤]病気が重くて今にも死にそうになること。
涙がまるで馬鹿のように流れている。信ずる者よ来れ主のみもと……遠くで救世軍の楽隊が聞えていた。何が信ずるものでござんすかだ。自分の事が信じられなくてたとえイエスであろうと、お釈迦さまであろうと、貧しい者は信ずるヨユウなんかないのだ。宗教なんて何だろう!食う事にも困らないものだから、あの人達は街にジンタまで流している。信ずる者よ来れか……。あんな陰気な歌なんか真平だ。まだ気のきいた春の唄があるなり。いっそ銀座あたりの美しい街で、こなごなに血へどを吐いて、華族さんの自動車にでもしかれてしまいたいと思う。いとしいお母さん、今、貴女は戸塚、藤沢あたりですか。三等車の隅っこで何を考えています。どの辺を通っています……。三十五円が続くといゝな。お濠には、帝劇の灯がキラキラしていた。私は汽車の走っている線路のけしきを空想していた。何もかも何もかもあたりはじっとしている。天下タイヘイで御座候だ。
救世軍
きゅうせい[救世]世の中の混乱・不安を救うこと。
[ー軍]軍隊式の組織で、民衆伝道と救済事業とに力を注ぐ、キリスト新教の一派
[ー主]迷い悩む人類を救済する人。メシア。[狭義ではキリストを指す]

林芙美子からは八つ当たりの対象になっておりますが、現在も慈善活動を続ける素晴らしい組織のようですね。
ジンタ
じんた[語源未詳]宣伝・映画館・サーカスなどに使われる、街の楽隊

華族さんの自動車にでもしかれてしまいたい
華族(かぞく)は、1869年(明治2年)から1947年(昭和22年)まで存在した近代日本の貴族階級。
かぞく[華族]爵位を持つ人とその家族。[明治政府によって始められ、敗戦後廃止]
[公家華族]江戸時代の公家で、明治維新後、華族になったもの。
[大名華族]江戸時代の大名で、明治維新後、華族になったもの。
調べれば長くなりそうです。紹介はこれっくらいで、あとはご想像ということにしましょう。
今回のまとめ
これにて、短いけれど母との幸せな暮らしは終わり。
月に三十五円出すという日本橋の薬屋の家での約束が無ければ、すぐにでも東京を引き払って、母とともに岡山に行くことができただろうに、薬屋との仕事の約束が出来たがために母と涙で別れることとなる。
それなのに、次の段(十一月×日)には、セルロイドのおもちゃ工場で色塗りの仕事をしている。ままならない人生である。
がんばれ芙美子!
次回お楽しみに!
