
DRの裏技!|トヨタ流開発ノウハウ 第29回
◆ISO9001のデザインレビュー
製造業でISO9001を取得している企業では、設計者が恐怖するDRが存在します。
多くの企業では、DRが設計審査であり、次の工程に進んでも良いかどうかの承認行為のみに扱われています。
はたして、承認行為のみが本当に正しいのでしょうか。
それではISO9001のデザインレビューに関する記載内容を確認してみましょう。
7.3.4設計・開発のレビュー設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとおりに体系的なレビューを行わなければならない。
a)設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b)問題を明確にし、必要な処置を提案する。
レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含まれていなければならない。
このレビューの結果の記録、及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。
このように書かれています。
ISO9001の内容を端的に解釈すると確かに「承認」行為と考えることができるかもしれません。
特にa)の「要求事項を満たせるかどうかを評価する」の部分です。
しかし、本来のDRは、承認行為のみではありません。評価することはもちろんですが、b)の「問題を明確にし、必要な処置を提案する」が重要な部分です。
a)とb)の考え方をまとめて、DRを定義すると私は次のように考えています。
◆DRの定義
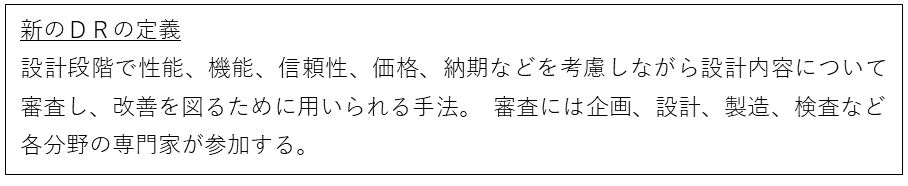
本来の姿は、問題点を抽出し改善策をDR参加メンバーで考えることです。
DR参加メンバーによる設計部門の応援活動です。DRが設計者の説明会や設計者をつるし上げにする会であってはならないのです。
そこでそのような状況にならたないための「裏技」を紹介しましょう。
◆DRの裏技、仕組みについて
DRを全員で議論する場に変えるためには、下記の2つの仕組みが必要です。
① 資料の事前配布+設計者の説明の省略
資料を事前に配布し、参加者にDRまでに内容を読み込んできてもらうのです。そうすることにより、DRでの設計者の説明が省略できるのです。
設計者の説明を省略することができれば、つるし上げにあう確率も少なくなるでしょうし、説明会のみになることもありません。また、資料のみでは分かりにくい部分については、要点のみをDRで説明するようにしてください。
事前配布は多くの企業が実施していますが、事前配布の目的は、設計内容の説明を省略することを目的としなければなりません。事前配布しておきながら、DRの最初で説明しているようでは意味がありません。
②問題点の事前抽出
DRは問題点を解決する場ですので、問題点を抽出することは事前に済ませておきます。DR参加者が事前に配布された資料を読み込み、問題点を抽出し、DR参加者が全員書き込めるドキュメントに問題点を書き込んでいきます。
DRの主催側である設計者は、事前に書き込まれた問題点を確認し、その問題点に対する対応策を考えておきます。DRでは、その対応策を解説していき、その対策の方向性で問題ないのかどうかを議論していきます。
また、設計のみでの対策では難しい場合、設計部門からDR参加の部門に対応をお願いしたり、設計と協力して解決する道を探っていきます。
このように事前に問題点を抽出することで、DRでの思い付き発言などが少なくなり、一方的な問題提起がなくなるでしょう。
これらの内容をまとめたフローを下記にしまします。
◆DRフロー

このようにDRの在り方を変えなければいつまで経っても設計者にとって恐怖のDRになり、問題点が上がらないようにしたりすることで品質をあげる活動にすることはできないでしょう。
ISO9001に書かれている「問題を明確にし、必要な処置を提案する」を実現して初めてISOの設計審査の意味が実現できるのではないでしょうか。
また、DRを設計者の負担にならないよう効率的に実施する策も考えておかなければなりません。DRを開発難易度で可変するDR(省略するDR)です。
フルモデルチェンジのように新製品を開発する場合は全てのDR(企画DR、基本設計DR、試作DR、金型DR、量産試作DRなど)が必要になってくるでしょう。
しかし、マイナーチェンジのような場合は、開発プロセスを意図的に省略し、DRも合わせて省略していくのです。
このような可変DRを実施している企業は少なく、100%DRを実施するか、もしくはDRをまったく実施しないかになってしまっています。
適切にDRを実施するべく開発難易度に合わせて、可変DRの仕組みを構築してください。その結果、機能の喪失や商品性の欠如に繋がるような問題点を事前に潰すことができ、問題の未然防止が実現するでしょう。
いかがでしょうか?
フロントローディングプロセスとなるよう昔からあるDRの仕組みを見直してみませんか?
設計者が恐怖に感じるDRではなく、設計者が「DRを実施しておいてよかった」と思える仕組みに改革してください。
講師プロフィール

株式会社A&Mコンサルト
代表取締役社長 | 中山 聡史
2003年、関西大学 機械システム工学科卒、トヨタ自動車においてエンジン設計、開発、品質管理、環境対応業務等に従事。ほぼ全てのエンジンシステムに関わり、海外でのエンジン走行テストも経験。
2011年、株式会社A&Mコンサルトに入社。製造業を中心に自動車メーカーの問題解決の考え方を指導。
2015年、同社取締役に就任
2024年4月、代表取締役社長に就任
主なコンサルティングテーマ
設計業務改善/生産管理・製造仕組改善/品質改善/売上拡大活動/財務・資金繰り
主なセミナーテーマ
トヨタ流改善研修/トヨタ流未然防止活動研修/開発リードタイム短縮の為の設計、製造改善など
※2024年6月現在の情報です
近著
