
TDL二次創作「A twinkle of Mouse」13.ホーンテッドマンション①
「ぜ〜〜〜〜〜〜ったい嫌だ!!!!!」
反抗期の子どものように主張するデイビスを、今度ばかりは、誰も馬鹿にする者はなかった。みな、どんよりと表情を曇らせながら、なるべく目の前に佇むそれを視界に入れまいと、無言のままに顔を逸らしている。
「こういうところは虫の巣窟だって、俺は知ってる。死ぬほど知ってる。クリスタル・スカルの魔宮で、しこたま学んだ」
親指を噛んでブツブツという呟きにつづけて、続々と寄せられる懸念の声。
「私も、スーツが埃で汚れるのは好ましくないな」
「酒なんかあるわけねえよなー、こんなところ」
「怖いかな? ねえ、怖いのかな、ここ?」
珍しく四人一同の意見が一致し、全員揃って尊い天からのメッセージを受信した気がした。曰く、『この洋館は素通りしなさい、大丈夫、東京ディズニーランドには三十九ものアトラクションが存在します、愉快なアトラクションは他にいくらでもあります。お隣の、クリッターカントリーに行くのです』と。しかしそうは問屋がおろさない。ウエスタン・リバー鉄道の懐かしい汽笛が鳴り響く中、ざわざわと揺らめく樹々の合間から、橙の薄い飴にも似た玻璃の外燈が、その館への道を形作る。陰気に——不吉に——何よりも無気味に、ゲストたちが笑いさざめく東京ディズニーランドの園内で、その門を超えた土地の付近だけは、閑然たる静寂に支配されていた。
今、我々の目に映るのは、荒れ果てた小高い丘の上に遠く、次々と小塔を垂直に建たせた、築年月数百年は経とうかという、臙脂色の古色蒼然たる豪邸の廃墟で、よく見ればその煉瓦の積まれた様は、手入れする者もなく、放置されてきた歴史をそのまま物語るかのよう、アメリカ河からぬめつく風が吹くと、丸屋根の頂上に風見鶏として取りつけられた蝙蝠が、軋む音を立てて回転し、裏庭にたたずむ枝垂れ柳は、たわむ腕を揺らして、館に虚しく取り縋った。色褪せた礎石には細かい根が絡まり、傍らに多くの墓石を擁していて、長年雨露に晒されたらしい、薄緑色のガラスと鋼鉄の枠で組まれた温室は、水晶宮を思わせる意匠の精緻さにも関わらず、今はあちこちの修繕を必要としている。さらに丘の麓へと目を移してゆくと、かつて使用人たちが行き交ったらしい拱廊を挟んで、腐食した枝葉に囲われた前庭に、ささやかな動物たちの霊園が広がっていた。かように小さな命であっても、誰かが心を尽くして埋葬したのであろうか、生前の姿をかたどった薄白い石像が、生い茂る草葉の陰に並んでいる。そしてそれを覆う、寡婦の如くうつむいた黒薔薇や、哀悼を秘めてざわめく糸杉、熱のない炎の如く捻れた貝塚伊吹——正面には、埋めたばかりと思われる埋葬の跡までもが、風に土を吹かせて、永遠に沈黙しているのであった。
この贅を凝らした屋敷の正門の門柱上には、堂々と腰を落ち着ける、青銅で生み出されたグリフィン——長く優美な曲線を描く肢体に、ルシフェルを思わせる翼、鋭い鉤爪と嘴を持ち合わせた番人が、訪問者をじっと見下ろしている。時々、その目が黒いダイヤモンドの如く不気味に光ったかと思うと、通り過ぎてゆくゲストへ、数秒の間視線を走らせ、次の瞬間には、ぎょろついた金属の目玉が、ふたたび陰気な表情を浮かべている、という具合であった。
「じゃ、全員一致で、ここは素通りするってことでいいな?」
「異議なーし」
「さっさと行こ行こ」
「あれ、おめえら、ちょっと待ちやがれ」
と、ゾロゾロ通り過ぎようとした一行を押しとどめ、鉄柵の合間から中の館を振り仰ぐエディ。
「なんだよ?」
「あそこの窓を、今、見慣れた影が通り過ぎた気がしたんだが」
言われた通り、彼の寸胴な人差し指が示している、中庭の向こう側へと全員が注目した先は、険しい岩場の合間から中庭を見下ろす、鋭い切妻屋根を戴いた離れの小屋。煉瓦の壁に嵌め殺されている、摩りガラスを貼り合わせた窓の彼方、ぼうっと妖しいパンプキン・オレンジの光芒を、一瞬、明らかにトゥーン調のシルエットが遮った。その手袋に包まれた片手を振っている、耳の長い影は——

「「「「ロジャー!?!?!?」」」」
一同が同時にあげた声。それが届いたかどうかは知る由もないが、影は一、二度、周囲を見回すと、毛を逆立てて何かに驚愕し、たちまち窓の前から逃げ去ってしまった。
「お、おい、エディ。今のって、確かにロジャーの影だったよな!?」
「ああ、あの馬鹿げたモヒカンと、長い耳に、やたらおちゃらけた片手の挙げ方……ロジャーしかいねえ!」
「すごい説得力だ」
「ちっと庭先まで行ってみっか。ロジャーの野郎、まさかこの館に閉じ込められてるってわけじゃねえよな?」
「ちらっとだけ、確認してみるにこしたことはないかもね」
寂れた館の入り口は厳重に閉ざされ、人っ子ひとり入れそうな気配はなかったが、実際に彼らがそこへ足を踏み入れるのに、何も難しいことはなかった。ふと気づくと、ホーンテッドマンションの門の下には、いつのまにか、一人の髪の長いメイドが立っていたのだ。まるで陰鬱な老樹のような佇まいで、深緑の古めかしいロングドレスに、下働きを表すヘッドドレスを身につけている。ファンタジーランドは全体的に、一昔前の衣装が多いというのに、そのキャストのコスチュームだけは、なぜか浮世離れしているように思え——それはとにもかくにも、舞台となった時代からそのまま抜け出してきたような、薄気味悪いほどに手垢にまみれた臨場感を、その衣服に纏わせているからだろうか。
ミッキーは遠慮がちに腰を引きながらも、微妙な距離を介して語りかけた。
「あのー……」
「…………」
「入りたいんですけどお……」
「…………」
「これ、OLCの入館カード……」
おそるおそる、ミッキーの差し出す証明書を一瞥したメイドは、無言のままに手を伸ばして、錆びかかった鉄門を軋ませながら開けてゆく。俯いたままのその真っ白な顔は、能面の如く無表情だったのに、なぜか一行の目には、その瞳の奥が奇妙な愉悦を湛えているように映った。ミッキーは項垂れたキャストの前を通り過ぎた後で、その人物には聞こえないように、そっとひとりごちた。
「あんなキャストさん、いたかな?」
「え?」
「キャストの顔と名前は、だいたい覚えているんだけど。あの人は、見覚えがないなあ……」
「新入りなんだろ。気にすんなって、ちゃちゃっと行って、さっさと出てこようぜ」
一同は正門をくぐり抜け、真上から見下ろしてくるグリフィン像にビクビクしながらも、敷地の奥へと入り込んでいった。どうやら庭は、代々の墓地から溢れた死体を埋めて、臨時の墓として利用していたらしい。一歩踏み出すと、いきなり出迎えてくれるのは、黒々とした土に突き立てられた、まばらな墓石——蔦や薔薇が伸び放題となり、野生のパンジーの咲きこぼれる花壇であろう場所に、なぜか足跡と、掘り返した痕跡がなまなましく残る。そして墓碑には、死者の名前と、その最期の顛末を表した、かくなる文言が刻まれていた。
DEAR DEPARTED
BROTHER DAVE
HE CHASED A BEAR INTO A CAVE
世を去りし兄弟、愛しきデイヴへ
熊を追いかけて洞窟へ
HERE LAIES
GOOD OLD FRED
A GREAT BIG ROCK
FELL ON HIS HEAD
R. I. P.
善良なる老フレッド、ここに眠る
大岩に潰された石頭
安らかに
MASTER GRACEY LAID
TO REST
NO MOURNING
PLEASE
AT HIS REQUEST
Farewell
マスター・グレイシー、ここに眠る
弔いは不要
要求に従うがよし
さらば
MASTER WEST LAID
TO REST
NO MOURNING
PLEASE
AT HIS REQUEST
Farewell
マスター・ウェスト、ここに眠る
弔いは不要
要求に従うがよし
さらば
この館にも秩序が保たれていた頃には、果たして、何人の庭師を必要としたのであろう。今や破滅が、没落が、崩壊が、この館のどこもかしこもを塗り込め、虚無の土地へと変え果てていた。複雑な枝を張りめぐらせた樹々は淋しく直立し、深緑の柱に支えられた四阿の薄暗さに灯る、幾つもの蜜柑色の洋燈が吊り下がった物陰は、不自然な無音を醸しだしている。広大な庭の突きあたりは、臙脂色の煉瓦の壁に覆われており、そこに石造りの壁泉が備えつけられているが、しかし険しい角を生やしたその恐ろしいガーゴイルの口は、辺りの朽葉と同様に干上がり、もはや一滴の水も残されてはいない。その剣呑な顔と、むー、と難しそうに睨めっこし合うデイビス。
「こえー顔。こんな気色悪い噴水を取りつけるってのは、いったいどういう趣味なんだよ」
「見て見て。こっちは、まだお水が出るみたいだよ」
ミッキーは言いながら、近くの水飲み場を背伸びして見た。少し捻っただけで、しょわわーと澄みやかな水が噴きあがるのを、喉を鳴らして飲み、爽やかに口元を拭う。
「お前、よくこんな廃屋に引かれた水道水なんざ飲めるな。何入ってるか分からねえじゃねーか」
「東京ディズニーランドの水は安全です」
「王自らの体で証明してゆくスタイル」
「しかし、いまだに水が引かれているとはな。実は人が住んでいるのか?」
「ま、まさか。僕だって、ここは何十年も前から、人の住んでいない廃墟だ、って噂しか聞いたことないよ」
慌てて首を振るミッキー。スコットとデイビスは顔を見合わせた。果たして、なぜそんなエリアが東京ディズニーランドに存在するかは、OLCとイマジニアのみぞ知る。所詮は単なる噂話か、あるいは——ここに住んでいる者たちは、人ではないのか。
庭を迂回して少し奥へ行くと、花壇がある。かつては見事にその剪定の技を誇ったであろうその園には、もはやどこにも秩序はない。伸び放題となった深紅の薔薇や、紫のブッドレア、鶏頭"ドラキュラ"、それに小さなパンジーが、毒々しい花弁を開いては華やかに咲きこぼれ、土の露わになった箇所では、横倒しになった鉢や壺に紛れて、そこにもまた、命を悼む形跡が繰り広げられていた。デイビスたちは、枯れ草の合間に過ぎてゆく、逝去した動物たちの像を目で追った。死してなおも鎖に繋がれ、骨のありかを示す犬——幸福に酔い痴れて昇天してしまった豚——夕食前に隣人を訪れたのが最後となった家鴨——ふと不吉な気配を察し、そこで時が停止した栗鼠——そして、今世で九回死んだと伝えられる猫。動物といえども、この世を生きた者が永遠の眠りについたという事実に、さすがに神妙な空気が漂う。そして、背の高い草むらに埋もれた、鳥の水飲み場を呈する盆の淵には。
「あっ、見ろよー、スコット。蛙の墓も造ってあるぜ」
「ほう? 珍しいな。この館の主人は、随分と慈悲深いようだ」
どうもこの家の人間たちは、動物に特別な愛着を持っていたようだ。鳥や鼠を刻みつけた水飲み場の柱の彫刻を辿ってゆくと、その足元には、こんな簡潔な墓碑銘が。
"OLD FLYBAIT"
He Croaked.
Nov. 21, 1853
「……この、日本語に訳しづらいブラック・ジョーク」
「イマジニアはこういうことを平気でするからな」
肩をすくめるスコット。本国がアメリカなので仕方がない。
花壇を横切り、さらに奥へと至る鉄製の門を押すと、血の凍るような軋みとともに、ほとんど岩に埋まった館の中庭が、ぽっかりと口を開けた。その場所の荒れ方は、これまでよりなおいっそう酷かった。岩が壁を叩き潰し、木の根が煉瓦を食い破り、崩れかかった瓦礫の下に敷き詰められるのは、奇妙に整然として見える石畳。それ以外は伽藍堂で、めぼしいものは何も置かれていないがゆえに、妙に胸苦しい虚無感を覚える場所である。辛うじて目を引くものといえば、左手の壁沿いに穿たれた、薄暗い空間くらいか——水捌けの悪いそこには、納骨堂への入り口が、壊れた鉄門を引っ掛け、時折りぶらぶらと風に揺られていたのだった。
恐々と中を覗いてみる一行。霊廟へと続く薄暗い道は、まだ増築が完成していないのか、積み上げた煉瓦や石膏、突き刺さったままの鏝が、地面に見捨てられたままになっている。そして、彼らはすっかり気づかなかったが、その数世紀に渡って渇き切った石膏は、よく見れば、骨を刻みつけた足跡のようなものが、薄闇の中から外へと向かって、浮きあがっているのが見えたはずだった。
デイビスは溜め息をついて、コキコキと首を鳴らしながら青空を見上げた。
「うーん、中庭までやってきたものの、ロジャーの手がかりがどこにもねえな。この離れの小屋も、そもそも入り口自体が存在しないから、入りようがないし。見間違いだったのかな?」
「しかし、全員があのシルエットを見たのだろう?」
「僕は見たよ」
「俺も見たぜ」
「何だったんだろ。集団幻覚ってわけか?」
腕を組んで呟かれたデイビスの問いに、ミッキーは肩を縮こませながら、ぽつりと言った。
「その……まさか、こんなことはないと思うけど……
—————ユーレイ、だったりして」
不自然な沈黙。頭上の葉叢がいやにざわめき、不吉な葉擦れが支配してゆく下で、その静寂を葬ろうとするように、デイビスが精一杯虚勢を張って言った。
「まっさかー、ここは楽しい楽しい東京ディズニーランドだぜ? そんなマジモンのオカルト話なんざ、所詮は想像力の産物——」
しかしそんな彼の言葉も、途中で誰かに無下にされたかのように打ち切られた。背後から酷く甲高い音が響いてきたかと思うと、薄暗いアーチ道の先の両開き扉が、ゆっくりとこじ開けられていったのだ。全員の眼差しが、吸い寄せられるように集う。扉がこまねく暗闇の底には、幾らかの蠟燭の妖光が、まるで誰かが火を点じたばかりの如く、微芒として内部のホワイエを照らしだしていたのである。
「……えええええ、大した風もないのに、建て付け悪すぎるだろ。こりゃ、買い手なしの不良物件だなあ」
は、はは、と乾いた笑いをこぼすデイビスに、しかし周囲の返した反応は、相も変わらず異様なものであった。つまらなそうに扉を見返すスコットは別として、エディとミッキーは、その場に凍りついて佇んだまま、何か手招きをしている人間でも見るように、凝然として身じろぎひとつしないのである。
「おい。おい、どうしたんだよ。……エディ? ミッキー?」
心配そうに顔を覗き込み、軽く手を振ってみるデイビス。しかし、彼らが弾かれたように動き出すのは同時だった。
「テディ。……テディ!」
「ウォルト。待ってったら!」
「お、おい、お前ら、どこへ行くんだよ!?」
慌てた制止の声も耳に入らないのか、二人は一心不乱に駆け出すと、扉の隙間をすり抜け、闇の底へと吸い込まれていった。
「あいつら、いったいどうしたんだ?」
「分からない。何か幻覚でも見ているのか?」
果たして、庭先に残された霊感ゼロの二人は、足元に枯れ葉を転がしながら、ボーゼンと佇むしかなかった。これまで微かながら匂いを漂わせるばかりだった恐怖が、いよいよ信憑性を増して、デイビスの胸に迫りくるように感じられる。
本当にここには、何かがあるのでは。
……とは、とても言えない。チラーっと、自分の横に立つ人物に目をやるデイビス。スコットはこういった話をまるで信じない人間で、もしも大真面目に持ちかけたとしたら、絶対に馬鹿にされるに決まっている。胸中に燃える強烈なプライドが邪魔して、ただただ、デイビスは生唾を飲む。
しかし、次に心霊現象の順番が回ってくるのは、実は彼だったのである。何かが視界を掠めた気がして、ふと、何気なく振り向いた先。明らかに生身の人間とは異なる儚い雰囲気を漂わせて、ざあ、と揺れる柳の木の下、デイビスの目に飛び込んできたのは。
「———————ダカール……?」
それは————
忘れもしない、往年のインドで出会い、たった一日だけ、宝物に囲まれた秘密基地の洞窟で、夢を語り合ったあの少年。確かに、その姿は半透明で、向こう側の景色が透けているけれど——目にありありと蘇るのは、黒曜石の断口を思わせる、艶と流れを兼ね備えた巻き髪に、張りのある練り絹の肌、飴色に照り映える引き締まった唇、僅かに歪められた凛々しい眉と、漆黒の呵梨勒を思わせる佇まい。出会った頃と何もかも同じ——僅か一桁の年齢に釣り合わぬ厳格さを湛えつつ、微風に流れる枝垂れ柳を見あげていた。
その時、じわ、とデイビスの胸に懐かしさが込みあげるのと同時に、その薄青く発光している霊体も、彼の存在に気づいたようだった。鋭い目を微かに細め、廃墟の庭園に立つ青年を見極めようとする少年は、その面影が遠い記憶の中から呼び起こされた途端、すうっと両目も大きく見開かれた。
(その、女にだらしなさそうな軽薄な顔。デイビスか?)
「ダカール。本当にお前なのか……!?」
(ああ、僕だ。ネモ船長と呼んでくれてもいいぞ、もっともこの年齢の頃の僕は、まだ偽名を名乗ってはいなかったがな)
傲然と語る態度まで懐かしいが、少年の足元は、よく見れば、地面から数インチほどふよふよと浮いている。デイビスは唖然と呆けた顔で、その微かに発光する透き通った面影を、上から下まで見つめながら、
「お、お前、登場する作品を間違えていないか? これは『空の上の物語』の続編で、お前がメインやってたサブストーリーは、もうとっくのとうに終わったんだぞ」
(いわばゲスト出演ってやつだ。子どもの姿をしているのは、いつまで経っても、僕の心は少年のままだから)
「また意味不明なことを……貴重なショタ枠を狙おうとしたって、お前はこの時系列じゃ死んでるってことになってるから、参入は無理だぞ」
(ふん、主人公の座を独り占めかよ。ケチな奴だな)
「ケチじゃねーってば、聞いてたのかよ、人の話をよッ!!」
ともあれ、かつて、ともに冒険の夢を見た友人が、今も目の前にいる、という事実に、デイビスは思いがけぬ感銘を禁じえなかった。突然、虚空と話し始めた彼の背中に、スコットのドン引きした眼差しが突き刺さるが、そんなのはどうでもいい。久方ぶりの再会なのだ。デイビスの心は、半年分、若返ったかの如く躍る。
「しっかし、幽霊になってもお前はお前なんだなー、安心したぜ。相変わらず、こまっしゃくれてるっつうか、可愛くねえっつうか」
(悪かったな。お前もその平然と失礼なことを言うところ、ちっとも変わっていない)
「つうか、なんでTDLに? お前のテーマポートは、ミステリアス・アイランドだろ?」
するとダカールは、ふい、と館に眼差しを向けた。そして、しばらくの間、風に耳を澄ませると、
(なんだか、懐かしい音が聞こえてきたから)
と囁いた。
それとともに、暗く広大なホールの片隅で、誰かが重厚な音を爪弾いたような気がした。最初は、遠い背後の鉄柵を越えて聞こえてくる、ゲストたちの笑い混じりのざわめきや、『空飛ぶダンボ』のレトロな鉄琴の旋律、『ピーターパン空の旅』の海賊船の動き出す音が紛れ込んできたのかと思った。しかし、真実はそうではなかった。明らかに、それは彼らが向かい合う廃墟の、開かれた扉の向こう側から聞こえてきていた。耳を澄ますと、果たして、この館のどこからであろう、重々しいパイプオルガンの音色が、胸の潰れるような反響を重ねて、倍音を創りあげてゆくのが耳に入る。まるで堅牢な建造物の如く、生と死の逃れようのない真理が織り交ぜられてゆくかのよう、そしてその響きに煽られて、鍵盤をあやつる者の怒り、哀しみ、無念に満ちた幻影が、荒れ果てた庭に立つ彼らの目にも、ありありと思い描かれてくるのだった。
(聞こえるか? あれは僕のだ。ノーチラス号に備えつけられていたパイプオルガンを、誰かが、ここで弾いてる)
ダカールが囁くように言った。パイプオルガンの音色は高まり、やがて、バッハのトッカータとフーガを奏で始めた。それは微かながらも激しく、尽きもせぬ未練をそそぎ尽くすかのように、館の蜘蛛の巣をわななかせ、無人の廊下に鳴り響いていた。稀代の作曲家、イーゴリ・ストラヴィンスキーが称したように——まさしく、呼吸をしない怪物の呻き声が聞こえてくる。
まるで、

誰かが、
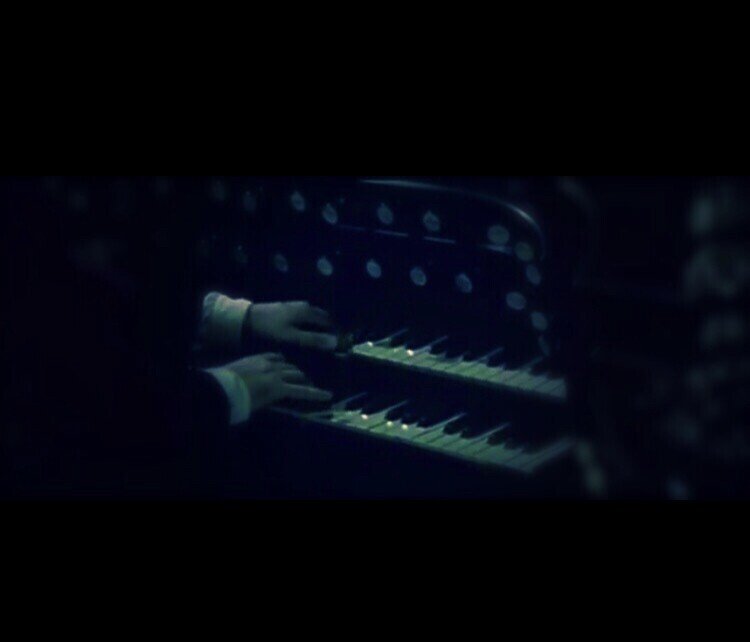
闇の奥底で、息づいているかのような……
一斉に震撼する金属管、ひとつのフーガを織り成しつつ、次々と墜落してゆく音符たち。そして威厳に満ちた旋律が上下を繰り返しながら、やがて長い和音に辿り着くと、狂おしい時間がいつまで続いたものだろう、その指を鍵盤からあげるなり、すべてが解放され、ふと打ち止んだ。
風の中に、得体の知れない静けさが広がる。少しずつ、何事もなかったかの如く、背後のゲストたちのざわめきが耳に戻ってきてからも、なぜかこの館の領地は薄ら寒く、時が止まったかのような感じに覆われていた。ダカールは厳粛に唇を引き締め、デイビスと向き合うと、ゆっくりと語りかけた。
(気をつけろよ、デイビス。この館は、邪悪な気配が充満してる。生半可な人間では、生きては帰れない)
「で、でも、俺の友達が中に入っちまったんだよ。置いてきぼりにするわけにはいかねえだろ?」
(関係ない、足を踏み入れるな。ここは魔の棲まう館なんだ。生命のある者が入れば、たちまち餌食になるぞ)
けれども、厳しい口調で言い終えるや否や、彼は片眉をあげながらデイビスの胸のあたりへと顔を突き出し、
(あれ? でもお前、護身人形を持っているのか?)
「え?」
(それなら、何とかなりそうだな。だが忠告しておく、油断すると、それが命取りになるぞ。
ここに足を踏み入れる以上は、全員必ず一緒に行動しろ。パイプオルガンに触れてはいけない、あれは死者たちの眠りを妨害する。そして、大事なことはもうひとつ。
————紫の男には、けして近づくな)
「紫の男……?」
(では、ホラーに付きものの謎めいた助言もしたし、僕は退散するか。またな、デイビス)
「お、おい。待てよ、ダカール!」
(わー)
咄嗟に、飛び退ろうとしたダカールの足首を掴むと、びたん、と物凄い音が響いて、彼は派手にすっ転んだ。あ、掴めるんだ。その手応えのなさと、絶妙にひんやりとした感触にビビって、思わず、手を引っ込めるデイビス。
「———ダカール。死んだ人間は、魂が残るのか?」
(…………)
「死んだら、みんな同じところに行くんだろ? 教えてくれ。俺たち生きている人間は、いつか、死した人間に会えるのか?」
肉体を持たないスピリットだというのに、なぜか転んですりむいた鼻を赤く腫れあがらせながら、ダカールは静かに首を振った。
(———僕もなぜ、自分が幽霊となって存在しているのかは分からない。人は、生きているうちに生の秘密を紐解くことができないように、死の秘密もまた、死んだ後であろうとも解き明かせない)
「解き明かせない……?」
(だが、もし生前に強い想いがあれば、死者はそのゆかりの地にとどまると聞く。それに——生者と交流することだって)
ふわり、と風が吹く。足元の枯れ葉が、ゆっくりと微風に引きずられて、瑣末な音を立てた。それは、かつて一度も耳にしたことのない死後の話。デイビスはその不可解な神妙さに瞳を揺らしながら、生まれて初めて、未知の領域であるあの世について語りあう機会を得る。
「天に召されない、というのは——不幸なことなのか?」
(分からない、それは故人が何を想ってこの世に留まるかによるだろう。僕は海を見たくて、たびたびこの世を訪れてるけど)
「ピクニック気分なのかよ」
(……それと、ミステリアス・アイランドの様子も。僕が死んだ後も、クルーたちは前を向いて、偉大な海を愛そうとしてくれている。同じ世界を生きてゆくことはできないけれど、彼らは僕の精神を受け継いでいる。僕はそれだけで、満足しているんだ)
俯きながら、ふわり、と風に漂うように沈思するダガールを見て、デイビスはふっと胸を衝かれる。この誇り高い少年と出会った時、故国の植民地化に絶望した彼に、海の存在を教えたのはデイビスだ——あれから何十年もの時が経った。インド独立戦争や、家族の惨殺、深海への逃亡と、新たな秘密基地の設立を経て、なおも人生を終えた後でも、その概念だけは宝石の如く、彼の魂を魅了し続けている。そのことを悟ると、まるで彼との時を超えた友情を、海だけが、その神秘的な青の中で記憶していてくれたように思えた。
「ダカール、お前は……そんなにも、あの島のことを——」
(すまない、デイビス、もうすぐ雲間が切れる。とにかく用心しろよ、この館は呪われている。けして、魂を取り込まれるな)
「ダカール?」
その瞬間、雲と雲の合間から太陽が漏れ、眩ゆい光線が溢れ返るのとともに、彼の幽体から燐光が吹きこぼれてゆくのを、デイビスは見た。
手を伸ばそうとして、覚えず、その動きを憚る。それをしたところで、何になる?
だって、彼はもう死んでしまって———俺と出会ったあの頃と同じじゃ、ない。
(—————ここから先は、お前の物語だ)
眩むような閃光が目を灼くと、まるですべてが夢であったかのように、ふたたび瞼を押しあげていったそこには、長くうねる腕を揺らした柳が、さらさらとその枝を躍らせているばかりだった。遣る瀬無い思いが胸に込みあげるのと同時に、スコットが彼の頭を軽く小突いてくる。
「終わったか。何を一人でブツブツ言っていたんだ?」
そう囁くスコットの肉体は、透けてもおらず、暖かい手のひらを持っており、微かに呼吸を波打たせて生きている。そんな当たり前のことが、今は酷く安堵をもたらした。
「……死んだ友達が、いた気がしたんだ。さっきまで、そこに……」
言いかける途中で喉が詰まり、自分の目尻が微かに濡れているのに気づいた。スコットはその様子を馬鹿にせず、ただハンカチを差しだすと、優しく彼の肩を叩いた。
「さて。私とお前、久々の二人パーティだな」
「おー。そういやここ最近は、エディやミッキーと一緒の時が多かったもんな」
「くれぐれも私の足を引っ張るなよ」
そんなわけで、結成、ストームライダー組。慣れている人間とコンビを組むと、やはり安定感が違う。
目指すべきは、不気味に開かれた洋館の扉。近づけば近づくほどに、背筋が寒くなりそうなオルガンの音が大きくなり、鼓膜に忍び込んでくる重厚な低音は、微かに地の底を顫動させ、足元で数枚の枯れ葉がかさつく。
「い、行く……か?」
「進むしかないだろ?」
若干後退気味のデイビスとは反対に、スコットは半目になって隣を見る。湿っぽく冷ややかな回廊をおそるおそる辿ってゆくと、木製の重々しい両扉には、艶々としたオーク材に、悪魔じみた装飾が彫りつけられているのが見えてきた。二人が中へ身を滑らせて、数秒後。後からぷるぷる震える一本の腕が伸びて、閉じかかるドアを全開にしておいたのは、せめてもの抵抗の証である。
うおー、暗ー。太陽の降りそそぐ世界に慣れていた目は、蠟燭しか照らすもののないホワイエに取って代わられて、一瞬、ざわりと眩暈のようなノイズに覆われる。数秒経って、黒白のざわめきの中からゆっくりと浮かびあがるのは、マントルピースの陰。まるで今際の際のようにすら思える、シャンデリアの幽けき黄金の蠟燭の光に、暖炉を備えつけた豪奢なホワイエが、ぼんやりと照らし出されていた。絨毯はしっとりと彼らの足音を吸い取り、いきなり、自らが宙に浮いたような気がする。部屋の隅、蠟燭の合間、やたらと蜘蛛の巣が這っているがゆえに、どこからどう見ても、廃墟にしか思えないのだが——その時、後ろからばたん、と軽い音が響いた。振り向くと、スコットが、これでよし、と言わんばかりの顔つきで安堵の吐息をこぼし、満足げに両手をはたいている。その頭へ、後ろからスパァァンッッと思いっきり反動をつけてデイビスがハリセンを叩きつけ、よろめくスコットの頭が、ゴンと壁にぶつかった。
「ばっきゃろー、スコットーッ!! なんでわざわざドアを閉めやがったーッッ!!」
「開けたら閉める。当然のことだ」
「アホかーっ、ドアストッパーを使ってでも開けたままにしとけよーっ!!」
「ならん、外から砂が入ってくる! 貴様、簡単そうに言いやがって、壁や床にこびりついた砂を掃除するのにどれほどの手間がかかるのか、分からんというのかッ!!」
な、なんだこいつ。いったい何のスイッチが入ったのか、突然、有無を言わせぬ迫力で詰め寄ってくるスコットに、デイビスは恐れをなして、半歩後ずさった。気のせいか、迫りくる彼の姿に、幻の三角巾とハタキが付随して見える。
「見ろ、頭上でシャンデリアを! 蜘蛛の巣まみれになのは、後ろのドアを開け放していた結果だ。絨毯だって、土で汚れれば見る影もなくなる。それに暖炉の上の、あの男の肖像画だって傷むだろ! そうしたらお前、責任取れるのか!?」
「そんなことが理由になるかーっ!! 俺たち、これで館の中に閉じ込められちまったんだぞ!!」
「密室であろうがなかろうが、掃除より重大な事項はなし!」
「このスカポンタンがーーーッッ!!!」
ふたたび、景気よく響き渡るハリセンの音。そして、そのツッコミの挙動が起こした僅かな風のせいか、それまで暗雲の如き蜘蛛の巣に絡め取られたシャンデリアの、微かな断末魔をあげて揺らめいていた蠟燭が、ついに最後の炎も尽き果て、ふっと灯が消え去った。途端に、停電の夜のような暗黒が訪れ、彼らの喧騒は嫌が応にも打ち切られた。しかしそれでも、その密室は、完全な闇に陥ることはなかったのである——マントルピースの上に飾られた蠟燭に、ひとりでに火が灯ったかと思うと、それは無気味に揺れ動きながら、この館の主の肖像画を照らしだし、その人物の輪郭が、薄ら青い燐光を帯びて、彼らの目を引きつけたからである。
「え……?」
————そこで、
デイビスは見た。
スコットも見た。

嘘のような静けさの中で、顔色の悪く痩せこけた貴公子の絵画は、やがて、その哀しげな表情を浮かべたまま、抗いようのない時の流れに侵され始めた。といっても、表面に塗られたニスが剥がれ落ちたり、油彩具が色褪せたりするのではない。その人物が、目の前で本当に年老いてゆき、哀れな人生の最期を露わにし始めたのである。そして、その零落と交わるように、どこからともなく流れてくる和音——それは、ゲストたる彼らを迎え入れようとする、ホストからの心ばかりの葬送曲なのだったが——に紛れて、墓土のように枯れ果てた、一人の低い男の声が聞こえてきたのだった。
【扉ひとつない部屋で、身の毛もよだつ不気味な響きが、館の中に広がる。蠟燭の炎が風もないのに揺れ動く。ほら、そこにもここにも亡霊たちが——
諸君の恐れおののく姿を見て、彼らは喜びの笑みを浮かべているのだ……】
果たしてその囁きは、あまりに明白に、その肖像画の向かいゆく先を示唆しすぎていた。頬は影を落とすほどに肉が削げ落ち、蒼白を超えて土気色へ。高貴なる服は破れた襤褸へと腐り果て、丁寧に撫でつけた髪は白髪が僅かに引っかかるばかりとなり、そして、そのさらなる下が覗いてきた。
いつのまにか年月に晒され、顎から歯を剥き出しにして白骨化した骸骨は、その眼窩に嵌る目玉を爛々と光らせながら、こちらを見て——笑っていた。

「すっ、すすす——ス、コ、ッ、ト、、、!」
「落ち着け、そう震えるな。突然何を言い出すのかと思ったが、この骸骨の言っていることは正確じゃない」
歯の根がかち鳴るほどに恐懼しながら首根っこを掴んでくるデイビスに、くゎんくゎんとしつこく頭を揺さぶられながらも、腕組みをしたスコットが冷静に告げる。
「扉なら後ろにあるだろ。このおどろおどろしい雰囲気で語る内容が間違っているというのは、普通に恥ずかしいな」
「お、おう、確かにそうだったな。スコットの阿呆が閉じちまいはしたけど、一応、まだここに出口が……」
しかし、デイビスの手がそろそろと壁の上を滑った先には。
「————————あ、れ……?」
かさついた壁紙が、どこまでも茫漠とした手触りを伝えるばかり。そして、這わせた指の下から、壁紙に敷き詰められた目玉模様が、瞬きしそうなほど一様に自分を見つめているのに気づいた。
その瞬間、さあっ——と血の気の引くような音が彼の全身に取り憑き、目の前の暗闇が急激に迫ってくるような感覚とともに、眩暈がした。ほとんど本能的に手をスラックスになすりつけるデイビスの後ろで、スコットは火のない暖炉に囲まれた虚空を見下ろしていたが、突然、躊躇いもなく腕をその中へと突っ込むと、何か硬いものを攫み、無理矢理それを引っ張り出した。何匹かの蜘蛛が、慌てて煤を散らしながら逃げる。埃に覆われたそれに、大層不快そうに顔を顰めはしたものの、しかし塵埃を手で払いのけながら、確信した顔でデイビスを振り返る。
「タチの悪い悪戯だな。見てみろ」
差し出された彼の手の中で、くるくると何かを回しながら、頼りない雑音をこぼしている四角いものは。
「テープレコーダー……」
「幽霊の正体見たり枯れ尾花、だな。これはもっと、作為的なものを感じるが」
「じゃ、じゃあ、あの年老いていった肖像画は何なんだよ?」
「簡単な仕掛けだ。幾つかの映像を重ね合わせて投影し、クロスフェードの要領でそれぞれの光量を調整する。幻灯機でよく使われていた手法だよ」
本当に、そんなものなのかな、とデイビスの胸にちらと影が過ぎったが、スコットが迷いない口調でそう言うからには、そうなのかもしれない。見ろ、仕掛け扉だ、と手招きするので、暖炉の横の壁に近づいてみると、
「あれれ、なんだ、この部屋?」
「ふむ……」
覗き込んだ彼らを出迎えるのは、奇妙なまでに背の高い八角形の部屋だった。広漠とした空間で、明らかに——生活用途が見えない。というのも、床には何も置かれていない一方で、天井はありえないほどに床から遠いのだ。すると突然、背後の扉がひとりでに閉まると同時に、スコットの持っていたテープレコーダーがひとりでに回り、再生され始めた。ぎょっとするデイビス、無関心に目をそそぐスコット。くぐもったバリトンは、オルガンの単音のメロディと絡み合いながら、不気味なほどに魅力的な声で語りかけてくる。
【紳士ならびに淑女の諸君、ホーンテッドマンションへようこそ。私はこの館の主、ゴーストホストである。フフフフフフ……
さあ、もっと奥へ——後ろの方のために、もうちょっと詰めてもらえるかな? もう、引き返すことはできませんぞ。全てはここから始まる……】
「う、後ろの方なんて、誰もいねーよ!」
「いちいちやかましい奴だな、対多人数想定アトラクションなんだろ。そう無闇に俺にくっつくなよ」
「ひとりにすんなよー、スコット!」
「だから、さっきからここにいるだろ。擦り寄ってくるな、気持ち悪い」
怖気を振るいながら叫び返すデイビスと、イライラしつつ彼を引き剥がし、距離を取るスコット。その話し声ですら、天井の高い部屋では虚ろなエコーが付き纏う。そう、そしてデイビスの語る通り、確かに彼らの背後には誰もいなかった——しかしその部屋には、すでに先人が、薄暗い中から測り知れぬ存在感を漂わせていたのだが。まるで地上のものには何の関心もないというような殺風景な部屋に立てば、畢竟、彼らの目は上へと吸い寄せられることになる。すると、一も二もなく、視界はそれに制圧されてしまうであろう——目玉をギョロつかせたガーゴイルたちの握り締める燭台と、さらにその上に架けられた、妖しい火影を照り返す四枚の肖像画に。蠟燭の光を受けて、重々しい沈黙の中から地上へと影を投げかける巨大な絵画を見る限り、ここは間違いなく彼らの牛耳る時空であり、デイビスもスコットも、彼らの手に落ちた獲物にしかすぎぬように思えてくる。さて、何が起こるのか、と身構えていると、擦り切れかかったテープレコーダーが、薄気味の悪い口上を告げた。
【まずは私の一族を見るがいい。この、魅力的な姿を———】

十九世紀頃の人物であろうか、性別も年齢も雰囲気もばらばらの四人の人物は、確かに奇妙な魔力で目を惹きつける——そう、ナニカがおかしいのである。世間によくある、一族の栄光を伝えるために華美に誇張されたものとはまったく違う、なんてことのない光景を切り取っただけの絵画なのに、まるで、本当に生きているようにまざまざと感じられるのは、この絵に注ぎ込まれた、画家の執念のなせる業なのだろうか。とりわけ、それらの絵にちぐはぐな印象を与えているのは——妙に飛び出た、その眼球。まるで蛙の卵のように爛々と光るそれは、絵画だとは思えないほどの異様な気迫を漲らせながら、愚かな生者たちを見下ろしている。
「ふん、楽しい楽しい一族ご紹介ツアーの開始ってわけか? では、何が起こるのか、じっくり見学させていただくとしようか」
どこか挑戦的に腕組みするスコットの隣で、頼むから挑発するのはやめてくれよお、とじりじりテレパシーを送るデイビス。そして沈黙の果てに、それは出し抜けに訪れる。
レクイエムが、止まった。
完全な闇と静寂に包まれた中で、それとなく、しかし徐々に明らかに、不思議なことが起こり始めた。最初は、床が吸い込まれているのだ、とデイビスは思った。徐々に奈落の底へと降りてゆく。いや、天井が不可解なほど迫り上がっていっている——あるいは、部屋の次元が歪み、縦に引き伸ばされている。すべては手の届きようもなく遠ざかってゆき、まるで自分たちが小さく、どんどんと縮んで、下へ下へとめり込んでゆくような気がした。それと同時に、もはや天高く頭上を支配してゆく絵画の存在感は、押し潰されそうなほどである。果たして、何が正しいのだろうか? 全ての常識が狂うような感覚とともに、肖像画もまた、恐るべき変貌を遂げてゆき、額縁の下に隠されていたこの一族の、本当の運命が明らかになってゆく。
山高帽を被り、悠然たる微笑みを浮かべた紳士、ビッグ・ホッブズ——それは二人がかりで彼を肩車したもので、土気色にまで青ざめた最も不運な者がもう腰まで浸かっているのは、二度と生きては抜け出すことのできない流砂。
日傘を差して愛らしく首を傾げた淑女、サリー・スレイター——そのほっそりとした美しい足は、一本の細い綱の上に立ち、真っ赤な口を開いたワニが、今にも細い綱が千切れる瞬間を待ち構えている。
うるわしい花と真珠の耳飾りが似合う、上品なマダム、アビゲイル・ペイトクリバー——彼女の腰掛けているのは、墓石の上。斧で頭を叩き割られた旦那は、永遠に未亡人の尻の下で、血の涙を流し続ける。
もじゃついた顎髭を生やした、禿頭の中年男、アレクサンダー・ニトロコフ——その太い足は、おかしな下着姿を晒しながらダイナマイト入りの樽を踏み、今まさにその導火線は火花を立てて、眩しい蠟燭の火に炙られている。
そこに描かれているのはいずれも、死の風の前に立つ、おかしくも哀れな灯火。しかしそのような中でも、スコットたちを見下ろしてくるのは、燭台の光芒を浴びて猫のように光る、彼らの愉悦を湛えた目。出口もなく、逃げ場もなく、暗闇から四方を取り囲む絵画は、ただひたすらに高く高くそそり立ち、そして、今度こそ、テープレコーダーなどとは無関係に、完全に部屋を支配する静寂の中で、めぐるようなホストの声が聞こえてくる。
【
こ
の
不
思
議
な 部
気
配 屋
を が
、 伸
諸 び
君 て
は い
感 る そ
じ の れ
た か と
だ 、 も
ろ
う 諸
か 。
君
の
目
の
よ 錯
覚
な
う の
か
く 。
、
見
る
が
良
い
… .. .
… .. ..
この部屋に
は、
窓 も
扉も
まったく
ない。
フフフフフ… … .. .. .
慌てても、
もう遅い。
果
た
し
て
諸
君 こ
は、 の
部
屋
か
ら
出
る
と
こ
が
で る
き
な
か
?
・
・
・
私
な
ら
、
こ
や
う
っ
て
出
る
が
な
あ
・
・
・
】
「ふぁ……」
この、文字通り縦に長いナレーションを聞いているうちに、デイビスは口を半開きにして、ひくつく眉間に皺を寄せた。部屋の伸びあがりに乗じて、長年積もりに積もったハウスダストがパラパラと落ちてきたせいで、急に鼻がムズムズし始めたのである。
「ハアァーーーーーックシュン!!!!」
特大のくしゃみが口からぶちまけられ、彼らは、その部屋における最大のクライマックス・シーンを目撃する機会を逸した。鼻水混じりに撒き散らされた汚い爆音に、すっかり二人とも気を取られたせいで、窓のない部屋に突然鳴り響く雷鳴にも、頭上にぶらぶらと揺れている首吊り死体にも、まるで気づくことはなかったのだ。
「God bless you.」
「……どーも」
祝福の言葉を投げつつ、ポケット・ティッシュを渡すスコットに、ずび、と鼻を啜りながら、デイビスがおもむろにティッシュを引きだす。秋口はどうも鼻腔の調子がよろしくない。
スコットは、もう一枚引き出したティッシュを細長くちぎると、正多角形に囲まれた壁の隅へ、順繰りにそれを翳し始めた。両手に蠟燭を握り締めたガーゴイルの燭台たちは、何も語らずに、藤色の焔を瞬かせるばかりである。
「なー、スコット、さっきから何してるんだよ?」
「隙間風をチェックしてる。……なんだ、ここに抜け道があるじゃないか」
古典的な方法だが、あっさり、出口のヒントは見つかったらしい。漏れてくる空気に煽られたティッシュは、スコットの指につままれて、リボンのようにちらちらと棚引いていた。
「でも、ドアノブも、手かけもないよ。どうやって開けたらいいんだろう」
「貸せ。強行突破が一番早い」
「?」
「怪我をするからどいてろ」
スコットは、ちょいちょいと指で招いて、デイビスを背後に下がらせると。
ばごおおおおおおおおんッッッッッッ
と轟音を立てて壁を薙ぎ倒す。たった一蹴りだったが、結果はご覧の通り。蹴破られた木材がへし折れてゆく耳障りな音とともに、靴底の跡を付けた壁面がスローモーションで倒れ、ずずん、と一面に無数の埃を舞いあげるのを見て、スコットは冷静に振り向きつつ言った。
「開いたぞ」
「解決方法が力技すぎる」
んでもって雑。何もかもが。身も蓋もない大穴がぽっかりと空いた先からは、微かに湿った冷たい風が流れ、空気は不思議な動きを見せている。二人揃って、ひょっこりと壁向こうを覗いてみると、ますます薄暗い廊下が、闇の彼方へと通じてゆくばかりである。しかし、やはり蜘蛛の巣を絡ませたシャンデリアだけは、茫漠と火を揺らめかせていて、壁に彫りつけられた悪魔の彫刻に、光と影とを刻みつけていた。
何の躊躇もなく歩きだすスコットを、そわそわと落ち着かない様子で、デイビスも追う。回廊は次第に暗くなり、闇の中に琥珀色の光芒を投げかけるシャンデリアを受けて、彼らの影法師がめぐるように壁を過ぎてゆく。それは何か背筋をゾッと撫でさするものであり、亀が首を引っ込めるように萎縮しながらも、デイビスは蚊の鳴く声でスコットに訴える。
「なー、スコットー、そんな早足で歩くなよー」
「ミッキーとエディが心配だ。先を急がねば」
「す、少しは、俺の心配だってしてくれていいだろ……」
「ポート・ディスカバリーに住む人間ならば、非科学的な事象など恐るるに足らん。
言っとくが、俺にベタベタするなよ? 遊園地のバカップルじゃないんだ、貴様が私に抱きついてきた時点で、即座に地面に張っ倒す」
「なんだかなぁ」
前方は物騒この上ない男、後方は不気味な雰囲気に挟まれ、ちくちくとした居心地悪さを感じざるをえない。
不安に駆られながらも、細長い廊下を見回すデイビス。色褪せた深紅の壁紙は、相変わらず、おびただしい目のような模様で、気味が悪い。しかしそれだけではなく、絶えずどこかから、何十という視線が纏わりついてきて、自分たちを見つめている、という感覚を拭えないのだった。
生唾を呑んで、豪奢な額縁に閉じ込められたひとつひとつの肖像画に視線を走らせる。周囲の絵画は、その恐々とした視線に応えるかのようだ。カウチに横たわり、官能的な曲線を描く謎めいた女性——その双眸は、まるで猫のように光っている——黒々としたマントを羽織り、宵闇にコウモリを携えた、鋭い牙の貴公子——蛇のような髪を逆立て、静かにこちらを睨みつける貴婦人——そして、どこからか雷鳴が聞こえた瞬間、窓もないはずのこの廊下が、一瞬、閃光を瞬かせたように思う。白と黒がひっくり返るコンマ数秒のうちに、その絵画の中の人物たちは真の姿を露わにし、その血に飢えた狼の眼光を、石化させるメデューサの目玉を、爛々とした化け猫の瞳を、稲妻とともに明滅させるのだった。
それは、瞼の裏に残るほんの残像の中にしか、気づくヒントはないのかもしれない——そう、よほど深く心を奪われて、肖像画たちを覗き込もうとしなかったのなら。それゆえデイビスが気になったのは、その一瞬の変貌ではなく、絵画に描かれた、まるで生きているかのようについてくる彼らの生々しい眼差しだった。この薄気味悪さは何なのだろう。ふと浮かびかかった予感を打ち消すように、首をぶんぶんと振っても、背筋の凍るような感覚は拭えず、単なる錯覚だ、と笑い飛ばすことなど、とてもできそうにはなかった。
「な、なんか、やたら絵画と目が合う気がするんだけど。気のせいかな?」
「ふうん。一目惚れされたんじゃないか?」
「あんた、またそうやってテキトーなことを——」
「オカルト的な話題は嫌いでね。……デイビス、火」
命じられて、咥え煙草を箱から引き抜きつつ、軽い音とともに橙黄色の炎を点じ終わったライターを、ぴし、と弾くようにスコットへ投げつけながら、しっかしこいつも、肝の据わった奴だよな、とデイビスは思う。たまに抜けた発言を繰り返すのと、潔癖症だということ以外、怖いものなど何もないのでは。……姿勢良く背筋を伸ばし、たくましい肩を微かに屈めるようにして、隙間風から守りつつ火を移したスコットは、僅かに眉を顰めながら、空中に向かって長い息を吐いた。
「禁煙は?」
「お前の口が言えるのか、デイビス?」
二本の煙草が入り混じった薄白い紫煙の中で、肩をすくめてみせるデイビス。しかしここ最近は、自分一人で煙草を燻らせる機会が多くなっていたものだが、ディズニーランドに来て以来、控え気味だったスコットも喫煙してくれるのは、何となく嬉しいものがある。二筋の白い煙が棚引き、こつり、こつりと靴音を立てながら、二人の会話だけが、微かに反響を伴いつつも浮かんでゆく。
「なあ。ここに飾られているのって、もしかして、この館の元住人だったりするのかな?」
「なんで?」
「いや、館の侵入者を威圧する役割でもあるのかなー、と思ってさ……」
「そんなに怖いのか? 肖像画の多くがこちらを見るように描かれるのは、当たり前のことじゃないか」
「だって、薄気味悪ィじゃん。嫌なんだけど」
「なるほど。安心しろ、ならばその不安を吹っ飛ばしてやる」
「?」
言いながら、スコットの親指が、きりきりとライターの炎調整螺子を回してゆくと、
ボワああああぁぁぁァァッッッ———
突然立ちのぼる凄まじい火柱に、髪の毛の逆立つデイビス。スコットはめらめらと業火の立ちのぼらせる光に、そのクレイジー極まる顔面を照らしだしながら、
「今後、私たちと目が合った絵画は、灰と化すまで焼き尽くす」
「放火魔の発言じゃねーかッッ!!!!」
ドン引きするデイビスと同様、肖像画の方も、命(?)の危険を悟ったのだろう。やべー奴がいる、とでも言わんばかりに、すべての絵画が火柱から無言で目を背けてゆく。
「ふっ、炎があれば、人類はいかなるものも恐るるに足らず。よく言うだろ、いつの世も、火炎放射器は最高の護衛道具だと」
「ンな受け売り、聞いたことねえぞ」
妙に勝ち誇ったドヤ顔をするスコットと、呆れ返るデイビス。すると、そんな彼らを見咎めるように、薄暗い虚空から、忠告の言葉が轟いてきたのだった。
【もう一つ、絶対に火は使わないでほしい。
亡霊たちは強い光が好きではないのです——】
突然の響き渡る声に、デイビスは尻を針でつつかれたように飛びあがったが、どれほど見回しても、周囲にまるで他の気配はない。天井も、壁も、床も、何も変わったところはないのに、どこからか、くすくすと小声で笑われている気がした。恐る恐る、颯爽と前を行くスコットの背中をつついて、遠慮気味に提言してみる。
「お、おい。火を使うなってよ」
「あ? なんだ貴様、俺に禁煙しろと?」
「え、えーっと。そんな健康的な理由じゃなかったみたいだけど」
「やかましいな。最近の喫煙者は肩身が狭いんだ、小説の中でくらい好きにさせろ」
スコットが廊下に漂わせる紫煙を見つめながら、いつもならケチケチとシケモクになるまで吸い尽くす彼も、この時ばかりはこっそり、携帯灰皿で火を揉み消し、謎の忠告に従った。
(知らねえからな。スコット。館の住人たちの怒りを買っても———)
その傲岸不遜な態度は、果たして、命知らずと言って良いものかどうか。割合に繊細な精神を宿したデイビスは、TPOを華麗に無視する相棒の図太さに、神経を疑わざるを得ない。
まもなく、廊下がほの明るくなった。頭上高くへと優雅なアーチを描く、ガラスを張り巡らせた温室——外から見えていたあの水晶宮の如きサンルームに差し掛かったのだろう。矮小な彼らを呑み込んで、天井を覆い尽くすほどに広がる巨大な玻璃から射してくる月の光が、碧みを通り越して菖蒲色の憂鬱を帯び、現世とあの世とを一枚の透明さで隔てつつ、人気のない廊下の大理石へと染み込んでゆくのが、目の前に繰り広がる。かつては豪奢な植物園として、多種多様の緑が生い茂っていたのであろうが、今や遠い日々は思い返すだに虚しく、割れた花瓶や花びらが散らばる深海のような静寂の底に、十字架状の光と翳が落ちてゆく。時が止まったかのように思えるその空間の花々は、いずれも元の見分けがつかぬほどに朽ち果て、永久に過去の栄光を失いつつあった。
細い滝の如く月光の落ちてくる天蓋の破れ目から迷い込んだらしい、濡れたように艶めく翼を羽ばたかせる鴉は、あるいは刻々と腐り落ちてゆく屍肉でも啄みにきたのだろうか——周囲の花に埋もれて、異様に装飾の凝った中央へ横たわる漆黒の箱は、通夜を迎えた棺桶である。そして、竜胆色にぼんやりと灯る燭台を押しあげ、棺の蓋を破って、一本の手が、大鴉の頻りに鳴き喚く下から、悲痛な声で訴えかける。
「Heeeeeeelp! Heeeeee——」
その上から、どすん、と乱暴に棺桶の上に腰掛けて蓋を閉ざすと、スコットは長い一服を吸って、霞のように立ち込める紫煙とともに溜め息をついた。
「ふう。まずはミッキーたちと合流しないことには、話にならないな」
「無敵かよ」
凄い、こいつと一緒にいると、全然怖くない。蓋に挟まれて急速に元気を失ってゆく棺の手を見つつ、ボーゼンと立ちすくむデイビスを脇に置いて、スコットはつつー、と棺の上を人差し指でなぞると、その埃の付着具合を鼻先に近づけて念入りにチェックした。
「しかし、埃っぽいな。いったい何年掃除をしていないんだ、この屋敷の使用人は」
「やめろよ、そういうイヤミな姑みたいな指摘」
「汚い場所は我慢ならん。せっかく建築や調度品は歴史的価値が高いのに、全部水の泡だ」
「へーえ、ここって、不動産価値高いの?」
「分からないのか?」
スコットは人差し指と親指を擦り合わせ、粉をふいている絨毯の上へと埃を革靴で均しつつも、斜め上の天井を見あげながら言った。
「オランダ・ゴシック様式だ。垂直様式の煉瓦造り、採光の尖塔、切妻屋根、使用人たちの通るアーチ道、古めかしいが豪奢なシャンデリア。オランダ人の入植時代を模した、涙ぐましい懐古趣味だな」
「あんた、なんでそんなこと知っているんだよ」
「実家に似てるから」
「え……」
まるで今日の夕飯は鶏だと言わんばかりに平然と言うスコットに、デイビスは七面鳥のような声を出して絶叫した。
「えーーーーーっ!?!? あんたの実家、こんな大金持ちだったの!?」
「うるさいなあ。耳元で大声出すなよ」
キンキンとする鼓膜を耳で塞ぎつつ、スコットはすこぶる嫌な顔をして、
「大したことはない。発展途上国だったから、貧富の差が激しかったんだ。俺はたまたま、一握りの金持ちの家に生まれただけだ」
「ほへー、そんじゃ、子どもの頃から贅沢し放題だったわけ?」
「羨ましくも何ともないだろ。貧困に喘いでいる国民から巻きあげた金だ」
とスコットは長い息を吐きながら、吸い殻から輝きつつ墜落してゆく火花を、ぼんやりと見つめていたが、急に、その面を月翳へとあげて、
「ここの主人も、ずいぶん悪どいことをやっていたんじゃないのか? まともな人間なら、わざわざ装飾用に棺なんぞを置いたりしないだろう」
「いや、だから装飾じゃなくて、本物なんじゃねえの? 手ェ見えてるぞ、その棺桶の蓋の下から」
「どれ?」
「どれ? じゃねえだろ。その萎びた黒いやつだよ」
「ああ、これか」
ようやく、自分の腿の近くにある手を見つけても、冷静に視線を送り続けるスコット。いったい、何をするのだろうか、と見つめていると、そのままバッチイものでも触る手つきで屍の指をつまみあげるなり、ずるるるるんっ、とわかめの如く棺桶から引き抜いてみせた。
「スコット、頼むからやめてくれーッッ!! アンタ、さっきからやりたい放題しすぎだろーがッッ!!」
「何だよ、お前が言い出したことだろ? 本物かどうかって」
「素手で触ってくれって言ったわけじゃねーよ!」
「そうギャーギャー喚くなよ、たかだかミイラだろ。まったく、みっともない」
ぺいっ、と引き抜いた手首を地面に捨てると、その青紫色に干からびた屍の手は、突然、生命を得たようにゴソゴソと動き出して、指を蠢かせながら暗闇の方角へと這いずっていった。
「あれ。どこかへ行ったな」
「俺はもう色んな意味で、あんたの方が恐ろしいよ、スコット」
小刻みに震えあがるデイビス。肝っ玉が大きいどころの話ではなく、もうなんか、色々とおかしいとしか思えない。
【彼らは死ぬほど諸君に会いたがっている。
この亡霊はもう待ちきれないようだ——】
「何?」
スコットは眉根を寄せて、ふっと煙草から口を離すと、吸い殻の穂先を携帯灰皿ですり潰した。
「こ、今度こそ空耳だとか言うなよな〜、スコットぉ……」
「いや、今のははっきり聞こえた。なんだ? さっきから、誰の声なんだ」
スコットは片腕をあげ、デイビスを背後に庇いながら、素早く、天井付近の死角となっている箇所に目を走らせた。しかし——何も見えず、誰もいない。緊迫に包まれたサンルームの彼方、夜の闇が覆い尽くしている遠くの枯れ枝に、一瞬、ぎらりと反射するものを認めると、ただちに彼の目が見開かれ、
「伏せろッ!!」
「へ?」
「安易に月明かりに身を晒すな!」
後頭部を押さえつけられるがまま、言われた通り、スコットとともにびたァんと地べたに貼りつき、息を殺してみる——が、いくら待っても、木霊が広がる沈黙の底で、何が起きるはずもない。せいぜい、数秒してから、ホー、と梟が鳴いて、その黄金の目を煌めかせつつ、窓の外をぱたぱた飛び去ってゆくだけ。……頭上を吹き抜けてゆく月光の静けさと、デイビスからの気まずい眼差しも意に介さず、スコットは大真面目にゆっくり顔をあげながら、ワナワナと彼に囁きかける。
「危なかった。もう少しで俺たちは撃たれるところだった。ここはなんて危険な場所なんだ」
「ぜってー嘘。ぜってー今のは単なる無駄骨だったろ」
「彼奴ら、赤外線暗視型監視カメラを仕掛けて、こちらをうかがっているに違いない。デイビス、赤いLEDライトを探せ」
「軍隊仕込みの現場調査はやめろよー」
「おい! これ以上馬鹿馬鹿しい脅迫を続けるつもりなら、この棺桶をひっくり返してガラスを叩き割るぞ! それでもいいのか!」
しん、と静まり返る廊下、聞こえるのは、どこかから屋内へと迷い込んできたらしい、はたはたと躍るコウモリの羽音ばかり。若干気味悪そうに周囲を見回すデイビスの背後で、一匹の闇の生き物が鋭い牙をしのばせながら、次第に首元に近づいてくる、まさにその一刹那。スコットは目にも留まらぬ超速でその翼を鷲掴みにし、距離一センチで目の前を掠めていったデイビスを、ひいいいいいい、と縮みあがらせた。そして心臓をどくどくと暴れさせている自身の相棒には構わず、手のひらに掴んだそれを一瞥すると、
「ふん、単なるコウモリか。ドローンなんぞの類いではないようだな」
と静かに、サンルームのガラスの破れ目から外へ逃がしてやる。ぱたた、と夜空へ羽ばたいてゆくのを見届けたスコットは、胸から取り出した携帯用のアルコールスプレーを手に吹きつけ、丁寧に擦り合わせて除菌した。
なんなんだよこいつは、超人なのかよ。不穏なフラグを一掃してくれる分、そばにいるとすっげー心臓に悪いんだが。
「ここの館の主人は、随分と悪趣味な愉快犯のようだ。俺から離れるなよ、デイビス」
「言われなくたって、あんたが全部不気味な気配を踏み倒すから助かってるよ」
さながら、立ちはだかる障害すべてを薙ぎ倒してゆくブルドーザーの如し。絶えず警戒しながらも、怪奇現象という可能性は微塵も頭にないらしいスコットに、デイビスは心臓に生えた毛の本数の、絶対的な差を感じる。
しかし、監視カメラが存在する、というスコットの読みは、あながち的外れというわけでもなかった。実際、彼らは常に眼差しを向けられていたのだった。カメラなどという近代的なものではなく——水晶球に込められた、黒魔術によって。
「ふふん……」
暗闇に閉ざされた部屋。そのぬめつく影に紛れ、ぼう、と霧を渦巻かせて輝く水晶玉に映し出される二人を、妖艶な紫の瞳は見つめ続ける。その肉体のうちに秘められた魂を追って。
幽霊屋敷探索はどんどん進む。たかだか廊下に過ぎぬ長い回廊にも、飽きぬように様々な意匠が凝らされているらしく、次は簡素なサロンが設けられていた。蜘蛛の巣が重く垂れ下がる燭台が置かれたままとなっているが、相も変わらず、誰の手によってなのか、火が点じられており、床には、百合から剥がれ落ちた無残な花びらの如く、楽譜が数枚、拾いあげる手もなく散らばっている。そして、幾重もの埃が覆い被さり、その表面がほとんど真っ白になった丸椅子が収められているのは、優雅な四本の猫足で鍵盤を支えた、十八世紀後半のものかと思われるスクエア・ピアノ——背の低いがゆえに、茫洋と薄白く透ける楽譜の向こう側には、夜闇に包まれた蕭々たる空と、石造りのバルコニーを見晴るかすことができた。窓枠いっぱいに射し込んでくる青い月明かりは、ガラスに付着した僅かな塵埃を輝かせつつ、このピアノに整然と並ぶ薄茶けた象牙の白鍵や、その傍らの古いオケージョナルテーブルに飾られる、水一滴すらも残らないほど乾涸びた花瓶の花を、退廃的な瞑想の中に沈めていた。
譜面の前に立って、二人はおもむろに顔を見合わせる。
「弾ける?」
「まったく」
「俺も弾けない」
「さっきの声の主の物かな。まだ音が出るのかは分からないが」
首を傾げるスコット。そして、彼の太い、靴墨で美しく磨かれたような指が、褐色に薄汚れた鍵盤に触れようとしたちょうどその時、デイビスの耳の奥に、先ほど柳の下でダカールが呟いた、あの幼くも厳格な声が蘇ってきた。
(———パイプオルガンに触れてはいけない。あれは死者たちの眠りを妨害する)
気づけば、デイビスの指は、目の冴えるほど清潔なシャツに包まれた、スコットの手首を掴んでいた。そして、少しの間を置き、驚いたように彼の顔を覗き込むように見つめ返すスコットに向かって、
「や、やっぱりやめておこうぜ、楽器に触るのは。へ、へへへ……」
スコットは不可解に思ったようだが、特に逆らう様子もなく、黙って腕を下げてそれに応じた。そして一歩後ずさると、改めて、降りそそぐ月の光の中で、そのピアノをまじまじと見る。
「ま、確かに、触っても意味がないか。私たちのうちどちらも、まともに弾けないんじゃな」
その言葉を聞いて、改めて、互いを見つめ合うふたり。なんか、俺たち、こういう藝術的なことに向いてないんだよな。言うな、デイビス、パイロットは飛行機さえ動かせればそれでいいんだよ。すると不思議なことに、八十八鍵の揃った鍵盤の幾つかが、ゆっくりと奥底へ押し込まれていったかと思うと、次から次へと、和音を響かせて、まるで霊界の彼方から聞こえてくるかのように、音楽がひとりでに流れ始めたのだった。ペダルは上下し、ハンマーは波打つ弦を叩き、ピアノは複雑怪奇な旋律を歌い続ける。まるで見えない何者かが、この訪問者たちの魂を魅惑するかの如く。デイビスもスコットもすっかり感激して、まるで高級ホテルのロビーにいるような気分になった。
「へええ、上手いじゃないか。よく訓練されたピアニストのようだ」
「すっげーなあ、電気も通ってなさそうなのに全自動とは。どこまでゲストの要望に応えてくれるもんかなあ」
デイビスは鍵盤に歩み寄ると、おもむろにかぱりと口を開け、節をつけて歌い始める。
「♪ミッキマ〜ス、ミッキマ〜ス、ミッキミッキマ〜ス」
「音痴な奴」
「うるせーなあ」
するとピアノは空気を察したのか、驚くことに、ちゃんと伴奏してくれたのである——ただし、多分に短調にアレンジされてはいたが。しばらく、調子外れなデイビスの声に合わせて、ミッキーマウス・マーチの陰気な音色が奏でられ、引っ込みのつかなくなった歌声とともに、謎の音楽会が続く。
「飽きた」
「だろうな。次へ行こう」
肩をすくめ合い、終わらぬ廊下をさっさと歩いてゆく二人。そしてその後を、ピアノの椅子に腰掛けていた影がするりと動き、束の間の足跡を埃の上に落としながらついていった。
「あっ、スコット。図書室だぜー」
「お前、こういうところ好きなんだっけ? 意外だよな」
「本の匂いって、落ち着くんだよなー。読書も好きだし」
若干ふわふわと浮き足立ちながら、デイビスは早速、本棚を覗き込み始めた。薄暗いが、実に品の良い書斎といえた。壁の一面を書架として、床にまで書物が積まれており、その手前には読書用の肘掛け椅子とサイドテーブルが二つずつ用意され、おあつらえ向きに、燭台まで置いてあった。その蠟燭の朧ろな光芒に照らされて、生き物のようにうごめく二人の濃密な影は、大きく本棚の上を飛びすさってゆき、壁龕に埋め込まれたバロック時代の滑石の胸像は、静かに彼らの動きを目で追った。
「初版ばかりか。大したコレクションだな」
「たくさんあるんだな。でも、背表紙が古くなっていて、読めねえや」
背伸びして本棚を覗きながら、ふーっと息で塵を吹き飛ばし、咳き込むデイビス。長い年月は、背表紙に刻印されたインクを掻き消すどころか、装丁の破けた中から、頁を綴じている糸までもがほつれていて、少し触れようとしただけでも、指に埃混じりの粉が付着する。それに幾らかの本には、すでに埃の手形がついていた——説明のつかないその痕跡に、ハテ、誰か無作法者がここに忍び込み、紙面を手繰ったのかな、とデイビスは首を傾げる。スコットは、どさりと肘掛け椅子に重い身を投げ出すと、天井の暗闇に達するまで壁一面を埋め尽くす本の海を見て、
「こうもたくさんあると、何を読むべきなのかさっぱり分からないな。お勧めの本でも教えてくれるとありがたいんだが」
「本屋じゃねえんだ、そんなのあるわけねーだろ? 所詮は個人の書斎だよ」
肩をすくめて返すデイビスに、ま、それが当然か、とスコットも溜め息をつきかけたところ、床に積まれていた一際古い本の一冊が、ゆっくりと角で地をつくように歩いて、大きく飛び跳ねるなり、肘掛け椅子に腰掛けたスコットの膝にぱたりと収まった。
「ああ、どうもありがとう。……ん?」
今、なんか変なものを見たよーな気が。頭上に?を浮かべるスコットの隣で、デイビスは意気揚々と本棚から一冊抜き出して、
「見ろよスコット、これ、面白そー。『人間の身近なものに擬態するモンスターたちの生態について』」
「なんだ、こんなところにRPGゲームの攻略本があるのか?」
「いいや、結構大昔に書かれた本みたいだぜ。ふうん、人食い植物、生きる甲冑、顔の飛び出す絵画……」
そのまま、象牙のような指で古びたページをめくり始めたデイビスは、あっという間に本の世界に入り込んだのか、隣のソファに腰掛けながら読み耽る。熱心に目線を動かしているのを見る限り、なかなかに興味深い内容のようである。
仕方なしにスコットも、手元にある書物に手をかけた。少し軋むが、古い分、天鵞絨張りの背もたれは柔らかく、それがひとりでに前後する感覚は心地良い。微かな揺れに身を委ねながら、最初のページを開くと、そこには何も書かれていない紙が、ざらついた面を向けているばかりだった。その次のページも。さらにそのまた次のページも。落丁か? と不審がる彼の目の前で、果たして、不思議なことが起こりだした——彼の開いているセピア色に色褪せたページから、ゆっくりとインクが滲み出し、ひとりでに文字を綴り始めたのである。
「これは……」
まるで血痕の滲むように細い洋墨の線が染み込み、見えぬペン先は、やがて一連の文章群を浮かびあがらせてゆく。スコットは驚愕を隠せずに、その文字を穴の開くほど覗き込んだ。
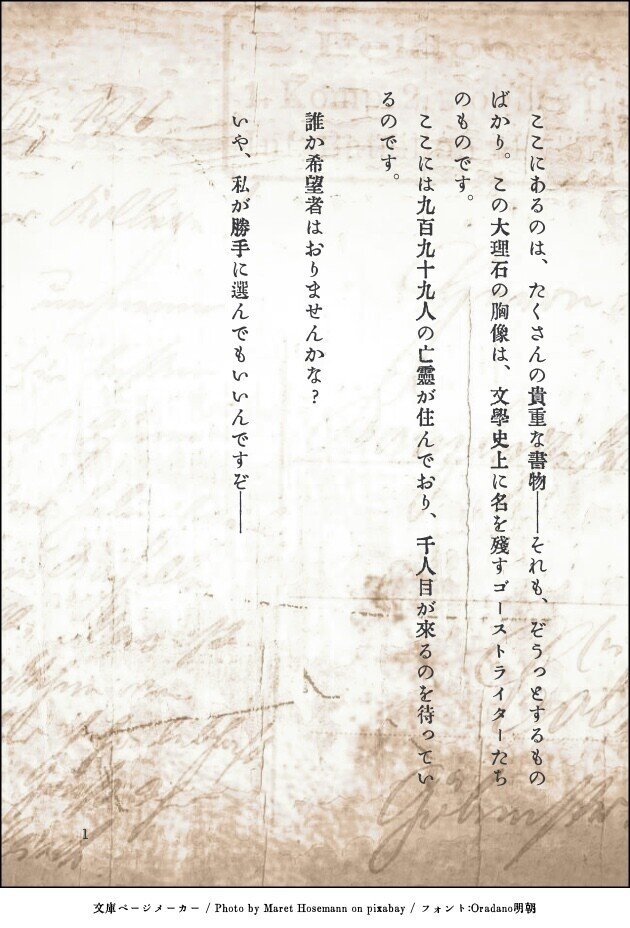
ぶ、文庫ページメーカー。クレジット表記が妙にリアルだな。ふと横を見ると、サイドテーブルに開かれたままの本のページが、ぺらり、とめくれてゆく。どこからか風が吹いてきたのだろうか、と顔をあげたが、書斎のどこにも窓はなく、ただ本の放つ重々しい威圧と、洋墨で塗り込められたように陰々たる暗闇が広がる以外、外へ通じるものは何もない。
よく考えてみれば、なぜこの屋敷は、こんなにも暗いのか。シャンデリアや燭台のすべてに火を灯したとしても、この程度の明かりにしかならないのであれば、もっと採光に気を使うはずであろうに——この溺れそうに続く暗闇の中で、かつて多くの人間が生きて生活をしていたとは、到底想像することなど不可能だろう。
「なあ、デイビス。この館はやはり、何かがおかし——」
とスコットは振り返り———
桑の実色の燭台の灯る傍らで、自身の尻を半分椅子に喰われかけているデイビスと、目が合った。
「えっ……」
思考がフリーズするスコット。あまりにアホすぎる目の前の絵面に、肝心の言葉が何も出てこない。
なんだ? これはいったいどういう状況だ? ケツが椅子にハマって、そのまま抜けなくなったのか? 大の大人が、何をどうやったら、そんな情けない事態に陥るんだ?
しかし、みしみしと肘掛けを軋ませながら、また一口獲物を呑み込んでゆくソファの咀嚼音で、ハッと我に返り、
「ちょっ——」
と声を出したのが、餌食となっているデイビスの覚醒にも繋がったらしい。それまで意識を完全に石化させていたのが、全力で金切り声を捻りだす。
「融合しかかってる! 融合しかかってる!!」
「なんなんだ、この怪物ソファは!?」
その瞬間、紛れもないデイビスの腰掛けているソファから聞こえてくる、けたたましいほど極悪な哄笑に、ゾクゾクゾクゥッ——と全身鳥肌を立たせながら、骨の髄まで嫌悪感を掻き起こされたスコットの脳内が、エマージェンシーモードに切り替わる。ブザーが鳴り、赤いランプがぐるぐると光を放ちながら回る、気分は緊急命令を受けた軍用基地の如くである。
「スコット、頼む! 何とかしてくれー!!」
「よし、緊急用の斧を探してくる! こうなったら尻もろとも、バラバラに破壊するしかない!」
「前言撤回する、あんたに頼んだのは全力でまずかった!!」
「冷静になって考えろ! 本体とケツと、どっちが大切かは言うまでもないだろう!?」
「その選択肢がおかしいだろーが、最初からケツも俺の本体の一部なんだよッッ!!」
ギャーギャーと文句を言うデイビスに、スコットは負けじと声を張って言い返そうとしたが、そのうちに、背後に奇妙に揺れ動いている梯子を目にして、はっと閃き、何かを思いついたようだった。
「待っていろ、デイビス! 今助けてやるからな!」
なぜか上から聞こえてくる声に、半泣きになっていたデイビスが目を挙げると、そこには毎日見慣れている同僚の、敢然と梯子のてっぺんに掴まっている姿。さながらスーパーマンの如く輝くスコットの精悍な顔、そしてその手の先には、本棚のうちで最も分厚い書物の一角が。
「な、なんだよ、スコット。あんた、まさか——」
事態を察して蒼白になってゆくデイビスとは裏腹に、天井近くまで達して彼の上に影を落とすスコットは、書架の奥へ颯爽と手を突っ込むと、真下の怪物ソファに向けて。
「とあーッッ!!!」
「本を飛び道具として扱うなーッッ!!!!」
断末魔か遺言かも分からぬ叫びが響くと同時に、どささささささ、と凄まじい数の本の雪崩が襲いかかり、デイビスはソファもろとも横倒しになって、書物の山に埋もれた。スコットは素早く床に飛び降りると、その山のてっぺんにわななきながら生えている、墓標のような一本の手を掴み、力を込めて引っ張りだす。
「デイビス。無事か?」
「俺は感謝の言葉と怒りの言葉を、同時にあんたに言いたい」
周囲の本が一面に滑り落ちてゆく中から、ゾンビの如くぬっと蘇り、恨みを込めた目で睨みつけてくるデイビス。どうやら尻は自由の身となったが、それ以上に深刻なダメージを全身に被ったようである。ずきずきと波のように襲ってくる打撲の痛みから、当分は解放されることはなさそうだった。
「これで貸しがひとつできたな。後でウイスキー奢れよ」
「どちらかというと、怨恨の方が強いぞ」
「———そうだ、ソファは!」
急いで振り返る二人。すると、ちょうど背もたれを真っ二つに引き裂く口を開けて、刺繍に縫いつけられたギョロつく目と、彼らの視線とが、ぱちりとかち合った。途端、むしゃしゃしゃしゃ、と気味の悪い声でその妖怪が笑うと、渦巻く静かな煙を吐くなり、ふたたびソファは、静寂の底で、不思議な顔の模様を背もたれへと浮かばせていた。
「「…………」」
沈黙する二人。スコットは、整った顎をさすると、感心したような口振りで、
「ツイているな。こんなところで新生物発見、か」
「どう見ても違うだろ!?」
「カメラはないか? ナショジオに写真を売り飛ばそう。高く売れる」
「(こいつ、まさか正真正銘のアホなんじゃなかろうか)」
デイビスは噛み跡のついた尻をさすりながら、忌々しげに歯を軋り合わせ、ブツブツ愚痴をこぼした。
「くっそー、まだヒリヒリするんだが。あの野郎、思いっきり噛みつきやがって」
「ソファだって、たまには噛みたくなる時もあるんだよ。犬がじゃれついてきたようなものだろう?」
「おい。あんたはそう言うけど、そのじゃれつきのせいで、俺のケツが半分喰われかけたんだぞ」
「 (笑)(笑)(笑) 」
「てめえふざけんなッ!!! さっきから絶妙に煽りやがって!!!」
せっかくゴーストライターたちが執筆した書物も、スコットの手によって多くが落ちてしまい、床は惨憺たる有様だった。こん、と降りそそいでくる最後の一冊が、虚しくデイビスの後頭部に当たり、不機嫌そうに唇を引き結ぶ彼のそばで、スコットは乱雑に散らばった本の一冊を拾いあげると、
「なんだか、懐かしいな」
とゆくりなく呟いた。
「何が?」
「いや、お前って、訓練生の時から、フライト試験の前は必ず資料室に入り浸っていたよな」
「あー? そりゃ試験前は、誰だってひーこら汗かいて勉強するもんだろうが」
「……いや」
膝をつき、床にばらけさせた本を拾い集めながら、スコットの黒々とした指がゆっくりと躍り、擦り切れた装丁をなぞっていった。
「珍しいなと思ったよ。大抵の訓練生は、操縦技術を少しでもましなものにしようとして、フライトシミュレーターに籠もりがちだろ。でもお前は、前提条件と同規模のストームを調査し、過去数十年の資料を総浚いしていた」
どこか色褪せたような口調で囁くスコットは、そのたくましい腕に五、六冊抱えて立ちあがると、背伸びをし、今度は分厚い書物を順に頭上の書棚へと収めてゆく。一九〇センチにまで達する彼の背丈は、高い棚にも、何とか届くようだった。
「……そ、そんなの、当たり前のことだろ」
「ふふ。ストームライダーのパイロットは華やかなイメージがあるが、実際はそういった地味な仕事がメインになるからな」
軽く肩を揺らしたスコットは、唇を緩めたまま、顔だけで振り返り、
「だが結局、そういう奴がパイロットに選ばれる。だろ?」
と笑った。
デイビスは、物珍しげにスコットを見つめ返した。彼が何を言いたいのか、はっきりとは分からなかったし、いつになく白い歯をこぼした、子どものように無防備な笑い方も、いったい何を意味しているのかは理解できなかった。その一方で、どこか面映いくらいの言葉に、自然と微笑がのぼってきて、言い訳がましい台詞が滑り出る。
「別に、将来や試験を考えてのことじゃない。フライトシミュレーターは元々、そんなに好きじゃないんだ。それよりもきっちり知識を吸収して、本物のフライトを、完璧なものにしたい」
「お前のスタイルは、風を読むからな。確かにシミュレーターじゃ、限界がありそうだ」
「ああ、それに資料室に行くと、勉強しなきゃいけないことなんて、山のようにあるって分かったよ。操縦に、飛行機の設計に、ソフトウェアだろ。気象、海洋、流体力学、重力理論……学問ってホント、奥が深いよな。知りたいことが、まだまだたくさんあるんだ」
デイビスは微かに目を細めると、その指の一本一本に、壮大な意味と天空まで広がる世界を携えて、ひいふうみ、と数え始めた。少年のような顔をしていた。まるで彼の周囲を、切ないほどの自由の風が吹き抜けてゆくかのように。
「地上にいる時、空は青い天井に見える。スロットルを叩き込んで、操縦桿を握り締めて、真っ直ぐに雲を突き抜けて、……するとようやく、超えるべきものを超えたような気になる。世界の何もかもが消え去って、俺が正しかったんだって気分になる。
もっと遠くに行きたい。そのためなら、どんなに難しい知識だってほしい。不謹慎、かもしれないけれど。嵐のさなかでも、空に飛び立つと、安心するんだ———」
ぼんやりと虚空を見ながら、何の考えもなしに舌を回しているうちに、自らが、分不相応の真面目さに偏りすぎている、ということに気づいたデイビスは、
「ま、ミッションの制約上、分かんねえことってのはいつまでも残るんだけどな。もっと専門的に学ぶ時間が取れたら、色々変わってくるんだろうけど」
と、頬を掻きながら、はにかむようにつけ足した。
そうか、と答えたっきり、スコットはしばらく梯子に寄りかかり、高い鼻の輪郭を薄闇に浮かばせたまま、本の表紙に手を滑らせていた。が、やがて、
「実るよ。お前の努力は、必ず実る。お前が志したのなら、どんなことでも」
と、独りごとのように囁いた。
それを聞いて、デイビスの胸の奥底が、静かな水の如く清められたように思う。人望の厚いスコットと絶えず比較され、問題児、問題児と騒がれてばかりだった頃、それがCWC内で半ば恒例化したジョークとなっていたようだが、スコットだけは別だった。口喧嘩や皮肉は多々あれど、不必要なところでは、けして彼を揶揄しない。それに、言葉に出してフライトの才能を認めてくれたのは、スコットが初めてであり、そしてスコットの他には誰もいなかったのである。
———愚鈍な訓練生どもと、私と、どちらの方が信憑性があると思うんだね? 君も一流のパイロットになりたいのなら、第三者からの妄言になんぞ心を乱すな。
互いに顔は見知っていながらも、初めてまともに会話したあの日、万年筆をスーツの胸ポケットに仕舞いながら、取るに足らぬことのようにそう言ったスコットの横顔を、昨日の出来事のように覚えている。そしてその時、これが彼の下に配属された初日であるにも関わらず、予感がした。この人物の前では、道化のように振る舞わなくても良い。周囲の重荷から解放され、心から素直になれるのだと。
三枚目の役割が性に合わぬわけでもなく、ただ単に、求められていたことに応えようとしただけ。それが彼らなりのコミュニケーションで、多少の見下しはあれど、むしろ親愛の証なのだと思い込もうとしていた。だが、スコットは違った。はたから見れば、誰といようが、自分は大層なお調子者に見えたことだろうが、他の人間に対しては演技やサービスである一方で、スコットに対しては——単に、好かれたかったのだ。
しかし、シミジミと語り合っているが、こんな不気味な状況下で、なぜのんびり回想なんか始めたのだろう。俺たち、何か根本的なところがズレてるんじゃねえのか? とデイビスが首を傾げたところで、スコットは塵まみれになった両手をはたくと、行こうか、と穏やかに誘う。自ら話題を振ったにも関わらず、彼自身は何も語らないのだった。
そしてその時、ふと、スコットはどうしてパイロットに憧れたんだろうな、という思いが湧きあがってきた。誰もが脱帽するほど正確無比なフライト技術を持っているはずなのに、普段の業務では、その人望のせいか、その肩にはマネジメントの比重がのしかかり過ぎているように思う。陰でベースに、もっとスコットをフライトに集中させてやれよ、と進言した記憶もあったのだが、苦笑いが返ってくるだけに留まってしまった。結局、彼の代わりにメンバーを束ねられる者は誰もいなくて、デイビスもリーダーとしての経験が浅いからこそ、自らその役を買って出てくれているのかもしれない。
でも、俺はもっと、スコットのフライトを見たいんだけどな、とデイビスは目を細める。洗練された彼の操縦技術を盗んで学びたいのも山々だが、何より、いつもは淡々とした表情を崩さないスコットも、ストームライダーを前にした時ばかりは、微かに昂揚した笑みを浮かべているのが好きだった。もう季節は秋に入ってしまって、嵐は落ち着き、彼がストームライダーに乗り込む姿は、長らく目にしていない。それを喜ぶべきなのか、残念がっても良いのか、彼には判別する術がなかった。
「ンンンンン、何だろー、ここ……」
「占い部屋? しかし——誰もいないようだ」
新たに彼らの迷い込んだ部屋は、完全に漆黒に閉ざされた中で、ぽつんとテーブルがひとつ、タロットカードが散らばった卓に、少し前まで誰かが腰掛けていたように思える椅子、ただそれだけ。血生臭さや、曰くつきの気配はゼロ。ぼんやりと天井を覆う黒いヴェールも、部屋の中央のブックスタンドに立てかけられた謎の本も、確かに神秘的ではあるが、先ほどまでの湿った感情を誘いだす、おどろおどろしい不穏さは皆無といえた。
しかしなぜだろうか、これまでに通ってきた空間の中で、間違いなく、最も不気味なのがここであった。近いうちに、何か良くない惨劇が起こるような——自分たちは、今はまだ、それを目の当たりにしていないだけのような。薄ら寒い風が通り抜けていっても、容易に幽霊や死者のイメージと結びつきはしない。それが恐ろしいのだ。全きの無人——何のためにあるかもよく分からない、とにかく不可解一色に塗り潰された部屋を目にして、デイビスとスコットは何かしら、背筋がうすら寒くなるのを感じた。
「子どもの泣き声が聞こえる……」
「えー? 何も聞こえねえけどな」
ぽつりと漏らすスコットと、耳の穴をかっぽじるデイビス。確かに、たまさかに微かに触れ合う鈴のような音がする以外、暗闇は沈黙に支配されている。
「もしかしたら、ミッキーが泣いてるんじゃねえの? 割と近くにいるのかもな」
「ああ。だが、もっと幼かったような……」
「おーい、ミッキー! いたら返事しろよー」
メガホン代わりに、口元に手をあてがって叫ぶデイビス。すると、遠くからか細い声がこだましてきた。
「デイビス! スコット! よかった、僕はここだよ——!」
しかし、その途中で不自然に言葉が切れたかと思うと、一瞬の間を挟んで、ずだだだだん、という謎の音が聞こえてくる。そして濛々と広がってゆく、何とも言えない沈黙と気まずさ。
「……あいつ、コケたな」
「まったく、世話のかかる子だな。本当にあれで王様なのか」
見えなくても目に浮かぶ顛末に、思わず腕を組んで天井を仰ぎ見るデイビス。隣のスコットも、あちゃー、と言わんばかりに額に手を当てている。
占い部屋を抜けると、虚空は一気に解き放たれて、宮殿でもかくやあらずというほどの、二階まで吹き抜けるグランドホールが広がっていた。天井からは、煌びやかな水晶を垂らしたシャンデリアがぶら下がり、恐らくは、饗宴の晩餐に舌鼓を打つ貴人や、音楽家の旋律に身をゆだねる賓客たちの優雅なワルツを、そのほのかな灯火の下に照らしだしていたのであろう。今は見る影もないほどに荒れ果て、この打ち捨てられた廃墟を訪れる者はいないけれども、かつてこれらの床の穴がひとつ残らず塞がり、暖炉のとろ火が輝くばかりに燃え盛っていた時代には、飾り立てたドレスを身に纏い階段を降りてゆく者、馬車から手を差し伸べ、居丈高に扉を潜り抜ける者、束の間の舞踏のロマンスに身を投じる者、黄金のゴブレットの底に毒薬を隠す者、仮面や、蠟燭や、西洋梨や、翻る扇、粉っぽい泣きぼくろ、その他数々の豪奢にしてあまりに果敢ない浮世の歓びに溺れるかの如く、踊り、踊り、踊り続けた色彩の渦たちの生き様が、長い年月を超えて、今なおまざまざと目に浮かぶようである。
しかしその過去の栄華も、積み重なる巨大な時の波が押しやり、このグランドホールに残された者は、今は水を打ったような静けさの底に、たったひとり。階下にぽつねんと倒れていた一匹のネズミは、ようやくふるふると起きあがると、階上にいる友へ目掛けて、艶やかな装飾をされた長い階段を、懸命に登っていった。
「デイビス! スコット!」
「おーい、ミッキー! こんなところにいたのかよ」
一目散に駆け寄ってくるが早いか、真っ先にデイビスの腹に顔を埋ずめるミッキー。この短時間に随分と苦労したようで、体のあちこちが埃にまみれている。
「ワアーン」
「お前なー。仲間を置いて、勝手にどっか行くなっつうの」
「よかった、無事だったか。こうも広大な屋敷だと、はぐれたら大変なことになるな」
「ほら、せっかく再会できたんだ。何も泣くことはねえだろうが」
デイビスに背をさすられているうちに、ミッキーはようやく落ち着いてきて、自身の尻尾に絡まっている蜘蛛の巣をつまみあげ、嫌そうに捨てながら、
「でもエディは、館のもっと奥深くへ行ってしまったんだ。僕、なんだか怖くなって、ここでデイビスたちが来るのを待っていたんだよ」
「それで問題ない。さっきのお前は、まるで何かに取り憑かれたようだったぞ」
とスコット。彼の骨張った手が温かい頭を撫でると、大きな二つの黒耳が、その指に押されてぴこぴこと揺れた。
時計の鐘が鳴った。それはかまびすしい音量ではないにも関わらず、広大な屋敷の隅々に響き渡るようだった。
「あれ? もうこんな時間なのか?」
不審に思ったデイビスとスコットは、揃った動きでシャツの袖をたくしあげ、自身のパイロット・ウォッチを見る。ミッキーが背伸びして覗き込むと、暗闇の中で蛍光塗料により発光する針は、午後の十一時を示していた。
「わあ、もうすっかり深夜じゃないか!」
「この館は、時の進み方がでたらめだな。足を踏み入れた瞬間から、もう窓の向こうは夜になっていたしな」
「おう、へーきへーき。クリスタル・スカルの神殿もそうだったけど、どうせ外に出たら何ともねえから」
「全然参考にならないよ、そんな前例」
するとその時、ぐうう、ぎゅるるるるる、とデイビスの胃袋が暴れ回り、全員が目くばせした。どんな時でも腹は減る。そしていつのまにやら、白濁した霞が立ち上ってくるのを振り向くと、壊れかかった手すりのむこうの眼下に見える長テーブルの上には、湯気を立てた御馳走が。あまりにおあつらえ向きすぎる用意に、デイビスらの表情は引き攣った。
「ええええええええええ……さっきまで、あんな料理なんかなかったよな?」
「いつのまに現れたんだ? それに、いくら熱いとはいえ、二階まで湯気がのぼってくるなんて……あ、ミッキー」
「おいしそうだね! どんなのがあるのか、見に行こう!」
スコットの腕の下をすり抜けて、トトト、と走ってゆくミッキーは、嬉しそうに階段を駆け下りながら、ワクワクとして、長テーブルへ身を乗り出した。目の前には、揺れ動く紫の焔を灯した燭台の下で、ぼろぼろに破れたテーブルクロスの上に、新品の如く美しい金銀白磁の大皿が、なみなみと葡萄酒を注がれたゴブレットとともに照り輝いている。ミッキーはすっかり目を輝かせて、その中でも一際大きな蝋燭の立ったケーキにふーっ、と息を吹きかけた。
「スコット、デイビス。見てよ、立派な苺のケーキだ! ひょっとして、僕らを歓迎してくれているんじゃないかな?」
「おっ、うまそー。へへっ、いーなー、この一番デカい苺、いただき!」
「あーっ、それは僕が狙っていたんだよ!」
「こら、喧嘩するな。しかしこれはまた、凄いご馳走だな」
ケーキに今にも鼻先をくっつけそうになるミッキーの襟首を、ひょい、とつまみあげながら、後ろからスコットが覗き込む。大したメニューだ——ナプキンやカトラリーの隙間に、所狭しと置かれているのは、汁気たっぷりの鴨のテリーヌ、とろけるようなフォアグラを載せたステーキ、見事な血を滴らせる七面鳥の大皿、焦げ目のついたパンプキン・パイに、充血のように紅い人参のジュレ、よく冷やした鱒のマリネ、大きな兎の丸焼き、新鮮なカブのサラダ、果物の盛り合わせ、輪切りのウナギのスープなどなど。しかし、いかんせん、ほとんど襤褸切れとしか見えぬクロスの上にそれらが置かれているので、できたての如く湯気を立てるそれらには、違和感しか覚えることができない。何か、手をつけることを迷わせる——料理はどれも、実になまなましく蠟燭の光を反射するからこそ、より一層、不潔とも言える周囲の蜘蛛の巣や荒廃した椅子とのコントラストが、無気味に思えてくるのである。
で、目下の問題は。
「……どうする? 食べるかい、これ?」
「食べ物を無駄にするのは感心しないが……しかしさすがに、怪しすぎるだろう」
「でもさ、これを逃したら、次いつ食えるかは分からねえぞ?」
「ふむ。ではひとつ、実験といくか」
スコットは窓辺へつかつか歩み寄ると、バァン、と力いっぱいガラスの扉を開け放ち、残る二人の肩を勢いよく震わせた。そのまま、無言で庭先に進み出るスコット。何をするのだろうと後ろから見守っていると、彼は庭の蔓延った枯れ木を見上げたまま、いきなり、ニュッと口を突き出した。そしてそのタラコ唇から漏れてくる、いつものバリトンとは似ても似つかない、ピ-チクパ-チク、ピ-チクパ-チクというヒヨコのように可愛らしい鳴き声に、若干フリーズするデイビスとミッキー。すると、その鳥真似の声に惹かれて、一羽の鴉がスコットの足元へと降り立った。すかさず、夕餉から少しずつ盛った取り皿を、サッと鴉の前に置くスコット。嘴を突っ込み、喜んで食べている——わけではなく、頻りに首を捻りながら口にしているようだが、目をしっかと開いてつぶさに眺めるスコットの眼差しは、その食事風景から、少しの異変も拾わない。やがて腹が膨れて満足したのか、そのまま、カア、と鳴いて、鴉は目の前に糞を垂らしながら飛び去っていった。そのふわふわと最後に舞う黒い羽毛を前にして、順繰りに隣と目を交わす一行。
「……なんともないな」
「鴉も災難だね、勝手に命懸けの毒見をさせられて」
「しかしこれで、遠慮なく食事を口にできる」
「俺たちってホント、いつも行き当たりばったりに冒険を進めてゆくよなー」
そこで彼らもまた、袖をまくると、数百年前の人々と同じく椅子に腰掛け、ナプキンを敷いて、いそいそと優雅な晩餐テーブルにつき、食事にあずかることにした。
—————の、だが。
「……く、喰ってる感じがしない」
「相当なヴィンテージ・ワインのはずだが、匂いも味もないな」
「このケーキ、全然甘くないよ」
噛めば噛むほどに砂のような味がする食事は、思った以上に楽しくなかった。見た目による期待が爆上がりだっただけに、ひたすらに無言で落ち込む一行。何より、周囲の雰囲気がよろしくない。不気味な隙間風の悲鳴が鳴り響き、透き通る襤褸切れのような紗幕が揺れる下で、蠟燭は芒洋と、この三人だけの奇怪な晩餐会の食卓を照らしだし、所狭しと並べられた皿の隙間を、時折り、美しくも毒々しい色を煌めかせた蜘蛛が、素早い動きで逃げてゆく。時々、鋭い稲妻が食卓を照らしだすと、皿に乗せられた食物が死んだように光る。広大なホールの片隅で、三人のカトラリーが小さくぶつかる音だけが、居心地悪そうにこだましていた。
「おーい、誰か、何か喋ってくれー! この酷い食事を乗り切るには、会話で誤魔化すしかねえよー!」
とうとう、黙々と食べるのにすら飽きたデイビスが、椅子に身を投げ出し、行儀悪くのけぞりながら悲鳴をあげる。スコットは見事なテーブルマナーを遵守し、美しい所作でキコキコと肉を切り分けつつ、
「そういう言い出しっぺのお前がまず喋れ、デイビス」
「おお。そんじゃー、スコットからのリクエストにお応えして」
「別にリクエストはしちゃいないけどな」
「ごほん。これは、エレクトリック・レールウェイの乗客から聞いた話なんだけどさ、昔々のこと、ある村一番の美人を取り合っていた野郎がいてさ。イカボードっつう、でっかい耳と鷲鼻の、ヒョロヒョロした男と、ブロムという名前の、力自慢のガキ大将だ。美しいカトリーナに夢中になった二人は、村のあちこちで火花を散らしていた。イカボードは、野暮な野郎の割には、意外とダンスが上手くてさ。村中の奴らが集まったハロウィンの夜なんかも、カトリーナと一緒に宴で踊って、大絶賛されたんだ。ブロムはそれが気に入らなかった。そして、宴に参加した村人たちを集めると、そのスリーピー・ホロウ村に伝わる、首なし騎士の話をしたんだよ。
そいつは、ハロウィンの怪物たちの中でも、とびきり恐ろしい化け物だ。どんな怪物も、どんなお化けも、そいつの話は口にしない。生前の悪業で断頭台に立って、哀れな騎士には首がない。だから命日には毎年、闇夜の中を馬で駆けて、かぼちゃを手に持ちながら、探しているんだ、まだ首の皮が繋がっている人間をな。もうかぼちゃ頭は嫌だ。誰かと頭を取り替えたい。出くわしたら最後、剣を振り回し、どこまでもどこまでも追いかけてくる。気をつけろ! 橋の向こう側まで走るんだ。俺が一年前に首なし騎士に出会った時、必死に橋まで突っ走ったら、奴は跡形もなく消えた。だから用心しろ、今夜は必ず出てくるぞ。蹄の音が聞こえたら、迷わず走れ。もう逃げるしか道はない——ってな。
迷信深いイカボード氏は、カチカチと歯の根を鳴らしながらも、そんな馬鹿げた伝説は噂にすぎないと言い聞かせ、やっとこさ、馬に乗って家路についた。ハロウィンの宴は終わり、もうすっかり、夜更けになっていた。
その日は、月の綺麗な夜だった。闇はどんどんと深くなり、星がひとつ、またひとつと消えていった。暑い雲が空に漂っていた。一面に蛙の声が聞こえ、コツコツと馬の蹄の音が響いた。深い森の中で、イカボードはキョロキョロとしながら、今にも卒倒しそうな恐怖を押し隠した。景気づけに吹いた口笛も、この森の中では、不気味に木霊するばかり。フクロウの鳴き声も、狼の遠吠えも、彼には恐ろしくて恐ろしくて堪らなかった。早いところ、こんな気味の悪い森を抜けて、橋に辿り着きたくて仕方がない。けれどもそのうちに、イカボードの跨っていた馬が、ちっとも前に進んでいやしないことに気づいた。夜も更けて、もうこんな時間だ、馬も恐怖に疲れて、うとうとと眠りこけちまっていたんだ。怒り狂ったイカボードは、しこたま、馬の尻を殴りつけ、馬は哀しげにいなないた。ところがなぜだろう、それでも蹄の音が、どこからかはっきりと聞こえてくるんだ。パカラッ、パカラッ、パカラッ、パカラッ——徐々にこちらへ近づいてくる——まるで、生きている人間を探し回っているかのように。肝を冷やしたイカボードは、必死に逃げ出そうとして、木の根に足を取られて、派手にすっころんだ。その間も、蹄の音は、もうすぐそこまで迫っている。殺される! ガタガタと震え、脂汗を絞り、恐怖に縮こまりながら目を見開くと、そこには、風に揺れるいくつものすすきが、倒れた木の幹を叩いて、馬の蹄そっくりの音を響かせているじゃないか。自分の馬鹿馬鹿しいほどの迷信深さに、思わずイカボードは、腹を抱えて、大笑いしちまったのさ。すると突然、自分の笑い声に混じって、もっとけたたましい、もっと地獄の底から鳴り響くような高笑いが聞こえてきたんだよ。振り向くと、黒い馬をいななかせているのは、かぼちゃ頭を片手に、マントをはためかせた首のない男。今度こそ、イカボードは死ぬほど毛を逆立たせて、仰天した馬に飛び乗ると、猛烈な勢いで駆け出した。馬は速い。だが首なし騎士はもっと速い。どこまでもどこまでも、剣を振り回して追いかけてくる。森は長く、何度も首なし騎士の剣が空を切った。そのたびに響き渡る、あの恐ろしい悪魔の高笑いは、イカボードの耳を支配して、心臓が破裂してしまいそうだった。それに、あの蹄の音だ。パカラッ、パカラッ、パカラッ、パカラッ——イカボードは涙を流して息を荒げ、気が狂いそうになりながらも橋を目指した。そしてとうとう、それが目の前に見えてきた。潺々と流れる水の上に、丸太が渡されていている。彼は歯を食いしばって、その橋をしゃにむに抜けた。馬はぜいぜいと息を切らして、ようやく、その場に立ち止まった。心の底から安堵が広がってきて、イカボードは思わず、神に感謝した。首なし騎士は立ち往生する。水の流れている向こう側へは、どうやっても渡れない。とその時、首なし騎士は、手に持っていたかぼちゃ頭を燃えあがらせた。そして、あの不気味な高笑いとともに、炎に包まれたかぼちゃが飛んでくる。振り返ったイカボードの視界は、見る間に、燃え盛る炎でいっぱいに。
翌朝、スリーピー・ホロウの村人たちが見つけたのは、橋のたもとで粉々に砕け散ったおばけカボチャと、イカボードの帽子。みんなが村中を捜したけど、足跡は途絶えて、痕跡ひとつさえ、どこにもない。
カトリーナはブロムと結婚し、幸せな一生を歩んだ。何もかもがめでたし、めでたし。それきり、イカボードの行方を知る者も、口に出す者も、だーれもいなくなっちまったのさ。
————だって、その話を口にすると、あいつがやってくるからな」
しん、と沈黙が広がるホール。長い物語を語り終えたデイビスは、一息つくと、やおらへらりと相好を崩し、
「あはは、なーんちゃって! ごめん、あんま面白くなかったかな——」
言い終わるか否かというそばから、かちゃちゃちゃちゃ、と金属のかち合う音。ふと隣を見れば、

ミッキーが平然とした表情のまま、まるで電動ドリルのように小刻みに震えているのだった。
「ミ、ミッキー。そんなに怖がらなくたっていいだろ……」
「どうしてデイビスは、わざわざこんな場所で、僕たちに怖い話をするんだい?」
「しのごの言わずに、二人ともちゃんと食べろ。エディを見つけるまでは、まだまだこの館には滞在しなきゃいけないんだからな」
ふう、とスコットは溜め息をつくと、軽くナプキンで口元を拭って、きっぱりと言った。
「大丈夫だ、ミッキー、こいつの言うことなぞ本気にするな。所詮は、人を怖がらせるための作り話に過ぎないよ」
「えーっ、盛り下がること言うなよ。無粋な奴」
「とにかく、恐怖心が心の中にある限り、どんなものでも幽霊に見えるだろ。そんな下らない妄想を恐れて、イカボードのように、何もない現実にさえ脅えるなどと、本末転倒だ」
「本当に? 本当に、首なし騎士は出てこないのかい?」
「ああ、私が保証する。まあ、なかなか面白い話ではあったがな。しかしどうしても作り話だと笑い飛ばすことができないのであれば、はっきりと理屈で否定し、心に平穏を取り戻すしかない」
スコットは、皿の上の最後の一切れを咀嚼すると、それを飲み込んでから、一気に言った。
「良いか、この世には幽霊も、お化けもいはしない。死んだ人間は、もうその人生を終えて、二度と蘇りはしないんだ。彼らがまだこの世を彷徨っていると信じるのは、死を経験した人々に対する冒瀆だ」
———あまりに判然と言い下した、その言葉に。
デイビスは、慄然たる衝撃を受ける。果たして、そうなのだろうか? 人は死した瞬間、何もかも露と消えてしまうのだろうか? この館に足を踏み入れる前、確かに彼は、死した友人の姿を見た。あれは夢だったのだろうか? ダカールは言った、強い想いが残れば、ふたたび生者と交流できるかもしれないと。デイビスの胸がざわめく。もしも魂が残るというなら——自分にも、もう一度会いたい人間が、たった一人だけいる。その願いを誰にも打ち明けたことはなかったけれども、たった半年前に経験した別れは、今も彼の心を占め続けているのだった。それが死者への冒瀆だというのなら、ではこの思いは、どうしたらいい? 幽霊とはまさに、死を受け入れられない人間たちの創り出した、切ない幻影から生まれたものではないのか?
(幽霊でも良いから、会いたい、と思うのは。
……俺が、間違っているんだろうか)
そしてデイビスは、今まで意識的に目を背けていた、広大なホールの反対側の、荘厳なパイプオルガンに眼差しを送る。かつて、ノーチラス号に備えつけられていたというのならば、このオルガンもまた、ダカールが残した遺品のうちのひとつに違いなかった。ここにくるまでの調度品や部屋は、微かに人の残り香を感じさせるような気配を帯びていたのに、一切を儀式的な崇高さへと高めるそのオルガンは、まるで、すべての死した人類に捧げられた墓標のようだ——今は前に置かれた椅子は空虚のまま、弾き手を知らずに薄闇に沈黙しているが、ひとたび鳴り始めれば、この館にはびこる狂おしいほどの虚しさを満たそうとして、永遠に挽歌を奏で続けるのではないか。食卓に座るデイビスとはかなりの距離を隔てているのに、その重々しい存在感は、まるで轟音の怪物が押し迫ってくるかのように感じられる。
(ダカールの忠告していたパイプオルガンって、あれのことだよな。……こっちから触らなければ、何も起こらねえだろうけど)
天に向かって聳え立つ、無数のパイプ。鈍い黄金に光るあれが、恐ろしい予感を駆り立てるのだ。まるで怨念に満ちた異界に通じているような——そこまで考えて、デイビスはふと、ダカールと同じように、エディもまた家族を奪われた人間なのだったと気づく。しかし、ダカールが西欧に対する復讐の炎を燃やしたのと比べて、エディの漂わせる気配は、もっと無気力で、寂しかった。彼はきっと、自分の弟が殺された理由を、自分の中に見いだしたのだ——生き残ってしまった者としての不条理なまでの罪悪感を背負い込みながら、今日までの日々を過ごしてきたのであろう。
「そういえば、エディと連絡を取るのに、トランシーバーが役立ちはしないのか? あれには魔法がかかっていて、どこにいたって通じるはずだと聞いたが」
「確かに、もう片方の無線機はエディが持っているんだけど……何度かけても、彼は全然応答してくれないんだよ」
「そうか……エディはああ見えてしっかり者だし、この中で一番の年長者だ。大丈夫だと思いたい……が」
ミッキーとスコットが交わしている会話も、どこか耳を素通りして、デイビスの頭には入ってきはしない。むぐ、と味のしないパンを喉に押し込みながら、エディの顔を脳裏に蘇らせる。背が低い割には小太りで、大きな鼻に丸い眉、と親近感を漂わせる男だったが、目だけは違う。脆い、というよりは、どこか諦念を感じさせる、あの静かな瞳の色。そして、亡き弟の服を身につけたデイビスを、月明かりの中で静謐に見守る眼差しや、白雪姫の継母に銃口を向けながら、小さく口をついて出た言葉が、記憶の底から順繰りに思い起こされてくる。
———いいじゃねえか、似合ってるぜ。あいつよりは、ちょいと色男すぎるがな。
———俺ぁ、いつでも、どこでも死んだって構わねえ。そのつもりで、ずっと一人で生きてきたんだ。
(大人だから大丈夫……とは、俺には思えなかったんだよな。エディは)
むしろ、その長く孤独な年月こそが、彼の強さと弱さ、両方の根源ではないだろうか。長年、孤独の河水に身ぬちを晒して、半ば精神が同化しつつあるからこそ、少しでも秤が傾けば、何の疑問もなく、冷たい水底へと身を沈めていってしまいそうに思えた。
「さて、そろそろ食事は良いか? 今夜はもうここまでにして、明日からふたたび、エディを捜索しよう。こうも暗い屋敷を歩き回って、またはぐれてしまう方が、よほど怖いからな」
「うん、そうだね。エディは今頃、大丈夫かなあ」
「無事を祈るしかないな。だが焦っては、却って事態を悪くしてしまう」
そう告げて椅子から立ちあがるスコットに、またもや遠くから、赤子の泣き声が聞こえてきたような気がする。ふっ、と彼が顔をあげると、やはり轟くような静寂が、薄暗さと同化している。しかし、その悲痛な泣き声は、彼の耳に憑いて離れない。まるで、自分を見つけてほしい、と彼だけに訴えかけるかのように。
(なんだろう、な。この、胸騒ぎは)
スコットは首を振って、嫌な考えを打ち消した。今はともかく、エディと合流することだけを考えねばならない。その最善策は、無闇な妄想に囚われず、落ち着いて、冷静に行動することだ。
しかし、彼の呼びかけに、いつもの明るく飄々とした声が返ってこないのを不審に思い、やおらスコットは振り返った。彼の後ろに立ったままのデイビスは、青い顔をして俯き、ぼうっとした眼差しを落としている。
「デイビス? どうしたんだ。体調でも悪いのか?」
「俺——ちょっと、エディを探しに行ってくる」
「デイビス?」
「なんだか、あいつを一人にしたくないんだ。心配なんだよ」
「デイビス、どこへ行く!? 馬鹿、戻れ!」
スコットの腕を振り切って駆け出すデイビス。みるみるミッキーたちの姿が遠ざかってゆき、一人になった彼の四方八方から、膨れあがるように、闇の気配が襲いかかる。
鐘の音が鳴り、廊下はねじ曲がってゆく。奇妙な轟音が鳴り響き、変質してゆく。いつのまにか、異空間へと迷い込み、鬼や魑魅魍魎が辺りを跋扈しているのかもしれない。それでも、探さないわけにはいかない。息を荒げながらその廃墟を駆け抜け、誰に記憶されることもない霞んだ月の光に照らされるうちに、無性に切なく、やり切れない思いが差してきた。生者から死者への思いなら、その感情を知っている。どこか罪悪感に近い——それまでの自身の所業を問い質すような苦痛。埋めるに埋め尽くせぬ、あの見知った愛おしさに対する、絶大な喪失感。しかしここには、根本的に、それらとは違う哀しみがある。膨大な空虚の中ですべてが磨り減り、目的は枯渇していて、神も自己もない。誰に訴えたら良いのかも、何を足掻いたら良いのかも判別のつけがたいままに、ただ溺れそうに深い哀しみが、月明かりに照らされる世界を突き抜けてゆくだけなのだ。
ここは死者から見た世界だった。彼らは生の世界から遅刻して荒廃した、惨めな廃墟の中に取り残されていた。生と死の循環から蝶番の外れた、この永遠に明けない夜の中で、爪を立てたり、呻き声をあげたり、泣き叫んだりしても、何も意味はないのだと。そして、切れ切れになった霊魂のいずれもが、こう叫ぶ。もっと生きたかった。人として生きたかった。こんなまがいものの生命を得て、煉獄に置かれるつもりではなかったと。それこそが、異形の者へと堕ちた魔物たちの、終わりなき悲劇なのである。どれほど他の存在に救いを求めようとも、何も満たされず、何も変わらず、灼けつく焦燥に駆り立てられながら、何もかもが単なる逃避にしかならない。だからこそ彼らは、際限もなく生者を引き込む。怖がらせようとする。それらすべてが、孤独な喘ぎに、束の間の夢でも良いから生きる意味を感じたいと望む、漂流者たちに最後に残された足掻きなのであった。
死者は言う、永遠の虚無とは、悲劇である。ひょっとしたら、これは何かの罰なのかもしれない。自身は世界から否定されている、お前は死んだのだと。誰も、これを救う手段はない。救われぬままに、今日も幽鬼として眠らずに彷徨い続ける。それが何年、何十年、何百年と続く。気の狂うことさえも許されない。
「どこ行っちまったんだよ、エディ——」
汗に濡れ、息を荒げながら、デイビスはその生きた者の名をこぼした。この月明かりの中では、恐怖よりも哀しみの方が、呑み込まれた瞬間に二度と立ちあがれなくなってしまいそうで、何倍も恐ろしく思えた。
けれども、恐ろしい死者の巣窟にしか見えない館も、ほんの一握りの世に残された者から見れば、微かな希望を見出せそうで。ずっと心に思い描いていた者の姿に、その樹の陰から、窓からそそぎ込む月明かりの下から手招きをされたのなら、その場から動かぬままでいられるかは分からない。エディもまた、そうして禁忌を犯すことになるとは分かりつつも、死者と二人だけで話したいことがあったのだろう。そう思うと、苦しいほど灼けつく何かが、喉の奥に込みあげた。
(俺は本当は、何かをエディに言うべきだったんじゃないか。エディはずっと前から——もう一人では、自分を救えないところまできていたんじゃないのか)
ずっと自身の臓腑を焼いてきた罪悪感が、ここにきてちりちりと胃の底を炙ってきた。しかし、何を言えばいい? 死者への哀しみなど、他人がみだりに触れるべきものでも、容易に言及できるものでもないのに、それでもなお、絶え間ない自責の念を拭えずにはいられない。
あんたが心配なんだ、エディ。
そんな風に自分を責めなくったって、いいんだよ———
デイビスはぐっと拳を握り締めると、梟が重々しい翼をはためかせる夜空の下で、月明かりを浴びながら、大声で呼び続けた。
「エディ、戻ってこいよ! 頼むから返事をしてくれ! エディッ!!」
「デイビス、戻ってこい! さっさと返事をしろ! デイビスッ!!」
何度目かの陰々と広がる木霊を、果てしない廊下が呑み込むのに嫌気がさして、ついに頭を抱えてしまうスコット。その足元で、ミッキーは困ったように眉をハの字にしながら、彼を心配そうに見あげていた。
「まいったな。彼は、随分遠くまで行ってしまったみたいだね……」
「もう良い、あの馬鹿は置いてゆく。せっかく苦労して合流したのに、また散り散りになっちゃ世話ないな」
「どうするつもりだい?」
「子どもは就寝時間だろ。安全なベッドを探しに行こう」
そう言うと、スコットはミッキーを連れて、廊下の端に向かって歩き始めた。無数の扉——今はしんとしているけれども、鈍い銀に光る甲冑や、巨大な口を刻み込まれた振り子時計が、傍らをゆっくりと過ぎてゆく。そのたびごとに、ミッキーの尻尾は縮みあがり、まるで心電図のように震えながら宙を漂っていた。
「怖いのか?」
ミッキーは慌てて、自分の尻尾を真っ直ぐに引っ張り、ニカッと白く揃った歯を見せたが、そんな彼の背中をスコットは軽く叩くと、
「大丈夫だ、私がついている。言っただろ、誰かと一緒なら、きっと怖くないって」
「う、うん。そうだね」
「さあ、おいで。我慢する必要はない」
と、暖かく乾いた手を差し出す。
一瞬、何か不思議な生き物でも見るように、ミッキーはそのコーヒー色の掌を見つめていたが、やがて嬉しそうにその手を握り締め、胸いっぱいに満ち足りた笑顔を向けた。それを見たスコットは、もう片方の手で、やや乱暴に頭をくしゃくしゃと撫でてやる。くすぐったそうに笑い声をこぼすミッキーは、パークを訪れる他のどんな子どもとも変わらず、あまりに容易く、あまりに面映いやり方で、身近な人間を信じ切ってしまう節があった。
「スコットはまるで、僕のお父さんみたいだね」
「うん?」

「一部では、これが僕のパパだといわれているけれど」
「安心しろ。確実に、血は繋がっていないと思うぞ」
「スコットのお父さんって、いったい、どんな人なんだい?」
「私の父親?」
少し眉をあげて、意外らしい目つきでミッキーを見つめるスコット。今までのどんな人間も、彼にそのような質問をしたことはなかった——スコットはしばらく黙っていたが、やがて視線を外すと、遠い昔を思い出すように、蒼い水のような月明かりの中に身を沈めた。
「そうだな、厳格で、保守的で、甘ったれたことは許さないエリート主義者だ。私が故国の高校修了試験で、国一番になったのを、大層誇りにしていた。だが私は家を飛び出し、妻との結婚を選んだから、実家からは勘当された。もう帰ることもないだろうな——私も、ポート・ディスカバリーに移住してしまったし」
「大変な人生だったんだね。……それじゃあ、お母さんは?」
「…………」
スコットは容易に答えなかった。少しの沈黙を置いて、湖のように澄んでいながらも、物哀しさの混じる笑みが浮かぶ。
「静かで……優しい人だったよ。もう朧げにしか思い出せないが」
「そうなのかい?」
「ああ。私が六歳の時に、病で亡くなったんだ」
ミッキーは、黒い鼻に幾つもの月翳を反射させながら、薄く目を細め、遠い日の記憶を辿るスコットの顔を見あげていた。
「それからの親父は、色欲三昧でね。彼は経済界に名を轟かせる地主だったし、金を撒き散らせば、いくらだって寄ってくる奴がいた。それでさんざん狼藉を働いて、その不祥事もまた、金で握り潰したんだ。
こんな大人にはなりたくないと思った。いつか復讐してやると誓っていた。寮にぶち込まれた時は、随分荒れていてね……同級生を追い回したり、ナイフで教科書を切り刻んで、屋上から撒き散らしたりしたものだ。もっとも、あそこにいた学生たちのほとんどが、気の狂うような閉鎖環境の中、孤独な怒りを燃やしている者ばかりだったが」
淡々と語られる言葉に、静かに、透明な痛みが混じる。虚ろな靴音を響かせていたスコットは、ミッキーが無意識に距離を取っているのに気づくと、月の光のように寂しげな表情で、
「私が怖いか?」
と尋ねた。ミッキーは慌てて、丁寧に首を振った。
「スコット。君も、僕と同じなのかい?」
「何がだ?」
「僕は、孤児なんだ。両親や姉はいるけれど……僕だけ、孤児になったんだ」
尻尾を地面に垂らして、ミッキーは小さな声で続けた。
「世界中の人に愛されたとしても、それはたまたま、今だけなんじゃないかって。お父さんやお母さんが、僕を手離したように、いつか酷い失敗をすれば、僕は見捨てられるんじゃないかって。そんな気が、ずっとしているんだ」
月の光の中に静かな疑問を響かせたミッキーは、しかしスコットが言葉を失っているのに気づくと、それまでの寂しい笑みを打ち消して、
「ハハッ、だから、毎日を大切にしないとね。パークにいる僕に会いにきてくれるゲストたちへは、いつも感謝しているよ——」
と言い直す。スコットは、肯定も否定もすることなく、不意に立ち止まると、こちらを見つめているミッキーを、優しい力を込めて抱きあげた。
「わわっ——」
「軽いんだな、お前は。もっと食わないと、大きな鼠になれないぞ」
「公式身長を超えちゃいけないことになっているんだ」
「あ、そう。過酷な仕事だな」
かくっ、と肩を落とすスコット。完璧なスタイルを要求される、スーパーモデルみたいなものなんだろうか。
「———礼拝堂だ」
燦々と月の光がそそぐ窓の向こうを見つめ、ぽつりと呟くスコット。ミッキーが彼の首に掴まりながら見ると、バルコニーの向こう側に、確かに、十字を冠したこぢんまりとした建物が見える。
「ディズニーパークって、対外的には宗教色を排除していることになっているんだろう? 神頼みや十字架が効くのか?」
「効くってことにしないと、この先の展開が厳しいし、いいんじゃないかな」
「なるほど、じゃ、今夜はあそこを寝床にしようか。眠っている間でも、この館の怪奇現象から守ってくれるだろうからな」
二人は外に出ると、目印となる十字架を頼りに庭を辿り、錆びついた礼拝堂の扉をこじ開けた。長らく使われていなかったようで、綻びた臭いが、しんと心に沁み入るように広がる。茫漠たる月翳と静かな埃の中に、ワイヤーが切れて傾きかかった十字架と、ステンドグラスの極彩色の翳に彩られた祭壇、そして三、四人は座れるかというチャーチベンチが、粗雑に並べられている。果たして、ここで天の法が説かれ、神のしもべが跪き、最後の祈りを捧げられたのは、いつの日だったのか——今は失われた古の熱情が、床に散らばった聖書の破片から、微かにうかがえるばかりである。足音を殺して歩くたびに、それらの残骸は砂まみれの床に擦りつけられ、意味のない乾いた音を立てた。
スコットは、ベンチの上の土埃を払うと、上着を脱いで、まだ体温の残るそれを、ベッドシーツ代わりに敷いてやった。そして、海のように穏やかな静寂の真ん中で、おいで、と微かに反響をともなうバリトンが、晏如としてミッキーに語りかけてくる。
「硬いが、許してくれ。寝られるか?」
「うん。大丈夫だよ」
「そうか。これは、悪夢を見ないためのおまじないだ」
「ハハッ——」
スコットは、子どもには大きすぎる上着で彼を包み込んでやると、ミッキーの頭を撫で、その額に軽いキスを贈った。こんなこともしてくれるんだな、とミッキーは意外に思う。それは彼への愛情というよりは、日頃ともに過ごしている家族たちに対して、スコットがどのように深く心をそそいでいるのかを、遠回しに伝えるものだった。
目を開くと、高い天井の影から守るように、彼の顔を覗き込んだまま、ゆっくりと頬を撫でてくれるスコットの顔が見える。睫毛も、鼻の輪郭も、その薄い唇も、それぞれが微妙に色調の違うなめし革のような皮膚の上へ、茫漠とした明かりがそそいでくる。世界を暈すほどに透き通る、その光。黎明を含み始めた揺らめきのような月光に照らされて、目の前の男は、聖像の如く美しかった。
「僕ね。君のことが、大好きだよ」
ミッキーは宝石のように純粋な目で彼の姿を見つめながら、微笑んで言った。月の中に微かに瞳を透かしながら、スコットは静かに瞬きした。
「ああ。私も、好きだよ」
「死なないでね、スコット。僕のそばから、いなくならないでね」
「大丈夫だ、死にはしない。必ず、お前を守るよ」
彼の手に、小指を絡ませるスコット。暖かい上着に包まれながら、ミッキーはくすぐったそうに笑った。スコットは何も言わなかった。どこか痛ましげに、しかし掌中の珠を透かすかの如く優しい瞳で、こちらを見ている。深い瞳だった。その淵に漂う漆黒には、何の私欲も保身もなかった。横たわりながら見つめ返す眼が、眩しそうに震えた。いつしか、天にまで昇っていた月明かりがほんの少し傾き、とろとろとまどろみ始めた意識の片隅で、温かいものが一瞬、彼の頭へ静かに添えられたかと思うと、遠くの方で、キイ、と蝶番の軋む音が聞こえた。
それでも、ミッキーは瞼をあげなかった。呼吸をひそめ続け、ドアの閉ざされた気配が過ぎ去った後で、途方もなく広がってくる礼拝堂の沈黙も、眩暈のするように心細い虚空の耳鳴りも、全てが彼は独りなのだという事実を思い知らせてきても、何も気づいていない振りをするしかなかった。
大人は、いつも嘘をつく。そして、ヴィランズがつく嘘よりも、身近にいる優しい人間の口にする嘘の方が、よほど深く心を傷つける。けれども、なんてことないように笑って、気づかない振りをすれば、けして、彼らを困らせることはない。だから明日からも、元気いっぱいの役を演じなければならない。
ミッキーはごそりと身を丸め、夜の闇に消えかかりつつある体温と匂いとに包まれながら、震える声を押し殺した。
「一人は怖いよう、ウォルト……」
(く、そ。いねえな、エディの奴……)
樹の幹に手をつき、荒い呼吸を落ち着かせようとしたデイビスは、汗に濡れた前髪を掻きあげた。目の前には、荒れ果てた庭園が広がっている——これほど広大な館だ、彼らが屋敷に立ち入る前に目にした裏庭などは、所詮使用人用に開放したものでしかなく、こちらこそが本命と言うべき庭なのであろう。優に館の数倍を占める面積は、もはや森、というのが相応しい様相だった。枯れ葉を今にも風にちぎらせそうな樹々が、うろに棲まう生き物の目を赤く光らせ、激しい羽音とともに飛び立たせる。滑らかな蔦は、月翳に艶めいてはその指を宙へと彷徨わせ、雑草の蔓延る足元を、蛇が素早く通り過ぎたかと思うと、沼地を覆い尽くす水面を身をくねらせながら泳いでゆく。湿地が多いせいか、鈴のようなキリギリスやコオロギの声に混じって、蛙がひっきりなしに呻いており、時折り、烏に突かれて暴れ回っているらしい、微かな水飛沫の音が聞こえていた。闇の中で生々しく繰り返される生と死の気配に、スリーピー・ホロウ村の伝説が、今更ながら、ゾッと脳裏をよぎる。あーーー、やっぱミッキーの言う通り、あんな怖い話するんじゃなかったーーー。後悔してももはや後の祭りだが、めぐりめぐって首を絞めてくる自分の愚かさに、髪をぐしゃぐしゃに掻き乱さざるをえない。
(こんな怪しい場所を一人で、どこに行きやがったっていうんだよ。エディ、頼むから、自殺だけはしないでいてくれよ——)
とにかく、彼が生きているという証拠の、何かひとつでも良いから欲しい。もう何十分と、こうして手がかりを求めて探し回っているのに——ほとんど焦燥に取り憑かれて俯いた刹那、ふと、こんがらがっていたその思考が止まる。土を踏み躙る彼の足元に、もうひとつ、何か人工的な溝が刻まれているのを見つけたのである。
泥を踏んだ、靴跡。
デイビスの心臓が、ずきん、と重く痛んだ。お、落ち着け。暴れ回る鼓動を押さえ、喰い入るように目を見開きながら、デイビスの眼差しは必死に、ひとつらなりの動線を追った。雲から漏れてくる月明かりを頼りに、爪先の方向に、もうひとつ、さらにひとつと痕跡を見つけ——そう、確かに、エディはここを通っていったのだ。地に残された足跡は、何かに迷った様子など微塵もない。雑草や水溜まりにも構わず、とつとつと納骨堂へと向かい——そこで、忽然と途絶えていた。デイビスには、それが指し示す意味も分からず、ただ呆然として、最後の足がかりを見つめるしかない。
「……エディ」
彼は、静かにその名を呼びかけた。当然の如く、それに対する返事は——ない。
「エディ!」
今度こそ、デイビスは悲鳴に近い金切声で叫び、駆け出そうとして——その足が、そのまま、どこまでも地面に埋まってゆく。一瞬、ぐらりと天と地がひっくり返る感覚がした後、ゆっくりと倒れ込み——彼が覚えていられたのは、そこまで。星の如く鳴き交わす蛙の声に包まれながら、弛緩した全身は力をなくし、ふっと、暗黒の淵へ意識が吸い込まれていった。
「御苦労。意外に早く片付きそうだな」
ほんの指の合図だけで、倒れたデイビスのそばから、ざざ、と数十の影が呼び戻される。それらを従える主人の、優雅さと下品さとを両立させた姿は、あたかも、野良生活を堪え忍んできた貧乏貴族のようだ——葡萄色の羽飾りが揺れ、髑髏の描かれたシルクハットに、嫌味なほど整った口髭、にやりと歪められた唇からは、前歯に隙間が空いているのが見える。大した長身だ、けしてたくましい筋骨を持つわけではないが、艶のある燕尾服の下から覗く浅黒い腹は、力を漲らせて引き締まっている。それに、煌々と輝く瞳の色は、世にも珍しい、紫であった。
癖のある顔立ちではあったが、七割方の人間が、この男を端正だと答えるであろう——しかし、このどうにも溢れ出る色香と胡散臭さとが、容易に彼に見惚れることを阻んでいた。うかうかと魅入れば、そのまま、魂を奪われそうな予感がする。現に、彼はそうして数多の命を地獄へと導いてきたのだ。
「心配いらない、我が友よ——あと一押しで、ミッキー・マウスは手の中だ。チェルナボーグ様も、この私に褒美を取らせてくれるだろう。我が愛しの、ニューオーリンズの街をな」
唸り声とともに駆けめぐる影に語りかけながら、男はさらに唇に染みつく下卑た笑みを深くした。
「そうさ。麗しのニューオーリンズ——哀れなるニューオーリンズ。貧乏暮らしとはもうおさらばだ。私こそが王として、あの街に君臨するのだ」
言いながら、男はおもむろに、深く意識を手放したキャプテン・デイビスににじり寄ってゆく。そして、ゆっくりと、節くれだった長い指を並べた手を伸ばしてゆく背後から、
「近寄るな」
と牽制の声が飛んできた。
ぴくり、と用心深く眉を跳ねあげ、燕尾服を翻して、細身の男は振り向いた。厚い雲が垂れかかる月明かりの下、広々とした肩を張り、たくましい腕を組んだキャプテン・スコットは、夜闇を背負うように傲然と立ちながら、
「その馬鹿は、不本意ながら、私の相棒でな」
と言い放つ。月光に白く映える彼のシャツの襟が、さやさやと風に揺すぶられていった。
男は逡巡した様子だったが、やがて丁寧にシルクハットを手に取ると、くしゃくしゃの黒い巻き髪を夜空の下にさらして、形式ばった挨拶を口にする。
「これはこれは初めまして、ディズニーシーの住人ですかな? 遠路はるばる、この東京ディズニーランドへようこそ。
————何しに、ここへやってきた」
「不良品回収、というところか。まったく、CWCの外でもこの問題児っぷりとは——おい、デイビス。起きろ」
まるで目に見えぬものとして扱うように男のそばをすり抜け、木の下に歩み寄ったスコットが、ぺし、と軽く頬をはたいてみたものの、やはりデイビスの頭はくたりと脱力したままである。手首に指を当てて測ったが、脈拍は正常——ただ、意識が未だに浮上してこないだけ。一瞬、ちらとスコットの目線が、背後の紫の男へと走ったが、やおらデイビスの身を木の根へ寄り掛からせると、さて、どうしたもんかな、と首を捻る。
「お困りのようですな?」
「困るに決まってるだろ。どうしてコイツは、こんな野外で、すやすや眠りこけることができるんだか」
「私が彼の面倒を引き受けても良いですよ。こう見えても、医療の類いには長けていましてね」
「本当か? こいつはバカだ、アホだ、向こう見ずでしょうもないほど鼻っ柱の強い、精神年齢ゼロ歳児の傲慢野郎だ。一般人が容易に手懐けられるとは思えんが」
「……そこまで言う必要はないのでは」
「そうかね?」
平然と肩をすくめてみせるスコットは、一ミリもその無表情を変えることはない。常人と比べて感情が薄いというわけではないが、長年、彼の人格を理解してきた人間でなければ、その喜怒哀楽を悟るのは、酷く骨が折れるだろう。その巌のような肩に手をかけると、男は商売用の笑みを貼りつけ、馴れ馴れしく誘いかけた。
「お客さん。あなたの未来を占ってさしあげましょうか?」
「もう占いは済んだ、ペニーアーケードでな。そして不本意ながらも、その時の忠告に粛々と従ってる」
「ほう、忠告とは?」
スコットは煩わしそうに振り向くと、シャツの胸ポケットをまさぐり、引き抜いたカードを無造作に弾いて投げ捨てた。爪のように硬い音を立てて樹の幹に当たり、空気を切るようにひらめきながら落ちていったそれには、
『あなたはパートナーの愛に支えられて、どんなに辛いことも乗り越えることができるでしょう。あなたのパートナーにいつでも誠実でいてください』
という文言が、手相の絵の裏側に書かれていた。
「安らかな眠りを邪魔したな。この馬鹿は連れて帰る。一晩の宿をどうも」
よいしょとデイビスを肩に担ぎ、おもむろに帰ろうとしたスコットの前へ、耳を埋め尽くすような風の音を引き連れ、瞬時に紫の煙に化けては元の姿を取り戻した男が立ち塞がると、香辛料を思わせる刺激的な臭気の中で、朧ろに移ろう影を、その抜かりのない顔に深く落としながら囁きかける。
「まあまあ、そう急ぐなよ、お客さん」
「私に、何の用だ」
「このファシリエから、少々ご挨拶を」
不思議に痺れるような匂いのする煙の中から、カードを差し出した。スコットはぼう、と半透明に燃える月翳に透かして、不審げに片手で受け取ったカードの文字を読みあげる。
「タロット占い、お守り、秘薬——"願いごと叶えます"……?」
「私は普段ギャンブルには手を出さないが——賭けてもいいですよ。私は今、かの有名なストームライダーのパイロットとご一緒している……」
「ああ。確かにこいつはこんなナリでも、ポート・ディスカバリーの救世主として、顔が売れているからな」
合点が入った、というようにぶっきらぼうに返答するスコットに、慌ててファシリエは両手を振る。
「いやいやいや、とんでもない。私が興味あるのは、あなたの方なのですよ。ミスター・スコット」
「私だと?」
「ありとあらゆる世俗の人間が、そこの若造に目を奪われると思いましたか? まあ、ゆっくり語り合おうではありませんか。そのお荷物となるお友達は、地面に置いていただいて」
敬語で口調を和らげてはいたが、その裏側に走る大いなる威圧と緊張感に、ふと、スコットは動きを止めた。しばしの沈黙の後。彼は静かに膝を折ると、けしてファシリエから目を外すことなく、慎重にデイビスの身を地面に横たえた。その眼には、隠すこともなく、ありありと警戒心が光って見える。
「そう——そう! 聞き分けの良いことは大事ですよ、キャプテン・スコット殿。あなたは非常に聡明なお方のように見える」
「この質問を貴様にするのは二度目だが——いったい、何の用だ。まさかこの私と、拳で語り合いたいとでもいうのか?」
「とんでもない、私はこの通り、痩せこけたひ弱な男でねえ、肉体で勝負を挑む気なんかありゃしませんよ。私がしたいのは、もっとあなたに得をもたらすことだ。つまるところ——交渉、です」
言いながら、懐の隠しに手を入れると、紫の粉を取り出した掌へ、ふっ、と息を吹きかけるファシリエ。彼の息吹から急激な魔力を得た粉末は、夜空へ舞いあがりながら、網膜を灼く鮮やかさで燦然と輝く。無数の雨粒が滴れるように、全ては燐光の下にみるみる掻き消え、新たな世界へと塗り潰されてゆく。客人の内に秘められた、欲望の力によって。
「少々特別な仕入れ先から手に入れた粉でして。"トリップ"は、初めてかな?」
飄々としたファシリエの言葉が終わるか終わらないかのうちに、ついに火花は底へ辿り着き、現実を夢の一幕へと書き換えた。閃光の落ち着いた気配を察して、スコットはようやく、静かに瞼をこじ開ける。それはトリップと謳うには、あまりに当たり障りのない光景だった——一面を埋め尽くす、茫漠たる白い光の中で、子どもたちが、砂場を掘って遊んでいるのだ。これまで、豪奢なレストラン、王子のなり代わって宮廷暮らし、などといった、煌めきに溢れた夢に慣れていたファシリエは、周囲に広がる日常的な景色に、面白そうに、目を瞬かせる。しかしスコットにとっては、それこそが何よりも憧れていた幻だったのだ。立ちすくむスコットの眼差しは、ひとえに、甲高くはしゃいだ声をあげる、ひとりの幼女へとそそがれていた。
(だめー! キャプテン・スコットは、あたしのパパだもん! ほかのだれもとっちゃだめ!)
クレア———
あまりに幸福そうに、誇らしげに、そして当然の如く。彼と血の繋がった娘は、小さな飛行機のプラモデルを翳しながら、英雄たる父の名声に浸っていた。けれどもけしてそれで天狗になることはなく、人々の命を守り抜こうとする父の精神に感じ入り、深く尊敬を捧げていたのだった。
そのクレアが、父親の影に気づく。望外の歓喜を湧かせた眼差しが投げかけられる。愛おしさの塊のように娘が駆け寄ってきて、両手を伸ばし、数度小さく跳ねた。
(パパ、おかえりー! 今ね、みんなと、ストームライダーごっこをやってたの!)
スコットは深く胸を揺すぶられて、その甘えに満ちた煌めく瞳を目に映し込む。確かにこの瞳には、己れの滾らせてきた血脈が流れている。そして、いつものように抱っこをせがむ娘の脇の下に、堪え切れぬように、その手を差し入れようとした。瞬間、煙が纏わりつき、クレアの顔が泥の如くぐにゃりとねじ曲がる。心臓が打ち砕かれるような悲痛とともに、スコットの背筋を、冷たい戦慄が走り抜けた。
「———触れたな」
「!」
「もうお前は私と取り引きのテーブルに座っている。契約が終わるまで立つことは許されぬ。おっと——妙な真似はしでかそうとするなよ、お前の安全のために。ここは、客人の無事が約束された場所ではないからな」
見る間に、煙が生きたイタチの如く彼らの周囲を取り巻き、奇矯な叫び声が引き攣れる中で、スコットはたちまち、自分が逃げ場を失ったのを感じた。目の前の娘の姿は幻と掻き消えて、もはや跡形もない。煙の半分は、瞬きも終わらぬうちにテーブルを形作り、薄赤いテーブルクロスの裾を揺らして静まった。いつのまにか——そこは漆黒の闇に包まれた、占い部屋の円卓である。しかし明らかに、先ほどとは空気が違う。電気と磁気を帯びたように脈打ち、その床には紫の光を放つヴェヴェ(注、ブードゥーの魔術の紋様)が、幾つも鼓動し、妖しい魔力を浮きあがらせているのである。光と翳の緩やかに交錯する様は、まるで黒紫色の海の底に沈んだかのようにすら思える——そして、その揺らめく燐光に照らしだされて、部屋の隅に山ほど積みあげた髑髏に針の突き刺さった人形、天井から垂れ下がる呪術の仮面、棺桶、コイン、数珠繋ぎとなった首飾りに古びた本、そして得体の知れない薬香を燻し続けるキャンドルは、順繰りに自らを鈍く反射させていった。
愉快でたまらなそうな笑みを浮かべたファシリエが、その高い背を翻しながら、妖しい身振りで燕尾服の裾をぱっと払うと、不思議なことに、奥の椅子が滑るようにひとりでに動いて、当然の如く主人を座らせた。彼の視線は愉快そうにスコットに見据えられたまま、馴れ馴れしい表情で頬杖をつき、
「さあ、客人、私の席につきたまえ。もっと近くへ——そうそう、怖がらずに。
何をまごついているのだ、叶えたいことがあるのだろう? お前のその夢を叶えてやるぞ——ブードゥーの魔法、未知の力を見せてやる!
———それに、秘密の"お友達"もいる……」
と誘いかけた。すると、頭上から吊り下げられていたブードゥーの仮面たちが、一斉にその口を開き、瞳を真っ赤に燃えあがらせながら、囁くような歌声を吹きかけた。
♪He’s got friends on the other side......
スコットはしばらく、自分の周囲で、不気味に渦巻きながら髑髏の紋様を吹きかけてくる凶風へ、醒め切った冷徹な眼差しを投げていたが、やがて男の導くがままに、もう一方の椅子に重々しく身を沈めると、薄暗い笑みの下から悪どい歯を覗かせて、ファシリエを傲然と見つめ返した。
「ふん。どうやらこの私を見くびっているらしい」
「とんでもない、これほど肝の据わったお客さんは初めてだとも。ベニエでもいかがかな」
「話をずらすな。先に言っておくが、私は自分に利益をもたらす契約しか結ばない。貴様に私を満足させる手札がないのなら、交渉の始まる前から、可能性はゼロだ」
「そう喧嘩腰になる必要はないだろう。お忘れのようだが、私は占い師なんだよ……お前の行く末は、すべて、この手の中だ。お客さんの口の悪さに、ついつい手が滑って、悪いカードがめくられてしまった暁には——いったい、どうなると思う?」
「廃業だろ。ヘボ占い師が生きてゆけるほど、占術業界は買い手市場ではなかったはずだからな」
皓々と放たれる床からのヴェヴェの波紋に、両者の頬が絶え間なく舐められる間、どこからか現れた大蛇が、獲物を見極めるように、二人の会話の交わされる下をゆっくりと這ってゆく。その滑らかな鱗に足首を撫でられつつも、ひとえにファシリエの瞳を見据え続けるスコットから放たれる威圧感は、尋常でなかった。この闇黒に支配された部屋の中央で、一際強靭な肩を白く冴えたシャツに包み、無遠慮に頬を支える、骨張った一本の指を立てながら、立ち込める靄に射し込む魔光に炙られ、どっしりとした美しい脚を投げだしている。他に観客は一人もいないにせよ、側から見れば、果たしてスコットとファシリエのどちらが有利な人間であるかは、誰にも判別がつかないであろう。
「さて、さて、さて」とファシリエの声が二重に響く中、彼の背後の影もまた、ゆっくりとその髭の生えた顎をなぞった。
「自分の立場をまだはっきりとお分かりでないご様子だ。この席についてまで、まだ減らず口を叩く客といえば、相場は決まっていてね。勇敢——向こう見ず——傲岸不敵。しかし私に言わせりゃ、その本質はたった一言。"愚か"、だ」
「だからどうした。詐欺師に対する態度など、貴様にごちゃごちゃ言われる筋合いはない」
「まあ、いいだろう。屈強な男を跪かせて後悔させるのは、醍醐味のうちの一つだからな」
その時、不意に、スコットの足元で覚醒しかかっていたデイビスが、う……ん、と小さく声を漏らした。それに気づいたスコットは、樫色に磨かれたグッドイヤー・ウェルトの革靴を後ろに引くと、勢いをつけて、彼の体を思いっきり蹴りあげた。
どすぅっっっ————
という重い手応えとともに、藝術的なシルエットを躍らせて、呆気なく宙へ舞いあがったデイビスは、ずざざざざざざ、と部屋の床を滑ってゆくと、濛々と埃の立ち込める中で、ふたたび、浮上し始めていた意識を手放す。というか、失神した、の方が正しいかもしれない。とにかく彼の上には、天使の輪を掲げて、肉体から抜けかかった魂が浮かんでいた。
「気にしなくていい。で、用件は?」
「…………」
まるで蚊を叩き潰しただけというように清々しく尊大な態度に、さすがのファシリエも、呆然として言葉を失う。
彼はくるりと手を翻すなり、空中から水晶を取り出すと、悠然とテーブルの中央に置いた。内部には白い霧が渦巻いていて、さながらこの世ではない場所へと繋がっているかのようである。その艶やかに透き通る表面を、骨張った指先だけで撫でながら、ファシリエの魔的なバリトンが囁きかけてくる。
「私は占いと名のつくものなら、何だってできる。水晶に手相、数秘術にルーンまで——だがこのファシリエが最も得意とするのは、タロットカード。喜び……苦しみ……哀しみ……この世のありとあらゆる事柄が、このカードの裏側に秘められている。ご存知か?」
「無関心な話題だ」
「まあ待ちたまえ、今にお前も気を引かれてたまらなくなる。なんたってこれが指し示すのは、真実の未来——だ。これを知りたがらない人間など、この世に一人だっていはしない」
スコットはただひとすじ、不興な眼差しを向けると、
「有り難い講釈は、それで終わりか?」
と端的に切り捨てた。
「貴様の楽しい楽しいカード遊びが、私の人生にどう影響するのか、考えがあるならぜひとも教えていただきたいものだが」
「おやおや、無粋だねえ、ドクター・ファシリエのカード占いの的中率は百パーセント、ニューオーリンズでも有名だ。信じた方が良いよ、お客さん」
「ふん、占い師未満のチャチな輩が使う手段だな。要するに——貴様が、インチキ占いの結果を行動に移して、予言した未来を"現実"にしてきたってわけだろ」
ぴく、と相手の眉がねじ曲がるのを見つめながら、スコットは顔色ひとつ変えずに言ってのける。
「人間の屑と言うのに相応しいな。そうも堕落してまで、己れのカリスマ性を吹聴したがるとは」
一瞬、笑みを消したファシリエの胸中で、どろりとした感情が膨れあがってゆくのを見物するスコット。彼は隙っ歯の合間から歯笛を鳴らすと、不気味に歯を剥き出して笑った。
「お客さん、頭がカタいねえ。望みを叶えるのはとっても"簡単"だ。C’est la vie, mon ami」
「私は貴様の友人になどなった覚えはない。安っぽい自尊心を満たそうとするイカサマ占い師がお友達などと、金輪際ごめんだね」
「黙れ!」
ファシリエが力を込めてどんと杖を突くと、素早く蛇が頭をもたげ、スコットの肩を素早く登ってゆくなり、彼の首元で鋭い牙を剥いた。
「貴様、状況を分かっているのか。今度私の神経を逆撫でたら、本当にこの場で、頸動脈を切り裂いて咬み殺すぞ——!」
息の漏れてゆくような蛇の威嚇音が鳴り響く。しかしスコットは、ますます傲然と醒めた顔つきでその様を眺めつつ、
「それで?」と短く訊ねた、「白雪姫の継母よろしく、私の生き血を林檎ジュースのようにでも絞り取るとでもいうのかね?」
張り詰めた沈黙が空間を満たした。ファシリエは震える息をひそめ、スコットは少しも臆する気配がない。が、やおら、ファシリエが振り払う仕草を見せると、巻きついていた蛇はふたたび、だらりと頭を垂らして、漆黒の床を移動していった。
「グリムヒルデの言った通りだ」と忌々しげなドクター・ファシリエ、
「ストームライダーのパイロットは、どちらも信じがたいほどふてぶてしい——命知らずなのか——あるいは単に、頭がイカレちまっているだけなのか。
だが、鋼は硬ければ硬いほど、簡単に折れやすいものだ。今から私が、それを証明してみせよう」
歯茎を剥き出して、不吉な笑いをこぼすファシリエ。不意に、心にさっと薄暗さが差して、スコットは睫毛をわななかせた。目の前でほくそ笑む男の背後の壁紙に、ふと、骸骨の印章を垣間見たように思ったのだ。しかし影の過ぎ去った壁には、単に、複雑な蔦模様が広がるばかり。不吉な徽などは、どこにもない。
この男は———何かが、普通の人間とは違う。
胸を占め始める、おかしな猜疑心。それを秘し隠すように、スコットは強く手を握り締めた。なぜ——単なる見間違いに過ぎぬものが、こんなにも不安を駆り立てる?
「ここは死者の世界と生者の世界の交差点。その二つに踊らされた全ての人生を、ドクター・ファシリエは知っている。
生と死——どちらが強いのかは、言うまでもなかろう?」
「たわけた寝言をいうな。死は生に勝つ。だが死者は、生者に勝てない」
「それは嘘だ。降霊させたい者がいるのだろう? たった一言でいい——会って、話がしたい。そのためなら、命など捨てたって構わない、と」
スコットの顔色が変わった。と、見る間に、その罅の入った心をめがけて、妖しいファシリエの言葉が忍び込んでくる。誰もが奥底に秘める弱みにつけ込む——これこそがまさに、彼の得意とする人心掌握術だったのである。
「他の連中とは違う——あまりに心の奥底に仕舞いこんで、おくびにも出さない。相当に触れられたくない記憶をお持ちのようで」
「貴様が入ってきて良い領域ではない。それ以上首を突っ込むな。恥を知れ!」
「おやおや——お客さん、大分と気が荒いねえ。まあ、そのまま黙って、席についたままでいなよ。シッ——ご覧、奴らが目を覚まし始めた」
Hush———
スコットは素早く周囲に目を凝らした。ぐっと低く腰を屈めたファシリエが、まるで蠟燭を吹き消すように人差し指を立てるのと同時、暗闇の中から一面、ひそやかな溜め息にも似た呼吸が漏れてきたのだ。それも、部屋中にひしめくほどの数が、一同に。
息を潜め、額に汗の玉を浮かべたスコットには構わず、ファシリエはまるで蠟燭でも吹き消すかのように自身の長い指先に息を吹きかけると、コツコツと水晶を爪で叩き、余裕綽々に歯を剥き出した。
「魅惑的な夜の静寂を乱してならないよ。そうでないと、奴らは起きて——勝手に、魂を食い殺してしまう」
「何?」
「ファシリエのブードゥーの館へようこそ、キャプテン・スコット殿。さあ——貴様の、運命を占う時間だ」
どこからか取り出したカードを両手に取ると、まるで曲芸師のように扇状に開き、ニイ、と口角を吊りあげる。そして、そのおびただしいすべてのカードを、薄暗い天井へと投げあげた。
すると、不思議なことに———
ばら撒かれたタロットカードたちが、まるで無重力を手に入れたかのように、ぴたりと空中へ静止したままでいるのだ。手品——しかしこんな技は、今までのどんな高名な手品師すらも披露したことがないだろう。そう、それは確かに魔法だった。ミッキーがあれほどまでに取り戻したいと願っていたそれは、今や、ヴィランズの方が遙かに強い力を手にしていたのだ。それだけではない、ファシリエが長い息を吹きかけると、その微風に導かれるようにささやかな音を立てて、何十ものカードが惑星の如く回転しながら、呆気に取られるスコットの周囲を取り囲み始めるではないか。ファティマの手を描かれたタロットは、めくられるごとにその表面の寓意画を変えて、映し出す。この世で繰り広げられた、数多くの人生——彼がその優美な指で占い、弄ばれてきた者たちの運命を。
「カードだ。カードだ。カードは語る——過去から現在、未来まで……」
シルクハットの下からほくそ笑むファシリエの言葉に操られて、すべての手札は、絶えずゆっくりと自転しながら、如実に物語っていた。それは地上に溢れかえる、数々の悲劇。恋人に去られて地に泣き伏せる男、子の病に感染しながらも看病する母親、遠い街へと売り飛ばされた少年、二度と弾けない往年のヴァイオリンを前に立ち尽くす老女。しかしそのことごとくが表となり、裏となり、永遠に救い出せぬ一枚のうちに、絵画となって動きを止めている。
そして、その中に———
(エディ——!)
多くの髑髏に囲まれたまま、その中央で骸骨を抱き締め、嘆き伏す一枚の男の絵柄が、スコットの目を奪う。その中折れ帽も、背の低く小太りな体型も見覚えがあったが、しかし表情だけは——これほどに惨めに打ち捨てられた顔は、見たことがなかった。死人とも見紛うほどに生気を失い、その身をやつしている。スコットが急いでカードに手を伸ばそうとした瞬間、その手札はたちまち雲散霧消し、後には揺らめく髑髏の煙が立ちのぼってゆくだけ。
「おっとと、触っちゃいけないよお客さん、これは他の客人のカードなんだから。それに、まだまだ占いは続いているんだ。危ない真似はしでかさない方が、身のためだ」
呆然と虚空を掻いたその腕を、たちまち、床から這い登ってきた蛇のとぐろが絞めあげてゆき、思わず苦痛に呻くスコット。そのまま、全身に隙間なく巻きついてくる蛇の重みが、一挙にのしかかってくる。崩れ落ちるようにテーブルに倒れ込みつつも、ふたたび、掻き散らされた煙がゆっくりと象り始めるカードの中の人物へと眼差しを投げたが、もはや拘束された手はどこにも届かず、指一本、動かすことは困難である。なおも万力の如く締めつけてくる胴体は、滑らかな鱗をこすりつけ、全身の骨を軋ませてゆく。血流がめぐらずに茫洋とした耳鳴りに覆われた感覚の片隅で、紫の男が喉元に突きつけてくる鋭い杖と、赤くちらつく蛇の舌が躍る。何とか肺から空気を逃がそうと、スコットは苦しげに呼吸を弾ませた。
「く……」
「黙って見ていろ。焦るなよ、くれぐれも慎重にな。これは——お前の——物語なんだ」
杖についた宝石と同じように紫の瞳を光らせながら、ファシリエは笑う。影もまた笑う。まるで双子のように、二人は一つ。蛇に縛められて倒れ伏すスコットを見下ろし、光と翳の合間で嘲笑った。
「さあて、その犬のように惨めな格好では、三枚のカードを選ぶこともできないだろう。この私が、貴様の手札を選んでやるとするかな? おっとご心配なく、お代は不要。特別に、初回無料ですよ」
「やめ、ろ……」
「Messieur, je vous demande pardon?」
「やめろ、と言ったんだ。私の行き先など、貴様には決められない。悪趣味、だ……!」
「ククク、その悪趣味な男の前に屈伏しているのは、いったい誰だ? この機会を見逃しちゃいけないよ、お客さん——さあ、いよいよここからが、ドクター・ファシリエのショータイム!」
杖で煙を巻くようにしながら、宙を舞う数多のタロットを引き寄せてゆく。スコットはどうしようもなく、酸欠に息を荒げながら、自らの人生が弄ばれるのを見守るしかない。
闇に響く高笑いとともに、刺激臭のする煙を縫って、素早く彼の手捌きによって駆け巡るタロットの合間を、幾十、幾百と跋扈する笑い顔の影。くすくす、くすくすという小さな声が集まり、"あちら側のお友達"へと捧げられた供物と、契約者たる男が対峙する、テーブルの周りを飛びすさり始める。悪い夢でも見ているかのようだ——浅い息を繰り返すスコットの鼻先で、彼は鋭い杖を振り翳すと、宙に浮かぶカードのうちの三枚を回転させ、そのひっくり返された内実を目の前に突きつけながら、野卑と高貴を兼ね備えた笑いを露わにした。
「貴様の過去は"吊るされた男"。克服を自らに誓いながら、精神では否定し——永遠にやってこない懺悔の日を待ち侘びている。
このカードが象徴するのは、お前の現在——どうやら、家庭は順調のようだね? 林檎の樹に絡みつく蛇と、暖かい光に満ちた"恋人たち"の姿が視える。そしてこの先に待ち構えているのは、破滅を司る"死神"のカード——この正体が私だとでも? ククク、まさか、そんなことでは面白くなかろうが!
お前の未来には、"緑"が視える——貴様の首を絞めることになるのは、もっと絶望的で、もっと親しみのある、日頃からよく見知っている人間だよ。お前は奴から自由になりたくて、今の場所から別の場所へ、身軽に飛び跳ねてゆきたいのだろう。そう——そいつがいったい誰なのか、もうすでに、心の奥底では察しがついているはず」
その言葉に、びっしりと冷や汗を滲ませているにも関わらず、スコットは微かに顔をもたげた。見下ろすファシリエの顔は、影に覆われてまるで見えない——しかしその紫の瞳は、嗜虐的な炎をちらつかせ、彼の中の導火線にさらなる火をつける。
「お客さん、どうやら生まれつき運が悪いね。かつて街中から賞賛を集めた、天才パイロットの座——それは哀れにも落雷に邪魔され、見る影もなく若者に奪われ……今や、お前を顧みるものは誰もいない」
「黙れ——」
「前にも進めず、退くこともできない。澄ました顔の裏で、ひそかに念じたことがあったろ、あの小僧さえいなければ——と?」
「彼は俺の相棒だ!」
「そう、相棒であり、英雄であり、お友達であり——お前から名声を奪い去る、あの緑の目の男。予言する、彼は近い将来、貴様の全てを終わらせる死神として、貴様の未来に立ち塞がる存在になるだろう」
「貴様がデイビスのことを軽々しく語るな! あいつは、あいつは——」
「お前はあの若造を憎んでいる。もう一度、奴に奪われた名声を取り返したい。それこそが、お前の奥底に巣食う、魂からの望み」
ざわざわと、蛇が肢体に絡んではのたくる。応酬の果てに、哀しいまでに歯を喰い縛り——絶望というよりは、酷く孤独な、すべてを失ったような瞳をわななかせているスコット。それを見下ろし、ファシリエは夜空の三日月のように唇を歪ませると、ぐっと身を乗り出して、彼の耳元に仕上げの毒を注ぎ込む。
「"相棒"か、実に都合の良い立場だ。体面を保つのに必死だな?」
「頼むから、もうやめてくれ……! 俺の顔に泥を塗りたいのなら、充分だろう!」
「所詮どんなに取り繕ったって、貴様は本物の英雄になどなれやしないのだ。頼れる相棒? 優しい父親? 違うね——本当のお前は、足掻いても足掻いても十も下の若造にすら追いつけない、無様で、滑稽で、人一倍弱さを渦巻かせている男。
貴様はあいつを憎んでる。大した犠牲を払ったこともないくせに——羨ましいよなあ、今やあの小僧こそが、ポート・ディスカバリー中の名声を集めるヒーローなのだから」
「貴様は何も分かっちゃいない——この私が、あいつを憎むはずがない! これ以上私にふざけたことをそそのかしたら、ぶち殺すぞ!」
「ふふん、図星か。奴は夢を叶えた。だが代わりに、貴様の夢は潰れたな。ヒーローになりたかっただろ? 人々の命を救い、家族に誇らしく思ってもらいたかっただろ? お前もストームライダーの主人公に——なりたかったよな?」
ファシリエの囁くひとつひとつが、焼き印の如く熱く染み込んでゆく。けれどもスコットは、精神を滅茶苦茶に踏み荒らされながらも、けしてその眼から敵意を掻き消すことはなかった。彼がふたたび顔をあげた時、まるで子どもが本気で刃物を向けるように、震えながら、しかし細い切実さを帯びて——食い入るような殺意の光を掴んでいる。その必死さに、ファシリエはぷっと噴きだすと、彼のオールバックの頭を掴むなり、思い切りテーブルに叩きのめした。凄まじい衝突の音が部屋中に鳴り響き、痛みにひゅっと息が詰まるスコットを、占い師は笑いながら見下ろしていた。
「ぐっ——!」
「そう睨むなよ。安心しろ、どんな奴らも皮一枚剥げば、口に出すのも憚る欲望が蠢いている。そしてそのちょっとしたお手伝いをするのが、我々のお仕事でね。それではご紹介しよう、こちらが麗しき我が友、マダム・レオタだ……」
ぐい、とファシリエに短い髪を掴まれるがままに、霞がかったスコットの目が、宙を泳ぐ。唇を切ったらしい。血が口の端から垂れ下がり、小さく床に滴るのを感じながら、彼の眼差しは虚ろに、テーブルの中央に置かれた水晶玉へとそそがれた。
——Serpents and spiders, tail of a rat,
Call in the spirits, wherever they're at.
スコットは息を呑んだ。いつのまにか——水晶玉は皓々とした光を湛え、神秘的な波紋を揺らめかせている。そしてその霧の奥には、一人の女の生首が浮かんでいるのだ。痩せこけた青白い肌に、海藻のように濡れた黒髪。血の気のない唇は、低い呪文を唱え始め、あの世への扉がこじ開けられてゆく。はっ、とスコットは振り向いた。一瞬、陽気なトランペットが、何かおかしなフレーズを演奏した気がした——いや、空耳などではない。暗闇の中に様々な楽器が浮かびあがって、この水晶玉の霊媒師の呼びかけに、亡霊たちが応え始めているのである。
「これでも非科学的なことは信じないとでもいうのかね——キャプテン・スコット殿?」
にたり、と笑ったファシリエの姿でさえ、みるみるうちに、白い骸骨の顔へと変じてゆく。さながら、生と死を司るブードゥーの男爵のよう——この日初めて、スコットは恐怖を感じた。それは己れの生命が、完全に自らの手をすり抜けてゆく感触、もはや生きる望みは完全に絶たれ、断崖へと追い詰められたのだ、と悟る、純粋な恐怖だった。
ドクター・ファシリエ——いや、今やけばけばしい彩色を施した髑髏の化け物と成り果てている——はうやうやしくシルクハットを手に取ると、囁くように、彼の持てる最後の秘密を告白する。
「さあて、ストームライダーのパイロット君。地獄への土産に、良いことを教えてやろう。アメリカン・ウォーターフロントにいたお前たちを、奈落の底へと突き落としたのは——この、私だ」
「何?」
「シリキ・ウトゥンドゥに命じて、お前たちを転落死させるつもりだった。まさかあの馬鹿げたウサギが、マンホールとインスタント穴をすり替えているとは思わなかったがね……
———あの時、死んでいればよかったものを」
——Rap on a table, it's time to respond,
Send us a message from somewhere beyond...
ガタン、とテーブルが乱暴に揺さぶられ、大きな音を立てた。
スコットは身悶えする。その額には冷や汗が浮かび——何度身を翻そうとしても、固く締めつけてくる大蛇が彼を戒め、立ちあがることすらできず、びくともしない。その指には、鋭い歯を兼ね備えたタリスマンが近づいてきている。ファシリエはゆっくりと舌なめずりしながら、まるで目の前の光景に魅せられたかのように、恍惚とした笑みさえ浮かべていた。
「やめろ——離、せ……!」
「離さない。私は、お前の、魂がほしい」
じっとりと近づいてくるファシリエの顔。次第にその目は、毒々しくちらつく蛍光色さえ湛えるようになる。
——Goblins and ghoulies from last Halloween,
Awaken the spirits with your tambourine.
「ああっ——!」
「さあ、お食事の時間だ。心配しなくて良い、すぐには殺さない——用済みになった時点で、あの世行きの切符を渡してやる。まずは、このドクター・ファシリエの魔術の力、とくとご覧あれ!」
飛び散る血飛沫とともに、噛みつかれたスコットの指から噴きあがる鮮血の筋を飲みくだし、みるみるうちに紅く染まってゆくタリスマン。牙は相当に深く食い込んだようで、スコットは絶え間ない苦痛の波を噛み殺しながらも、ファシリエに操られるがまま、妖しい呪符にどくどくと血を吸われてゆくほかなかった。彼の手のうちで真っ赤に鼓動する様は、まるで心臓そのもののようだ——鬼の如き形相をしたそれに、スコットの魂が吹き込まれてゆき、二人の会話は異様な影と雰囲気の中で交わされる。
「なぜ? なぜ私の魂を?」
「客人よ、お前はまだ気づいていないのだ。我々は何としてでも、あの忌々しいミッキー・マウスを、この世から葬り去らねばならぬ」
「私がいる限り、あの子にけっして手出しはさせん!」
「そうそうそう、よく理解しているじゃないか、そういうことだ。我々はありとあらゆる手を使ってあの鼠を引きずってくるよう、チェルナボーグ様からの命をあずかっている。つまるところ、お前は——その餌にすぎん」
「ミッキーは、貴様の自由にはならない。一人にしないと誓ったんだ! 私は必ず、あの子を……私の、子どもたちのことを——!!」
「ククク、足掻け、足掻け、だが呪いは止まっちゃくれない。さあ、心の準備はできたか? ハハー、できていなくとも、誰も待っちゃくれないがね。それでは、Au revoir、我が友よ——変身、スタートだ!」
不気味な音楽が轟き、ゴム毬の如く弾み出した彼の心臓が、不自然な動悸が鳴り響かせるのを感じた。まるで周囲の笑い声とビートを合わせるように、暴れ狂い、猛り狂い、もはや意志などで喰い止めることは到底できない。
それは紛れもない、「向こう側」からの音楽。カードの裏と表の如く、現世と向かい合わせの世界。そして、血管は明らかに両生類の如く飛び跳ね、ぐるぐるとめぐる血に、稲妻のような痺れが混じり始めた——スコットは直ちに悟った。タリスマンと、自らの心臓は同期している——もはや、血の契約は果たされてしまったのだ。そしてタリスマンから溢れ出る緑の閃光が、どんどんと彼の身を押し包み、目の前はもはや鮮やかなグリーンの一色となった。緑は、なおも細胞の底まで染み込んでゆき、何やら太古の記憶が呼び起こされて、全身からぬるぬるとしたものが滲み出るのまで感じた。
——Creepies and crawlies, toads in a pond,
Let there be music from regions beyond.
マダム・レオタの詠唱は止まない。スコットはその全身を、絶え間ない緑の閃光と大蛇のとぐろに呑み込まれてゆく中で、倒れ込んだままのデイビスにちらと目を走らせた。先ほど蹴り飛ばしたおかげで、ファシリエの魔力からは遠ざけられたはずだ——スコットの周囲を取り巻く煙の圏内を免れており、徐々に脚を伝って攀じ登ってくる呪いの人形たちもまた、スコットの姿しか目に入れていないように見える。太鼓が高まり、ますます音楽と黒魔術の沼に引きずり込まれてゆく彼を前にして、艶やかな顎髭に指を絡ませながら、夥しい影との契約者たるファシリエは、思案に耽るしぐさを見せた。
「ふうむ、toads、か。そういえば、ここらの裏庭の水溜まりには、泥水を啜って生きているぬらついた連中が、ウヨウヨしていてね。いずれは烏に突かれて餌になるか、魔女の釜でじっくりと煮られるか……ハハー、どちらにせよ、気位の高いお前には、こたえられないほど屈辱的な幕切れだろう?
変わる——変わる——それでいい——はてさて、ご満足いただけるといいんだが、ムッシュ? だが、責める相手を間違えるなよ。
何かあっても、それは私じゃない———
奴らがしでかしたことなのだからな!」
(望みは叶う——)
(だが何かを失う!)
ブードゥー人形たちがけたたましい声を出して、今、供物として差し出されようとする犠牲者を笑った。宙に浮かぶ楽器はかまびすしいほどにがなりたて、調子外れの渦と成り果てていた。楽器の音色はいよいよ大きくなり、天も地もその旋律に巻き込まれ、永遠の舞踏へと駆り立てられた。数多くの人形たちや蛇に覆い尽くされ、もはや餌食となる瞬間を待つばかりとなったスコットは、徐々にその輪郭を黒魔術の煙のうちに融解させてゆきながらも、最後の最後で、その瞳に焼き殺さんと言わんばかりの炎を閃かせた。そのぎらぎらと抉るように輝く強烈な双眸は、喰い縛った奥歯から漏れる喘鳴の下からであろうとも、凄まじい激昂を漲らせた光で相手を射抜く。呪術師は、男の殺意の眼差しを身震いするほどの愉悦で受け止めつつ、唇を下劣にめくりあげ、狂気じみた様子で隙っ歯を剥き出しにした。その姿は、まさしく闇の中に生ける悪魔。
そして、渦巻く煙の中で———刃のように交錯する、二人の凄惨な眼がかち合う。
「ドクター・ファシリエ———いつか必ず、貴様を……!!」
「ああ、待っているよ……いつかお前の伸ばした手が、私のタリスマンに届く、その時までな……!!」
水晶玉が一面に閃光を放ち、最後の稲妻の残響が過ぎ去ると、それに続いて、小さな鐘の音が鳴り——やがて、家中のすべての振り子時計の鐘を引き連れ、轟かんばかりになる。きっかり、十三の時が告げられた中で、亡霊たちの漏らす奇々怪々の嬌声とともに、けらけらと笑う人形の声がひとつ、寂しく空っぽの風に吹き抜けた。
ファシリエは、細い腰を屈めると、その長い指でそっと、"スコットだったもの"をつまみあげ、テーブルの上に置いた。その水晶玉からは、もはや降霊師の姿は過ぎ去り、映り込むのは一匹の緑色の生き物の、曲面にねじ曲げられた小さな姿だけである。それを見下ろしながら、彼はシルクハットのつばに手をかけると、紳士の如く微笑んだ。
「君たちの心が通じたらしい。一族が蘇り、舞踏会の準備を始めたようだ。私も楽しんでくるとするか——では、哀れな、高慢な蛙くん。また後ほど……」
微かな光が漏れるとともに、遠くの方で、キイ、と蝶番の軋む音。まもなく、無惨にも扉が閉められてしまうとともに、無人となった部屋には低くしわがれた蛙の声に混じって、あの切ない、かすかな赤子の泣き声が聞こえてくるのだった。
* 参考資料・一部台詞引用・一部画像引用
『ホーンテッドマンションのすべて』ジェイソン・サーレル、講談社、2017年
NEXT→https://note.com/gegegeno6/n/nb353a8419ca8
一覧→https://note.com/gegegeno6/m/m8c160062f22e
