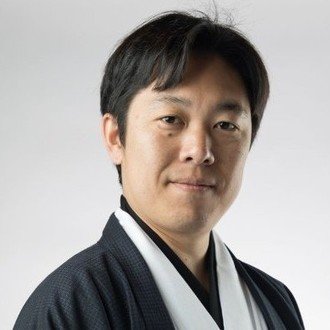#Slack AIは組織を変えるパワーがありそう
当たり前にやっていることなので、外から指摘されないとその凄さみたいなものをやっている当人も認識できないみたいなこと、ありませんか
今日はちょうどそんな話が出たのでSlack AIに絡めてnoteを展開してみようと思います
Slack AIを使い始めたというのは先日書いたnoteの通りです。もしよければ御覧ください
ここから10日ほどがたち、SlackAIが実際どのように使われていくのかみたいな話を後日談としてまとめていこうと思います。その後にそれらを踏まえてのお話しを。
Slack のワークフロー作ろうと思って画面開いたら、Slack AIによるプロンプト生成が使えるようになっていた
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 6, 2024
使えるかなーとおもったら、外部連携のワークフローには未対応なんだね pic.twitter.com/pLc8v62qIJ
Slack AI がONになるとワークフロービルダーにSlack AIノードが現れるのでチャンネル要約ボタン使ってみたら、こっちは言語設定効かないんだね。実行ユーザーがワークフローになるからなんだろうなー。 pic.twitter.com/nxcRkLz0xK
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 6, 2024
#Slack AI Day1のリバネスグループの様子
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 6, 2024
- 社内ミーティングがハドルに完全移行した
- Slack AI議事録はかなり好意的に受け入れられた
- 対面ミーティングでもうまいこと音声を入れるためにどうしたらいいかを考え始める人が現れた(俺もそう思う)
-…
Slack recap
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 6, 2024
昨日のtweetチャンネルのハイライトは焼き芋だな🍠 pic.twitter.com/Qnr6rMCK4f
おお!これが #Slack からSalesforce 検索するあれか!!と思ってやってみたらエラーでた
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 6, 2024
なんでーな pic.twitter.com/cA6D3i33kK
#Slack AI DAY3
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 8, 2024
tweetsチャンネルがリバネスっぽかった。
数学の質問か〜(ちなみにこのやり取りは英語できたものが日本語になってます) pic.twitter.com/EL2gv9ykuB
#Slack AI WEEK2
— George リバネスCIO/リバネスナレッジ代表 (@geeorgey) November 11, 2024
- まとめの設定は結構進んでいる
改めての話
リバネスグループはSlackを使い始めて9年になるのですが、それ故、いにしえのやり方が根付いたままになりがちです
今朝の全体ミーティングでは「スレッドを使おう」という話しを改めて展開…
Slack AIが働きやすい情報空間を作れ
リバネスがSalesforceを導入したのは2014年でした。研究者だけで始めたリバネスという組織。営業マンなんかいないので、それぞれのスタッフが自分で案件を追いかけてそれらを集計するみたいなやり方で行けるのは40名位の組織までだったと思います。
個人商店から組織運営へ移管するために必要だったのがSales Cloudの導入であり、営業のプロになりたいのではなく、サイエンティストによる社会課題の解決を第一にするのであれば、その他の部分はプロの知見を使うのが良いよねという判断で、世界最強であろうSalesforceを選択したという経緯があり、そこから10年、なんとかかんとか事業も成長してきたと思っています
その発想はなかった
今日の会合で聞いた一言ではあるのですが、「生成AIが活躍しやすい方向に人間が変わっていけば良い」という旨をお話したところ、その発想はなかったなという反応を頂きました。これは弊社としては(というかリバネスCIOとしては)当たり前にやっていることで、Sales Cloudでの成功はSales Cloudに人間を合わせたところにあると言っても過言ではなく、であれば今回の生成AIの波にうまく乗る組織が何をすべきかと考えると、生成AIに人間が合わせるというのが正解になる訳です。
例えばSlack AIで表現すると、ハドルミーティングのAI議事録という機能があります。これを使ってみるとびっくりするほどよく書けてるなと思う一方で、拾われていない情報がいくつもあるよねということに気付くわけです。そこで考えるのは、なぜ拾われなかったのかであり、AI議事録の性能がわるいなぁという反応をすることでは無い。
うまく拾えているポイントがあるのであれば、うまく拾われないのはそのテーマを話した人の話し方に原因があるわけです。その解像度を組織の中で上げていく必要がある。
例えば、話し始めるときに最初に何のテーマについての会話なのかを宣言してから始めるとか、シンプルに固有名詞を省かないとか、そういった行動様式を生成AIに合わせていくというのが今最もパフォーマンスするやり口であり、その少しの努力で得られる果実が大きくなるというのは恐らく簡単に感じられるのがSlack AIの良いところだと思う
努力の結果がインスタントに得られるSlack AI
ハドルミーティングのAI議事録については、会議のセッティングをしなければならないので少し時間がかかるかもしれない(それでも十分に短いサイクルでPDCAが回るでしょう)
一方で、スレッドの要約、チャンネルの要約についてはボタン一発で呼び出せる訳です。チャンネル要約については、数ある投稿のすべてをやり直すということは難しいですが、少し長いスレッドを見つけてきてその要約がしっかりと機能しているのかというのは誰もが簡単に実行することができます
つまり利用者に対するフィードバックスピードがめちゃくちゃ早いんですよね。これはツールを使うにあたって思った以上の恩恵を与えてくれるはずです
どのように生成AIに情報を渡していくことが、結果を得やすい形なのか。これを走りながら簡単に試すことができるというのは良い体験になるのではないかと思います
組織を変えるパワーをどう生んでいくのか
こういうのは一人ひとりの社員が実際にテクノロジーに簡単に触れるという必要があります。1年半前にParty on Slackをリリースしましたが、これはSlack AIの実装まで待てないから作って無料リリースをしたという経緯があります。
Slackアプリもここに来て生成AIアプリの取り込み用のUIを強化していますし
こういう物を通して組織を変えていくにはより多くの人が簡単に使える。そしてそれを共有できるという仕組みが良いのではないかという仮説が強化されていくなと感じています
ということで、Slack AIスタートから10日目の感想と、これからの人間のあり方の話でした。
いいなと思ったら応援しよう!