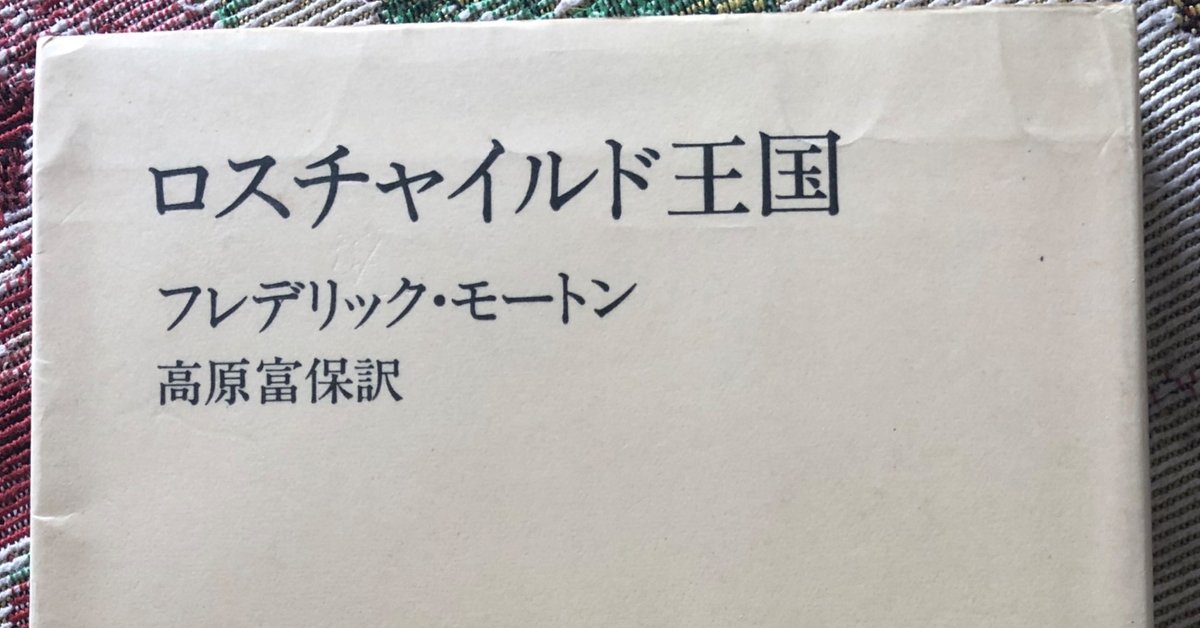
「目からウロコ」の本day3「ロスチャイルド王国」
南仏を旅行することになった時、ロスチャイルド家の別荘にだけは絶対行きたかった。コート・ダジュールはフェレ岬の突端にあるそのお屋敷は、「別荘」というより、「館」。王宮のようなインテリアもすごいが、庭園も広大で、しばし呆けるように海をみていた。
眼下のコート・ダジュールには、ヨットが一つ、二つ。金持ちのための空間だなー、と改めてため息をついたものだ。
しかし、そんな「別荘」一つでびっくりしている場合ではなかった。ロスチャイルドとは、この「全世界」に君臨した、王冠を戴かぬ王家ともいえる存在だったのだ!
それをわからせてくれたのが、「ロスチャイルド王国」 (新潮選書・フレデリック・モートン著・高原富保訳)。

「第一章を読んだだけで、ロスチャイルド家の魅力にとりつかれてしまう」という扉に書かれた草柳大蔵氏の言葉そのものに、私も最初の1ページから、まるでアラビアンナイトの世界にいざなわれるように、1764年の、フランクフルトの、マイン川に近く薄暗いユダヤ人街に入り込んでいった。
この世界で、その名を知らないものはいないだろう「ロスチャイルド」家。政治、経済、宝石、ワイン、植物、石油、鉄道、その他もろもろ・・・。
「ロスチャイルド」の名前が連なっていなくても、その分野でもっとも活躍している企業や団体には、必ずといっていいほど「ロスチャイルド」が出資していたり、実質的な経営者だったりする。
それは、今に始まったことではない。
ヨーロッパの歴史の中で、日本人には想像もつかないほどの差別と隔離を受けてきたユダヤ人でありながら、彼らはどうやって王家の金庫番となり、国と国との折衝のキーマンとなりえたのだろう。
イギリスでは首相を親しく家に招いて世界を動かす陰の立役者になれたのか。
フランスでは王政、革命、また王政、そして共和政とめまぐるしく政権が変わる中、ナポレオンもブルボン王朝も、どんどん衰退していったのに、
なぜ唯一生き残ることができたのか。
そして、
初代よりロスチャイルド家がこだわった「ハプスブルグ」家の地・ウィーンで
彼らはいかにしてヒトラーと向き合ったか。
はたまた、イスラエル建設とロスチャイルドとの関係は?
あまりに面白い歴史絵巻。これまでおそわってきたものすべてが、まったく違う色で塗り替えられる思いだ。
先見の明を持つとはどういうことか。流浪の民が認められるためには何が必要か。「内側」の人々の証言や資料がほとんどのため、クリティカルな視点に欠けるのは否めないが、それを補ってあまりある「史実」の重さ。なぜ題名が「ロスチャイルド王国」となっているかがずっしりと体に響く。
ロートシルト・ラフィットのワインが好きな人、
デビアスのダイアモンドに見せられた人、
蘭の花には目のない人。
ぜひぜひ、ロスチャイルドの世界をかいま見てください。
いいなと思ったら応援しよう!

