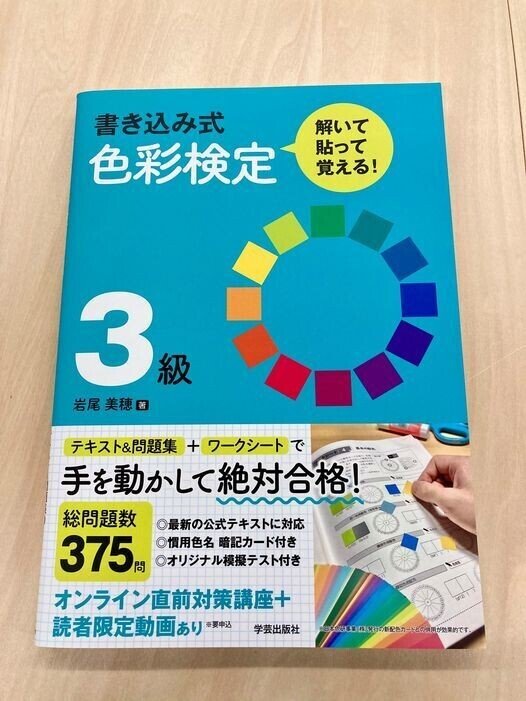「書き込み式 色彩検定3級」おすすめ勉強法!①
来月に迫ってきた「色彩検定」。
この記事では、学芸出版社から発行された参考書『書き込み式 色彩検定3級』を使用した色彩検定の勉強法について、担当編集者がおすすめする方法をご紹介します。
まだどの参考書で勉強するか迷われている方、ぜひお手に取ってみてください!
本書は、
・解説本文
・確認しよう!
・練習問題
・ワークシート
・模擬テスト
で構成されています。
このほかに、切り取って使える「慣用色名カード」やPCCS色相環・トーンマップもついています。

慣用色名カード
ではまず、さっそく本文を読んでいきましょう!
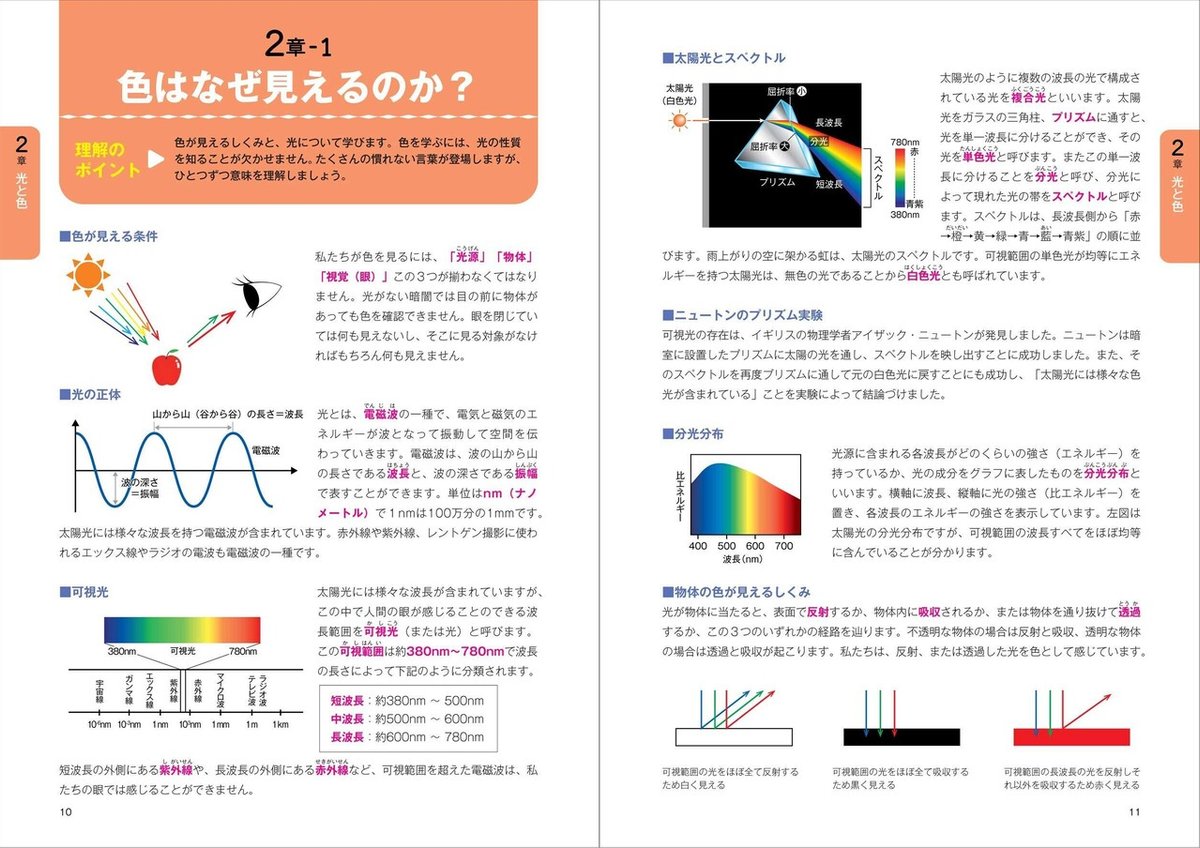
重要な語句は赤字になっています。
重要語句や図の意味が理解できれば、必ずしも文章を上から読んでいかなくても大丈夫です。まずは図だけ眺めてみるのもOK。
時間がない方は、ざっと本文を読んだらすぐに「確認しよう!」を埋めていくのも良い方法です。
重要部分がよりピンポイントで頭に入ります。

「確認しよう!」の解答は書籍ウェブサイトで公開しています
※「確認問題の解答」タブ
▼赤ペンで記入して、市販の赤シートを使うのもgood!

※赤シートは付属していません。スミマセン・・・
こんな調子でまずは全体を通して勉強していきましょう。
各章末の練習問題は、1章終わるごとに取り組んでも良いし、最後にまとめて取り組んでもOK。
繰り返し取り組めるように、別のノートに答えを書くのも良いでしょう。
練習問題については、また別の記事でも取り上げたいと思います。
次回は本書の目玉であるワークシートについてご紹介します!
(編集部・K)
いいなと思ったら応援しよう!