
【外苑前野球ジム】動作解析プランから紐解く投球動作~捻転差~
前回のnoteでは、並進運動から回転運動への移行の話をしました。
まだ見てない方は先にこちらを読んでから、見てもらうとわかりやすいと思います。
今回は、回転運動で特に大事になる捻転差(separation)に着目していきます。
投球動作は、並進運動と回転運動により成り立っていることは、過去のnoteにて説明してきました。
ボールをリリースさせるタイミングは、並進運動を終え、回転運動中です。
そのため、回転運動が適切に働いていなければ、並進運動で産出したエネルギーを効率的にボールへ伝達することができません。
運動連鎖により成り立つ投球動作は下肢から順次動いていきます。
そのため、ステップ脚が着地してからの回転運動では、骨盤が最初に投球方向へ回転していきます。
ピッチャーをやってきた人は一度は言われたであろう「身体を開くな」という指導ですが、ステップ脚着地時に言われると思います。
ただ、骨盤だけに着目してみると実は開く(投球方向へ向いている)状態の方が良いと報告されています。¹⁾²⁾
前回のnoteでステップ脚は、着地後固定され、身体の回旋の軸となるということを記しました。
では、骨盤が閉じた状態(右投手なら三塁側を向いた状態)でステップ脚が固定されてしまうと、身体を回旋させることが困難になります。
そこで大事になってくるのが捻転差(separation)です。

捻転差(separarion)とは、写真のように骨盤の回旋角と上胴(上体)の回旋角の差のことを指します。
先ほどの「身体を開くな」という指導ですが、「上体を開くな」という言い方に変えると適切であると考えられます。
骨盤は開いた状態だが、上体は閉じた状態
この形が体幹を通じて効率的にエネルギーを伝達させるために重要になります。
ゴムを捻じった状態をイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。
では、今回の対象を見ていきましょう。
対象:20代 草野球
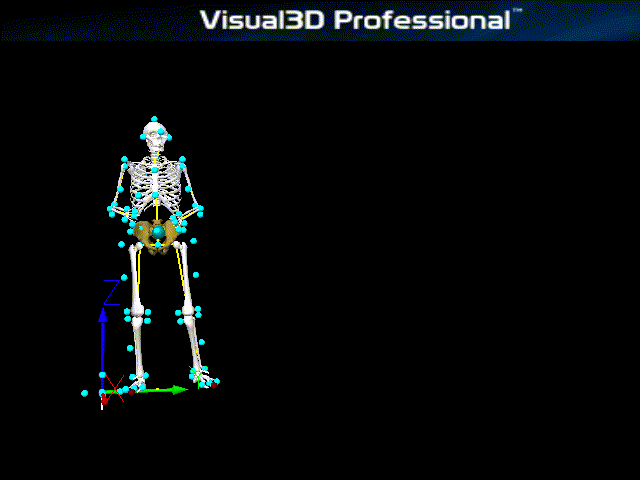
アセスメント前のステップ脚着地時の回旋角度
骨盤:44.35° 胸郭:46.30°

下のグラフ:骨盤に対する上胴の回旋角度
上記のグラフを見るとわかるように、対象のステップ脚着地時の捻転差(separation)は約2°とほとんどありません。
この状態では、体幹でエネルギーを生成し、上肢に伝達できるエネルギー量が少なくなってしまいます。
そのため、対象には以下の指導を行いました。
・胸郭の柔軟性を改善させるトレーニング


・捻転差を生み出すトレーニング


アセスメント後の結果が以下になります。

アセスメント後ののステップ脚着地時の回旋角度
骨盤:56.17° 胸郭:61.34°

下のグラフ:骨盤に対する上胴の回旋角度
対象のステップ脚着地時の捻転差は約5°となりました。
アセスメント前は約2°だったので、約3°増加しています。
3°程の変化なので、球速に大きな変化はありませんでしたが、継続してトレーニングを積み捻転差を拡大していくことで球速が増加していくと思われます。
【参考文献】
1)Stodden, D. F., Fleisig, G. S., McLean, S. P., Lyman, S. L., & Andrews, J. R. (2001). Relationship of pelvis and upper torso kinematics to pitched baseball velocity. Journal of applied biomechanics, 17(2), 164-172.
2)Dillman, C. J., Fleisig, G. S., & Andrews, J. R. (1993). Biomechanics of pitching with emphasis upon shoulder kinematics. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 18(2), 402-408.
このような動作解析を受けてみたいという方はぜひ上記よりお申し込みください!
お問い合わせもお気軽にご連絡ください。
