
長田幹彦『大地は震ふ』
1 意外に知られていない?
今年、2023年は関東大震災から100年ということで、さまざまな本が出版された。
表題にあげた本『大地は震ふ』(大正12年12月25日再版、春陽堂 *初版は12月18日)は、一時期、反自然主義の耽美派系統の作家に関心があって、長田幹彦の作品を集めていた時期に入手したものである。大阪古書会館のたにまち月いち古書即売会で購入したと記憶している。

*装幀は広川松五郎か?
書名が物語るように、関東大震災の体験を作家の視点によってとらえた作品である。自身の体験だけではなく、聞き書きで得た他者の体験も描かれている。一人称で書かれたものでも、もしかしたら他者の体験かもしれないと思わせる作品もまじっている。

入手したときは、珍しい本を手に入れることができたと喜んだ。
しかし、調べると国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている。
公開日は2021年6月1日となっていて、それほど古くはない。
震災を取り上げた文学のリストがいくつかあるが、この本は記載されていないのではないだろうか。すべてを確認したわけではないので、誤認であれば修正したい。
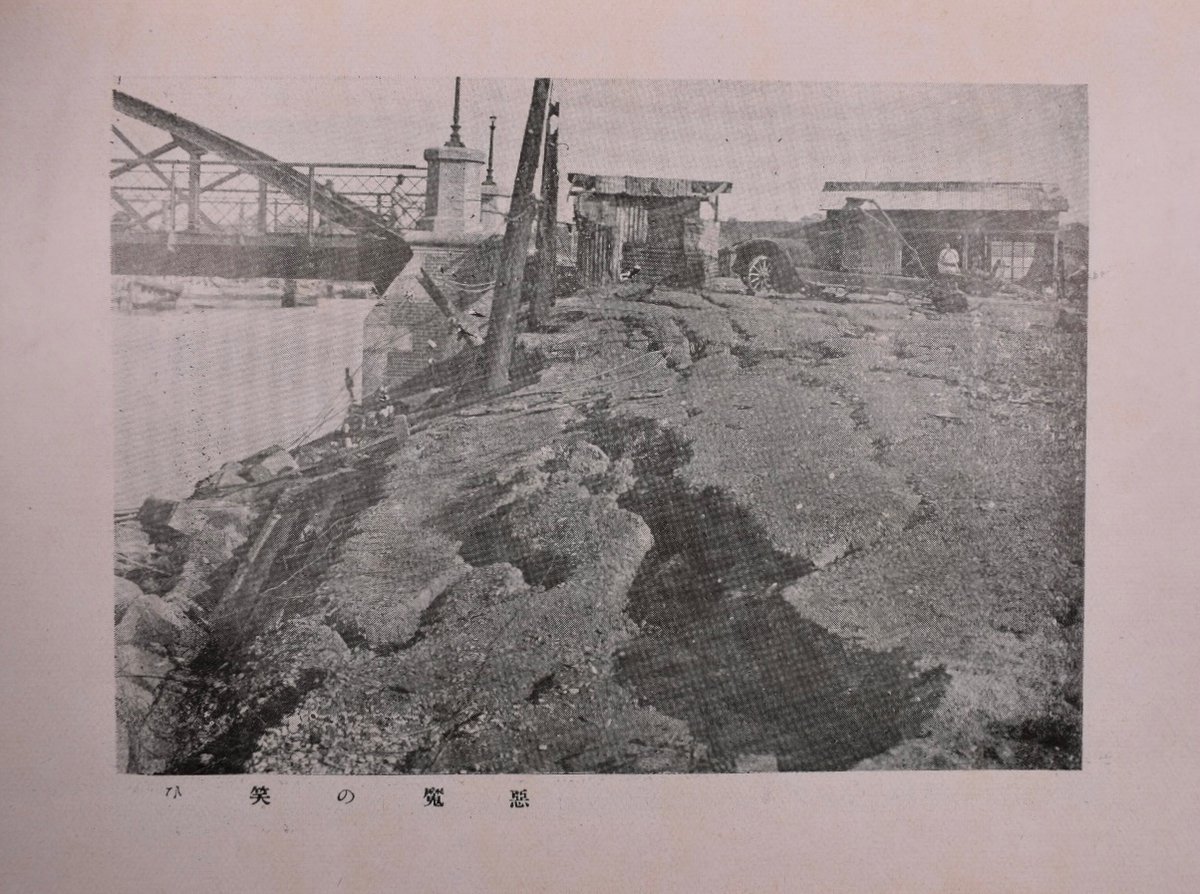

2 春陽堂を支援する
この本は、関東大震災によって、灰燼に帰した出版社春陽堂を支援するために刊行されたことが「小序」に記されている。
春陽堂は震災で大きな被害を受けた。
日本橋の大街衢の一角に立つて、古風と健実とをもつて雄を為してゐたわが春陽堂も遂に恐ろしい災厄の手を遁れることが出来なかつた。過去五十有余年の長い歴史をもつたあの土藏造りの老舗も、九月一日午後九時を過ぐる頃に至つて、万巻の書と共に空しく灰燼に帰してしまつた。明治から大正へかけての隆々たる文運に棹し、光輝ある幾多の貢献をわが日本の文藝史上に胎した店舗も斯くして廃滅の路傍に徒らなる残礎を止むるのみの悲運に際会したのである。偉大なる文人巨匠が惨膽の苦心になる著作の紙型は挙て一炬に附せられ、その珍蔵せる得難き墨痕、書幅並に古木版等も遂に救ふによしなかつた。混乱の際とて詳細なる計数のうへの額はまだ分明しないが、併し少くともその損失は二百万円以上に上るものと思はなければならぬ。 財政の基礎も確固で、猶且つ巨資を擁してゐた老舗のことではあるが、それにしても恐らく東京に於ける出版業者中最も手痛き打撃を蒙つたものゝ劈頭に数へらるべきであらう。
春陽堂は、美濃国不破郡荒川村(現、岐阜県大垣市)の出である和田篤太郎によって興された。和田は16歳で上京し、書籍の行商から始めて、春陽堂を明治期を代表する出版社に育て上げた。
春陽堂は文芸出版に力を入れ、尾崎紅葉、夏目漱石、志賀直哉、芥川龍之介の単行本を刊行し、文芸誌『新小説』を発行した。
長田幹彦(1887−1964)は、劇作家として知られた兄秀雄の影響で早稲田大学英文科在学中から創作を始め、東北・北海道を旅役者などをして放浪し、その体験をもとにした小説で話題となり、後、祇園を題材とする情話文学に転じ、流行作家となっていった。
長田は、春陽堂と縁が深く、「小序」に次のように記している。
私自身にしても、春陽堂に寄託してある第一作「船客」から最近に出版した
「永遠の謎」に至るまで四十五種の著作及び全集の紙型をすべて失つてしまつた
その報を得た時には私自身も殆んど茫乎として為す処を知らなかつた。併し翻つて慮みるに、私が初めて文壇に名を列してから今日に至るまで常に出版のことに当つて多大の好意と援助とを与へて呉れた春陽堂は私にとつて銘記すべき恩人の一人である。その恩顧を想ふと、すべてを不可抗な天災の為す処と潔く断念すると同時に、私は一作家としてその損害は共に負ふ可きものであり、且つは又平常の厚志に酬ゐる為めに此際に処して最善の力を致すのが至當であると思惟した。
短編、戯曲と紀行を収めた『船客』は大正2年1月刊、長編『永遠の謎』は大正12年3月刊である。

『長田幹彦全集』第10巻 (非凡閣、昭12年) 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1186102 (参照 2023-12-29)
全集とあるのは、『長田幹彦全集』全5巻であるが、『春陽堂書店発行図書総目録 1879ー1988』(1991年6月、春陽堂書店)では、「大正年間発行年月不明出版物」とされていて、刊行時期はわからない。昭和期に刊行された非凡閣発行の全集は見かけるし、国立国会図書館デジタルコレクションでも公開されているが、この春陽堂版の全集は古書目録でも見たことがない。
長田の記述から、震災までには一部か全部が刊行されていたことが推定される。
「紙型」とあるのは、活字組版の複製を作るときに使われるもので、塑性や強度がある厚紙である。それを活字面に押し当てると、凹版ができる。そこに鉛を流し込めば凸版ができ、それを印刷に使うのである。つまり、紙型が保存されていれば再版、重版が簡単にできるのであるが、震災でそれが焼失してしまったのである。
春陽堂に恩義を感じている長田は、次のような提案をする。
そこで主人和田氏に復活のことを慫慂する旁々、一時私の著作の全部から生ずる物質上の報酬を辞退し、猶ほ本書の著作権及び発行権を挙げて同氏に提供し、多少たりとも復興の資に宛てゝ貰ふことにした。
長田は被災して打撃を受けた春陽堂を支援するために、急遽刊行する『大地は震ふ』の印税と、一時的に全著作の印税を辞退したのである。
3 『夜警』を読む
さて、この『大地は震ふ』を紹介しようと思ったのは、先にふれたようにあまり知られていないことが一つの理由だが、もう一つ、収録された『夜警』という作品に衝撃を受けたからである。
『夜警』は、震災時に暴走して問題行動を起こした自警団を描いている。
『夜警』は、次のように書き出されている。
丁度大地震があつてから三日目の晩である。私は寸暇を偸んで、避難していつた先の或家の門の処に戸板を敷いて、そのうへで夜露に打たれながら肱枕をしたまゝ寝てゐると、もう午前二時頃とも思しい真夜半に、忽如夜陰を衝いて恐ろしい叫び声が聞える。初めのうちはうつらうつらとしてゐたので、何を叫んでゐるのだかよく言葉は聞えなかつたが、漸次と近づいて来るその声を聞くと、何んでも、男の方は皆武装して角へ集つて呉れと触れ廻つてゐるのである。
自警団は自発的に構成されたのではなく、9月2日に内務省警保局から自衛するようにとの旨の指令が出されている。
そのことは、上記に続く記述から推定できる。
その日の夕方の申合はせに依ると、萎靡した警察力には信頼が出来ないといふ處から十二時から先はその町の人々が交代に夜警に出ることになつてゐて、もし何か異変のある場合には、歩哨に立つてゐるものから急報するから、皆一斉に武器を執つて、指定の場所へ集合して呉れといふことになつてゐたのであつた。
そこで、「私」は「用意の軍刀」を腰につって町の角に向かった。
集合を呼びかけている声の主は、夜警をするようになって知り合った大学生で、彼は次のように説明した。
「やあ、よく起きて下さいました。どうか大至急に彼処の坂の角のところへ被来つて下さい。今実は下の橋の方から急報がありまして、その、怪しいものが十人程拳銃と凶器をもつて潜入して来たさうですから、我々も至急に警備に就かなけりやなりませんから・・・・」
大正8年1月1日発行の雑誌『文章世界』(第14巻第1号、博文館)には、文学者たちの住所が記されているが、長田幹彦の住所は「麹町区飯田町三ノ二二」となっている。震災当時も同じであったかは確認できていない。
また、わずかながら、人から聞いたことを一人称で記しているという可能性もある。
大学生の説明を聞いて、「私」は胸の高鳴りをおぼえる。
私はそれを聞くと、俄かに胸が高鳴るのを覚えた。平常なら少くとも不気味な心持ちがして、幾分なりとも恐怖の念に襲はれる筈であるのに、もう私は大地震以来、連日の不眠と極度の興奮とで精神が異常な変調を呈してゐるので、却つて残忍な、野獣のやうな狂暴性ばかりが無上に突き上げて来る。斬らば斬れ、殺さば殺せといふやうな絶望的な無謀さも手伝つて、全くの処節制なぞといふものは薬にし度くもなかつた。
ここは大事なところで、「野獣のやうな凶暴性」が震災という異常事態におかれている自分に生まれてくることを記している。
「平常」ならありえない心情がわいてきて、暴走する準備ができたのである。異常なことに加担してしまう危うさがとらえられている。
「私」が坂の角につくと、もう何人かが来ていて、団長格の「某製麻会社の重役」に、避難してきた女性があつまっているテントを守護してほしいと依頼される。
樹林の奥をすぎて畑の中にあるテントにつくと、子ども、老人は横になっているが、女たちはうずくまって押し黙っている。
日本橋方面の住民で、炎を避けて逃げてきたのである。
「私」は「まるで昔の騎士のやうな子供じみた勇敢さを胸一杯に感じてゐた」。
テントの守備について「私」は裏の方で「怪しい物音」がするのに気がつく。
「私」は抜き放った軍刀をもって、音のする方へ向かう。
「白い浴衣を着た人影」がとらえられるが、それはひとりの老婆であった。老婆は飯びつを脇に置いて草むらをかきおこしていた。
「私」はその老婆が、昼間、炊き出しの配給があった時に、よくばって玄米のむすびをひとりで9個も手にして顰蹙をかったことを思い出す。
老婆は玄米のむすびを食べかねてそれを捨てているのであった。
「私」は飢えているものがいる中での老婆の振る舞いに腹が立って、「憤怒のあまりに有無を云はさずその老婆を刀の峰で殴ろうとした」。
しかしその時、銃声がして、「私」は刀の峰で老婆を殴らずにすんだ。
その時、向ふの樹林の中で突如に物凄い銃声が六発ほど続けざまに夜陰を劈いて響き渡つた。それと同時に、阪の下の方でもわあッと鬨の声が聞えて、四辺は俄かに騒然とした殺気を帯びて来た。私はもうそれどころではなくなつて、一斉にどよめき立つ天幕の中の女達を制しながら、自分も白刃を提げて銃撃の聞えた真暗な樹林の方へ走つていつた。樹林の底では怪しい者を追跡するのか、たつた一つ提灯の火が人魂のやうにちろちろ動いてゐた。
4 加担してしまうことの恐ろしさ
「私」がじっさいに軍刀を使う場面は描かれずに『夜警』1編は閉じられている。それが創作的な配慮であるのかどうかはわからない。
最後の騒ぎの結果についても記されていない。
これは純粋なドキュメントなのか、脚色が加えられた創作的部分があるのかもわからない。
冒頭の「小序」で長田は次のように記している。
本書に収むる処の作品は匆々の際とて推敲に推敲を重ねた純一なる芸術品でな
いことは論を俟たない。和田氏の嘱に応じて、災後第七日から急遽筆を起して僅か三週日の間に稿を了へたものであることは前以つてお断りをして置かねばならぬ。従つて作品の価値なぞは固より云為さるべきものではないと思ふが、併し少くとも稀代の災禍に当面し、又親しく実地に臨んで自ら探り得た題材に依つて筆を執つたものであるから、少くとも当時の実況を幾分たりとも如実に描破し得たものと信じてゐる。
「実地に臨んで自ら探り得た題材に依つて筆を執つた」という部分は、自身の体験だけではなく、取材によって得た他者の経験をも含むことを示唆している。収録作品には聞き書きに基づくものも多い。
『夜警』では、襲撃してきた者が誰であったのかは明確に示されていない。また、人々が流言に動かされていたのではないかという懐疑も示されていない。
ただ、ある状況の中では、人は残虐な行為に加担する可能性があることを、『夜警』は示している。
『夜警』を読んで想起したのは、クリストファー・R・ブラウニングの『増補 普通の人びと』(谷喬生訳、2019年5月、ちくま学芸文庫)という本である。
一般市民から構成された第101警察予備大隊はポーランドでユダヤ人殺害を行った。最終章の「18 普通の人びと」では、どうしてごく普通の人びとが虐殺者となっていくかについての研究者たちの議論が総括されている。
そこで紹介されているエルヴィン・ストーブという研究者の「特定の環境の下では、ほとんどの人が過激な暴力を行使し、人間生活を破壊する可能性をもつ」という認識はとても重い。
【編集履歴】目次つけ忘れたので追加した。
*ご一読くださりありがとうございました。
