
【ふなログ745】1週間前に富士登山。登頂ならずとも九合目からのご来光。
■
7/12(金)〜7/13(土)にかけて、
今年2回目の富士登山を楽しんできました。
ガイドさんを含む20人近くの仲間、今回は小学4年の長女と共にチャレンジしました。
ただ、今回は色々と思うところがあり、
なかなか言語化してまとめられないままでいます。
断片的になるかもしれません。それでも書いていきます。
■
今回私にとっては、
人生で16回目の富士登山でしたが、
今回、登頂を叶えることはできませんでした。
■
こういう書き方をして良いかも迷いましたが、
私個人としては、余程のアクシデントが無ければ
「ほぼ登頂出来るだろう」
という安心感と慢心もあったのも事実です。
■
実際、今回八合目で宿泊する前は
ウェアの中に雨水が浸水する程の土砂降りの悪天候。
しかし、
これよりも酷い天候に遭遇したことは過去数回ありました。
暴風雨と雷雨を伴い、
生きた心地せず、山小屋に転がり込んで登頂を断念したこともありました。
■
そのため、
「私個人が登頂する」だけの観点であれば、
嫌な言い方を承知の上ならば、
今回の悪天候は想定内で、ほとんど感情も動かなかったんです。
濡らしては困る衣服やタオルは、
インナーバッグに入れて濡らさないでおいたので、
着替えを濡らさずに済みました。
■
ただし、です。
一緒に連れてきた長女について、寒さ対策の配慮が行き届いていなかった。
子供は大人に比べて、体力的に保温が難しく
「身体の冷えからの回復が弱い」ということが頭になく、
身体が冷えた時に備えるための重ね着を、多く用意していませんでした。
■
そのため、9合目の手前でご来光を観測後、下山という選択を。


身体が急激に冷えて体力が落ちた娘と共に、
速やかに下山を選択せざるを得ませんでした。
■
一方で、ここまで共に登った仲間は皆、登頂を叶えました。
本当に素晴らしかった。
自身としては今回、登頂ならず。
9号目から5号目まで無事に下山して娘の体調も戻り、安全に帰還できました。


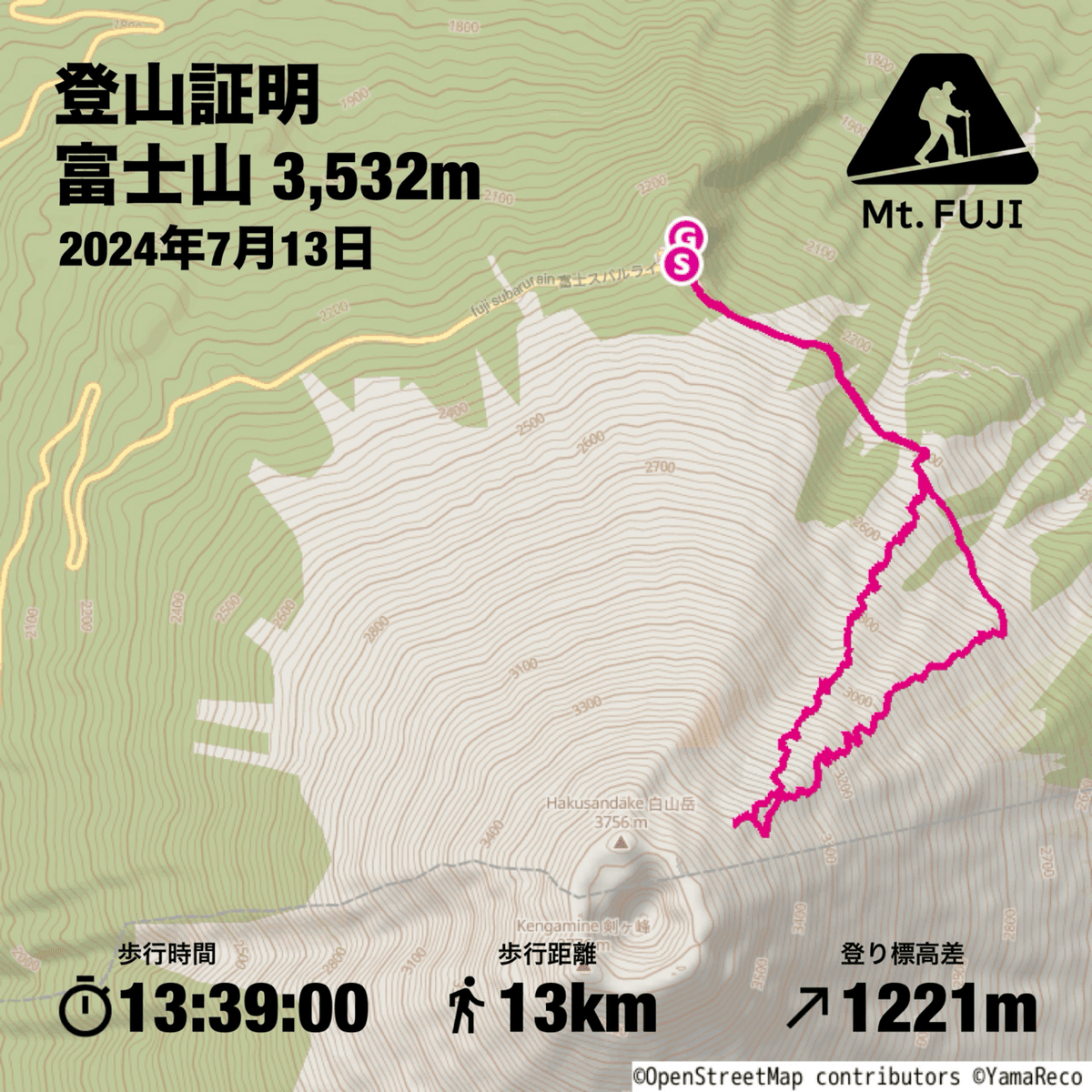
■
我々と共に的確な助言と共に下山してくださった
ガイドさんには、感謝しかありません。
助言だけでなく、登頂を断念した娘を元気付けるような
雰囲気を作ってくださったり、とても素晴らしいガイドでした。
「赤富士と紅富士の違い」の話は、帰宅後に娘は妻に嬉しそうに話してました。
■
「登山しているからと言って、経験者とは言えない」
とも、ガイドさんには仰って頂きました。
あらゆることを想定して準備し、
必要なことがあれば、周りの力を借りたり相談することも必要。
PDCAも回していく必要があります。
■
単独行ではなく、
人を伴う、または集団戦というのは、
自分以外の人のことを考え、命や心を支え合う必要があります。
「自分のことだけで精一杯」
それが人の実相なのかもしれません。
ただし、そこを敢えて、他者に思いをいたす。
時には命を預かり、元気を分け与えるからこそ、
楽しく力強く前進できる。
■
思えば、仕事もそうですね。
自分のことだけでなく、関わる人の状態や状況を知り、
働きかけるからこそ、大きな価値が生まれてくる。
■
しかし、一番感じたのは、
こうして色々と、自然の厳しさや苦難を乗り越えた後の
雲海を望む景色や、ご来光を拝むことができる感動です。
そして同時に、何よりも安全に下山できて、
日常生活に戻った後の、日常生活の有り難さです。
■
「生きていてよかったな」と。
娘もよく頑張った。
悔しかったようなので、また来月登ることにします(笑)
■
今回学んだことを、最後にまとめます。
登山するからには、いかなる天候にも耐えられる準備をするべし(それ以外は極限までカットする)
同行者がいる場合、お互いに声を掛け合って登る。声を掛ける側も声をかけられる側も、力が湧いてくる。「声で支える、押す」ということ
ただ経験しているだけではダメ。あらゆることを想定して準備する。周りにも配慮する。相談する
登頂することも大事だが、安全に下山するところまでが登山。そこまで考えて準備する
正しい姿勢、深呼吸は大切
苦しい、ということは「生きている証拠」
■
それでは、
今日も素敵な1日をお過ごしください。
