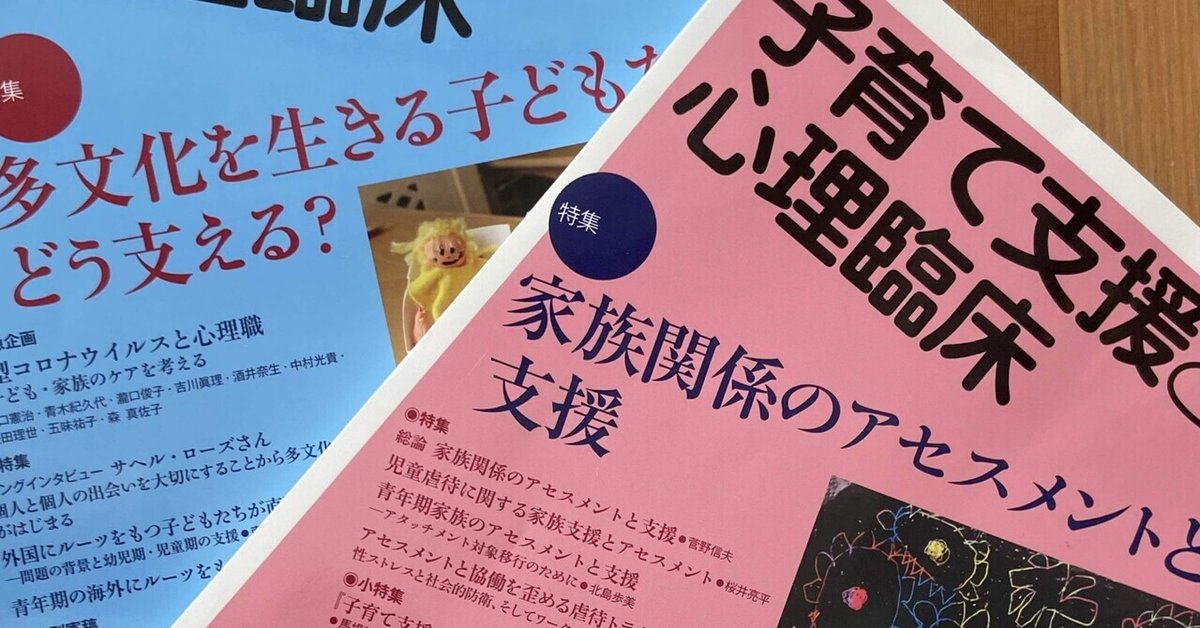
アピアランス〈外見〉問題は移行期に悪化しやすい(『子育て支援と心理臨床』より②)
子育て支援に関わる人々の協働をめざし、心理臨床の立場から子育て支援の取り組みと可能性を発信する雑誌『子育て支援と心理臨床』が、年1回小社から刊行されています。各号では子育てに関わる様々なテーマを特集してきましたが、そのほかにもエッセイや連載などで多角的な視点から子育ち・子育てを考える記事を掲載しています。 このコーナーでは、そのなかから特に人気の記事・連載を紹介していきます。
前回に引き続き、医師の原田輝一さんによるアピアランス〈外見〉問題に関する連載を掲載します。
現代社会において、人の健康や幸福と深く関連する外見(アピアランス)。病気や外傷により外見に不安や困難を抱える人々に、どのような心理社会的支援を行っていけるのでしょうか。
原田輝一さんは、医師として治療に携わりながら、新興の学術分野である「アピアランス〈外見〉問題」の最新の研究成果を紹介し、その学術的知見と技術の導入をめざしています。本連載では、アピアランス〈外見〉問題の概要や、それに対処するための研究とケア開発の歴史について、事例を交えながら紹介していただいています。
*下記の内容は、『子育て支援と心理臨床vol.17』から転載したものです。『子育て支援と心理臨床』の詳細はこちらをご覧ください。
* * *
当直室の電話が鳴った。眠い目をこすりつつ、壁掛け時計は午前2時前を指していた。夜間当直の事務員から、私宛の電話だが受けるかと聞いてきた。眠気で頭はハッキリとしなかったが、とにかく電話を受けることにした。受話器から聞こえてくる声で、それが誰なのかすぐにわかった。ちょうど1年前、ケンカで下顎骨骨折を受傷して入院したことがある青年からだった。
もともと情緒不安定なところが多かった彼だが、その夜、以前にも増して調子の悪いことが聴いてとれた。言葉は途切れ途切れでうまく会話にならず、その声は苦しそうにも眠そうにも聞こえた。言葉を重ねても、その青年が何を話そうとしているのかつかめなかった。
私は徐々に焦りはじめた。ともかく彼は今、大きな混乱の中にいることだけは明らかだ。何か伝えようとしているのに、それをうまく言葉にできない。そして、私はそれを聴き出すことができない。よくない予感が、私の心の中で膨らんでいった。
「どうしたの? 何でも言ってごらん?」
断片的な言葉しか返ってこない。
「お父さんはどうしたの? 一緒か?」
何か言おうとしているのだが、うまく聞きとれない。
「今どうしているの?」
「……」
深いため息だけがわかった。やがて話もまとまらないまま、青年は小さな声で礼を言って、一方的に電話を切った。一瞬、私は夢を見ていたのだろうかと疑いながら、電子音を発するだけの受話器をしばらく見つめていた。それを置いたとたんに部屋から雑音が消え去り、静かな雨の音が、窓の外から心の中に染み込んできた。まだまだ寒い早春の夜の雨であった。
アピアランス〈外見〉問題と移行期
アピアランス〈外見〉問題について、前回のエッセイで紹介させていただいた。実はそうした問題は、今や多くの人にとって重大かつ深刻なテーマになっている。外見に障害がある人にも、ない人にも、現代社会は大きな影響を与え続けている。前回のエッセイでは、外見の障害が原因となって適応障害をきたしている人たちについて、理解・介入・包括的ケアについて述べた。
そうした青年において、成人期に至るまでの移行期で段階的に生じる問題は、特に重大である。一言でいえば、小児診療から成人診療への移行がうまくいかず、診療治療忌避が生じうることである。その結果、避けられたはずの合併症や予後の不良が発生する。特に健康上の問題がない場合でも、青年期は自分に対する感受性が高まるため、アピアランス〈外見〉問題を核としてネガティブなスキーマが形成されてしまい、同様に深刻な心理社会的問題が移行期に生じる。当然、家族関係も大きな影響を受ける。いくつかの研究によると、自尊感情のレベルに影響を及ぼす要因のうち、外見が一番強い影響力を持っていたという。小児期にはよくわからなかったことでも、青年期が近づくと、自分の違いに敏感になりはじめる。障害がない人であっても、体重・体型・身体的特徴・性的魅力には、多くの青年が気を奪われるようになる。
高いレベルで外見を賛美する文化的圧力は、多くの青年に圧力を加える。そして青年の中で、脆弱なグループは外見への不安を不必要に高めてしまうのである。加えて、少年少女期から凝視・不躾な質問・いじめ・排除を実際に経験することで、ネガティブなスキーマが抗いがたく身についてしまうことも多い。恋愛問題も深刻に影響する。
深夜、私に電話をかけてきた青年は、乳児期に口蓋裂の手術を受けていた。口蓋部は口腔内である。つまりこの青年の場合、顔の表面には、先天性の状態の特徴は認められなかった。しかしながら、若干の上顎骨の低成長が認められるため、顔全体として見た時には、目つきがやや鋭く、口元には不満があるかのような印象を他人に抱かせうる。しかし臨床家である私にも、彼の既往歴を知っていればこそ分かる程度であり、何ら情報がなければ、ごく普通の正常範囲内の顔貌と判断していただろう。つまり、客観的には正常範囲内だったのである。しかし、彼にそのことが大きく影響していた可能性は否定できない。手術後、しばらく母親に連れられて言語療法外来に通っていたのだが、いつの日からか、受診を呼びかけても来なくなっていた。
*****
深夜の電話から遡ること1年前、ケンカで下顎骨を骨折していた彼の、私は主治医だった。手術が望ましい骨折であったが、その前処置として顎間固定を行うことを説明した。顎間固定とは、上顎歯列と下顎歯列のそれぞれに細いプレートを取り付ける。歯とプレートを、細い金属のワイヤーで固定していく。プレートには小さなフックが付いていて、そこにワイヤーや輪ゴムをかけて、上下顎を最適のかみ合わせができる位置で固定する。
その説明をしている時からソワソワしていることが気になったが、いよいよ顎間固定をはじめようという段階になって暴れはじめ、拒否するようになった。想像するだけでも分かることだが、この顎間固定という状態は、確かにストレスが大きい。なにせ口が開けられないのだから。しかし、彼の恐怖をまじえた拒否の仕草の中には、彼特有の理由があるようにも感じた。
仕方なく、説得のために親を呼ぶことにした。夜になって訪れた父親は、仕事に使う小さめのセカンドバックを手にしていた。髪型も少しラフな服装も、それなりに流行を意識しているようだった。父から、いくつかのエピソードがわかった。本人が幼い頃に両親が離婚し、ずっと父親に育てられてきた。中学生頃から情緒不安定になり、家で暴れることはなかったものの、学校でよくケンカをするようになった。高校になってその傾向はさらに強まり、現在は登校していない。街で初対面の相手と衝突することも多くなり、今回の受傷もそうしたケンカが原因であった。
父親は彼に言った。
「親としてできることはもう限界だ。自分のことは自分で責任を持ってくれ」
目をつぶったまま黙って聞いている彼は、神経質そうに固まっている。しかし、その押し殺した表情の背後には、様々な感情の混乱が見て取れる。
結局、顎間固定はあきらめ、テーピングで固定・矯正することにした。首の位置への制限、開口運動に関する制限について説明した。落ち着きのない行動をよくとってしまう彼は、あまりうまく指示を守れなかった。しかし幸い、骨折部が大きく離解していくことはなかった。痛みが引いて、咬合状態の悪化がないことを確認して、退院してもらった。しかしその後、外来診察の予約日にも彼は来なかった。
承認への「渇望」とケアの「欠乏」
危機的状況にある青年のニーズを掘り起こし、ケアの提供や継続を欠かさないことが重要なのだが、そう簡単には事態は解決しない。家庭には様々な問題が潜在していることがある。たとえば小児期に罹患した外傷や疾患、あるいは先天性の状態(口唇口蓋裂など)がある場合、患児が物心つくその前の段階から、家庭内に大きな葛藤が生じている。そうした家庭の離婚率などはきちんとした統計として出されていないが、おそらく高いことは想像に難くない。どちらかが養育している場合もあるが、両親が育児放棄する場合もあり、子が施設収容されるケースもある。子の成長にとっても危機の連続だが、親にとっても試練の連続を越えていかねばならない。
子にとって、一つひとつの葛藤は独立した問題であっても、アピアランス〈外見〉問題の心理的特性として、それが核となってネガティブなできごとに関する記憶を吸い寄せて、巨大で堅牢なネガティブ・スキーマを形成しやすい。それが移行期に、予想外の悪影響を及ぼす。その時点で慣れ親しんでいる周囲環境は、たとえそれが小さな場であったとしても、子にとっての承認要求を満たしてくれる世界であろう。移行期はその承認を、受けられる保障のないものにしてしまう。さらに新しい世界では、否定や拒否を受けるかもしれないと、恐怖を感じてしまうかもしれない。
そんな青年にとって成人ケア(診療)への移行は敷居が高く、適応しにくい。成人サービスにおいては自立と自己管理が求められるが、こうしたことに慣れていない本人や家族にとっては、すべてが戸惑いの対象となりうる。ケアは与えられるものではなく、自ら引き出していかねばならないものとなるが、この点に「捨てられた」と感じてしまうことも多い。
青年は、自分の問題に正面から向き合うことに、抵抗感を持ちやすい。また、学校などと医療機関の診療時間が重複していることも、診療忌避を助長しやすい。さらには医療現場にも問題がある。もともと移行期の問題は、克服すべき問題として焦点が当てられていなかった。そのため医療スタッフにとってもモチベーションが上がらず、それをカバーする専門的技術も意識されることがなかった。小児期の治療技術の進歩に、成人期サービスのスタッフの知識が追いついていない点も、移行期問題への対応が抜けてしまう大きな原因となる。
様々なことが原因となり、重大な不都合が見逃されやすくなっている。病院によっては院内ケースワーカーがいるとか、担当の臨床心理士や精神科医にカウンセリングをお願いするとか、なにがしかの方法はある。しかし、移行期の先にある治療・ケア・サービスに対して、青年や親から求めようというモチベーションが働かないまま、問題が宙に浮いてしまっていることが多い。
*****
深夜の電話から1年余り経ったころ、今度は父親から電話があり、その青年の訃報を知らされた。以前の退院後、じきに親元を離れ、遠方で住み込みで働きはじめたという。そんな彼には、荷物は少ししかなかったそうだ。その中に、私宛の手紙があったので渡したいが、どちらに送ればよいかとのことだった。ちょっと考えた私は、葬儀に参列させていただき、その際に受け取りたいと返事をした。
仕事を抜けて葬儀に向ったが、あいにくの曇天の午後。少し生暖かい風に、かすかに小雨が混じりはじめていた。葬儀に参列したが、参列者は10
名ほどだった。見覚えのあった父親に挨拶し、彼が残していた手紙を受け取った。父親の後ろには、後妻とおぼしき喪服の女性がひっそりと立っていた。
「亡くなる前日から行方不明になっていたそうですが、次の日の朝、睡眠薬を大量に飲んで河原で死んでいるのが発見されたそうです」
警察の検死では特に事件をうかがわせる状況ではなかったという。薬を飲み過ぎて寒い河原で眠ってしまったのか、自殺する気だったのかは、結局わからなかったという。
私は受け取った手紙を開けてみた。それは書きかけの手紙だった。混乱した苦しい心の動きが、断片的に記されていた。
「うまく書こうとしても、頭が混乱してそうできない」
「話を聞いてくれてありがとう。あのとき、気持ちが少し楽になった」
「もう少し頭の中がスッキリしたら、診察を受けに行きます」
未完の手紙。投函されなかった手紙。彼は助けを必要としていた。しかし、それを求めることができない自分になってしまっていた。激しい葛藤に、身動きができなくなってしまっていた。
私はその手紙を内ポケットにしまおうとしたが、ふと思いつき、棺の中の、彼の顔のすぐ傍に置いてやった。
出棺後、最後の挨拶の時に、父親は苦しい心情を打ち明けた。
「どうしてなんでしょうか? 私は賢明にやって来たつもりなんです。どうして伝わらなかったんだろうか、何が間違っていたんだろうかと、心が締め付けられるのです」
私は躊躇しながらも、何か言葉をかけねばと思った。
「父親として、頑張ってこられたのだと思います。こうした結果には、いろいろな偶然がからんでいるものだと思います。もしも答えが出ないものであるなら、これ以上苦しむのはよくありません。彼自身も、お父さんにはそんなことを望まないでしょう。お気を落とさず供養してあげてください」
そうは言ったものの、何が足りなかったんだろう、何が次のスタートを邪魔し続けたのだろう、私やスタッフにできることは本当に何もなかったのだろうか、と反芻せずにはおられなかった。
その夜、すぐに寝付けそうもないので、窓を少し開けて雨の音を聞いた。ずっと続く雨音を聞きながら、一粒ごとの雨音が心に染み込んでくるようだった。空に昇っていって、やっと気がついて、しまったと思って、何か言おうとして、雨と一緒に戻ろうとしているかのような気がした。私はその雨音に、ずっと耳を澄ませていた。外気にはかすかな温もりがあり、本格的な春の訪れが近いことを報せていた。
原田輝一
医療・社会福祉法人生登会医師。急性期~回復期~社会適応期にわたる長期罹患患者において、一貫した心理社会的支援の重要性を認識してきた(特に重症熱傷領域において)。現在は医療福祉連携の全般で、最新の学際的知見と技術の導入を目指している。【主な著書】ジェームズ・パートリッジ著『もっと出会いを素晴らしく:チェンジング・フェイスによる外見問題の克服』(翻訳 春恒社 2013)、ニコラ・ラムゼイ著『アピアランス〈外見〉の心理学』(翻訳 2017)『アピアランス〈外見〉問題と包括的ケア構築の試み』(編著 2018)『アピアランス〈外見〉問題介入への認知行動療法』(翻訳 2018)いずれも福村出版。
