
TPN(中心静脈栄養) 意外と知らないこんなことやっていた! 病院薬剤師業務💉 ①
TPNってご存じですか??
total parenteral nutritionの略であり、直訳すると完全静脈栄養・・・
全然パットしないですよね。
病院では口から食事がとれない患者、また経鼻胃管などチューブで胃や腸に栄養を入れても、そもそも腸が働いていないから栄養が吸収されないなど様々な問題で血管(静脈)から直接栄養を入れる方法があります。
ではその栄養とは何か。主に炭水化物(ブドウ糖)、タンパク質(アミノ酸)、他ビタミン、ミネラルです。ちなみに脂質は分離するので混ぜたりはしません。
また静脈から直接投与する場合、消化管を介さないため消化されません。なので基本的には最終分解されたものを投与します。
(炭水化物→多糖→二糖→単糖【ブドウ糖】)
これらを投与する時に問題となるのが点滴の濃さです。脱水などにもちいられる維持液などでもブドウ糖などが入っていますが、維持液では1日に必要な栄養は補いきれません。
そのため点滴で完全に栄養を補うにはブドウ糖やアミノ酸がたくさん入った濃い点滴が必要になります。
濃い点滴を普段しているような手の静脈から投与したらどうなるでしょうか?
詳しく言うと濃い濃度の点滴を投与すると濃い液は外から水を引っ張る性質(浸透圧)があります。すると血管の外から血管の中に水を引っ張る強い力が働きます。それが続くと血管が耐えられず、血管炎や静脈炎を引き起こしてしまうのです。
簡単に言うと濃い点滴を入れると血管が耐えられません。
そこで登場するのが中心静脈です。わかりやすく言えば太い血管です。
ここから投与することで血管炎などのリスクを極端に下げることができます。これは濃い液を投与しても血流が早く、血液も多いためです。
さて長々とお話ししましたが、一度ここでまとめると・・・
TPNとは中心静脈栄養の略で、経口で栄養が取れない患者に点滴で栄養を入れる手法です。そして上腕などの細い血管ではなく、太い血管を使って投与する手法です。
ではここにいったい薬剤師がどう関与するのでしょうか?
実はこのTPNには問題が他にもあります。それは次のどれでしょうか?
1.非常に高価(点滴が1日数万する)
2.ばい菌が繁殖しやすい
3.配合変化が起きやすい
4.濃すぎてブドウ糖が結晶化してしまう
さてどれでしょうか?
正解はばい菌が繁殖しやすいです。
簡単でしたかね。
ちなみにですが、1の高価は、1日数千円はしますが、数万円と行くことはほとんどないでしょう。3の配合変化が起きやすいは、点滴の内容にもよりますが、点滴の量が多いので比較的配合変化は起こりにくいと思われます。最後に4の結晶化してしまうですが、今のところそう言ったことは聞いたことがありません。
TPNは基本的に高カロリー輸液とも呼ばれるほどカロリーが高く、ばい菌にとっては最高の環境といえるでしょう。ほんの少しのばい菌が入ることで1つの菌が倍、倍になった菌が倍に、倍になった菌がさらに倍にと指数関数的に菌が増殖してしまいます。
高カロリー輸液にはすでにブドウ糖・アミノ酸・ビタミン・ミネラルがすべて入って完成した輸液も存在しますが、中には患者さんに合わせて各製剤を混ぜ合わせます。この時に菌が混入すれば大変なことになります。
この時に活躍するのが薬剤師です。
病院の薬剤部には無菌室と呼ばれる部屋があります。この部屋の中にはクリーンベンチと呼ばれる作業台があります。
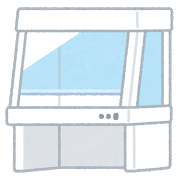
このクリーンベンチは中から外に空気が出ていて、中が陽圧になっており、菌が中に入らないようになっています。
この中で高カロリー輸液を調製することで菌が混入することを防ぐことができます。
これを調製するのが薬剤師のお仕事というわけです。
今回は回りくどくなってしまいましたが、次回は準備やクリーンベンチ内の操作などを説明していきたいと思います。
ではまた!
もしお役に立っていれば、【好き】、【フォロー】していただけると今後の頑張りになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
いいなと思ったら応援しよう!

