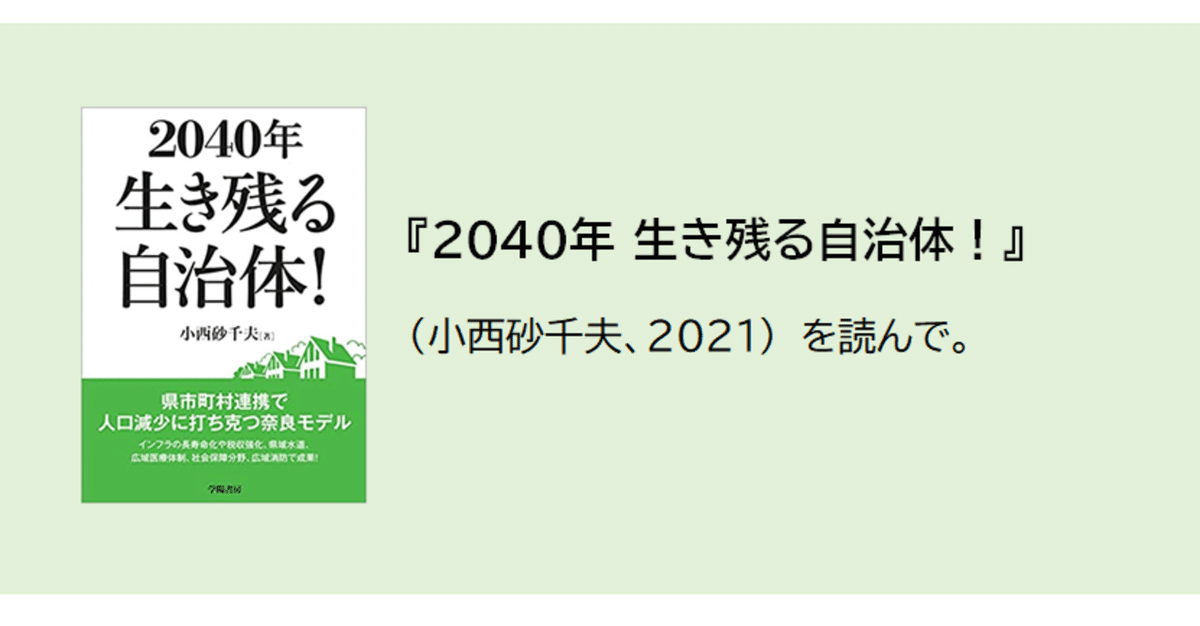
【書評】『2040年 生き残る自治体!』(小西砂千夫、2021)を読んで。
▮ 読後感
「官民共創」は社会課題や地域課題を解決できる概念だと思うのですが、議員時代にその失敗事例をたくさん見てきたので、「本当にそうなのか?」という懐疑心がずっとあって、自分なりに納得できる解を見つけるためにプロジェクトマネジメントや書籍での知見を積極的に学ぼうと心がけています。何が成功要因で何が失敗要因なのか。ある程度頭の中も整理できつつあるので、また文章にまとめられればと思っています。
著者は地方財政の専門家。地方議員をやっているときに幾つか書籍を読んだことがあります。本書は地方財政から少し離れて地方自治体の事務やガバナンスに目を向けた本です。
官民共創で意外に盲点なのが、自治体間連携による「官」が担当できる領域の拡大です。本書ではPPPP(パブリック・パブリック・プライベート・パートナーシップ)として奈良モデルの紹介がなされています。奈良県の取り組みは著者も書いてられるように特殊なのかもしれません。ただ、広域自治体である「都道府県」を巻き込んだ官民共創を頭の片隅に入れておかないと、薄い議論になってしまうかもと思いました。
▮ 注目した個所(抜粋)
●従来から地方自治法で認められている共同処理の仕組みである一部事務組合、広域連合のほか、協議会(管理執行)、機関等の共同設置、事務の委託を併せて、さまざまな手法を通じて広域連携を実現することが可能となった。このようにして、整えられた制度をいかに活用するかの段階に入っている。
(p28)
●実際に、地方自治法に基づく市町村事務の代行に期待する声は、小規模市町村から大きいにもかかわらず、代行する都道府県も事務の実施責任を負うことになり、市町村にしかない事務について必ずしもノウハウが蓄積されているとは限らないことから、取り組み事例はそれほどの広がりは見せていない。その一方で、奈良県や高知県では、かたちにとらわれず、県が持つ経営資源を活用して都道府県と市町村による一体的なサービス提供体制の構築をめざしており、そちらの取り組みの方が活性化している傾向がある。
(p38)
●奈良モデルとは、市町村合併が進まなかった県として、県が斡旋するかたちで市町村間の水平連携を促すことと、県による市町村行政への直接補完の両方を、さまざまな手法を駆使して、実現していくかたちである。その具体的な姿を見ると、県と市町村のあるべき姿を飛び越えた総力戦という表現がしっくりくる。
(p58)
●「・・・今後「奈良モデル」の効果を一層上げていくには、PPPの推進も念頭に、県(Public)と市町村(Public)に民間の活力(Private)を加えた連携・協働(Partnership)の形、いわば「パブリック・パブリック・プライベート・パートナーシップ(PPPP)」により、取組を展開してくことも期待される」として、PPPの考え方を奈良モデルに取り込む必要性を強調している。
(p89)
●「議員がお述べのとおり、奈良が埋没するのではないかという懸念は、当然あるものと考えております。明治時代の例で恐縮ですが、かつて明治九年、奈良県が堺県と合併し、さらに明治十四年、大阪府と合併したことがございました。その際、明治十八年に大変な災害が起こりましたが、その復旧予算が奈良地域にほとんど配分されなかったことから、合併解消の運動が起こり、明治二十年に奈良県が再設置されたという歴史も思い出されます。奈良県としては、県勢発展のため、県の立場、状況を踏まえて、オリジナルな戦略を進めていきたいと思います。関西広域連合の設立による成果がよく見えない、また懸念も予想される現時点では、設立当初からの参加は難しいと考えております。・・・」
(p102)
●中心都市があれば、合併という手法がありますが、南和が典型ですが、人口基準では十分、市になれても、ガバメントとして成り立たない。すると、テーマごとの広域連合とか、連携・協働が大切になって、そこに県が入らないと回らないという感じはします。
(p179)
●筆者の感覚では、「優良事例の横展開」という言葉は、あまり好きではない。優良事例は、簡単に横展開できるようなものではないからである。簡単に真似られる内容ならば、放っておいても浸透していくはずである。真の優良事例とは、どこかの自治体が苦労して考え、実践してきた内容であるはずだ。それが世間に認められ、評価されることはよいことだが、本当に値打ちがあるとすれば、それはおいそれとは真似られないはずだ。パイオニアと同じ苦労をしなければ身につかないからである。優良事例を紹介することはよいことである。それは自治体という「業界」における善政合戦を刺激するからである。しかし、広く普及する政策事例が、本当に価値のあるものとはいえないこともある。
(p207-208)
●副題にあげた、「奈良モデル」とは筆者の言葉でいえば「人口減少時代の県と市町村の総力戦」であって、その一つの具体的なかたちとして、今後も育っていってほしいと願っている。
(p208)
●〇・・・量的な補完ではなく、市町村共同のアウトソーシングを県が仲立ちするなどシンクタンク的な機能やコンサルティング機能を強化する方向性を考えている。
〇「奈良県・市長村長サミット」を開催することにより、改善案を政策に反映していくことによる市町村との信頼感の醸成や、データ分析等の県職員のスキル向上による県のシンクタンク機能の強化にもつながっている。
〇ただし、こうした方向に対しては、県が市町村に対しても金も口も出してしまうと、市町村に県に依存する意識や県との上下関係の意識が生じるのではないかとの懸念もある。
(p210)
▮ 目次
はじめに
第1部 人口減少時代の広域連携の選択肢
第1章 人口減少が進んだ2040年の姿が投げかける自治体の覚悟
第2章 人口減少と向き合う先進的取り組み
第3章 基礎自治体と都道府県の関係のあり方
第2部 2040年を先取りする奈良モデルの展開
第4章 奈良モデルはどのような経緯で形成されてきたか
第5章 道州制と関西広域連合への異論
第6章 原点としての道路インフラの長寿命化と市町村税の税収強化
第7章 県域水道のファシリティマネジメント
第8章 広域医療提供体制の再構築
第9章 社会保障分野における市町村との連携・協働
第10章 広域消防など「共同」の取り組み
第11章 知事、市町村長、県職員に聞く、奈良モデルを支えるもの
おわりに 君よ、知るや「奈良モデル」――全国の自治体は人口減少と向き合え
ーーーーー
◇プロフィール
藤井哲也(ふじい・てつや)
株式会社パブリックX 代表取締役/SOCIALX.inc 取締役共同創業者
1978年10月生まれ、滋賀県大津市出身の43歳。2003年に雇用労政問題に取り組むべく会社設立。2011年に政治行政領域に活動の幅を広げ、地方議員として地域課題・社会課題に取り組む。東京での政策ロビイング活動や地方自治体の政策立案コンサルティングを経て、2020年に京都で第二創業。京都大学公共政策大学院修了(MPP)。日本労務学会所属。議会マニフェスト大賞グランプリ受賞。グッドデザイン賞受賞。
◇問い合わせ先 tetsuyafujii@public-x.jp
