
六甲山中の巨大水車の大工業地帯
電気も蒸気機関もない時代、神戸の北に屏風のようにそびえる六甲山中に最先端技術を駆使した工業地帯があった。ここでつくられた産品は「日本一の酒処」である灘五郷や、江戸の照明をささえた搾油業、全国有数の素麺産地うみだした。その原動力は「水」。巨大水車の遺構は今もひっそり森のなかに息づいている。
山中に次々あらわれる「滝壺」と石臼

六甲山(931メートル)からわずか9キロで瀬戸内海にながれこむ住吉川を、JR住吉駅から3キロさかのぼった山のふもとに「五輛場」という案内板があった。谷間の山肌に5軒の水車小屋があった跡で、川沿いの廃屋は水車の管理棟だったという。
ちょっと上の、斜面に棚田のようにきざまれた平場にのぼると、石積みの壁でかこまれた幅1メートル超、深さ3メートル、長さ10メートル弱の溝がある。水車を設置した「滝壺」だ。山側から木製の樋(とい)で水を落とし、直径約5~6メートル、畳18枚分もある巨大水車をまわしていた。




標高差8~9メートルをのぼるごとにそんな「滝壺」があり、あちこちに四角や円筒形の石臼がころがる。石臼は六甲山でとれる花崗岩(御影石)でつくられた。四角い臼は杵でつく(胴搗)ためのもので、底にギザギザがある丸い臼は製粉につかわれたようだ。
本住吉神社(神戸市東灘区住吉宮町)境内の「住吉歴史資料館」には水車施設の模型がある。建物のまんなかに水車がすえられ、裏手の石垣の上から木製の樋で水車に水を落とした。水車の両脇には、米の精白につかう胴搗の臼や製粉につかう石臼がずらりとならんでいる。
「滝壺」の谷側には城郭のような石垣が積まれ、平場から約2メートル下に穴があいている。「滝壺」に落ちた水がここから排出され、さらに下の水車に樋でみちびかれていた。

江戸の照明をささえた菜種と綿の油
摂津(大阪府北部と兵庫県南東部)や河内(大阪府東部)では江戸中期以降は米作りより菜種や綿花の栽培がさかんだった。
与謝蕪村は1774年に「菜の花や月は東に日は西に」と詠み、「汽笛一声新橋を」で知られる鉄道唱歌の60番では「大阪いでて右左 菜種ならざる畑もなし 神崎川のながれのみ 浅葱(あさぎ)に行くぞ美しき」とうたわれた。摂津・河内の平野部は広大な菜種畑がひろがっていたことがわかる。
河内は日本一の綿花の産地でもあった。昔の日本人は主に麻布をまとっていたが、圧倒的にあたたかい木綿が江戸時代になると庶民にも普及する。綿花の畑に投入される金肥として、最初はイワシが、その後、蝦夷地からニシンがはこばれるようになった。
菜種や綿実(綿の実から綿毛をとりさった種子)からは油をしぼった。
寛永年間(1624~44)からボツボツ出現していた六甲山麓の水車は、享保年間(1716~36)には搾油につかわれはじめる。できた油の大半は人口100万人の江戸におくられ、明かりの燃料となった。六甲の水車は、蛍光灯に電気を供給する発電所のような役割をはたしていたのだ。
灘目の素麺は揖保乃糸の先生
搾油業につづいて、素麺の原料の小麦粉の製粉がさかんになる。
この地域の素麺は「灘目素麺」とよばれた。灘目とは、東は西宮市の武庫川から西は神戸市の旧生田川までの約24キロの地域の総称だ。日本の素麺の元祖とされる奈良の三輪素麺から技術を導入し、水車による製粉によって大産地にのしあがった。明治になると海外にも輸出され、1900年のパリ万博で表彰されている。
灘目には、播州・龍野の農民が出稼ぎにきていた。彼らが故郷に技術をつたえることで、龍野は「揖保乃糸」で知られる日本一の素麺産地に発展する。灘目の素麺は弟子である龍野に負けて日露戦争(1904)を境に衰退した。
先端技術の水車精白でつくられた「灘の酒」
この地域は六甲山の伏流水「灘の宮水」で知られる。酒の風味をそこねる鉄分が少なく、適度なミネラルが酵母の発酵をうながし,アルコール濃度が高く腐敗しにくい酒をつくるのに適していた。
古くからの酒の産地である内陸の伊丹(兵庫県)や池田(大阪府)周辺では、足で踏んで杵を上下にうごかして精米していたが、六甲山麓ではいちはやく水車精米を導入する。
地理学者の合田栄作が1941年に書いた論文によると、ひとつの巨大水車で、米の精白につかう胴搗の臼ならば40から130個をうごかした。さらに、足踏み式では精米歩合は92%程度だったが、水車では75~80%までけずることができ、端麗で辛口の酒は「灘の男酒」として高く評価された。
これらの酒は樽廻船によって江戸にはこばれる。灘五郷は江戸への「下り酒」の産地として、日本一の座にのぼりつめた。今も白鶴、大関、日本盛、菊正宗、剣菱、沢の鶴、白鹿、白鷹といった有名企業があり、全国の酒の4分の1をつくっている。
日本酒の水車精米は日露戦争後に最盛期をむかえる。80を超える水車小屋に計1万個の石臼がすえられ、各水車に十数人、全体で1000人もの人がはたらいていた。
酒米の精白作業は11月10日ごろから翌年2月20日ごろまで約100日間の季節労働で、播州などからの出稼ぎ労働者が昼夜交代で作業にあたった。各水車小屋は牛を3頭ほど所有し、住吉駅でおろされた米を牛車で運搬し、最後の山道は2俵ずつ牛の背にのせてはこんだ。
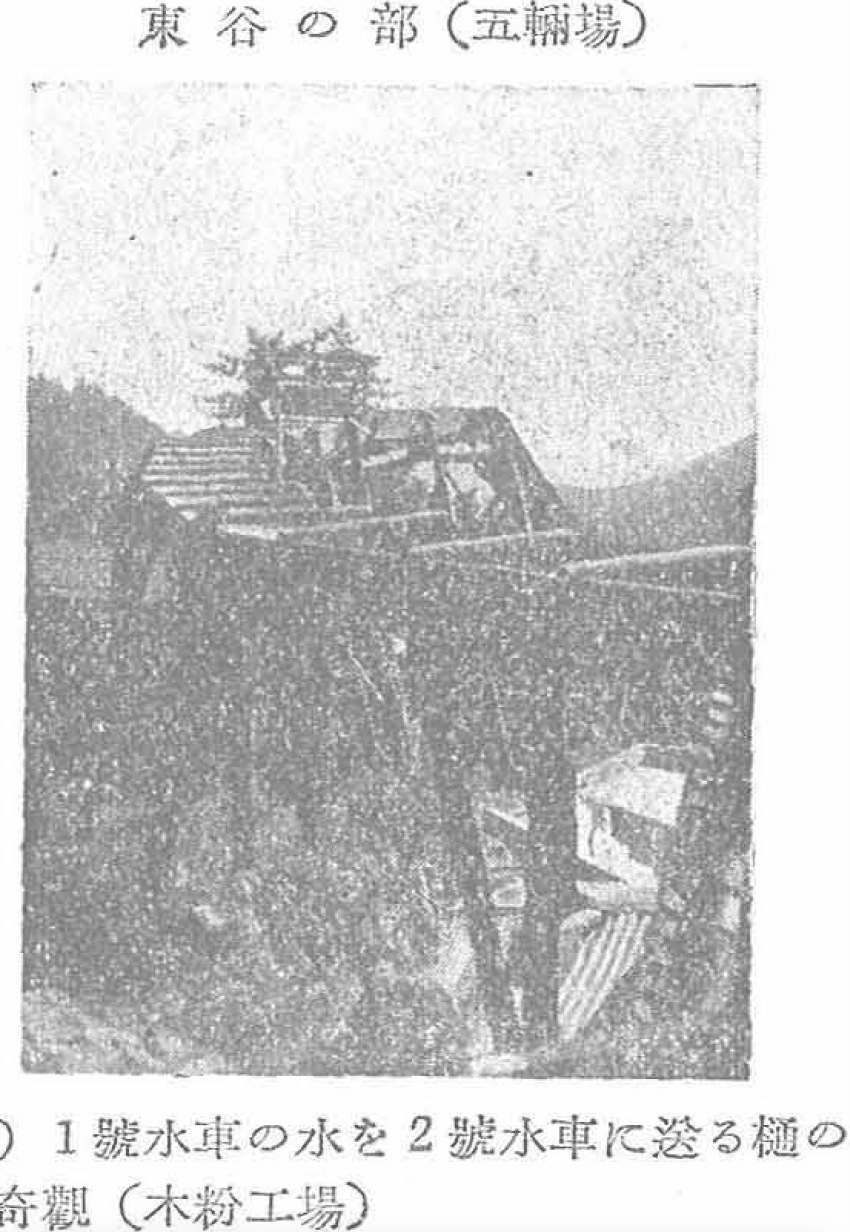
水車から水車へ空中回廊のように樋(とい)がはりめぐらされ、まさに工業地帯の様相だった。
だが1921(大正10)年ごろ発動機による精米がひろまると、水車精米は衰退し、1938年の阪神大水害で多くの水車が破壊された。
戦時の代替品づくりで一時復活
そのまま消えるとおもわれた水車は、戦争によって息を吹きかえす。
石油や金属が払底するなか、材木工場のノコギリ屑を石臼で微細な粉末にして、ベークライトなどの戦略物質や、食器や鋳物、歯車などさまざまな代用品に活用された。
前述の合田氏の論文によると、戦時中の1940年ごろ、住吉川沿いには20の水車が稼働していた。「労働者は半島人が多く、水車小屋の一部にある住宅に住んで、昼夜交代で一人ずつ働いている」などとしるされている。
戦後の復興がすすむにつれて水車は用済みとなる。
1979年、線香の粉をつくっていた最後の水車が火事で焼けて「水車工業地帯」は長い歴史の幕をとじた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
