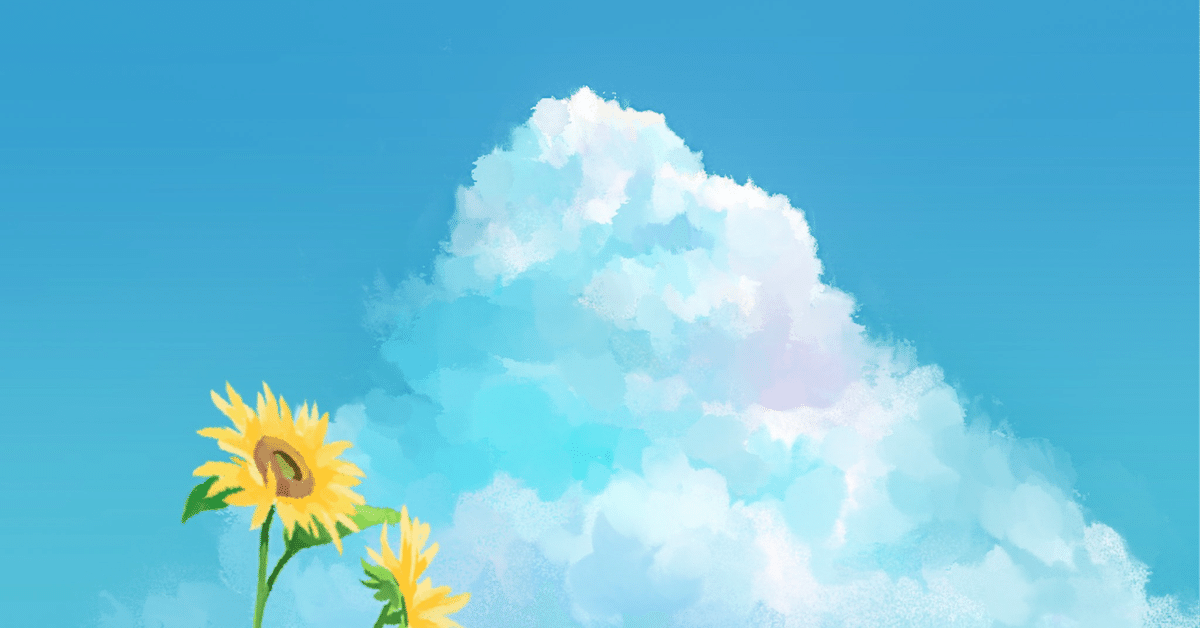
金曜の獏④(完)
その晩、僕はバクの夢を見た。
彼は突然真っ暗な僕の夢に現れ、神経質そうな足運びで近づいてきた。
「なんだ。女の子のすぐ横にも眠っているやつがいると思って来てみたら。何にもないな。すっからかんだ。」
彼は呆れたように呟いた。
僕はほとんど何も考えず、頭に浮かんだことをそのまま口にした。
「リリーの悪夢を、食ってやってくれないか。」
バクは僕を見とめ、物珍しそうな様子をした。
「絵本を読み聞かせるようになってからは少なくなったんだけど、リリーは、多希子さんや康則さんに置き去りにされる夢を毎晩のように見るみたいなんだ。その悪夢を、食ってあげてほしい。」
「嫌だね。子供の悪夢なんて、苦くて食えたものじゃない。」
「少しくらい、いいだろう。あなたは散々、リリーの夢を食っているそうじゃないか。」
「ちょっと端切れを味見しているだけだよ。」
バクは鬱陶しげにくるりと背を向けて、早足でどこかへ逃げていってしまった。
僕は取り残され、急にやりきれなくなり、呟いた。
あんな小さな子供にくらい、なんの憂いもなく眠れる夜をあげたっていいじゃないか。
「君がそれを願うことは、かえって傲慢ってものだよ。」
どこからか、バクの声が響いた。
翌日、普段は自分の部屋に戻って寝るのに、昨晩は莉々の隣であのまま眠ってしまった僕は、目を覚まして早々、莉々に夢のことを報告された。
なんでも、バクは僕の言ったようにお菓子の家をかじって穴をあけ、長くは居座らずにどこかへ行ってしまったという。無邪気に笑う莉々を見ていると、妙に恥ずかしくなって、僕は自分の夢のことを彼女に話せなかった。
昼間、莉々が学校に行っているとき、多希子さんから電話がかかってきた。莉々と話したくないのか、と訊ねると、彼女はそんなことはない、ただ自信がないのだと情けなさそうに笑っていた。
「母親として、あの子にどう接すればいいのかわからなくて、気がついたら病気にまでなっていてね。まったく、お姉ちゃんに神経質だと言われるのもわかるわ。こんなこと、みんな平気で乗り越えていくのに。本当に情けない。」
「莉々は、多希子さんのことを恋しがっていますよ。」
彼女はそれを聞くと、とても嬉しそう笑った。
学校から帰ってきた莉々には、お父さんもお母さんももうすぐ帰ってくる、と伝えておいた。
僕ははしゃぐ莉々を眺めながら、多希子さんがはぐらかすように言っていたことを考えた。
「急に莉々を預かることになって驚いたでしょう。ごめんね。あの人の妙なおせっかいなのよ。」
僕は、自分の部屋の、長い間ハンガーに掛けっぱなしになっている制服を見つめた。
「亮介くん。学校に行くの?」
「どうだろうね。」
莉々の頭に手を置いた。
「もうすぐ夏休みに入るからなぁ。」
今はまだいい。だが夏が終わったら検討してみよう。
おわり
