
【田辺朔郎】卒論が2兆円の超巨大プロジェクトに!~土木スーパースター列伝 #14
こんにちは、私はほぼ毎日鉄道の事を考えているドボジョです(*ドボジョとは土木女子のことです)。
今回は私の“最推し土木偉人”である田辺朔郎(たなべ さくろう)先生(=朔様)について、みなさんにご紹介するべく、土木の基本である「現地・現物・現人」の精神に則り、京都へ行ってまいりました。
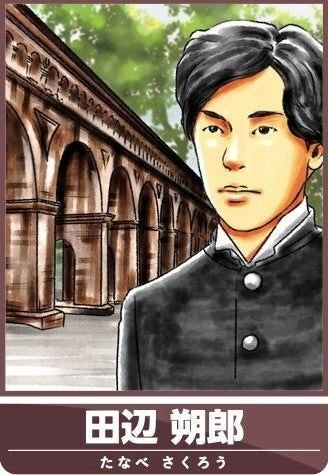
琵琶湖疎水記念館や蹴上のインクラインの他、教鞭を振るった京都大学の校舎、そして縁あって京都の朔様のご自宅でお孫さん(!)にもお会いできましたので、あわせてレポートしながら、朔様の凄さをお伝えしたいと思います!
大学の卒論がそのまま大事業に!23歳で琵琶湖疎水建設に挑む!

写真は京都市蹴上にある朔様の銅像です。若い!!
【田辺朔郎】1861年12月2日〜1944年9月5日
明治~昭和前期に活躍した土木技術者。琵琶湖疏水や日本初の水力発電所の建設、関門海底トンネルの提言、北海道の鉄道網建設に携わるほか、大学教授として土木工学を教えるなど、日本の近代土木工学の礎を築く。また、北海道狩勝峠の名づけ親でもある。
偉人の銅像はたくさんありますが、こんなに若い人物の銅像は珍しいのではないでしょうか。それもそのはず、朔様は若干23歳で琵琶湖疎水の主任技師(土木工事の責任者)に任命され27歳でこの事業を完成させています。現代であれば、リニア新幹線のようなビッグプロジェクトの建設工事に卒業直後の若い責任者が就くようなもの。しかもちゃんと工事を完成させているからすごい・・。
琵琶湖疎水について
https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007153.html
当時の日本は、大きな土木工事をするために外国から土木技術者を助っ人として招いていた時代。その中で朔様は大学で土木工学を学び、「琵琶湖疎水計画」を卒業論文としてまとめています。
朔様はこの論文で、琵琶湖から水を引くための長大トンネルの計画に「立坑を2か所設置する」案を盛り込み、これを現地の調査結果を踏まえて実現性が高いこと、工期短縮に大きく寄与することを提言しています。これが当時の京都府知事北垣国道の目に留まり、主任に抜擢されました(のちに、北垣国道の娘と結婚しちゃう!)。
首長の興味を惹くほどの卒業論文って一体なんなの??どんだけ高い視点で書かれていて、どんだけ深く考察されているの・・・と、私には想像もできません。
右手を負傷したため、左手だけで卒論を完成させた!

朔様の直筆文字がみっちり詰まったノート、尊い。(琵琶湖疎水記念館展示パネルより)
朔様が主任に抜擢された大きな理由を私なりに考えますと、計画内容の精度の高さは勿論、現地調査中に右手を負傷したために左手1本で図面を含めた卒業論文を完成させた根性と、未経験の世界にも正面から立ち向かうチャレンジ精神の持ち主であったことだと思います。
この怪我について「せめて負傷したのが左手であれば良かったのに」と同情する友人に対し「なに、同じ困難に立ち向かうなら左手一本でやり遂げた方が話の種になってよい」という強がりを言ったという逸話が残っているぐらいなので・・・朔様は相当負けん気が強い人だったようです。
既存の振動測定器が使いにくかったので自作しちゃう!

朔様は琵琶湖疎水完成後、北海道で鉄道を新設したり、シベリア鉄道の調査をしたり、東京帝国大学教授時代には日本全国の鉄道網計画の策定に参加したりと、日本の鉄道工学の礎を築いた一人でもあります。

1900年10月、朔様は40歳の時に京都帝国大学(現在の京都大学)の教授に任命されそのまま晩年を京都で過ごしましたが、現在の京都大学吉田キャンパスの赤レンガ校舎の2階に朔様の教授時代の部屋が残っています。
さて、この赤レンガ校舎の1階に、重厚な振動測定器が保管されています。 朔様は京都帝国大学の教授に着任後、鉄道橋梁の振動についての調査をしており、当時あった振動測定器が使いにくかったことから、自分で考案設計してしまったようです。周りに無いなら新しく作れば良い!教授になっても朔様のフロンティア精神が垣間見れます。


保管箱の製造番号の銘板に「田辺工学博士考案」とあります。また下の銘板には「島津製作所」とあることから、朔様が考案設計し、島津製作所が製作したものらしい。まさに日本が誇る技術の塊!です。
当時の東海道線や関西線の鉄道橋梁の振動をこれで測定し、その後の鉄道橋梁の設計標準の作成に寄与しました。その後に設計製造された鉄道橋のほとんどは今でも現役で日本の大動脈を支えている事を考えると、胸が熱くなりました。

この朔様の部屋から校舎の1階へ降りるための階段踊り場に窓があります。恐らく朔様もこの窓から外を眺めていたでしょうね。この窓からとても大きな杉の木が見えます。

この杉の根本に「大正元年ヒマラヤ杉 田辺朔郎寄贈」の石碑がありました。『田辺朔朗博士六十年史』によると丁度その年に朔様が京都市から水車の寄贈を受けており、これを大学構内に据え付けた、とあるので、同じタイミングで杉の木を寄贈したのではないかと思います。
メモ魔な朔様、土蔵風の書斎を自ら設計!

さて最後に、縁あって朔様のご実家を訪ね、お孫さんである田辺謙三氏にお会いすることができました。

朔様は(これまた・・)鉄筋コンクリート2階建ての土蔵風書斎を自分で設計し、様々な資料を保管していました。田辺家にある資料はなんと1万5千点以上!謙三氏によると朔様はかなりの「メモ魔」だった、との事。
確かに、琵琶湖疎水記念館には先ほどご紹介した卒論草稿のほか、アメリカへ水力発電の視察に行った時の記録など、朔様のノートがいくつか展示されていますが、どれもギッシリと図面や文字が書かれていました。どんな事も貪欲に勉強して新しい技術を吸収していった・・朔様の源のようなものを垣間見た気がしました。
「百石斎」の資料は現在土木学会で整理中とのこと。最終的にはこの「百石斎」を田辺朔郎記念館として整備するそうです。楽しみですね!
私もそうですが、土木技術者として仕事をしている方の多くは、朔様を知る頃には既に「琵琶湖疎水の工事責任者になった23歳の朔様」より年上になった状態であることが多いと思います。
「えっ?私より若いのに、もうこんな大工事を!?」という驚きとともに、自分ももっと挑戦できるのではないか?と勇気付けられます。そんな若手技術者の憧れと尊敬の念が、あの朔様の若い姿の銅像に表現されているのだと感じました。
さて今回は、京都を中心に朔様のエピソードをご紹介しました。コロナが収束したら次回はぜひ、北海道へ行って、鉄道マンとしての朔様の証跡をレポートしたいと思います!
最後に、今回大変貴重な御縁を下さった京都大学の高橋良和先生と、ご多忙の中お話を聞かせてくださった田辺謙三氏に心より御礼申し上げます。
文:N.F
ほぼ毎日鉄道の事を考えているドボジョ。
土木技術者女性の会・西日本支部長。
鉄道の事以外では、サウナの事を時々考えている。
