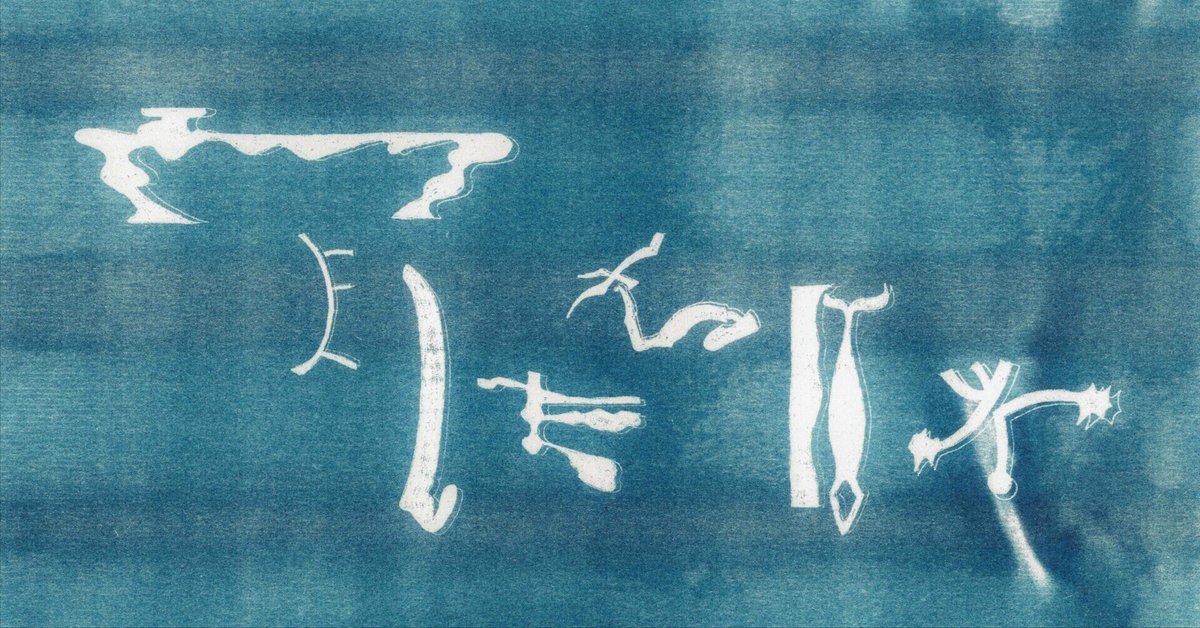
わたしたちは水 #2: ラリー・クラーク 写真集: LARRY CLARK: RETURN

子どもの頃、私はヤクザという人たちをミッキーマウスとおんなじような、フィクションの中の存在であると思い込んでいた。私が生まれ育った世田谷区にそんな人たちはいなかったし、彼らを見るのはいつも映画やテレビの中だったから。小学校に上がる前に住んでいたマンションに暴力団関係者が住んでいると警察が来たことがあって、だから暴力団は現実にあると知っていたけれど、それでもヤクザやドラッグやピストルは、戦争みたいに百年とか二百年前にあって今は正された“人類の過ち”なのだと思っていた。ヤクザもドラッグもピストルも戦争も、今もまだあると知ったのは小学校高学年か、もしかしたら中学生になってからだったかもしれない。

だから私はどこかフィクションを見ている気分で、この本を眺めていた。それは真っ白い中にぽんと目の粗い白黒写真が配置されているその構成とか、そこに映るのが自分とはまるで風貌の異なるアメリカ人たちの姿だからとか、そもそも私の生まれる前の時代の写真だからとかもあるけれど、でもやっぱり私にとって馴染みのないカルチャーを捉えたものだからだろう。『トレインスポッティング』みたい、とか思って、あれもイギリスの90年代の若者のリアルを描いているんだよな、と知識として思い出す。現実味はない。そういえば10代の頃に『KIDS』を初めて観たときも、日本語字幕が付いていなかったこともあり、どういうストーリーなのかさっぱりわからなかった。

それにしてもドラッグって、こんなに真剣な顔で打つものなんだ。腕を押さえてあげたり、近くで見守っていたりするひとの顔まであまりにも真剣で、お医者さんよりお医者さんみたい。打っているのはもしかしてインシュリンなんじゃないかと、一瞬本気で疑った。治療行為にしか見えないから。楽しむためでなく、苦痛の緩和なのか、生きるための。私はそれを言葉とか物語に没頭することでもってしていたけれど、環境が違えば注射器でもってしていたのだろうか。

写真にふれてみると、黒いところだけざらざらしている。と思ったが、ほかの写真にもふれてみたらそういう規則性があるわけではなく、すべてがつるりとしている写真もあれば、ところどころでテクスチャーがまるでちがう写真もあった。そのざらつきがなんとなく、かなしみの手触りという感じがした。かなしみの熱の手触り。それはドラッグを打ってあげる女性の腕のセーターの毛玉とか、沈みすぎるストライプ柄のマットレスとか、光をやわらかに包む薄いコットン素材みたいなテーブルランプからも感じた。ファストファッションや合成繊維に慣れた私からすると、彼らの身につけている服も、部屋のシーツやカーテンも、いっそ上質なものにさえ見える。そのせいもあるのか、ひりひりと今を生きようとする彼らの姿より、彼らを取り囲む無機物の方が、よほどあたたかな体温を宿しているふうに思えた。

大判だけれど薄くて軽いこの本が、なんだかすごく私のからだにフィットしたので、これを書くあいだもずっと抱きしめていた。細かくでこぼこした表紙は鮫の肌みたいで、大きくて平べったくて、硬い。本の上のあたりがちょうど鎖骨に当たる。ノックするとコンコンと高い音がする。ぎゅうっと抱きしめても痛むのは私の腕の方で、本はちっとも潰れそうにない。手放したあと、薄くて硬いものが肉体にめり込んでいた余韻を感じながらふいに、この本が好きだな、と思った。初めてこんなふうに本を好きになった。

______________________
執筆者
内田紅甘(うちだ ぐあま)俳優/エッセイスト
1999年生まれ、東京都出身。2007年に映画にてデビューし、現在は俳優業の傍ら執筆業も行う。主な出演作に『白河夜船』(2015年)『光』『アイスと雨音』(ともに2017年)などがある。2023年に代田橋flotsam booksにて初の個展を開催。
IG:@guama_uchida
______________________
いいなと思ったら応援しよう!

