
社会秩序と利潤追求の間にかける橋と、需要と供給の間にかける橋:ヘシオドス、孔子、仏陀とイブン・ハルドゥーンが見た利道と社会的結合の重要性
人類最初の経営指南書、ヘシオドスの「勤労と日々」
モノやサービス(役務)の交換のはたらきに関する人類最初の記述は、西暦紀元前700年ごろ、古代ギリシャで一介の羊飼いから起業し、大規模な農業生産業者・兼・海上輸送流通業者となったヘシオドス(Ἡσίοδος)が、詩歌の女神ムーサたちから「詩才の牧杖」を授かる形で、神がかりの状態で詠みあげた作品群の一つであり、経営指南書である「勤労と日々」(仕事と日、エルガ・カイ・ヘーメライ)であろうか(Ἔργα καὶ ἡμέραι; Erga kai Hemerai; Works_and_Days, 紀元前700年ごろ)。この中に、互酬関係や、富・財産(プリュートス, πλούτος)と正義(ディカイオシュネー, δικαιοσύνη)に関する詩句がいくつかある。ヘシオドスは、この作品を詠む契機となった、ヘシオドスに財産分与を要求する弟ペルシスとの調停(裁判)において、ペルシスと調停員に経営の基礎を説明する。ヘシオドスは、ギリシャ神話における世界創造以来の神々の善行と不品行を例示し、第309行以降において、富(プリュートス)と財(クリマタ)は人から奪うものではなく、正義を確保した方法で自分で形成するものであると強調する:

右下の木または岩に立てかけられている詩才の牧杖のほかに、竪琴も与えている。
Hésiode et une Muse (Gustave Moreau, 1891).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Moreau%2C_Gustave_-_H%C3%A9siode_et_la_Muse_-_1891.jpg

ムーサは眠るヘシオドスの額と牧杖に詩才を移している。
Hésiode et la Muse (Eugène Delacroix, c.1863). https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9siode#/media/Fichier:Palais_Bourbon,_Malerei_in_der_Kuppel_der_Poesie,_Szene-_Hesiod_und_die_Muse_(Eug%C3%A8ne_Delacroix).jpg

ヘシオドスが手にする牧杖に月桂樹の若枝の神聖な力で詩才を移す。
クルス† @TveracruzT, 2020.1.02.
https://x.com/TveracruzT/status/1212638397614841858
ヘシオドスの経営観
・勤労(エルガ)により、人は不死(ア・タナトス=名誉)を与えられる(with working they are much better loved by the immortals; καὶ ἐργαζόμενοι πολὺ φίλτεροι ἀθανάτοισιν)。
・勤労は恥ではない。不労(ア・エルガ)こそ恥(オネイドス)である(work is no disgrace: it is idleness which is a disgrace; ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος)。
・富(プリュートス)は徳(アレテー)と名(キュドス)を伴う(fame and renown attend on wealth; πλούτῳ δ᾽ ἀρετὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ)。
・見よ、富の故に、彼の信(オニニス)は大いに(メガ)育まれる(See, confidence exists with wealth; αἰδώς, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν)。
・財貨(クリマタ)は人から奪うものではない(Wealth should not be seized; χρήματα δ᾽ οὐχ ἁρπακτά)。
・あなたに与える者に与えよ、あなたに与えない者に与えてはならない(and give to him who gives and do not give to him who does not give; καὶ δόμεν, ὅς κεν δῷ, καὶ μὴ δόμεν, ὅς κεν μὴ δῷ)。
・ひとつ与えられたらひとつ与えよ、ひとつの不執行にはひとつの不執行でこたえよ(for one gives to a giver, but no one gives to a non-giver; δώτῃ μέν τις ἔδωκεν, ἀδώτῃ δ᾽ οὔ τις ἔδωκεν)。
ヘシオドスと孔子の類似
ヘシオドスの経営指南は、労務管理や農事暦・航海暦に関する内容も含む。ヘシオドスは、冬至の六十日後に、うしかい座アルファ星=アルクトゥルス(大角星)が「伏」になる(日没の際に見える)時期が(冬小麦の収穫という)春の始まりであること、オリオン座(オーリーオーン:猟戸座)とおおいぬ座アルファ星=シリウス(セイリオス:天狼星)が中天に昇り、アルクトゥルスが「見」になる(日の出の際に見える)時期が葡萄の収穫と乾燥の時期であること、利益を最大化するために貨物は大きな船に積むべきこと、春の数か月または夏至の五十日後の数か月が航海によい時期であることを、ペルシスに教える。不正でない利益の最大化は、ヘシオドスの経営観において最も重要なものの一つだった。紀元前6世紀後半〜5世紀、ヘシオドスより二百年遅れて現れた、車大工出身の孔子(紀元前480年ごろ没)も、ヘシオドスに似た経営観を述べている(「論語」里仁第四)。「富は徳と名を伴う」(金持ち喧嘩せず)というヘシオドスのことばには、対応する「恒産なき者は恒心なし」(貧すれば鈍す)という孔子のことばがある。孔子はまた「礼記」月令(らいき・がつりょう)に農事暦と季節ごとの星々の位置に関する古代の知識をまとめたと伝えられる。
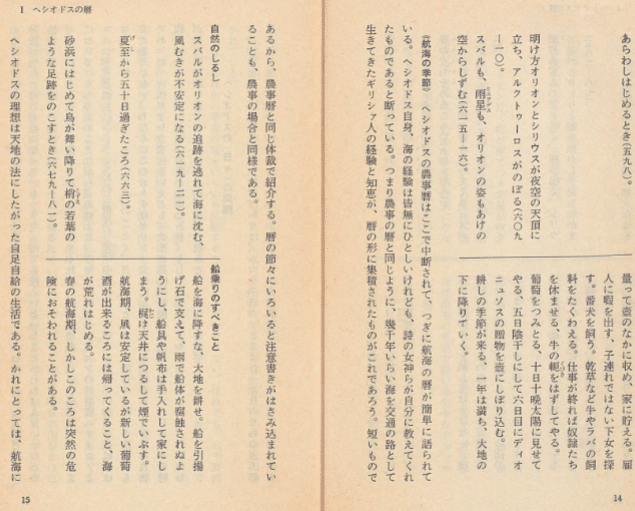
(「ギリシァ思想の素地 : ヘシオドスと叙事詩」久保正彰、1973)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12575423/1/11

(「中国古典文学大系」第三巻、竹内照夫訳、1970)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12574265/1/231
孔子の経営観
「論語」里仁第四にいう:
・孔子はいった。豊かさと高い地位を人は望むが、道徳性を確保して解決するのでなければ長続きしない(子いはく、富と貴とはこれ人のほっするところなるも、その道(どう)をもってこれを得るにあらざれば、処(を)らざるなり。子曰、富與貴、是人之所欲也、不以其道得之、不處也)。
・貧しさと低い地位を人は嫌うが、道徳性を確保して解決するのでなければ脱出できない(貧と賎とは、これ人のにくむところなるも、その道(どう)をもってこれを得るにあらざれば、去(さ)らざるなり。貧與賎、是人之所惡也、不以其道得之、不去也)。
南アジア~東南アジアで道徳性ある経営=利道を順守する過去世の仏陀
教育者としての孔子の関心事は、社会秩序と利潤追求の間の谷間に、どうやって正義の橋をかけるかということだった。紀元前5世紀の中国春秋時代、稀代の大商人ともいえる活躍を見せ、危機に瀕した魯を弁舌とアイデアで救い、「孔子教団」を支えた子貢(しこう:孔子の最年少の弟子)は、後代の日本の渋沢栄一のような、儒教に基づく経営理念(商人道、利道)をもち、孔子のいう「その道(道徳、正義)をもって富と貴を得」る儒商の先駆けであった。子貢こそ、孔子の最も優れた弟子だったのではないだろうか。ヘシオドスも、弟がペルシスではなく、子貢のような利道をまきまえた男だったら、さぞ教えがいがあっただろう。

https://www.kobo.com/jp/ja/ebook/_QljbsY5czGPJ1sznw6U9w
紀元前6世紀後半、孔子とほぼ同時代人だった仏陀は、ジャータカ(本生経)によれば、過去の転生において複数回、子貢のような利道を順守する商人としての人生を過ごした。ギリシャ語と同じ印欧語であるパーリ文「本生経」(Jatakamala)第十四話「船長スパーラガの航海」や、西暦4~5世紀の編纂と考えられるサンスクリット文・漢文・チベット文「大乗荘厳宝王経」(Karandavyuha-Sutra)の「商人シンハララージャの航海」(往 獅子国の事=シンハラ/スリランカ島への航海:漢文第三章、チベット文第二章)などに、「ブッダ過去世の大冒険」ともいうべき、商船団を率い、時には自ら舵を取ってインド洋を航海し、外国の王侯にもトップセールスを行い、羅刹女の王と愛し合い、造物主・観音と聖馬王バラハ(ブラクに似た荒ぶる天馬)に導かれて決死の救難・逃避行をはかる、まるで船乗りシンドバッドのような冒険商人としての過去世の仏陀の活躍が描かれる。
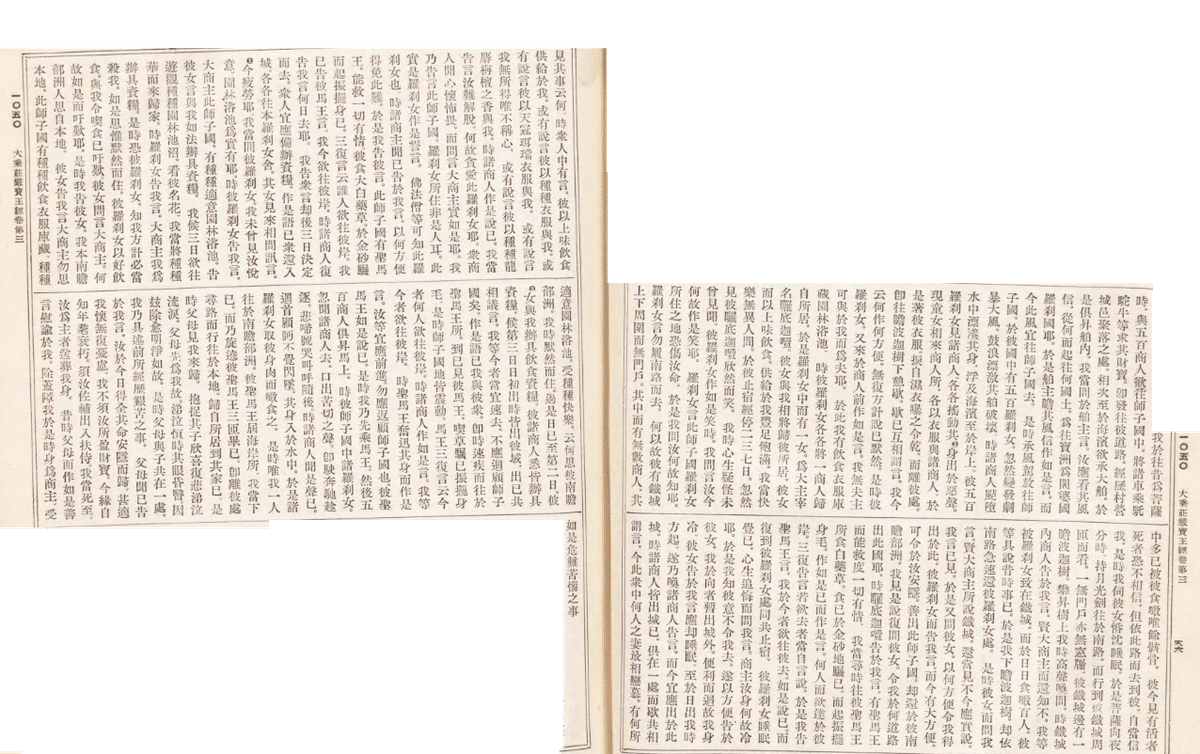
「大乗荘厳宝王経」(Karandavyuha-Sutra)第三章「商人シンハララージャの航海」(往 獅子国の事)(大正新脩大蔵経第二十巻、高楠順次郎編、1928)
「商人シンハララージャ」とは「獅子国へ交易に行って、生きて帰ってきた商人」の意か。「大乗荘厳宝王経」は「造物主である観音の菩薩行の旅」という密教的世界観に立つ。観音は世界を創造した後、世界主宰者をシヴァ(大自在天)に委ね、放浪の旅に出る。観音が獅子国に隣接する羅刹女の国で不殺生戒を授けた数百年後、商人シンハララージャの船団を迎えた羅刹女の王は、不殺生の戒めと羅刹女の本能(男を犯して食らう)の間で苦しむ。羅刹女の苦しみは、インド人商人を迎えた各地住民の、邪心と良心(殺して奪うか、公正取引で共存共栄を目指すか)の葛藤の象徴か。
https://dl.ndl.go.jp/pid/3435930/1/39?keyword=%E5%A4%A7%E4%B9%97%E8%8D%98%E5%8E%B3%E5%AE%9D%E7%8E%8B%E7%B5%8C

https://www.himalayanart.org/items/50204
しかし『インド経済史・古代から現代まで』(India+in+the+World+Economy: From Antiquity to the Present, Tirthankal Roy, 2012)は、古代インドの海上貿易商人や船乗りを、冒険者として扱わない。ロイ氏は、古代インド貿易について、「まず地理から始めよう」と、豊富な事例を提示しながら、古代貿易に関する地理的な要因の意義を述べる。それを踏まえて、古代貿易においても地理的な可能性と制約は明確であり、古代インド人の交易性向は決して文化的ではなく、南アジア・東南アジアの特定の地域や住民共同体の地理的位置による経費の節減性、危機管理の容易性を十分検討して行われたとする。インド人商人も航海者も、低コスト・低リスクの貿易ルートを集中的に開拓していた。もちろん、航海に絶対の安全はない。しかし、季節風(モンスーン)を考慮すれば、ヘシオドスが東地中海において「春の数か月または夏至の五十日後の数か月が航海によい」という航海常識を示したのと同じ、低リスクで航海が行える船出と帰帆の時期があり、方角があり、また需要が多く、治安が良く、金払いのよい地域に関する知識があったと考えられる。フェニキア人とインド人が開拓したこの航海知識は、ギリシャ人商人の「エリュトゥラー海案内記」(西暦50年ごろ)と中国人僧法顕の「仏国記」(西暦413-414年ごろ)により共有が開始され、ペルシャ人、アラブ人、トルコ人に引き継がれ、ポルトガル人、スペイン人とオランダ人によりほぼ完成された。日本でも、「元和航海記」(1618)のような航海技術書や、「華夷変態」(1644-1717)のような海外事情データベースが編まれた。ビジネス・マッチングサイトのようなものがまったくない時代、ハンザ同盟のような商館連携もなかった時代と地域では、フェニキア人、ギリシャ人、ソグド人のようなごく限定的な民族ネットワークを除けば、外国の港町や外国人居住区での、ユダヤ教やイスラームのような宗教ネットワークの、シナゴーグやモスクでの礼拝のあとの雑談、または安息日の食事会で行われる意見交換が、商人・航海者たちの安全を最大限保証する仕組みだったと考えられる。宗教と文化・文明・技術がしばしば同伴者だったのはそういうわけなのだろう。

ハノイを中心にベトナム北部に滞在する各国のムスリム・ビジネスマンの意見交換場所でもある。安くておいしい。

Technique du peuple Annamite (Mechanics and crafts of the people of Annam), Henri Oger, c.1910: Tome 2: 518. Tây Đen(西顛(顛の左にさんずいを、右にダブルダッシュ付す)=色黒な西洋人)
十四世紀イブン・ハルドゥーンが見た、人間が社会的結合を必要とする理由
14世紀後半、「歴史序説」(المقدمة Al-Muqaddimah, Ibn Khaldūn, 西暦1377年ごろ)第一章において、大法官(ムフティー・ル・ラアム)イブン・ハルドゥーンは、アリストテレス「政治学」(紀元前320年ごろ)の第一巻第二章「人間は自然に国的動物である」を踏まえ、「国的動物」を「社会的存在」(=ポリス的存在、マダニーヤ)とアラビア語で表現し、以下の前提に立つ:
「アル・フカマーウ(ギリシャの賢者たち≒アリストテレス)がいう通り、その本性において(ビットバイ)人間はポリス的存在である(アル・イインサーン・マダニユン=ポリティコー・ゾーオン)」(الإنسان مدني بالطبع; al'iinsan madaniun bi-al-tabey; ο άνθρωπος-φύσει πολιτικό ζώον)。
イブン・ハルドゥーンはギリシャ語のポリスを国家ではなく社会と理解し、人間は分業に依存する社会的動物であるという理解・前提のもと、次の文から、彼の考えを述べ始める。
・人間(アル・イインサニア)の社会的結合(アル・アイジティマア)は絶対に必要である(フィ・アナ…ダルイユン)(Human social organization is something necessary.
في أن الاجتماع الإنساني ضروري; fi 'ana al-aijtimae al'iinsania daruriun)。
・「その命(ハヤートゥハ)は、食物によって(ビ・アル・ギザ)生くる(バカウハ)」ように作られているからだ(God created and fashioned man in a form that can live and subsist only with the help of food.
لا يصحّ حياتها وبقاؤها إلّا بالغذاء ; la ysh ha-yatuha wa-baqawuha 'illa bi-alghidha')。
・また神は彼を食欲に導き、それを得ることを可能にする力(クドラ)を彼に与えた(He guided man to a natural desire for food and instilled in him the power that enables him to obtain it.
وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركّب فيه من القدرة على تحصيله ; wa, hadah 'iilaa al-timasih bi-fitratih wa bi-ma-rkkb fih min al-qudrat ealaa tahsilih)。
・しかし、個々の人間(アル・ワヒド・ミヌル・バシャリ)の力(クドラ)は十分ではない(イラー・アンナ…カシラタン)(However, the power of the individual human being is not sufficient;
إلّا أنّ قدرة الواحد من البشر قاصرة ; 'illa anna qudrat al-wahid min al-bashar qasiratan)。
「その命は食物によって(ビ・アル・ギザ)生くる」、このことばは、「旧約聖書」申命記でモーセが語り、「新約聖書」マタイによる福音書第四章でイエスが語った「人はパン(pane; הלח ; الخبز ; ψωμί)のみにて生くるにあらず」(=主である神の口から出る全ての言葉=マナ(manna; המן ;المن μάννα)によって生かされている)を理性で退ける、「ユダヤ教的・キリスト教的エヴァンゲリオン(福音)に対してイスラーム法学が提出するアンチテーゼ(反対命題)」となっている。北アフリカで報道記者として活動していたフランク・ハーバートは、この地で出会った「歴史序説」に触発されて、未来世界の星間戦争を、単なる銀河帝国興亡史としてではなく、全宇宙規模のサプライチェーン再編史として描くビジネス風の叙事詩的小説「デューン」を創作した(Dune, 1965~)。作中で人類存亡の鍵となるサプライチェーンの主役「超食物」メランジ(創作時点では石油の比喩だったようだ)は、イブン・ハルドゥーンが否定したマナを彷彿とさせる。この文章を書いたイブン・ハルドゥーンは十四世紀アンダルシアとマグリブを生きたアラビア語を話すセム系(ハドラマウト系)チュニジア人だった。ギリシャの賢者たち≒アリストテレスやヘシオドスの倫理学の伝統を汲む彼は、商業倫理(利道)についても詳述した(Munir Quddus and Salim Rashid, 2017)。イブン・ハルドゥーンは続けて記す:「一日分の食物、たとえば少しの小麦を仮定したとしても、その量の食物もまた、挽いたり、こねたり、焼いたりするなどの多くの準備を経て初めて得られる。これら三つの作業にはそれぞれ、鍛冶、木工、陶工などの複数の職人の助けを借りてのみ提供される器具や道具が必要だ。だから人間の社会的結合が必要なのだ」。そう、これは、換言すれば、人の生存には需要と供給の間にかける橋(マッチング)が必要だ、ということなのではないだろうか。ところで、現代の需要と供給のマッチング・デバイスはパーソナル・コンピュータ(個人用電子計算機)とスマートフォン(高機能携帯電話機)であり、その両方の普及は、プロダクトアウト(こんなものを売りたい)とマーケットイン(こんなものが欲しい)の絶妙な融合―「需要のないところから需要を創造した男」アップルを作ったスティーブ・ジョブズによるところが大きい。彼もまたセム系のシリア人である(祝日にニスティシマのような斎戒料理を食べる東方正教会信徒の家系)。彼の経営感覚に、ギリシャ・キリスト教・イスラーム世界の壮大な背景を感じる。以上。

https://dl.ndl.go.jp/pid/2979437/1/65

https://kautsar.co.id/detail/ibnu-khaldun-bapak-ilmu-sosial-dunia

フランク・ハーバートが描く部族長スティルガーの気難しさと誠実さ・敬虔さが入り混じる人物像は、マグリブの大法官イブン・ハルドゥーンとよく重なる。彼の発言と行動=ハーバートのイブン・ハルドゥーン理解なのだろうか。
https://filmaga.filmarks.com/wp-content/uploads/2024/03/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-13-300x300.jpg

遊牧民族が都市文明帝国を征服する仕組み、国家独占資本主義や社会主義計画経済が破綻する仕組みを説明する。この説明は論理的枠組み(ロジカル・フレームワーク)ではなく、彼が大法官を務めた諸国で収集した統計に基づくと考えられている。残念ながらその統計は現存しない。

(Munir Quddus and Salim Rashid, 2017)https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226443997-008/html?srsltid=AfmBOoqW-lMBrjT4C6UFhE-fb_2wIlrkVRye_RNaNVLYpiBN3HZOQgSW
